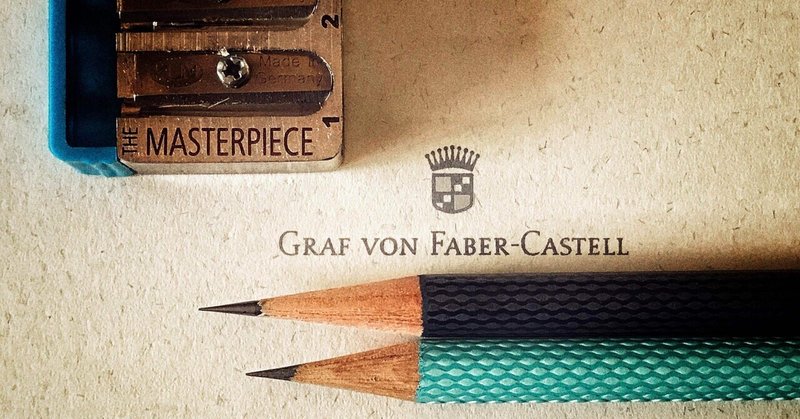
「手伝って」が言えない!?発達障害による援助希求の難しさがある子 〜課題&原因編〜
小学校担任として経験しそうな事例第三段は、発達障害による援助希求の難しさがある子についてです。
発達障害といっても白黒はっきりするものではなくスペクトラム、いわゆるグレーゾーンが存在するものです。しかし、今やクラスに3人発達障害の子がいるとも言われています。それだけ困り感を抱えている先生も多いということではないでしょうか。
今回も、
①課題と考えられる原因編
②対応と結果編
の二部構成でご紹介します!
※実際の事例を元にフィクションしたものを掲載します。
【Cさんの普段の様子】
・朝や帰りの支度や、授業を受けることは問題なくできる。聞かれたことに正しく答えるのは苦手だが、漢字などの暗記問題は得意で正答率が高い。
・友達に話しかけられると「うん」など簡単な受け答えはするが、自分から話しかけることはほぼない。
・援助希求が苦手。分からないことがあっても独自に解釈し、違うことをしていることも。どうしても困った時、担任が近くにいれば「先生〜、どうしよう〜」と言うこともあるが、稀。友達に聞くことは皆無。
発達障害による援助希求の難しさが見られるCさん。今年度から友達とコミュニケーションをとる練習として、通級指導教室に通い始めました。
【課題としたこと】
・身近な大人に援助希求ができないこと
正直なところ課題はたくさんありましたが、Cさんの1番の困り感を考え、大人への援助希求を課題としました。
【考えられる原因】
・発達障害特有のコミュニケーションの難しさ
・援助希求せずとも助けてもらえた経験の積み重ね
これまではCさんが友達に「助けて」「手伝って」と援助希求ができるようにと、Cさんの周りにいわゆる"優しい子"や"気にかけて声をかけてくれる子"を配置する支援をしてきたようです。しかしそれでは"援助希求せずとも助けてもらえる経験"が増える一方です。現状からすると、子ども同士の関わりはまだ先の話で、身近な大人に自分から援助希求できるようになることが必要だと私は考えました。
次回は②対応と結果編です。ぜひ一緒に考えてみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
