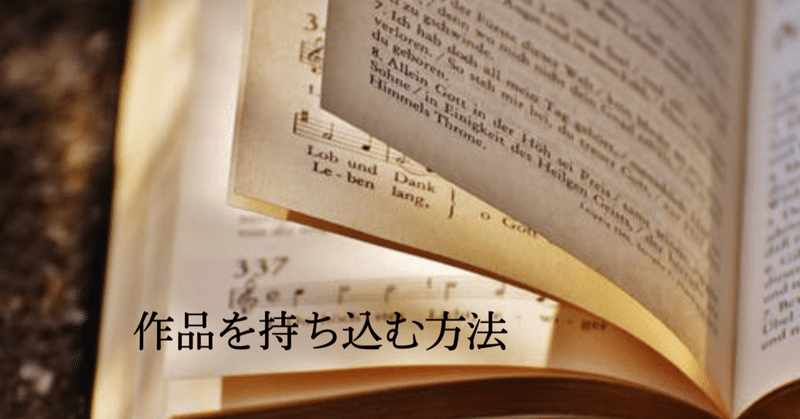
持ち込みの手順について〜企画提案書の書き方 その1
前回の記事で、自信作であれば、小説であっても出版社への持ち込みに挑戦しましょう、基本的なマナーを忘れないでください、と書きました。ただし、文芸書の出版の現場では、暗黙の了解事項がまだまだ多く、何も考えずに突っ走ると地雷を踏むことになりかねません。(かくいう私も、十数年前にエージェントを始めた頃は、編集者さんに怒られたり諫められたりしたことは数知れず……)
今回から、主に作家志望者、新人・若手作家向けを想定した、持ち込みの方法について、ご説明してまいります。数多くの失敗も重ねてきた私の経験値にすぎませんが、他の分野での持ち込みや新人賞への応募書類などと照らし合わせると標準的だろうと思っています。参考にしていただきつつ、ご自身の方法を見つけていただけると幸いです。
持ち込みの手順
出版社に作品を持ち込むときの流れは、以下のようになります。
① 持ち込みのための書類を準備する
② 編集者さんにコンタクトする
③ 検討結果に応じて交渉をする
手順① 持ち込みのための書類を準備する
持ち込みに必要な書類は、以下の3つです。
・企画提案書
・原稿
・(必要に応じて)添付書類
そして、もっとも重要なのが、これらの書類を持ち込む出版社や編集者さんに宛てた送付状(手書きでもメールでも)です。順にご説明します。
企画提案書の書き方
タイトルや著者略歴、作品の梗概(あらすじ)をまとめたのが、企画提案書です。書式や文量は自由ですが、新人賞の応募要項などを参考にしていただくといいでしょう。
例えば、以下のような内容と分量を目安としてください。
・タイトル、400字詰め原稿用紙換算枚数、筆名、本名、住所、電話番号、メールアドレス、年齢、職業、略歴などを記したもの(A4で1枚)
・作品の梗概(400字詰め原稿用紙1~3枚程度の分量)(A4で数枚程度)
このときに難しいのが、著者略歴、作品の概要の書き方です。原稿を検討していただくときに有利な情報は伝えたほうがいいのですが、アピールポイントばかり並べたものは敬遠されてしまいます。
著者略歴の書き方
基本的には、履歴書や職務経歴書などに記載するような生年月日や学歴、職歴、取得資格といった事項をわかりやすくまとめます。さらに、項目や文字数に規定があることもある新人賞への応募書類より少し詳しく、執筆歴、あれば受賞歴や出版歴なども説明しておくのがいいと思います。
私は出版社へ売り込む側であると同時に、エージェントとして作家から売り込まれる側でもあります。その視点からいうと、作者の専門性や独自性を把握する上で、どのような人生を歩んでこられたのか、どのようなことを学び、どんなお仕事をされてきたのかは知りたいものです。ただし、相手の気を惹こうとしてエピソードを盛ったり、ふざけたことを書いたり、お涙ちょうだいのストーリーを混ぜたりするのはやめましょう。あくまで、客観的な表現にしておくことがコツです。
新人の方の場合、受賞歴や出版歴はなくとも、どういう執筆修業をされてきたのかを添えるといいのではないかと思います。例えば、小説教室や文章教室で学んでいたこと、大学のサークルや同人仲間と文芸誌を作っていたことなどです。「プロとしての活動でもないのに……」と遠慮する方もいそうですが、編集者さんが講師の先生(小説家や評論家、編集者であることが多いですよね)と親しくしていたり、同じ大学の文芸サークルに入っていたり、文学フリマや文芸フェスティバルで文芸誌を見かけていたり……といったご縁があるかもしれません。接点が少しでもあると、「ちょっと先に読んでおこうか」なんてことにもなると思います。出版社以外が主催している文学賞やウェブ文芸誌、海外メディアでの紹介実績など、一般的にはあまり知られていない場合は、どういう媒体なのか、どういう評判を得ているのかについて少し説明をするようにしたほうがいいと思います。
実際に、私自身も「○○先生の指導を受けられていたのだな」とか「この企画で優秀賞を取られていたのか」「寄稿されている文芸誌は、たしかTwitterで話題になっていたものだな」などという理由で目を止めることがありますし、編集者さんへのやりとりで盛り上がることがあります。(次は「作品の梗概の書き方」へと続きます)
*文芸作品の持ち込みに関するご質問があれば、コメント欄にて受け付けております。直接お返事をさせていただく場合、note記事にてご質問内容に触れる場合とあると思いますが、あらかじめご了承ください。
お読みいただき、ありがとうございました!
