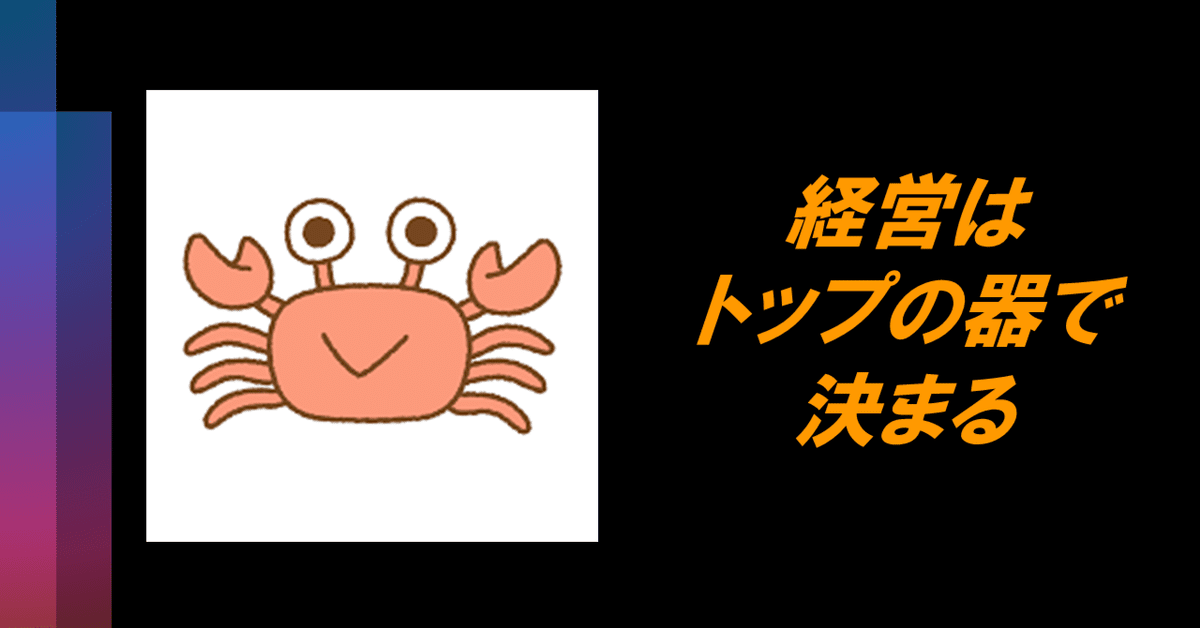
『稲盛和夫一日一言』1/12(木)
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 1/12(木)は、「経営はトップの器で決まる」です。
ポイント:経営者の人間性、いわば人間としての器の大きさにしか企業は成長しない。「蟹(かに)は甲羅(こうら)に似せて穴を掘る」
2011年発刊の『京セラフィロソフィを語るⅡ』(稲盛和夫著 京セラ経営研究部編/非売品)の中で、「経営はトップの器で決まる」というフィロソフィ項目について、稲盛名誉会長は次のように述べられています。
「カニは我が甲羅に似せて穴を掘る」と言われるように、業績はリーダーの器の大きさ、つまり「器量」の分にしかなりません。
器量とは、人生観、人間性、哲学、考え方、あるいは人格という言葉に置き換えてもいいでしょう。
組織が発展するにつれ、運営がうまくいかなくなるとすれば、それはリーダーの人間性が高まっていないからです。そのため、組織の拡大に伴って起こるさまざまな問題に対応できなくなるからです。
業績を立派にしていこうとするなら、リーダーが人間性を高め、人格を磨いていく以外に方法はありません。「心を高める、経営を伸ばす」というように、人格を高めることが、業績や組織を伸ばすことになるのです。(要約)
このフィロソフィは、京セラ社内では次のような事例で問いかけられています。
「あるアメーバ組織のリーダーが、小さなアメーバを見ているときには何とか治まっていたとしても、その後アメーバが次第に大きくなっていっても、引き続き治めていけるのかどうか?」
そこで問われるのが、リーダー自身が自分の器を大きくするような努力をしてきたのか、つまり自分が持っている人間性、人格、人生観、哲学、考え方といったものを向上させるよう努力をしてきたのかどうかというところです。
名誉会長は、盛和塾の前身にあたる盛友塾での講話の際に、それまでのご自身の歩みを振り返って「理念を高め続ける日々でした」と話されたそうです。27歳で京都セラミツクを創業されて以降、単に「経営の技術を高め続けてきた」のではなく、自身の「理念を高め続ける」日々を続けてこられた。
いかに名誉会長が、心のあり方を大事にされてきたのかを物語るエピソードではないでしょうか。
また伊藤謙介京セラ元会長からは、「一人の部下のことも満足に掌握できない、また一人の部下なら掌握できるが二人になればできない、あるいは十人程度ならうまく掌握できるが、百人になればできないとなると、それは人間としての器量、キャパシティがそこまで大きくなっていないということだ」とより分かりやすい言葉で教えていただきました。
名誉会長は、深く学び、実践することの大切さについて、「島津いろは歌」の一番に出てくる次のような一節を紹介されています。
「いにしえの 道を聞いても唱えても わが行いにせずばかいなし」
昔から伝わるすばらしい道理を聞いても、自分で唱えても、それを自分の行いにしなかったら何の意味もない。つまり、それを知っていること、それを言葉にするということだけでは何の価値もない。自分の行動に移さなければ意味がない、ということです。
自分が組織のリーダーとなってからは、特に組織の運営がうまくいかなかったり、組織内の人間関係がギクシャクしてしまったときなど、このフィロソフィを思い起こして「自分には何が足らないんだろう」と悶々とした時間を過ごしたのを思い出します。
人間、いくつになっても、少しでも自分の器を大きくすることができるよう、社会との関わりを通して日々精進していきたいものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
