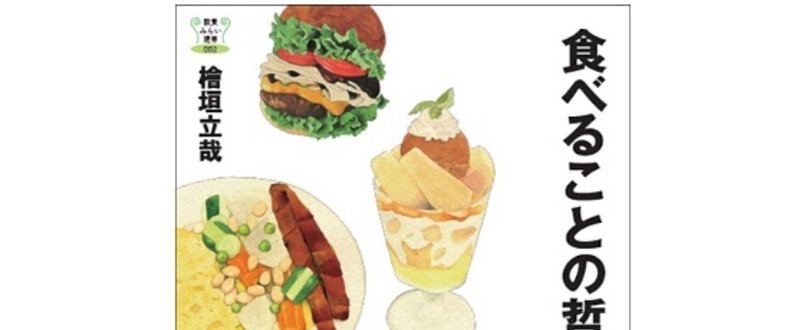
後ろ暗さと快楽の矛盾を思考する〜『食べることの哲学』
◆檜垣立哉著『食べることの哲学』
出版社:世界思想社
発売時期:2018年4月
食べることは他の生物を殺すことです。その営みには後ろ暗さと快楽が伴います。食べることを哲学するとは、その矛盾に生き、その矛盾を思考することにほかなりません。
そして後ろ暗さと快楽という食の両義性は、人間の身体には文化としての身体と動物としての身体があるという二面性にも通じることかもしれません。両者は「ぶつかりあってしか存在しえないのではないだろうか」と檜垣立哉はいいます。このぶつかりあいは食という事例に見えやすいすがたをとって現れる。「食べることの哲学」の意義はそうした局面において浮上するというわけです。
といっても堅苦しい哲学書然としたものでは必ずしもありません。裏表紙に書かれた謳い文句をそのまま引用すれば、本書は「フランス現代哲学と日本哲学のマリアージュで独創的に調理し、濃厚な味わいに仕上げたエッセイ」なのです。
〈第一章 料理の技法〉では、レヴィ=ストロースの有名な「食の三角形」を引用して「生のもの」「火にかけたもの」「腐敗させたもの」の三類型について考えます。そのなかでは「腐敗させる」ことにこそ「もっとも微細な文化性」が関与すると檜垣はいいます。腐敗をめぐる思考はいささか複雑な理路をたどりますが、本書全体をとおして一つの核となるものといっていいでしょう。
〈第二章 カニバリズムの忌避〉は、文字どおり人類のカニバリズムについて考察するものです。私たちにとって深くデリケートな論題といえますが、一見無関係な臓器移植に関して「自分が生きながらえるために他人を身体にとりこむという意味ではまさしく(飢えに起因するカニバリズムと)類似的行為である」と指摘しているのには虚を衝かれた思いがしました。
また米国発祥の「生命倫理学」に疑義を呈しているのも印象的です。いわく「生命倫理という学問分野がアメリカで成立したのは、そもそも医療裁判で免責になる裁判上の技術を考案するためだということは誰もが知っている」のだと。
〈第三章 時空を超える宮澤賢治〉は批評的な一章です。宮沢の著作を本書の文脈に連関づけて読むと「自然と文化のあいだに横たわるグレイゾーンにそのまま踏みこんでいく気味の悪さ」がそこここに溢れているといいます。「よだかの星」や「注文の多い料理店」が提示していることは「人類がカニバリズムを避けるという事態をさらに拡張したもの」です。自然のなかにある生き物と人間とは、それぞれが捕食関係にあります。両者の差異を狭めていき、その境界をなくしてしまうと、実はすべてがカニバリズムの忌避にひっかかります。このことは無視しえない論点であると檜垣は指摘します。
〈第四章 食べることは教えられるか〉は食育の実験授業として賛否両論を巻き起こした「豚のPちゃん」に関する考察です。それは小学生たちが校内で豚を飼育し、卒業時にみんなで食べるという計画で始められました。ところが卒業が近づいてきたとき、実際に食べるのか豚を殺さずに在校生に託すのかが議論になります。
この教育には無謀との批判が集まりましたが、「大変重要なテーマを突きつけてくる」ことも確かでしょう。檜垣は安易に結論的な評価を下すことを慎重に回避しながら、この授業ではいずれを選択しても「無責任」を選ぶことになるといい、教師の選択の無責任性こそは宮澤賢治のいう「ほんたう」の行為ではないか、と締めくくります。
〈第五章 食べてよいもの/食べてはならないもの〉では、反捕鯨映画『ザ・コーヴ』が俎上にのせられています。やはりクリティカルな一文です。この映画は論理的には破綻しているけれど、そこにこそ食にまつわる問題の意味が詰まっているといいます。
映画の作者がイルカの知性や情動性に対して評価をくだすとき、なぜそれがイルカに対してだけ向けられるのか。その線引きの根拠は必ずしも自明ではありません。クジラ・イルカ漁に反対している人は「ただ反対したいから反対しているのであり、本当はそれ以外の意味などないのでは」と檜垣が身も蓋もないことを問いかけるのもあながち暴論ではないように思われます。
〈第六章 人間が毒を食う〉では、あらためてレヴィ=ストロースが取り上げられます。人間は「どこかで毒につながる『腐敗したもの』をこよなく愛する」生き物。そうした意味で毒とは何でしょうか。
毒を食べることは、わざと「他のものを同化」することの業を、食の行為のなかで強調していることだとはいえないだろうか。それは他の生き物を殺していることとひきかえの「快楽」につながっている旨さではないか……。
〈最終章 食べないことの哲学〉では、一転して食べないことの哲学が展開されます。宗教における絶食や拒食症が哲学的考察の対象となるのです。「食べない文明」はある種の潔癖症の人々にとっては一つの選択肢であり、理論的には唯一の抵抗としてありえます。
しかし食べずに生きることはできません。ならば、もう毒を喰えばよいのではないか。「最初から毒を喰いつづけてきた人類は、別種の毒に適合するほどに強い。それだけのことかもしれない。食べないことの哲学の終わりには、毒であれ食べつづけるしかないという結論しかだせないのかもしれない」。
食べることにともなうある種の喜びや、それが抱える何らかの後ろ暗さは、社会がどのように変容しようと、生きている人間であるかぎり変わることはないとおもう。その境界線上のうえでいずれにせよ人間はもがきつづける。食べることは、こうした自然であり文化でもある人間の危うさについて、そのグレイゾーンを存分に示しつつ、なお地球のうえで、それでも先に進んで生きつづけなければならない人間の姿を、その情動すべてを含めて示すものであった。ここから紡ぎだされるもろもろの問いは、それこそわれわれがあるということの戸惑いそのものとかさなるものである。その戸惑いをひきうけることは、身体をもって生きている、人間でもあり動物でもあるわれわれの矛盾に満ちたありかたをはっきりと自覚することでもある。そしてそれは、身体をもち言語をもつわれわれの不可思議さを、よくよくわからせてくれる主題なのである。(p196)
さまざまな思索を経たのちに結論的に書きつけられた以上の文章は、一見するとまた最初の地点に回帰したようにも感じられなくもありません。しかしそれは初めに立っていたのとはやはり違う地点でしょう。うまく言えませんが、一歩二歩三歩、少しステップアップしたような場所。そこからみえる風景は本書を読む前とは明らかに趣を異にしているように思われます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
