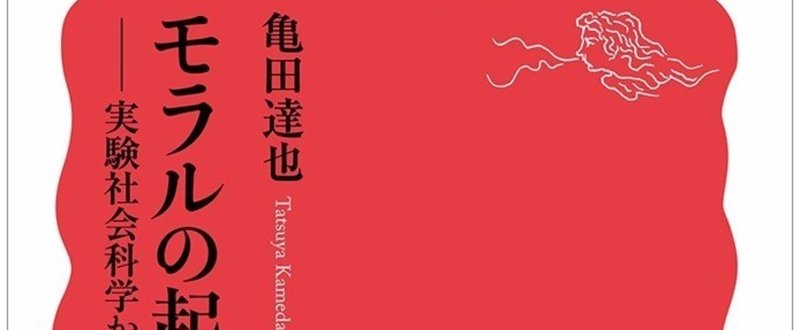
文理横断的な実験から考える〜『モラルの起源』
◆亀田達也著『モラルの起源 ──実験社会科学からの問い』
出版社:岩波書店
発売時期:2017年3月
人間の社会を支える人間本性とはいかなるものでしょうか。これは古来、当の人間にとって最も主要な論題の一つとして繰り返し問われ研究されてきたものです。本書はその問いに対して実験社会科学という新しいアプローチで答えようとする試みです。
まずヒトの社会行動や心の働きはほかの動物と比較したときに、どう位置づけられるか。そしてそのような生物学的基礎をもつ「ヒトの心」が「人の社会」の成立とどう関わるのか。利他性・共感性・正義など「モラル」を構成する人間の心の起源にそのようなステップを踏んで迫っていきます。
当然、そこでは分野横断的な態度が必要になるでしょう。本書では、脳科学、進化生物学、霊長類学、行動科学などに加え、人類学、社会学や行動経済学、心理学、哲学などなど、文理の垣根を超えて知見が動員されます。とりわけ様々な実験やゲームによって得られた知見や推論が多く参照されていて、そこに本書が実験社会科学を標榜している所以があります。
まず、霊長類学者のダンバーの調査によれば、霊長類の大脳皮質の大きさは、その種における群れのサイズとの間に正の相関関係があるといいます。群れのサイズが大きい種ほど大脳皮質が大きい。群れが増大すればするほど、必要な情報処理量(認知、判断、言語、思考、計画など)の増大も必要となると考えられるのです。進化時間におけるヒトの心の適応には、このような集団での生活形式が重要であることは明らかでしょう。
人間生活のもっとも根本的な基盤が集団にあるとすると、ヒトもまた、集団の中でうまくやっていくための心理・行動メカニズムを進化的に獲得しており、そのようなメカニズムこそ、生物種としてのヒトが備えている行動レパートリーの中でも中心的な位置を占めると考えることは、非常に妥当な推論のように思われます。(p18)
では、群れ生活への進化的適応を果たすうえで、生物種としてのヒトの社会行動や心はどのような仕組みになっているのでしょうか。結論的にいえば、ヒトは他者の行動や思いに対して極めて「社会的感受性」の強い動物だといえます。
ハチやアリのような社会性昆虫のコロニーでは、自分と同じ巣の仲間は遺伝子を共有する血縁者なので、自分の適応度を下げてもコロニーの仲間を助ける行動は、同じ遺伝子を残すという観点から意味があります。進化生物学では、この行動が個体と血縁者全体を含む包括適応度を上げると考えます。
しかし非血縁の相手とともに生きなければならないヒトの場合は事情が違ってきます。いくら群れレベルで望ましい結果を生む行動でも、当の個人の生き残りに不利になるようなら、その行動は定着しません。ヒトは、他者の意図を敏感に察知し、極めて戦略的に反応する「空気を読む」動物なのです。
それでは、どのようにしたら互いに助け合う安定した協力関係を作ることができるのでしょうか。
そこで言及されるのが「評判」の働きです。前出の霊長類学者ダンバーは、人が集まる場所での会話を分析し、会話のほとんどが「今ここにいない誰か」についてのゴシップであることを示しました。そのような噂話によって人は他者の情報を得る。それは対人マーケットにおいて重要な選別の機能を果たしているというのです。
近年の研究によれば、間接互恵性で見られるような自発的な親切行為や援助行動は、このような言語を介した「評判」のメカニズムを基盤として、ヒトの心に定着したのではないかと考えられています。
そのような考察を重ねてきたうえで本書が最後に重要な問題と考えるのは「共感/同感」です。アダム・スミスが「同感」こそは人間社会における秩序の最大の基礎になると論じたことはよく知られています。
近年、共感とは「思いやり」だけでなく身体模倣や情動の伝染などを含む重層的なシステムであり、その一部はヒト以外の動物たちにも共有されているのではないかと指摘されるようになりました。
一般に、共感には「情動的共感」のほかに「認知的共感」があります。後者は相手の視点を取るときに働くもので、より複雑な機制をもっています。認知的共感は、必ずしも情動的共感のように、いつでも直ちに「温かくやさしい思いやり」を生むものではありませんが、内集団を超える利他性を発揮するために、欠くことのできない本質的な役割を担うと考えられるのです。
正義やモラルの芽ばえのような行動は、さまざまな動物たちの集団にも観察されます。しかし、正義やモラルが言語という媒体を活かして、多くのメンバーを吸引する力をもつのは、人間社会においてのみです。たとえば、社会運動における不公正の糾弾などは人々を広く動員します。
とすると、政治的存在としての人間を動かす正義やモラルとは何でしょうか。その考察が本書のハイライトといえるでしょう。その具体的な課題として「分配」の問題が取り上げられます。
限られたモノをいかに分配するか。この分配の原理は、社会・文化レベルの要因によって規定されていることは、いくつもの実験によって明らかになっています。
大雑把にいえば、市場経済化が進んでいる社会ほど「フェア」な取引が文化規範となっているのに対して、市場取引とは無縁の伝統的社会では血縁や特定の相手を重視する行動こそが「正義」とされます。アメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブズが「市場の倫理」「統治の倫理」という二つの類型を提起したのは、そうした命題に対応するものといえるでしょう。
分配をめぐる道徳規範には文化差があるとすれば、個別のモラルを統合する「メタモラル」を構想するにはいかなる考え方が適切でしょうか。本書では、ジョン・ロールズの『正義論』などにも熱く論及しているのですが、結論として「功利主義」を挙げています。
哲学者のジョシュア・グリーンは功利主義こそが人類共通の基盤となり得ると考えました。功利主義には固有名詞がないからです。それは「自分を含めて誰かを特別扱いすることなく、人々の平等を前提として『幸福』の総量を最大化しようとする考え方」です。そこで著者は「功利主義の難しさ」を指摘したうえで、グリーンの主張する功利主義に共感を示すのです。
この結論にはおそらく賛否両論あるでしょう。私としては、ここに至るまでの論考が多彩なものであっただけに、功利主義を持ち出す結論にはいささか拍子抜けしたというのが率直な感想です。
しかしそのことを差し引いても、本書における様々な実験結果とそこから得られる知見には驚きや学びが多くあったことは間違いありません。一読に値する面白い本であると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
