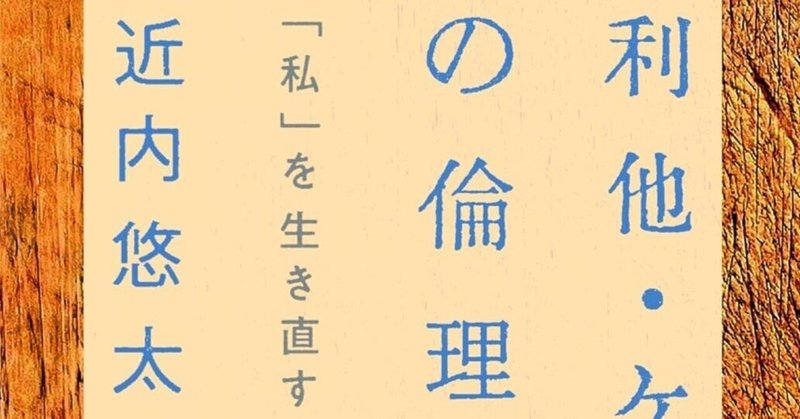
善意を空回りさせる前に読む本!?〜『利他・ケア・傷の倫理学』
◆近内悠太著『利他・ケア・傷の倫理学 「私」を生き直すための哲学』
出版社:晶文社
発売時期:2024年3月
進化生物学や進化心理学の研究では、人類にとって最も適した環境は数百万年前〜数万年前までの環境といわれているそうです。ヒトは、生存の危機に満ちたサバンナで生き残っていけるような心をその頃までに形成し、今日に至ったというのです。たとえば生き延びるのに有利な嗜好──糖質と塩分と脂質に対する強い嗜好──は当時の環境に適していました。しかし今はそのような嗜好は成人病の原因となるので害悪とされています。
通常、環境に適応することができなくなった種の運命は絶滅と決まっているはずです。しかし人類は今も生き延びています。それは何故でしょうか。
進化のプロセス、すなわち環境の変化とそれに応じた適応進化のメカニズムから外れた僕らの心は、互いに助け合い、互いにケアするようになった──。
言い換えれば、ケア抜きには生きてゆけなくなった種なのです。(p39)
前置きが長くなりました。利他心やケア抜きには生きていけなくなった生物種としてのヒトの倫理を考える。これが本書のコンセプトです。この問題の構え方からしてユニークではないでしょうか。
ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」が思考のベースになっていますが、村上春樹や遠藤周作、『ONE PIECE』『鬼面の刃』などの漫画作品をも参照しながら展開する考察は読者を退屈させることはないでしょう。
「善意の空転」という話から説き起こす導入も秀逸です。貰って嬉しいプレゼントよりも、貰うと困ってしまうプレゼントのほうが多いのではないか。その種の戸惑いは贈り物に限りません。相手を励ますつもりで言った言葉がかえって相手を傷つけることもある。このような「善意の空転」は私たちの日常にありふれています。
その背景は現代社会の多様性からみるとわかりやすい。多様性とはぞれぞれの立場が尊重されることです。個人ごとに「物語」があるのです。多様性によって特徴づけられる現代社会では、共通する「大切にしているもの」が見えにくくなっているとも言えます。だからこそ、自分が良いと思ったプレゼント=大切にしているものが相手にはそうでないといったことが発生するわけです。
そこで本書ではケアを「他者の大切にしているものを共に大切にする営為全体のこと」と定義します。この見方からすれば、ケアするためには、その他者が大切にしているものを把握する必要があるということになるでしょう。
それを踏まえて、利他の概念についてもまず「自分の大切にしているものよりも、その他者の大切にしているものの方を優先すること」と定義します。先取りしていえば、本書ではこの利他概念について哲学していくにつれて、利他の概念をアップデートしていくことになり、最終的には他者と関わることで自分も変わるという「セルフケア」の構造を見いだすことになります。
そのような利他やケアの具体例を文学テクストや漫画作品のなかから読み取っていきます。
なかでも『楢山節考』を引いて、利他=セルフケアを記述するくだりは、本書のよみどころの一つといえるでしょう。その作品はよく知られるようにかつて信州の貧しい山村にあった姥捨の風習を素材にしたものです。そこにどのような形で利他心が潜んでいるというのでしょうか?
主人公の辰平は自分の母親おりんを背負って山に捨てに行きます。辰平は立ち去る途中で雪が降り始めたことで気持ちを変えます。「楢山まいりの日に雪が降ると運がいい」という言い伝えがあったことに加えて、おりんが「わしが山へ行く時ァきっと雪が降るぞ」と言っていたから。辰平は、村の掟を破って引き返します。「おっかあ、雪が降ってきたよう」とおりんに伝えるためだけに。
近内は、ここに辰平の利他心を見出します。「振り返らず、掟通りに山を降り、おりんに最期の別れをしなかったことになるであろう未来の自分の傷をケアした」のだと。村の掟に従おうとすることは「自分の大切にしているもの」に違いないのですが、それよりも、傷を負うことになる未来の自分という他者のために掟を破るのです。未来の自分という他者への「セルフケア」が楢山節考の核心にあるというのが近内の読解です。
むろん辰平の一連の振る舞いを利他の概念で説明することには賛否両論あるもしれません。未来の自分とは結局のところ自己のバリエーションではないのかという異論もありうるでしょう。ただ、いずれにせよ『楢山節考』の読解に利他の観点を導入することには斬新さを感じることは確かです。
他者の傷に導かれて僕たちはケアを為す。そしてそのケアの中で、思いがけず自分が変わってしまう。利他が起こり、自己変容に至る。それが僕らに「生きている心地」「自分の人生を生きている実感」を与えてくれる。なぜなら、そのとき僕らは誰かに支配されることも、管理されることもなく、自由になっているからです。「これこそが私の劇だったのだ」という感覚が僕らに生きているという心地を与えてくれるのです。(p281〜282)
自己変容という観点は、東浩紀の『訂正する力』に通じるものがあるようにも思われます。それは第一義として「ものごとをまえに進めるために、現在と過去をつなぎなおす力」と規定されていました。実際、東は本書に好意的な反応を示しています。
前著『世界は贈与でできている』から四年。「受け取る」ことから「与える」ことに主眼を移した本書は、今後、利他やケアを論じる際には外せない一冊といえるかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
