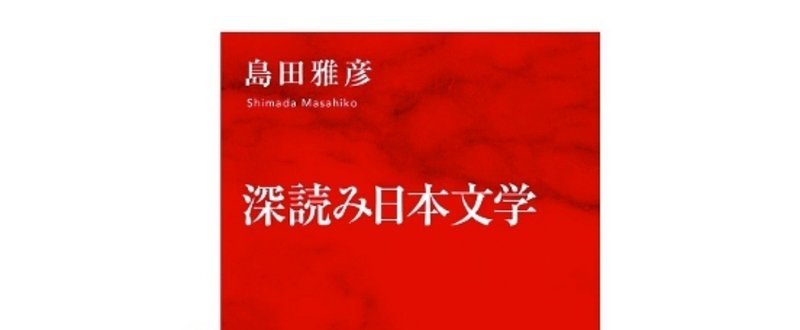
悪人の心には情を、絶望する者には希望を〜『深読み日本文学』
◆島田雅彦『深読み日本文学』
出版社:集英社インターナショナル
発売時期:2017年12月
文学とは実学である。エセ文学的な「言葉の悪用」をする人たちを批判するのが、文学の本来の役割である。文学は神話という最も古い形式から出発して、焼き直しを繰り返しながら時代状況に沿ったアレンジを重ねてきた。
……様々なアングルから文学に光を当て、その特長を言挙げすることから島田雅彦は始めます。期待感を抱かせるに充分な序章。結論的にいえば最後まで私を愉しませてくれた本でした。近頃出た文学論のなかでは出色の面白さといっていいと思います。
日本文化の伝統を支える概念を決定づけた作品として最初に取り上げるのは『源氏物語』です。その概念とは「色好み」。日本式求愛の流儀と呼ぶべき様々な恋愛パターンを網羅して「ジャパニーズ・ドン・ファン」の生涯を描いた作品として読み込んでいきます。
もっともドン・ファンがあらゆる世界に「敵意」をばら撒くのに対し、光源氏は「友愛」を運ぶ点に決定的な相違を見出します。それは狩猟民的態度と農耕民的態度の差異と捉えることも可能だというのが島田の見立てです。
江戸文学を再評価するにあたって導入するキャッチコピーは「ヘタレの愉楽」。それは「色好み」の伝統が江戸期の町人によって受け継がれたスタイルとみなすことができます。
井原西鶴の『好色一代男』は、世之介というデタラメな男の生遍歴を描いた、源氏物語のパロディです。『曾根崎心中』などで知られる近松門左衛門は心中を様式美にまで高めた作家といえるでしょう。彼らの作品はいずれも大衆小説であり、島田は「表紙や挿絵にアニメ調のイラストを多用している若年層向けの小説」であるライトノベルの原型をそこに見出しています。「サブカルチャーのルーツこそ、江戸文化にあると私は考えています」。
近代日本の代表的作家として登場するのは夏目漱石。
日本近代文学を解読することはすなわち、日本人の精神分析をすることに直結するという認識は柄谷行人の『日本精神分析』からの影響を感じます。また漱石と写生文との関係をめぐる批評的論考は、同じく柄谷の『漱石論集成』を下敷きにしたものだと思われます。
漱石の『こころ』に関しては、ヴィクトール・フランクルの「態度価値」を引用した姜尚中の読みを紹介しています。あれやこれや先行研究をいくつも参照している点では、オビにある「常識を揺るがす新しい読み方」というコピーはいささか怪しくなるのですが、それはおそらく編集者の仕業でしょうから、島田に罪はないと考えておきます。いずれにせよここでは道徳的で凡庸な読解は片隅に追いやられていることは確かでしょう。
樋口一葉は「少女文学の元祖」として読者の前に立ち現れます。今風に言えば「ガールズトーク」から生まれたような清少納言の『枕草子』以来の伝統を継承し、それを「一流の文学にまで昇華させた」実例として一葉が読まれるのです。彼女の文体は基本的には文語体ですが、同時代の男性作家に比べると「非常に自然かつ軽やかな文章」であるところに特長があるといいます。しかも現代に通じる社会性を持っています。それは文学史上の一つの「奇跡」ともいえるでしょう。
「スケベの栄光」を文学の分野で輝かせている第一人者として、当然ながら谷崎潤一郎が召喚されます。「自分は変態だという自覚をベースに、日本の『色好みの伝統』と『西洋の性にまつわる最新の科学的・文学的知見』をいいとこ取りして文学化した」というのが島田の見解です。
もう一つ興味深いのは「戦争といっさい関わりを持たない」ことを指摘している点。谷崎は戦争の時代には出番がありませんでした。遠くに空襲の火の手が上がるのを眺めながら『細雪』を書き、『源氏物語』の現代語訳に勤しんでいたのです。それはそれで一つの文学者のあり方を見事に示しているのではないでしょうか。
人類の麻疹としてのナショナリズムを文学史のうえで吟味するというのも今日的な興味深いテーマです。そこで参照するのは、志賀重昂『日本風景論』、内村鑑三『代表的日本人』、新渡戸稲造『武士道』、岡倉天心『茶の本』の四冊。島田によればいずれも後世の日本論の思想的な土台となった作品です。
志賀の本は文字どおり日本の風景を再発見したもので「素晴らしい風景や自然風土があるがゆえに、日本は素晴らしいのだ」というナショナリズムは今日のそれに真っ直ぐ継承されているものでしょう。内村の著作は日本の優れた人材を取り上げることで、日本人のプライドを高めることに寄与したといいます。『武士道』は日本人の道徳意識を高め、それを他国に知らしめたことでナショナリズム形成に大きな影響を与えました。『茶の本』は日本人の美意識や感受性を海外に向けて発信した作品であり、そうした文化的プレゼンスもまたナショナルプライドにとって大きな役割を果たしたのでした。
戦後の文学は「焼け野原の中で、どう生きていけばいいのか」を問いかける作品、もしくは「戦争に従軍し、帰還した元兵士たちの体験録」として始まりました。さらに「アメリカの統治下における文学」があります。
太宰治や坂口安吾ら無頼派の作品が俎上に載せられていますが、私がおもしろく感じたのは小島信夫の『アメリカン・スクール』の読みです。アメリカン・スクールの見学を許された英語教師たちの話で、この作品における「英語」を「日米安保」に置き換えることで現代日本の様相を見ようとする読解はなるほど「深読み」の標題に適ったものでしょう。
〈遊歩者たちの目〉とサブタイトルにふった章では、物語の舞台となる「場所」に焦点をあわせます。漱石の『三四郎』をとっかかりに、武蔵野を描いた大岡昇平『武蔵野夫人』や中上健次の紀州サーガなどに着目。とりわけ中上が描いた一連の「路地」文学を「リアルなファンタジー」と位置づける読みはあらためてこの作家への関心を掻き立ててくれます。
現代文学を読み解く補助線として、世代や経済、階級に注目する論考も一興です。とくに戦後に新しく現れた階級として「主婦」と「学生」に注目し、そこに現代文学の特徴を見出しているのは慧眼でしょう。現代文学が学生と主婦を読者層として想定したことは、社会背景として無視できない要素であると私も思います。
最後にテクノロジーと文学の関係を探ります。本書でも人工知能が重要な論題となることはいうまでもありません。人工知能が最も得意とするのはエンタテインメントだという島田の見方には賛同できます。大多数を相手にするエンタテインメント作品は約束事が多いので、人工知能もそのノウハウを学習しやすいというわけです。むろん純文学に対しても何らかの影響を与えることは間違いないでしょう。人工知能が日本文学のビッグデータから特有の感情や行動を学び、その中からいかなる言葉を紡ぎ出してくるのか。それはそれで一つの楽しみではあります。
ポスト・モダニズムの風が吹き荒れた頃、文学に対して懐疑を示すのが文学者としての定番的しぐさだった時期がありました。しかし冒頭にも記したように本書のスタンスはそれらとは異なります。何よりもそうした島田の基本姿勢が本書に好ましい読み味をもたらしているのだと思います。
文学とは時に不徳を極めた者を嘲笑うジャンルであり、権力による洗脳を免れる予防薬であり、そして、求愛の道具でもあった。文学は好奇心を鍛え、逆境を生き抜く力を与え続けてきた。文学は路傍に咲く一輪の花のように、悪人の心には情を、絶望する者には希望をもたらすものゆえ、非道な時代にこそ必要とされてきた。バラ色の未来が期待できない今日、忘れられた文学を繙き、その内奥に刻まれた文豪たちのメッセージを深読みすれば、怖いものなどなくなる。(p229〜230)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
