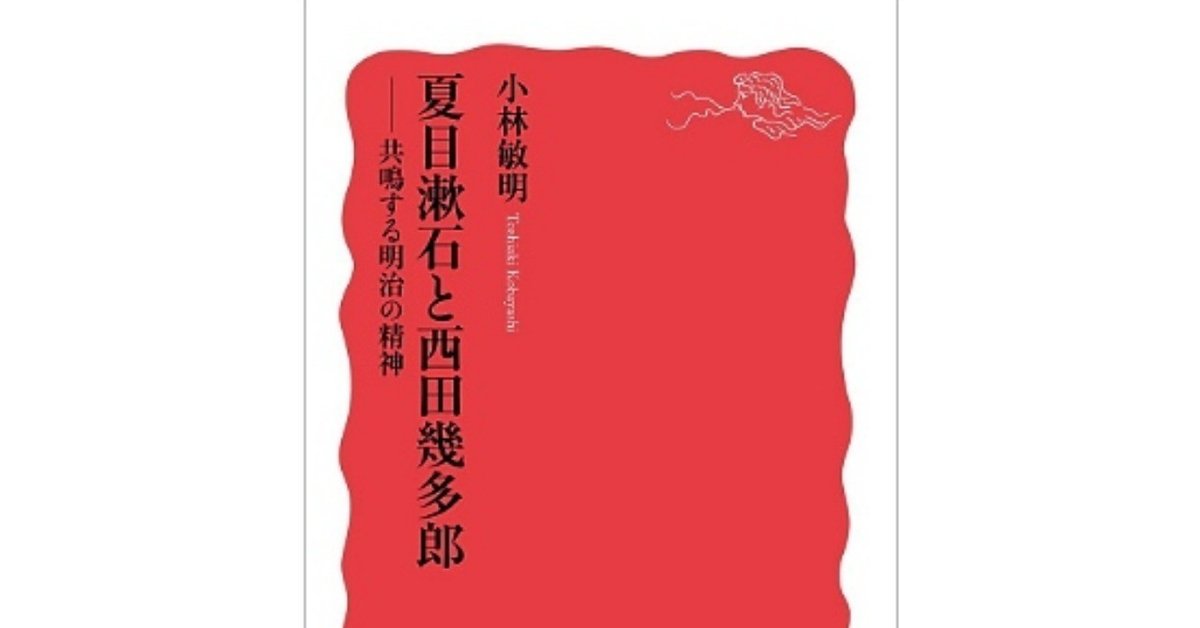
近代日本を体現した二人の同窓生〜『夏目漱石と西田幾太郎』
◆小林敏明著『夏目漱石と西田幾太郎──共鳴する明治の精神』
出版社:岩波書店
発売時期:2017年6月
1901年7月22日、ロンドンに留学していた夏目漱石のもとに、金沢に住んでいた西田幾多郎から手紙がとどきます。その手紙にどのようなことが書かれていたかはわかりません。しかしこのやりとりを糸口に、著者は二人の間に多くの共通点があったことを明らかにし、彼らを包みこんでいた時代環境やネットワークを検証していきます。これは近代日本を体現していたともいえる二人の知的巨人の精神史的評伝です。
漱石と西田は何よりも東京大学の同窓生でした。漱石は1890年に帝国大学文科大学英文科に入学し、三年後には大学院に進みました。西田は1891年に帝国大学文科大学哲学科選科に入学します。選科生とは今日でいえば聴講生のようなもの。ただし在学中は「お互いに顔を知っている程度」の関係でしかなかったようです。
小林はまた二人には「禅」に打ち込んだという共通体験のあったことに言及しています。西田が本気で禅と取り組むのは帝大選科生になってからのことで、1891年、鎌倉円覚寺の今北洪川のもとで修行を始めていた鈴木大拙を訪ねたのが最初。
一方、漱石は友人・菅虎雄の勧めで1894年末から正月明けまで円覚寺に参禅しました。ただしこの時すでに洪川は亡くなっており、西田や大拙とはすれちがいとなったようです。
いずれにせよ「禅」は二人の作品には様々な形であらわれていることは確かです。漱石に関しては『門』において参禅体験が活かされているのは有名でしょう。そのほか『我輩は猫である』『草枕』などの初期の作品にも、多く禅に関する言葉や人名が出てきます。
漱石に比べると西田の禅は本格的。禅における無字の公案を自分の携わる哲学の分野で考えたといっていい。西田は当時の哲学の中心をなす認識論、存在論、判断論、といった分野に「無」を導入しようとしたのでした。
そして、二人はともにベストセラーの著者として文壇・論壇にデビューし、さらには広く一般読者の間にもその名が知られるようになりました。
今でも難解をもって鳴る西田の『善の研究』が広く国民に読まれるようになったのは、当時の新興出版社である岩波書店によって再販されたことが大きい。同時に岩波は漱石の全集をいちはやく手がけてもいます。
個人的にはほとんど直接交流のなかった漱石と西田が、図らずも岩波書店というプリント・メディアの場で出会っていたということ、そしてそのメディアのもたらす力によって、あの難解な『善の研究』という哲学書がベストセラーにまでのしあがったという数奇な縁は知っておいていいだろう。(p127)
ところで、前半では二人に共通する心性として「反骨精神」や「独立心」をキーワードとして論じられています。
漱石にも西田にも「父親の欠落」ともいうべき生い立ちにおける問題がありました。「父親の欠落」によって超自我の形成が弱い場合には、戒めや罰への怖れが少ないだけ自己抑制が弱くなりがちですが、逆にいえば、弱い自己抑制は自己主張や反発心と合流しうる。その観点から、小林は二人に「人並み以上」の反骨精神や独立心を見出すのです。とりわけ西田の反骨心は四高在学中に発揮されました。上からの押しつけ的な校則を嫌って退学処分を受けた挿話に小林は彼の反骨心をみています。
ところが太平洋戦争が近づくと、西田と京都学派は軍部や彼らの周辺の人々に目をつけられます。一種の恫喝を受けながら、戦争体制に協力していくことを余儀なくされるのです。京都学派の戦争加担責任は戦後に厳しい批判の対象となりましたが、その経緯をみると釈明の余地がまったくないというわけでもなさそうです。
いずれにせよ、西田の独立心は戦時においても貫くことは困難だったといえるでしょうか。もし漱石が長生きしていたら太平洋戦争の時代をどう生きただろうかと、つい余計な想像をしてしまいました。
本書では綿密な考証に基づいて、二人をめぐる知的なネットワークをあとづけ、その作業をとおして近代日本の思想的な課題を浮かび上がらせます。
二人を並べて論じることで新たな視座が拓けるというところまではいきませんが、明治日本の優れた知性をこのように比較しながら読み直すことには一定の意義があるかもしれません。
