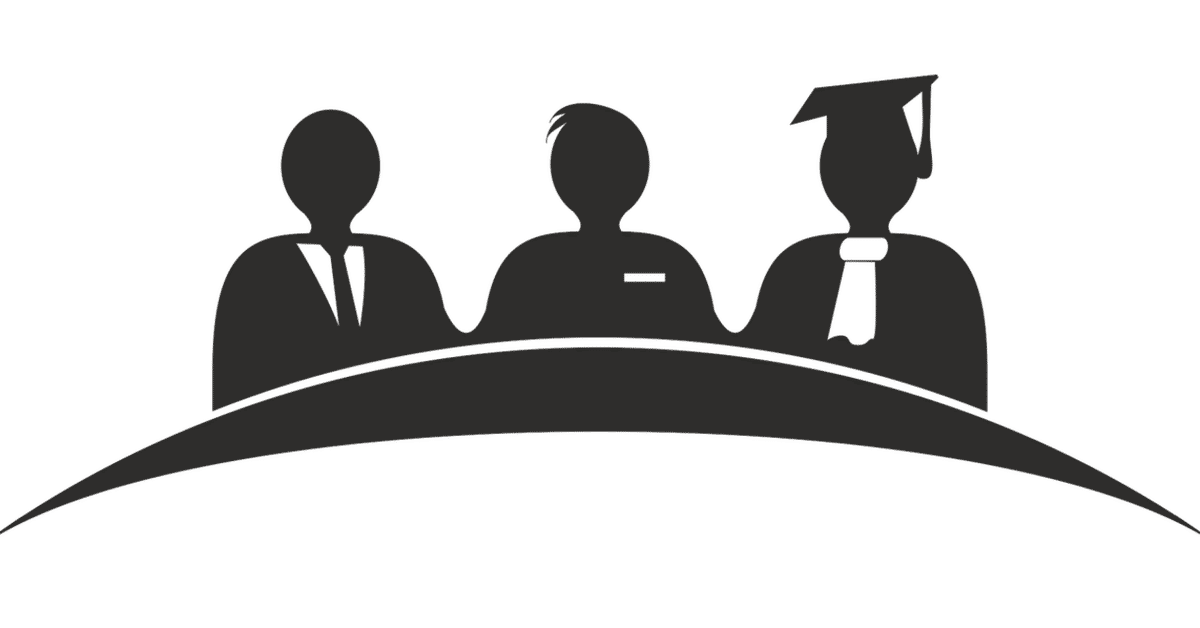
先生
ご近所でも有名な少年がいた。大人でも知らないような国の名前をすらすらと答え、学者でも解けないような問題をいともたやすく解いてしまうような、博識で知恵のある少年だった。そこまでは、ありそうな話だ。博識で知恵のある少年などごまんといる。小さい子どもが大人を驚かすほどの能力を持っているなんて、このご時世、聞き飽きるほど耳にしていることであろう。特筆すべきは、その少年の周囲の人々までもが、驚くほどに有能な人間ばかりだったことだ。問題解決能力に秀で、コミュニケーション力に長けた者ばかりが少年の周りを囲んでいた。少年が博識で知恵のある少年たり得たのも、そのせいだと思うことだろう。この文脈であれば。こうやって予想を覆すことを予感させる記述がなされているということは、当然、そうではない。その逆だ。少年が博識で知恵のある少年であったから、周囲の人間が有能になった。つまるところ、少年の有能さを周囲の人間に伝染させるほどの何かが、少年にはあった。その何かとは、教育力であった。少年を何より少年たらしめたのは、博識だったことでも知恵があったことでもない。ときに幼児を大人顔負けの博識にしてしまうほどの、比類なき教育力があったことである。故に少年は、みんなからあだ名をつけられていた。「先生」という愛称で。
少年は自らの能力を適切に見積もっていた。その探求心も、教育力も、それらがどれだけ平均的なレベルを凌駕しているのかを、少年は自覚していた。そして少年は、教えることが何よりも得意で、何よりも好きだった。博識で知恵のある彼のことなので、将来の夢だって当然に考えついていた。この世の中にあって、自分の特性が最も活用可能な職業。それは「先生」だった。
少年はその後、健やかに成長を遂げる。とある教師に出会い、夢を砕かれるその日までは。少年の夢を諦めさせたのはブラックと言われている教員の労働環境でも、その仕事の難しさでもなく、あるひとりの男性教師の卑劣な行い。それだけであった。男性教師は、表面的には人格者を演じていた。周囲の誰もが、男性教師のことを人格者であると信じて疑わないほどに。誰もが親しみを持って「先生」と呼ぶほどに。その信頼の裏で、男性教師は罪を重ねていた。自分に信頼を寄せる女生徒を監禁、ポルノ写真の撮影・販売、売春、その他、いじめの黙認、いや、それどころか先頭に立って生徒をいじめることすらあった。それくらいしていれば、誰かが男性教師の悪行に気づくはずだったし、気づいているはずだった。はずだったが、誰も声を挙げることはできなかった。声を挙げることがどういうことか、誰もが知っていた。男性教師に実権を握られていた学校という組織の中では、声を挙げることは、社会的に淘汰されることと同義だった。男性教師のクラスになった少年は、そういった事情を知ってしまった。クラスの雰囲気、周囲の教員の雰囲気、それら諸々のものを察して、理解した。男性教師の悪行を。知ったのならば、博識で知恵のある少年ならば、なんとかできたのではないだろうか?あなたはそう思ったかもしれない。当然、少年だって、なんとかしたかったに違いない。それでもなんとかできなかったのは、少年の力をもってしてもどうにもできやしないくらいにひどいありさまだったからである。そうして彼は、陰惨な現実に打ちひしがれ、やがて、教員という職業を嫌悪し、幻滅し、憎悪した。教師そのものが悪いのではないことくらい、少年には分かっていた。それでも男性教師と少しでもイメージが重なる時点で、教員という生き物を嫌わずにはいられなかった。俗に言う、生理的に無理という現象に似ていた。言うまでもなく、その嫌悪感は自分に対しても向けられた。男性教師と同じく「先生」という愛称で呼ばれていた、自分自身にも。
かつて博識で知恵のある少年だった青年は、夢破られ、高校を中退し、他の仕事に就くことを志した。間違っても「先生」などと呼ばれることのないような職に就くことを。高校を中退したとあらば、就職は難しいだろう。ただしそれは一般的な常識であり、一部の有能な人間にとっては学歴などは関係ない。青年の就職活動はとんとん拍子で上手くいき、瞬く間に職場が決まってしまった。
彼が最初に就いた仕事は、一般企業のサラリーマン。嫌がる人の多い、下っ端の営業の仕事だ。ここなら間違っても「先生」などと呼ばれることはないだろうと、青年は考えていた。が、選ばれし者に咲く場所など関係ない。彼は卓越した知識のお陰で顧客はじめ同僚らから次第に人気と信頼と尊敬を集め、あっという間に「先生」と呼ばれるようになってしまった。顧客や同僚から呼ばれるならまだしも、上司や役員にも「先生」などと呼ばれ続けたものだから、青年は心底苦しんだ。青年は、「先生」と呼ばれるたびに件の男性教師の顔を思い出し、それが嫌で仕事を辞めた。
次に選んだ仕事は、システムエンジニアだった。ブラックな職場で長時間労働、こんな社会の底辺のような職場でなら、「先生」だなんて天地がひっくり返っても呼ばれることはないはず。プログラミングだって学んだことはないし、どうあがいても高位のポジションに就くことはないだろう。その予想は外れないはずだった。しかしながら、それは一般的な人間に限った話であった。青年は自らの能力がどれほど秀でているのかを忘れてしまっていた。プログラミングなんてあっという間に身に着けてしまったし、新入社員だったはずが、いつの間にか先輩社員にまで指導を施すようになっていた。彼自身も気づかない間に、である。当然、「先生」と呼ばれるようになったので、嫌になって退職届を出した。周囲の人々は、彼がプログラミングの学習塾にでも転職するのだろうと思いこんでいた。彼が「先生」と呼ばれるたびに、夢を打ち砕いた男性教師の顔を思い出して、憎悪の炎に焼かれそうになっているのを知るよしもなく。
次に彼が選んだ仕事は、研究者であった。知的好奇心を生かすくらいであれば、「先生」などと呼ばれることはないだろう。くれぐれも大学教授のように、学舎で教鞭を振るうといった方向に進まぬよう、人に教えるという作業からは極力遠のいた。それだけ気を付けていれば「先生」だなんて呼ばれることも無いだろう、と、思うだろう。そこを覆すのが天賦の才を与えられし者の運命。青年はうっかりノーベル賞レベルの発見をしてしまい、一躍、時の人となってしまう。そこまでくれば、気を付けていようがなにしていようが関係ない。問答無用で「先生」と呼ばれてしまう。これまでのパターンをなぞらえて、研究者の職を辞した。彼を「先生」とはやし立てる人々は、彼が「先生」と呼ばれるたびにうつむくのは、彼が照れているからだ、と、一切の疑いを持つことなく信じ切っていた。ノーベル賞レベルの発見をしてもなお、謙虚なお人なのだ、と。もちろん、それは的外れな見解だ。その先生という言葉が、彼にとっては何よりも耳障りだったのだ。下を見てうつむくのは、苦悶に満ちた表情を見せて、他人からいらぬ心配を受けたくないからだったのだ。
その後、いくつもの転職を繰り返すも、彼が「先生」という愛称から逃れられることはなかった。作家、政治家、音楽家、消防士、市役所勤め、警察官、外交官、翻訳家、なにをどこでどうしようとも、「先生」と呼ばれてしまう。なにをどこでどうしようとも、知的好奇心旺盛で、教育力に秀でていて、教えることが大好きな己の性からは、逃れようがなかった。
本当に先生と呼ばれるのが嫌になり、彼はホームレスとしてさすらうことにした。それでも彼は、同じ境遇にいるホームレスを、有り余る有能さで救うごとに「先生」と呼ばれた。
「あああああ!もうやめてくれええええ!」
ある日、人目もはばからず、青年は絶叫した。「先生」と呼ばれることの呪い。生まれ持った性分。死にたくなる。そんなことを考えると、ほらまた、哲学者みたいね、なんて、結局は「先生」呼ばわりされてしまう。もううんざりだ。「先生」と呼ばれるたびに、あの憎き男性教師の顔がよみがえり、憎悪の炎が身を焦がす。
幾度となく転職を繰り返し、なかば「先生」と呼ばれないことを諦めていたころ、彼は医者になった。いかにも「先生」と呼ばれそうな職業だったが、もうどうにでもなってしまえと思っていた。すでに投げやりな姿勢になっていた。そんなある日、病院にひとりの男が意識朦朧の状態で運ばれてきた。よく見ると、どこかで見たことのある顔だった。彼は、このままでは余命幾ばくも無いと思われるその男の手術をかって出た。その男は、かつて自分の夢を打ち壊した件の男性教員だった。「手術しても治せなかったことにして、こいつを殺してしまえば、私は先生と呼ばれても苦しまずに済む。教員になっても問題ない。やっとこの苦しみから解放されるのだ」青年の心の中は、希望に満ち溢れようとしていた。「それでは、手術を開始する」
手術が終わって数日後のある日。彼はある病室にて患者の診察をする。ゆっくりと目を覚ました患者は、優し気な表情で彼を見つめる。「ああ、君はいつぞやの」男性教師は生きていた。いや、正確には生かされた。青年は結局のところ、男性教師を殺すことなどできなかった。殺したいほど憎い相手の命をその手に握ったとしても、それを握りつぶせる非情さなど、青年は持ち合わせていなかった。持っていたのは、優秀な指導者が、子どもたちの手をやわらかく握るときのような、そんな健やかな優しさだけだった。
「お久しぶりです」
青年はベッドの上の男性教師に優し気な声をかける。
「医者になったのか」
「ええ、まあ」
「やっぱり君は、先生だったね」
男性教師の言葉を耳にした青年は、自分をあざけるような微笑みを見せながら、病室を去っていった。ベッドの上に横たわる男性教師は、青年の去り際の、哀愁を帯びた横顔を、印象深く瞳に焼き付けたのであった。
サポートいただけると、作品がもっと面白くなるかもしれません……!
