
【旨そう、から始まる関心】春陽会誕生100年 それぞれの闘い 東京ステーションギャラリー
「春陽会誕生100年 それぞれの闘い 岸田劉生、中川一政から岡鹿之助へ」
日展、二科会や一水会などなど。
会派美術…と一口に言ってしまうと、「なんだかなーどうなのかなー」とか思いながら春陽会の解説を読み進むと各個人おのおの割と作風や表現が自由だったらしく、当時としてはちょっと面白い洋画団体ということがわかって見に行くことに決めた。
あとは岸田劉生の作品群とキービジュアルだった魚の絵に描かれた毛ガニが気になって。今年はカニに惹かれる。
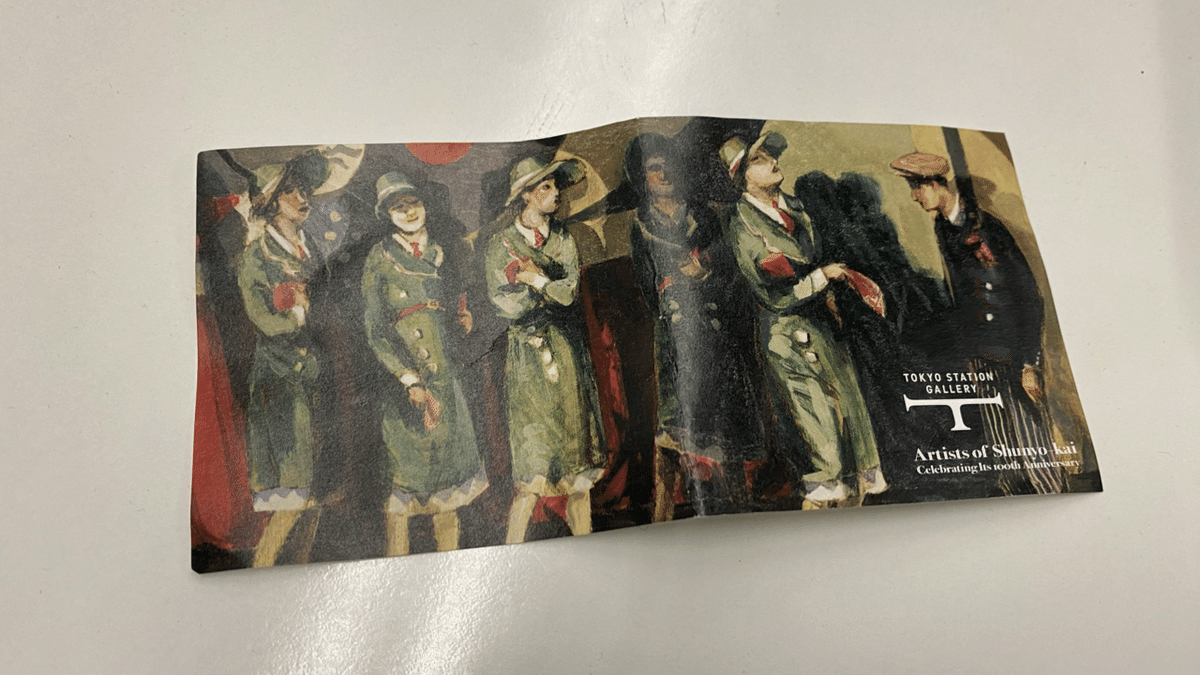
読売アンデパンダン展側からの近代、現代美術史の著書をよく読んでいたせいで「会派美術=古く、打破の対象」と思っていたフシがある。
でも「具体」だっていうなれば芸術団体だし、何かを表現するための大きなうねりを作るのに個人活動だけでは難しい時代もあったのだろう。
あ、ハイ・レッド・センターもそうか。
今風に言うならアートコレクティブ。
さて、気になった作品を以下に取り上げる。
岸田劉生の肖像画の違和感
この方、風景画描くととてもすっきりとしたパキッとした絵を描く。
重要文化財の切通の絵が著名ですね。私もあの空の青と坂道の絵は好きだ。
しかし肖像画である。
なぜ、手をこんなにちんまりと描くのだろう。
新聞の社会欄に風刺画をして描かれる政治家の絵のようでもある。
急に三頭心というか首から下がギュンと縮むのはなぜか。わざとか。
肖像画なんだけど立派さとか偉大さから急に乖離してくる岸田劉生の人物画。見ながらプッと笑ってしまうことがある。
そしてそこも魅力だと思う。

椿貞雄の冬瓜
冬瓜。よいですね、たっぷり水分を含んで今にもゴロンと転がりそうな。
でも冬瓜ってあまりまるごと売り場に無いし、改めて見るとでかいな。
なんでしょうね、この画面のおかしみというか。
どっしりしたモチーフって描いてて楽しいのかもしれない。
この椿貞雄の冬瓜を見てふと思い出した。
私の母は油絵を嗜む人だが、冬瓜を描いたことがあった。それを面白いと思ったのか、父が「おい冬瓜の絵を描いてる人いるぞ」と椿貞雄の個展開催情報を仕入れ、千葉市美まで見に行っていた気がする。5,6年前のことだ。
もしかしてこの冬瓜の絵、父と母が千葉市美に行った際に展示してあったやつか!?と思って出品目録と照らし合わせたが、今回私が見たのは豊橋市美術館蔵の冬瓜図で、千葉市美の個展では出展されていなかった様子。
しかし、冬瓜だけで結構な枚数を描いている。
冬瓜を見ると、母がコンソメとベーコンで煮てくれた冬瓜の煮物の味を思い出すのだ。自分でも作ってみよう。

メインビジュアルの岡鹿之助「魚」
あわーい描写ながらも美味しそうな魚たち。
お皿の模様もとっても素敵で、刺し身というより、アクアパッツァでもいける!という感じが「モダンさ」なのだろう。
でもね、手前の引き出しがうっっすら開いているのが気になるのだ。
閉めたい。ピッタリと、閉めたい。
この絵の甲殻類に惹かれたわけだが、実際の絵をみるとそこまでカニ的な主張がない絵だった。もっとカニに押されるかかと思ったが実物を見るとその違い、画面全体のバランスの良さを思い知ることとなった。
会派美術という概念も取っ払って
最近ここまで持っていた知識や先入観を一度疑うのも面白いと思っている。
もちろん合わないものは合わないし、惹かれないものは惹かれないのだけども。
出てくるとき「ファーーー!!良いものを見たー!」
とフワフワすることもあれば
「やっぱり合わねぇな、わからんわ」
と首を傾げなら出てくることもあるけれど。
いろいろグルグルとしながら結局、足は美術館へ向かう。
実物を見ないとわからない、ということだけは自分の中で確かなことだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
