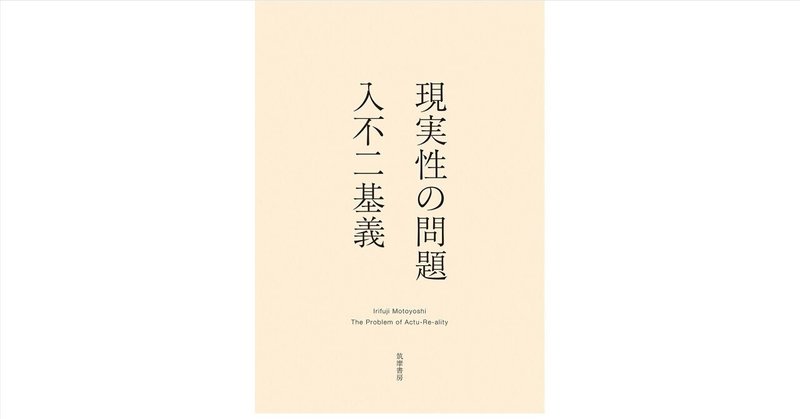
入不二基義『現実性の問題』「現に」という現実性の、記述可能性、認識可能性、存在可能性
はじめに
以前所感を書き、別noteで円環モデルを紹介し、さらに別noteで「現に」という現実性を解説した、入不二基義『現実性の問題』を読み解いていく。
「現に」という現実性を解説した際にも登場したが、「現に」という現実性は、記述された内容や輪郭とは独立のものである。だが、そのようなものが存在していると、どのようにして言えるだろうか。本noteでは、私から三つの疑問を提示し、それに対応する入不二の論旨をまとめる。
三つの疑問
改めて「現に」という現実性に対する3つの疑問を提示したい。
1.語りえるのか(記述可能性)
2.認識されえるのか(認識可能性)
3.存在しえるのか(存在可能性)
そして、入不二の答えを総括すると、「それ自体では語りえず、認識とは無関係で、だが存在する」ということになる。
内容や輪郭がないため「語りえず」、眼前に現れること(現前すること)も現れないこともあるために認識とは「無関係」で、「存在する」、ということになる。
記述可能性
まず、記述可能性について。
副詞としての「現に」だけでは、何が存在するのかについての情報は何もない。記述するべき内容がないため、物理的な存在のみならず、心の中のイメージすらも指し示すことができない。「現に」ということ以上の内容は、何も含まないのである。したがって、「現に」という現実性だけでは記述すべきものがない。「現に」という現実性は、何か内容を伴わなければ記述できないのだ。翻って、入不二は「現に」という現実性に、内容や輪郭を伴うことを「受肉」と呼ぶ。「現に」という副詞的な力に、内容や輪郭を伴う「受肉」を通して初めて記述が可能になるのだ。
「受肉」した暁には、内容や輪郭を伴い、命題や言葉で表現することができる。そうした命題や言葉は、他の「可能性」に取り囲まれることになる。例えば、「現にソクラテスは哲学者である」という命題は、「ソクラテスは哲学者ではない」や「ソクラテスは日本人である」などの、現実ではない他の可能性を背景にもつことになる(円環モデルの右半分に相当する)。
また、入不二は記述できない存在形態として、「潜在性」の場を想定する。「潜在性」とは、何かが私たちの眼前にありありと現れる以前の、存在形態である。記述以前の存在形態であるため、それは何であるかは言われえないし、何が現前するかも確定もしていないため、固定的な状態をもたない。かと言って、まったくの虚無ではなく、様々な現象を作り出し得る産出力をもったものとされる。入不二は、はっきりと現前していない漠然とした「感じ」でしかない「潜在性」も、「現に」の作用域で存在していると主張する。これが「潜在性」という独特の存在様態なのだ(円環モデルの左半分に相当する)。
認識可能性
次に、認識可能性について。
入不二の「認識」に対する理解は、「ありありと現前すること」=「認識」という具合である。そして、記述可能性とは独立している点も特徴的である。ゆえに、「ありありと現前しているが記述できない」という組み合わせも可能だと考えている(同書195頁)。「ありありと現前しているが記述できない」ものとは、まさに「潜在性」である。入不二にとって「潜在性」は、記述できないが認識できるものなのである。
しかし、入不二の記述にはダブルスタンダードに見える箇所がある。それは、「現実性の「受肉化」は、認識論的な水準へ引き下ろされることに相当し、現実性と潜在性それぞれの「脱受肉化」は、存在論的な水準へと引き戻されることに相当する(同書79頁)」と記している箇所である。「受肉化」は内容や輪郭をもち、記述可能になることを意味するが、ここでは「受肉化」が「認識論的な水準に引き下ろされる」ことと同義とされている。つまり、「記述可能性」=「認識可能性」という主張に見て取れる。
整合的・好意的に解釈するならば、「記述と認識はもともと関係がないため、受肉化にあたって現前することが伴うことはあくまで相関関係(外的な関係)であり、因果関係(内的な関係)ではない」ということなのかもしれない。確かに、クリアな認識は記述内容を豊富にもつであろうし、曖昧な認識では記述できる内容が乏しくなるだろう。認識と記述の双方の豊かさはスペクトラム的であり、しかもそれぞれ正比例して豊かになる。だから、因果関係を読み込むのは自然な過ちだとも言える。しかし、それはあくまで過ちであり、認識できることと記述できることは独立したものであるとして、0 or 1のデジタルで考えるならば、「記述0・認識1の潜在性」と、「記述1・認識1の受肉化」は両立する、と考えることもできる。
とはいえ、「記述」と「認識」にまつわるこの混乱は、何か重要なことを示唆しているように思える。
存在可能性
最後に存在可能性について。
入不二は、受肉なしの「現に」という現実性や「潜在性」のような、語りえることから逸脱した存在を認める。また、受肉なしの「現に」という現実性や「潜在性」が、認識できることとはまったく無関係に存在することを認める。このように、認識から独立した存在を認める点において、超経験的な形而上学的な色合いが強いと言えるだろう。しかも、それは「記述不可能」という特色をもつため、神秘主義的な色合いすら帯びている。例えば、「決して認識できないペガサスが存在する」という主張は、信じるか否かは別にしても理解自体はできるが、「まったく記述し得ない何ものかが存在する」という主張は、記述できない以上、何を主張しているのかすらわからないのではないか、という疑念が残る。しかも、入不二によれば、それは語りえないが認識することすら可能なのだ(「現に」の作用下にある、「潜在性」が該当する)。
だが、そういった存在が、認識はおろか、存在できるかについても、一考の余地があるだろう。というのも、そういった形而上学的な存在は単なる幻想であり、受肉化した内容から派生的に生まれたものが「現に」という現実性や、「潜在性」という概念である、と主張することもまた可能だろうから。その場合、真に存在するのは「可能性」の領域のみ、となり、キータームは「記述可能性の絶対性」ということになるだろう。これはまた別の機会に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
