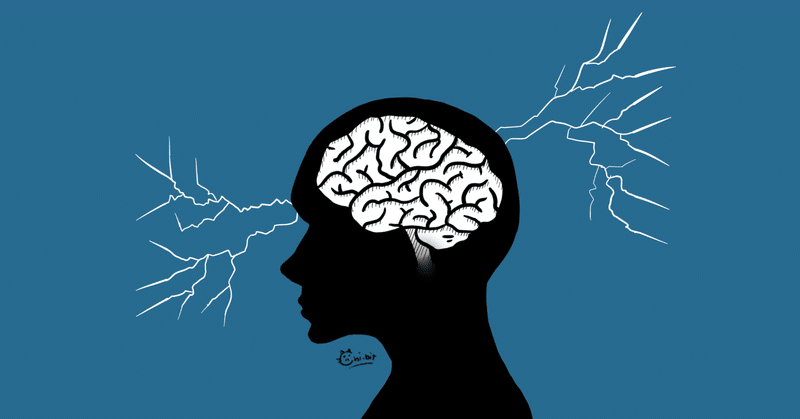
【読解】木島泰三「心と身体はどのような関係にあるのか?」
はじめに
本noteは、『現代思想2024年1月号 特集=ビッグ・クエスチョン(青土社)』に所収された、木島泰三「心と身体はどのような関係にあるのか?」を紹介するものである。木島は、古代の哲学者アリストテレス、近代のデカルト、現代のデネットとその対抗馬のチャーマーズを参照し、哲学史を概観しながら、難問「心身問題」の出自と現状を紹介している。
概要と要約
現代の「心身問題」は、「魂なき機械論的な世界から、どのように魂や意識といった存在を説明するか」という問題だが、古代のアリストテレスの発想は逆だった。アリストテレスは、まずあらゆる存在が魂の特性である「合目的性」=「目的をもった」存在であり、その目的に沿って、物体の運動なども説明できると考えていた(目的論的自然観)。デカルトの活躍した近代になるとこの世界観は覆され、魂なき機械論が支配的になった。だが、目的があるかのような生命の独特の振る舞いが説明困難になる。しかし、ここでダーウィンの強力な自然選択説が登場する。(本論文では紙幅の関係か、自然選択説のやさしい解説がないので本noteで補足する。なお、木島泰三『自由意志の向こう側』第5章に説明がなされているようだ)自然選択説は、数多誕生した生物のうち環境に適応した生物が生き残ったというものである。キリンの首が長いのは、首を長くしようとしたのではなく、首が長い形質を偶然もった動物が、環境に適応できたために生き残っているに過ぎない。それを、あたかも首を長くしようとするキリンの意志や目的を誤って読み込んでしまうがゆえに、機械論を逸脱するような魂や意識なるものの存在を重ね描いてしまうのだ。ダーウィンの発想は、目的論的自然観を機械論の範疇で解釈するよう迫ることになった。
現代のデネットは次のようなスケッチを描いた。心と呼ばれるものは、適応度を最大化する機能のことを指している。心は生存に役立つためのいわゆる善悪の行動の判断を司る。善い行動が生存に有利で、悪い行動が生存に不利、という具合だ。これが疑似的な目的論=機械論の範疇で心を理解することになる。我々が心があるとみなしている生命には、ミクロの構造に単純な演算を行う回路が組み込まれている。たとえば神経系、とりわけ脳は複雑に見えるが、ミクロの視点に立てば単純な電気回路(ニューロンの発火の有無)が集積されたものである。その電気回路たちのOn/Offのパターンを集積が、最終的な行動や判断のマクロなものになる。つまり、行動や判断などのふるまいは一見して心の存在を予感させるのだが、そこにあるのはただの電気回路でしかない。
ただ、これで終われば「心身問題」は生まれない。デネットに反論した対抗馬がいるのだ。チャーマーズは「意識のハードプロブレム」という概念を提唱し、機械論をはじめとする物理主義では、意識について取り扱えないと主張した。チャーマーズは「哲学的ゾンビ」と呼ばれる思考実験を前面に打ち出す。ごくふつうの人間に見えるが、意識だけが欠けているゾンビを考えることができる。脳の機能やふるまいが正常だったとしても、意識がない人間を想像することができる。つまり、デネットがいうような脳機能や判断や行動を行う生命であっても、意識がまったくない、ということが考えられると主張したのだ。これは、物理主義との決別であり、物理的な世界を超えた範疇に意識や心と呼ばれるものがあるということを意味する。
木島は最後に「ビッグ・クエスチョン」のデフレ的解消と題して、心身問題のような「ビッグ・クエスチョン」は単なる目くらまし、火がないところに火をおこすような「トリック」である可能性を考慮すべきだと、警戒を促す。これはチャーマーズのような、神秘的な存在を守ろうとする立場に対する警戒と読むべきだろう。私たちは難問への答えとして、壮大かつ重大なものを求めがちである。しかし、一種の疑似問題かもしれず、トリックを暴いてしまえば陳腐なものなのかもしれないのだ。
改めて、意識や心とは何か
さて、意識や心と呼ばれるものの両極を概観してきた。一方は物理的なもの、もう一方は、物理的なものを超えたものである。前者が正しければ、私たちは観察が可能なもののうちに意識や心というものを見出す。例えば、脳死が人の死とされて久しいが、これは脳のある特定の機能が失われたら、生命としてその人が失われたことにする、という発想である。だが、違和感を禁じ得ないかもしれない。脳死が人の死になったのは、法令によって定められたお約束である。この世界の真理なのであれば、このような規約が必要なのだろうか?例えば、水がH2Oであることが規約なのだろうか?この周波数の波を赤色とするのは規約なのだろうか?だが、想像に反して現代の科学哲学では、真理とは暫定的な規約であると考える。つまり、最も有力で効率的で合理的な理論を真理とするが、よりよい理論があればアップデートされる、という考え方である。デネットをはじめとする物理主義者は、意識を観測可能な水準で理解する以上、この科学の規約からは免れないし、彼らはそれでよいと思うだろう。意識や心の問題を神秘のベールから解き放ち、科学に仕立て上げたのだ、と。こうなれば、意識や心が目先の実践的な場面でも登場するようになる。例えば、AIは意識をもつのか?人権はないのか?だとか、昆虫は心をもつのか?だとか、目の前の肉親は本当に死んでしまったのか?だとか。これはチャーマーズには決してできない芸当である。チャーマーズは役立たずの懐疑論者のレッテルを貼られるだろう。そういった意味で、実用尊ぶ価値観が支配的であれば、間違いなく物理主義者が優勢である。
だが、ゾンビの思考実験を思い出そう。あの思考実験での直観を否定できるだろうか?すなわち、眼前のなんの変哲もない人間に意識がないかもしれない、ということに。一度でも真剣にこの思考実験をしたことがあれば、この直観を否定することは難しいだろう。
私たち実用的な意識・心の概念と、直観的に理解している意識・心の概念のギャップを行き来することになるだろう。実用は私たちに判断を迫る。眼前の脳死の肉親を見て人工呼吸器を外すか否か、人間と同じ機能をもつ故障した“親しい”ロボットを廃棄するか否か、私たちは判断を迫られる。その判断に際して物理主義は大いに役立つだろう。だが、本当にその判断は正しかったのか?そう不安になるのは、もしかすると、意識や心が物質を超えた神秘的なものであるという直観を、私たちが引きずり続けているからなのかもしれない。
さて、もっと不思議なことがある。意識や心が物理的であれ、神秘的なものであれ、なぜそのような考えが成立するのか。デネットが否定した、意識や心の存在は、まったくの意味不明な文字の羅列ではない。反対者のデネットですら、その概念を有意味なものとしてその世界観を理解し、その上で否定しているのだ。そうでなければ、いったいどのように否定できるだろうか。デネットはその存在を直観的には理解しつつ、別のものに還元して説明しているに過ぎない。だから、難問がいかにデフレ的に解決されようが、その中心には必ず、より直観的で根源的な概念が鎮座していて、それ自体の謎は増えることがあっても減ることはない。そこに直接手を伸ばすことは、やはり難しい。だが、ここをこそ考え始めることこそが、哲学の真骨頂と言えるだろう。それは科学の仕事ではないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
