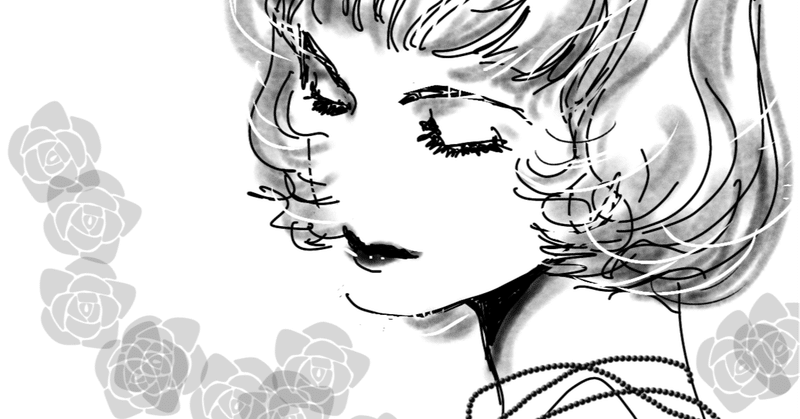
大人になれない僕たちは 第7話 写し鏡
似ているものに、人はどうして惹かれてしまうのか。
「一つ、お前に話をしてやる」
笹原は、自分が発掘したお笑いコンビに熱を入れ過ぎている。マネージャーとして優秀だからこそ、社長として言わなければいけない。
「男は、一人の物書きを見つけた。小説家を目指していたその男は自分の夢を諦め、編集者として彼を育てようと思い、それからの日々をその物書きに費やした。物書きはすぐに実力を発揮しだした」
笹原は、黙ったままだ。
「その男は欲が出る。物書きにあぁだこうだと助言し、コントロールしようとした。諦めていた夢をその物書きに重ねるように。物書きは、どんどんその男が窮屈になった。自信を失った物書きは、その男から離れ、二度と小説を書くことはなくなった」
長い説教に、笹原は、こんなに一生懸命だというのに何が不満なのかと俯いている。
「お前がやっていることは、その男と同じことではないのか」
その言葉を聞いて、笹原は逃げ出すようにオフィスから出て行った。
「あぁ、大丈夫ですかね」
青田が笑う。青田は、笹原と違いどこか冷めている。世の中を斜めに見ていて、ある意味、ゲームのように仕事をしてお金を生み出してくる。事務所としては、青田の存在は有難い。青田がいるから、周りが好き放題することができるのだから。
「今の話、誰の話ですか」
「さぁ」
編集者をマネージャーに、物書きを歌手とすれば、私の実話になるとは言えなかった。
20年ほど前の私は、自分の夢を彼女に重ねて見るようになった。操り人形にしてしまったのは、私のせいだ。彼女の才能は、開花することなく散ってしまった。笹原には、同じように間違えて欲しくなかった。
「俺、追いかけた方がいいっすかね」
「好きにしろ」
青田は、後を追う。あいつなら、うまく笹原を慰めるだろう。
笹原は、昔の自分に似ているところがある。あぁ、また重ねてしまったかと、成長しない自分が情けなかった。
今は、屋上から見える看板に彼女はいる。彼女は、私の手を離れ、今は違う世界で活躍していた。
私の夢は、ミュージシャンになることだった。10代からバンドを組んで音楽に明け暮れた。才能があっても消え、現実世界に引き戻されていく人間を山ほどみた。そんなやつらは口を揃えてこう言う。
「運がなかったんだ」
自分もその一人だ。そう思わないと前には進めず、気持ちを片付け、知り合いの紹介で裏方にまわることにした。マネージャーとしての才能は、確かにあった。私は大手事務所でそれなりに力をつけて、今はこうして小さいながらに芸能事務所を立ち上げている。
若手社長、そう呼ばれることに抵抗はある。まだまだ新参者だと、言われているような気がした。
看板の彼女は笑っている。彼女はもう、歌わない。モデルとして花開いた彼女の人生は、満足いくものなのか。私は、そう思うことですら、厚かましいような気がしていた。
夢を捨てなければいけないとき、果たして何を手放せば、前に進めるのだろう。捨てたはずの夢が、ふっと顔を出すことがある。そんな時は、今の自分を見失いそうで怖くなる。
私は彼女に惹かれていた。きっと彼女もそうだろう。どこかですれ違った二人は、もう重なることはない。
彼女と一緒に、大きな世界を見てみたかった。彼女は、私とは違う世界を、今は一人で見ている。取り残された私は、心の奥に穴が空いたままだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
