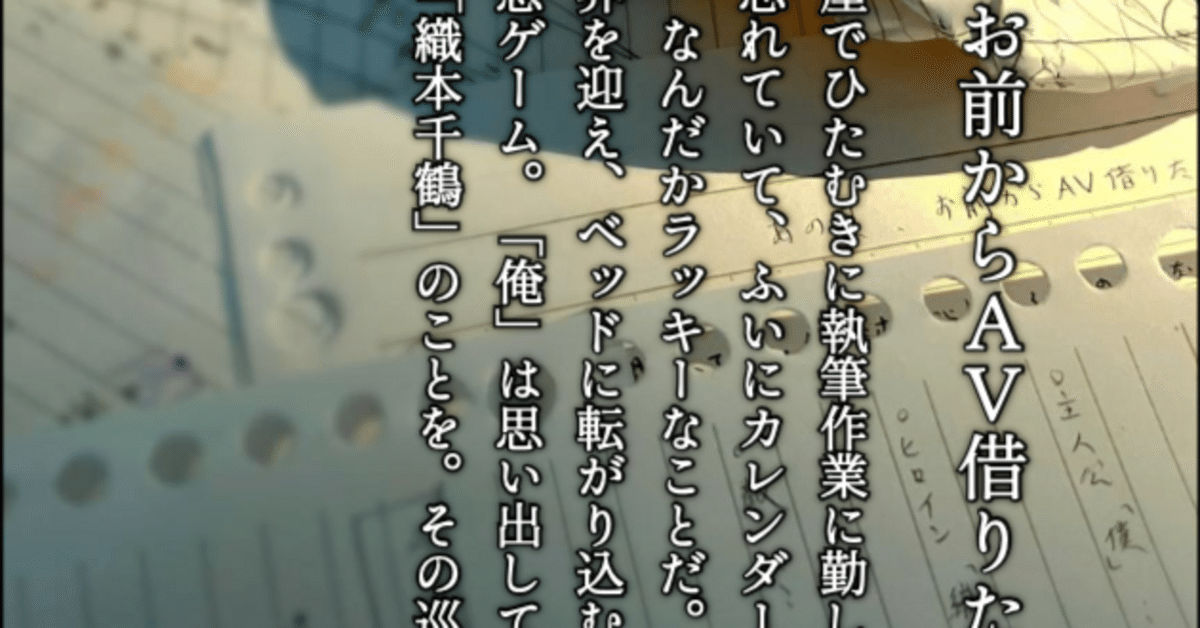
あの夏、お前からAV借りた。 / 虫我
この小説は、総合表現サークル“P.Name”会誌「P.ink」七夕号に掲載されたものである。本誌は2023年7月7日に発行され、学内で配布された。
1
カーテンは閉め切っていた。ヘッドホンから流れる名前の知らない曲が、外界の音を遮る。現時刻が昼なのか夜なのか分からない。ただ机上のモニターと手元のタブレットだけが、真っ暗な部屋の唯一の光源だった。
ペンを動かし、背景のパースが崩れていないかを確認する。左端の描き込みに納得がいかず、その箇所をアップにする。ペンを走らせ、また全体図を確認する。その作業を何度も繰り返した。初めよりかは良くなったと思う。が、疑問がよぎる。
果たして本当にこれで良いのだろうか。
ふと時間が無為に過ぎてると感じ、焦る。モニター端の時刻を見ると、すでに一時間が経過していた。急いで、タブレットの下敷きにされていた黒いノートを取った。ページをめくり、ネームに目を通す。次のコマの背景を、詳細に適切に想像する。頭の中でできあがった世界を三百六十度見渡し、一カットを決定する。空想を形に、ペンを走らせた。
線、線、線——。
作業中は無心が好ましい。余計な思考は絵を鈍らせるからだ。
そして、それが自分に起こっていると気づく。ペンを握った手の指と指の間が汗で滲む。
ノートに綴ったプロット。ストーリーはあれで良いのだろうか。主人公の心情に矛盾はないだろうか。展開がありきたりではないだろうか。描写が甘くはないだろうか。逆に詰め込み過ぎていないだろうか。
あれで本当に面白いのだろうか。
背中に嫌な汗が流れる。ペンを持ったまま、冷房の温度を二度下げる。再び画面に戻ると、自分が今どの部分に取り掛かっていたか忘れかけていた。しっかりしろ。そう自分に言い聞かせ、手を動かす。しかし、頭の中はさっきの自問自答を引きずったまま、煩悶としていた。Tシャツの汗を吸って肌にへばりつく感覚が苛立たしい。焦りは頭を支配し、ついには手先まで侵食した。
線がブレる。
それを機に、俺は乱暴にペンを置いた。ため息を吐き、目頭を押さえ、熱くなった瞼の疲れをとる。腕を脱力させ、天井を見た。軽いめまいに襲われる。
「……今日、何日だっけ」
独り言にしては小さく、がさついた声。自分がここ数日間喉をまったく使っていなかったと自覚する。
壁に張られているであろうカレンダーの方向を見た。光を浴び続けた目は、暗闇に慣れることなく、カレンダーの小さな文字を読み取ってはくれなかった。諦めて、タブレットをスワイプする。
七月七日。四時四十四分。
ぞろ目のフルハウス。
運を使うなら、こんなところじゃなくていいのに。
七月七日。何かの記念日だった気がする。思い出せない。自分の創作物以外のことを思考した瞬間に頭痛がした。これは、いつもの作業終了の合図だった。電源を落とすのも億劫で、電子機器をそのままに、ベッドに転がり込んだ。やわらかな布団に吸い込まれると同時に、確かな重力を感じた。手先の端から沈むような感覚。疲労は睡魔を呼び寄せ、次第に意識を泥のように融かしていった。
七月七日。
半ば夢の世界に入り込みながら、俺は連想ゲームのように、あの夏を思い浮かべていた。七月七日。七夕だ。短冊を書く。願い。織姫。
織本千鶴。
思い出す、彼女のことを。
彼女と出会ったのは、雲一つない晴天の日だった。
2
俺はサークルなんてものには入らなかったし、勿論友人と呼べる人間はひとりもいなかった。妄想を広げ、スマホのメモ帳に描き込んだり、つまらない講義には、後ろの席でパソコンを通して映画を見ていたりした。それが俺の日常だった。
「その映画、面白い?」
その言葉が自分に対してかけられたものだとは思わなかった。
イヤホンを外し、横を見る。そこには見知らぬ女性がいた。
「だから、それ、面白いの?」
彼女は俺の方を向きながらそう言った。授業態度に対するお咎めではなく、単なる彼女の興味関心から発せられたものだと直感する。
対人関係に不慣れなこともあり、声が裏返った。
「……いや、あんまり」
とっさに出た言葉は本心だったが、そのときの自分の頭の中では、彼女が何者であるかという問いが高速展開されていた。彼女をもう一度はっきりと見る。ハーフアップの団子は地毛っぽい茶色。白のフリルブラウス。ベージュのスカート。ふわふわとした雰囲気で、他人の警戒を簡単に紐解いてしまうような人相だった。
なんとなく織姫を連想してしまう。
脳内検索結果はゼロ件。類似する人物さえ出てこない。
しかしそもそも、大学に入ってから誰のこともよく知らないなと、ふと思い直した。
「ふーん。そうなんだ。君、熱心に見てたからさ」
「いや、授業があれだから」
と教授の後ろ姿を指さした。
「確かに言えてるかも。……ねえ、どの映画が一番面白かったの?」
「え?」
「だって君、いつも見てるでしょ。授業中」
そう言って、彼女は笑う。
よく見てるんだね、俺のこと。
このセリフはどこかで使えそうだ。なんて思いながら、何も言えず、ただ彼女の笑顔に目を奪われてしまう。
彼女こそが織本千鶴だった。
次の週も彼女は俺に声をかけ、映画の話題で盛り上がり、授業を終わっても語り続け、さらに翌週には授業をすっぽかして映画の話をした。
そんな日々がしばらく続いた。
俺の日常に彗星のごとく現れた、非日常。
正直言って、楽しかった。異性という特別な存在が目前に顕れたということもあるが、それ以上に、話が通じるということが、たまらなく嬉しかった。彼女の口からとあるマイナーな監督のデビュー作が出てきたときは驚きと共に高揚し、嫌いな監督が一致したときは、思わず運命というものを信じてしまった。
「私のおすすめさ、配信してないんだよね。円盤でいいなら貸すけど」
そう彼女から手渡された映画があることを思い出した。
引き出しに眠っていたDVDプレイヤーを引っ張り出す。埃を払い、段ボールを開ける。電源ボタンを押すと、淡く光り出した。動かないという心配はなさそうだった。
鞄からDVDを手に取る。ジャケットには、屈強で彫りの深い顔の三人の男が写し出された。
あらすじもジャンルも事前に知りたくなかったので、早々と、しかし丁重にディスクを取り出しセットする。虹色の銀盤が黒の機械に飲み込まれていった。
ディスプレイに映像が流れ始める。
その映画は、街頭インタビューのような形式から始まった。なんとなく洋画だと思っていたが、実は邦画なのかもしれない。見慣れたような都会が舞台で、映像に写っている女性が日本人だったからだ。
短いやり取りを交わし、シーンが切り替わる。どこかのホテルらしき屋内。
俺は、そこで違和感を抱いた。
それはつまり、端的に言うと、作品の雰囲気を感じ取れなかったからだ。結構な数の映画を見てきたと自負しているが、冒頭から数分経過しても、これほど何の映画か分からないものは初めてだった。まるで拙いホームビデオでも見ているかのようなエンタメ性のなさ、逆に溢れるリアリティ。これまで見てきた映画のどれとも毛色が異なっていた。
「なんだ、これ」
しかし、何故だろうか。既視感だけはあった。映画にしては新しすぎるが、俺の脳内ではある種の懐かしさすら覚えていた。
そして、違和感の正体に気づいたのと、映像の女性がひとはだ脱いだのが同時だった。
「AVじゃん、これ」
俺はそのとき、あまりの衝撃に茫然とし、ただそれを眺めるしかできなかった。そうしてしばらくした後、大自然を感じる鳴き声が止み、はたと正気を取り戻す。映像を一時停止し、ディスクを取り出す。印刷面を確認すると、読み上げるのも恥ずかしいようなタイトルが記入されていた。俺は、その辺に置いてあったケースを拾い上げる。しかし、それはかの映像の内容を示すものではなく、ただの洋画のケースだった。アカデミー作品賞受賞という文言。裏面を見ると、ジャケットの男の一人が銃を構えているシーンが切り取られている。開けて中を見ても、もう一枚目のディスクがあるわけでもなく、俺はケースを閉じ、そっと辺りに放置し、
もう一度、再生のボタンを押した。二回戦が始まろうとしていた。
3
もしかしてこの映像は、彼女の男親類のものであって、何かの手違いか神様のいたずらかで入れ替わり、彼女はそれを知らないまま俺に手渡したのかもしれない。と、そんな風なストーリーを仕立て上げ、後日、彼女に返却した。
「どうだった。面白かったでしょ?」
彼女の笑顔はいつになく眩しかった。
思わず、目が眩みそうになる。返答に窮し、四苦八苦。そんな懊悩も顔に出ていたと思う。彼女が異変に気づき、問答。俺は遠回しに、なるべくオブラートな表現(はたしてそんなものがあったのかどうか俺は知らない)で当件を伝える。
彼女はケースを開け、ディスクの印刷を見つめていた。
沈黙。
俺は自然と伏せていた顔を上げ、彼女を見た。彼女の顔は、カラスウリの実のように赤く紅潮し、それこそ湯気でも上がりそうなほど恥じ入っていた。開いた口も塞がらない、というよりかむしろ、口の開き方、何と言い訳すればいいか分からないという様子だった。
自分よりも当惑している人を見ると不思議と冷静になれるもので、俺の内心の起伏は収まっていた。
「いや、あの……、これは、その、違くて、……ぜんぜん違くて‼」
彼女は片言のような日本語でたどたどしく喋る。
代わりに当惑とは別の、名称しがたい感情。
めちゃくちゃに狼狽しながら対応する彼女を見ていると、本当にわざとじゃないんだ、とストンと何か腑に落ちたような気がして、じゃあそれ私物じゃんって結論に至り、俺はそこで初めて、女の子でもああいうの持ってるものなんだって感動に似た感覚を覚えて、
それが大学二年の夏で、
俺の青春らしき何かだった。
4
電話の着信音が、つかの間の休眠に終止符を打った。
アラーム音とは別の音程に、俺の腕は機敏に反応していた。枕付近の音源を掴み、「もしもし」とだみ声。
「おはようございます」の挨拶から始まり、名前を名乗る。担当編集者だった。俺はすぐに覚醒し、背筋を正す。
編集者との繋がりの中では、一番古株だった。
「はい、何でしょうか」
今日は打ち合わせも何も入ってなかったはずだ。一体何の要件なのだろうか。嬉しい知らせでもあれば、と思ったが、「おはようございます」のトーンがやけに暗かったのを思い出した。
電話越しの声が、謝罪と同情を告げた。担当の声が滔々と流れる。
「はい、そうですね。……はい」
紋切り型の励ましをかけられ、担当からの通話が切れた。
スマホを持つ手が、だらりと力なく垂れる。天井を見つめ、茫然自失となる。
担当から要件は、連載の打ち切りに関してだった。
ようやく掴み取った自分の夢。週刊冊子の一枠に載せられた自分の漫画。週更新で展開も悪くはなかったはず、しかし人気はなかった。
時間の問題だとは分かっていた。遅かれ速かれ、この漫画は冊子から姿を消す。どれだけ頭を捻ろうが、打開策も救済措置も思い浮かばず、ただ週更新で延命を繰り返す。
はたしてこれが俺のやりたいことだったのだろうか。ふいに浮かび上がった疑問を払拭する。認めてはならない。それを認めてしまえば、俺はほとんど死んだも同然だ。そう信じ、創作に打ち込む日々。
担当から連載の訃報を聞いた時、突き抜けるような落胆が襲い、そして同時に、どこかで安心する自分もいた。信じたくなかったが、胸の内のこの安息は本物だった。
「……何やってたんだろ、俺」
一体どこから選択を間違えたんだろうか。
ほとんどゾンビのようになった俺は、顔を洗い、服を着替え、部屋から出た。
外の新鮮な空気を吸わないと、気でも狂いそうだった。
5
蝉が鳴く。
直射日光とアスファルトから照り返す熱で、町はうだるような暑さだった。家を出てものの数分で汗が噴き出す。逃げるように日陰を歩く。影が終わり、別の影へと渡っていく。一体どこに向かっているのかも分からなかった。
気分転換にでもなればいい、と思っていたが、待ち受けていた灼熱地獄に完全に参っていた。二段アイスクリームが数十秒で、ぬるいマックシェイクになってしまいそうな温度。
どこかコンビニにでも寄ろうと思ったとき、TSUTAYAの看板が見えた。そういえば現在住んでいるアパートへの入居時、辺りを散策したのだった。確かレンタルショップも見かけた。いつか寄るだろうとカードを作り、結局何も借りることはなかった。カードは今も財布の中に入っている。
俺は店内に入り、クーラーの効いた涼しい風を浴びる。何かに導かれるように、棚に近づき、陳列された映画を眺めた。
どうせしばらく暇だろう。何作か借りていこうと思い、かごを手に取る。
目線を上下左右に動かし、琴線に触れるものがあるか探す。配信サービスにないものを基準に選んでいくが、一度見たものでもジャケットや裏面の説明が違っていて案外面白かった。
しばらく物色していると、黒いカーテンが視界に映った。大人になってから数年が経ったというのに、この布きれ一枚を隔てた一歩先の世界を見たことがない。興味本位で、大人の世界を垣間見る。そこには、一生手の届きそうにない大人の仕事道具たちとともに、大人しか知らない色をしたDVDが怪しげに並んでいた)。
いつの間にか鬱憤が手を突き動かし、棚に伸びる。どうせならこういうものも借りていこうと思った。気分にドンピシャのものを漁る。と同時に、そんなことをしている自分、というものに嫌気や気恥ずかしさを覚え、適当に取って外に出る。なんだか男としてのレベルが足りない気がした。こんなことを思って急ぎ足になる自分は心底童貞なんだと、出口のない自己嫌悪に煩悶とする。
無人レジを済ませ外に出ると、猛暑が帰り道を舗装していた。致死量の紫外線が背中を突き刺す中、俺はレシートの総額をぼんやり見つめながら、どこかバイトにでも応募しようか迷っていた。
6
「うちのサークル入りなよ」
いつかの帰り際、彼女はそう言った。橋の欄干にもたれ、川を眺めながら、「君みたいに映画好きな人沢山いるからさ」と付け加えた。
今日の彼女はピンクのワンピースで、蝉の大合唱の中、汗一つかいていない様子だった。涼し気に川のせせらぎに耳を傾けている。
対する俺は、額に垂れる汗を拭いながら、彼女の言葉を受け止めていた。
「……サークルか」
俺は、はっきり揺れていた。悩んでいた。入らない理由より、入るメリットの方が多く、後から思えばその中に、織本千鶴との関係も含まれていたと思う。
「ごめん」
当時の俺は、漫画家というものになりたかった。ならなきゃいけなかった。それは願望を越え、ほとんど使命のようなものとなって、常に俺の行動原理に居座っていた。
芸大にも入らなかったくせに、だとしても、今更諦めがつかなかった。時間が足りない。漫画以外のことに時間を割きたくなかった。映画はコマ割りや演出の研究になる。そういう意味で、彼女との会話は有意義だった。
サークルには彼女よりも詳しい人がいるかもしれない。たくさんの意見はより客観性を磨くかもしれない。新しいアイデアの源泉になるかもしれない。
でも——
でも、描くときはひとりだ。
自分と同じ漫画家志望たちとの差を埋めるなら、これから何千何万枚も描かなければならない。それが今の自分にできる最低限度の夢への切符だった。
時間はない。猶予期間(モラトリアム)が過ぎるまでに、何かを掴まなければならない。
「そっか」
彼女は何も言及せず、悲しそうに笑った。
天秤が傾きだす。今ならまだ、撤回できるかもしれない。ふいにそんな思考がよぎる。
「じゃあ、……また」
また、は訪れなかった。
俺は彼女とは逆方向に、橋を渡った。
7
部屋に戻る。机の上のモニターに映った描きかけの漫画が見え、失望感がふいに蘇る。電源を落とし、代わりにDVDプレイヤーを起動する。ビニール袋からレンタルしたものを無造作に掴み出した。裸体のパッケージが転がる。自分が興奮しているのかどうか分からなかったが、それを手に取り、挿入し、再生する。
映像が、流れる。
——織姫と彦星、出会う前は二人とも働き者だった。しかし、お互い惚れ始めると、仕事を放棄してしまうほど愛し合ってしまった。そのことに憤怒した天の神様は、二人を天の川で隔ててしまった。
七夕から織本千鶴を連想したのは、単純に織姫のイメージが彼女と一致したから。それだけだ。特に深い意味はない。
織姫と彦星は出会わなくても、もしかしたら仕事に嫌気がさすかもしれない。
なんとなく、そんなことを考えてみる。
見慣れたかのような街並み。安いインタビューに答える女性。
今まで俺は、大人の世界から目をそらしてきたのを半ば誇りのように思っているが、どうしてかその映像には既視感しかなかった。その理由も、すぐに思い出した。
——そもそも俺は彦星じゃない。彼女は交流関係が広かったが、対する俺は、もはや書く必要もないだろう。俺はただの、彼女の知り合いの一人でしかなかった。それも短い付き合いだ。俺のことなど、もはや忘れられていてもおかしくない。
映像を見つめながら、震えた声が漏れる。
「……ははっ、なんだよ、それ」
このビデオは、あの日、彼女から借りたものと同じだった。俺はパンツをひざ下まで降ろした非常に格好の悪い姿で、意地の悪い神様の存在を認めていた。
——あの日からもう何年が経ったのだろうか。数えたくもない。彼女は結婚したらしい。風の噂で聞いた。らしい、というのは、俺がその噂を確定させる情報網を持っていないことを意味する。
何故だか猛烈に泣きたかった。積もった年月が俺の涙腺を緩めたのかもしれないし、その空白が余計あの頃を美化したのかもしれない。涙の筋が頬を伝う。俺は、自分のものを握りしめながら、ただ流れ落ちる涙を止めることはできなかった。
「あれ……あれ……」
心が激しく騒ぎ立て、体はぴくりとも昂らない。映像がぼやけて、まともに見れない。故障でもしたのだろうか。俺はそれをじっと見つめていた。
——もし俺が、いつかの橋の上での彼女の誘いに応じていたら、今でも彼女は、俺のことを覚えていたのだろうか。あるいは、もっと別の関係になっていたのだろうか。
涙をぬぐうと、映像は幾分マシになっていた。代わりに俺の目玉が狂い始めた。
映像の女優の顔が、どう見ても織本千鶴にしか見えなくなっていた。さっきまではそんなことはなかったのに。何度も目をこすっても、彼女の顔は戻らない。
さながら宇宙だった。織本千鶴と俺を隔てるは天文学的な距離と質量と引力。光の届かぬ遥か彼方、追憶の正体は天の川だったのだと俺はこの銀河でいちばん信じていたかった。カササギが画面からあふれて織本千鶴が俺にふれた。ふれているのだ。目をこする。口をこする。喉をこする。この追憶を汚して、俺は天の川にすべてをぶちまけてしまいたい。叫ぶ。願いを。願い? 何が。俺は今、つまり、何も考えられない!
しかしいくら激しく欲しても、ついに絶頂は訪れなかった。そうしてしばらくすると、映像が切り替わった。そこに映っていたのは、大学生の俺だった。
俺は一人でキャンパス内を歩いている。ただ一人で、俯き加減で歩く。いつしかその隣には、織本千鶴が歩いていた。互いの手が触れて、握る。
それは、走馬灯のような過去回想だった。いや、過去回想ではない、そんな過去などないからだ。妄想だ。売れない漫画家の、反吐が出そうなほど拙いストーリー。俺に夢でも見せてくれているのだろうか。DVDプレイヤーは映像を流し続ける。
四畳一間のアパート。それは当時の俺の下宿先だった。しかし、あたかもずっとそうだったかのように、映像の中の彼女もそこに住んでいた。一度も食ったことない彼女の手料理を、映像の俺は頬張る。いつしか、冬になり、春になり、俺たちは大学を卒業していた。
時間が飛ぶ。
会社勤めの俺は、電話越しに謝りながら、パソコンで資料を作成していた。彼女はスーパーからの帰りなのか、自転車の重そうなかごに舵を取られそうになりながら、なだらかな坂を上っていた。ネギの飛び出た袋が良く似合っていた。
とめどなく溢れる、存在しない記憶。
映像の日々は過ぎる。初めて喧嘩をした夜。不器用な謝罪と、彼女の柔らかな微笑み。誕生日プレゼントのセンスのなさと、それに大はしゃぎする彼女。黒こげのパンケーキ。俺はおいしいおいしいと食べながら、彼女の隙を見ては直接はちみつを口に入れた。初めての夜。は上手くいかなかった。風が吹き、紅葉が落ちる。雪が降り、桜が散った。再び蝉が鳴き始めた頃に、新しい命も声を響かせる。
病院のベッドで、小さな手を握った。
顔は彼女に似ているのだろうか。
しかし滲んだ涙で、そこまで見ることができなかった。
DVDプレイヤーは止まっていた。いつのまにか映像がすべて終わったらしい。
「…………」
握っていた手は力なく解けていた。けつを丸出しにしたまま、俺は茫然と画面を見つめ、泣いていた。
いつかした選択の、あったかもしれない未来。
「俺は、……漫画家になりたかった」
ふいに言葉が零れた。誰に言ったでもない台詞が、じわじわと俺に夢からの覚醒を告げる。俺は、後悔をしているのだろうか。
「……違う」
もしあの頃に戻れたとしたら、俺は別の選択をするだろうか。俺のした選択は間違いだったのか。
「違う……。俺は、」
立ち上がり、パンツを上げた。机の上のモニターとタブレットを起こす。描きかけの漫画が、俺に最後の現実感を与えた。
きっと俺は、たとえあの頃に戻れたとしても、同じ選択をするだろう。
だって俺は、未だ夢の途上にいるからだ。
ペンを力強く握る。腹の内から湧いて出る感情が、線の勢いを助長した。
「……ずっと後悔はしてる。……でもそれ以上に、悔しいんだ」
俺は彦星になれないし、なりたいわけじゃない。
ずっと、星になりたかったんだ。いつか、織姫が気づいてくれるような一等星に。
「そのことをずっと忘れていた自分が」
腐ったような日々。その繰り返しの中で、俺は、そんな簡単なことさえも腐らせていた。
胸の内には、あの頃の願望が溢れ出していた。
今は星屑にさえなれない天の川に漂う塵かもしれない。
でもいつか、天の川の中でもはっきり分かるような輝きを持った星になりたい。そんな光で、彼女の瞳を奪ってみせたい。だから俺はまだ天の川を泳がなきゃならない。その夢に終わりはないかもしれないし、一生叶うことはないのかもしれない。
じゃあ、諦めるか? 描くのを止めるか?
今までの俺ならきっと、そんな疑問にいちいち手を止めていたのだろう。
息を吸う、
「止めていいわけねえだろ‼ ぶち殺すぞ‼」
モニターに反射した声で耳がうるさかった。もしかしたら通報されるかもしれない。
そんな思考をかき消す勢いで、俺は描き続ける。とめどない感情のすべて、目の前の創作物へ込めて、すべてを出し切るように、
止めない。
絶対に止めない。
ふと空を見上げた織姫が、天の川の光から俺を見つける日まで、
俺は、描くのを止めない。
あの夏、お前からAV借りた。/ 虫我
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
