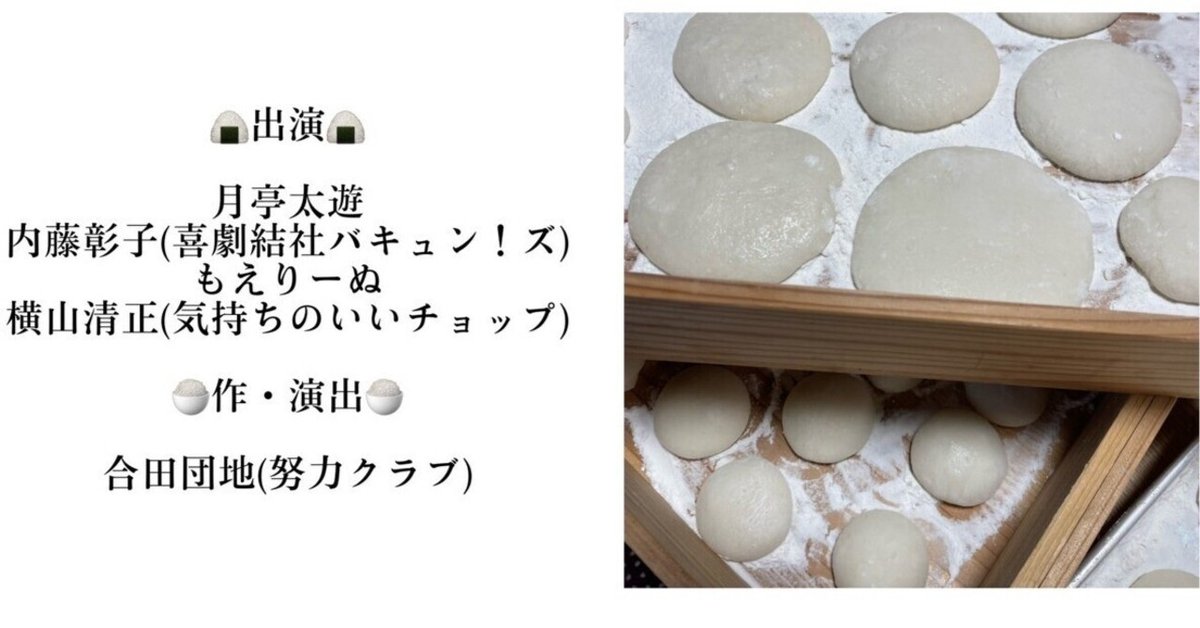
越境するコント、演劇の境界線
演劇とコントは異なる表現である――ということを、感覚的には理解できる。では、その境界緯線はどこにあるのか?と考え始めると、それはとても曖昧なもののように思える。
劇団「努力クラブ」で作、演出を手がける合田団地が「餅好き」というコントユニットを立ち上げた。その初めての公演が『餅畑』である。
出演者は月亭太遊、内藤彰子、もえりーぬ、横山清正の4名。お笑いの文脈で上演されるコントはコンビで演じられることが多いため、倍の人数ということになる。関係性や状況をある程度複雑にするためには、人数の多さは有効な手段と言えるだろう。
例えば、「餅の宿」と題したコントでは「もえりちゃん」が「るーちゃん」を半ば強引に里帰りに同行させる(このシーンは努力クラブ「世界対僕」の委託のシーンと重なる?)が、登場人物が二人だけであれば、故郷で起こる出来事の描写が難しかったのではないだろうか。
故郷では非現実的な出来事が起こるのだが、そのシーンでは「まれびと」のような異質な存在として、月亭太遊が演じる「餅の魔術師」が現れる。この配役も、非常に興味深い。演劇がメインの活動である内藤、もえりーぬ、横山に対して、お笑いがメインの活動である太遊の演技の対比が功を奏している――演劇としてのうまさ(発声の仕方や、演じ分けの巧みさ)と、お笑いとしてのうまさ(落差や緩急といった呼吸)がお互いを補強しあってうまく嚙み合っているように感じた。
『餅畑』では音をとても効果的に使用している。
冒頭のコントでは、チョップを極めた男が全力のチョップを繰り出す。舞台から響く鈍い音は、観客に痛みを実感させるには十分だ。その後のコントで、同じような鈍い音が出てくるシーンがあり――それは表面上には餅つきのシーンなのだが――舞台袖から音だけで表現される餅つきは、人を殴打する様子を連想させる。
その他にも、ダジャレのように(あるいはサブリミナル効果のように)随所に現れる「餅」という言葉の音が、複数のコントをゆるく接続させている。
演劇のフィールドでコントをするにあたり、ストレートな方法で演芸が引用されている。
漫才がしたい、という漫才(メタフィクション漫才)のような導入から、気が付けば演劇としか言いようのないシーンが繰り広げられる。
「漫才をやりたいと懇願する女性」が、いつのまにか、「煮え切らない態度をとる男に振り回される女に連帯する女」にすり替わっている――言葉で書いてしまうと飛躍があるが、コントとしては違和感なく成立している。それは、演劇であるからこそ成功しているのだろう。
コントと演劇の境界線については、明確な言葉にすることはまだ難しいかもしれない。それがどこにあるのか、「餅好き」の公演を補助線に紐解けたら……このシリーズが継続することを切に望みます。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
