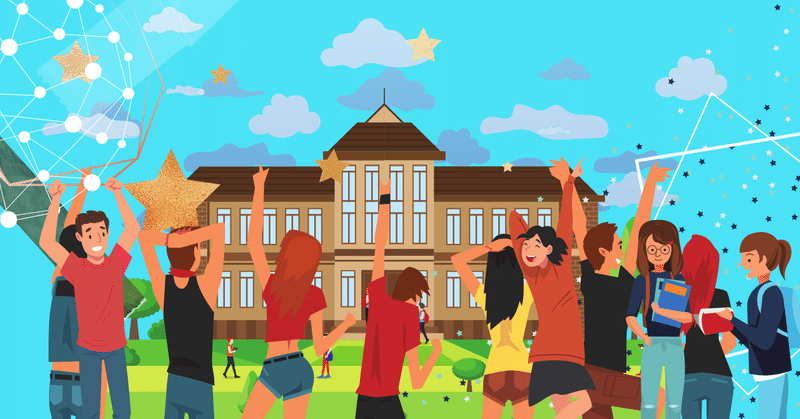
合格率47%国家資格公認心理師試験に、合格しました!
継続は力なり。
あなたが続けたいと思っていることは何ですか?
おはようございます!
りかちゃんです。
8月26日、公認心理師試験に合格しました。
1年以上続けてきた勉強。
詳しくはこちらをお読みください。
今回は合格してどうだったか、これから何をやりたいと思っているのかをまとめました。
———✨——-
どうやって受けた?
私は現役の中学校教員です。
今年の第5回公認心理師試験までは、「現任者枠」といって国が経過措置としてGルートというのを設けてました。
心理職ではないものの、対人援助職として5年以上経験があれば認められるルートです。
私のような教員以外にも、介護福祉士や看護師、保育士等、対人援助職の方が受けられます。
さまざまな団体が行っている、公認心理師現任者講習を受講→申請→試験資格をもらうという感じでした。
ただこの制度も今年まで。そしてあまりにも「なんちゃって心理職」が増えてしまうので、Gルート論争という物議をかましました。
合格してどうだったか
2021年3月妊娠→5月適応障害→6月現認者講習→11月出産→2022年1月試験勉強再開→模試受験→3・5月模試受験→7月本番
合格して感じたこと
「やったー!頑張った甲斐があったー!」
一方で心理職専門ではない私。
「カウンセリングがきちんと形になるように、研修受けて勉強しよう」
公認心理師として求められていること
みなさんのもつ、公認心理師のイメージ=カウンセリングといった感じかもしれません。
実際は一番国として求められているのは、「他職種連携」です。
「他職種連携」とは…??
という方も多いと思います。
これは、医療・福祉・教育・産業・司法の枠を超えて、クライアントの支援についてそれぞれが連携していきましょうねという取り組みです。
その重要な担い手の一つが、公認心理師ですよというお話。
例えばこういうケース。
14歳のA子さん。
虐待歴があり、児童相談所に保護されました。リストカット経験もあり学校にはしばらく通えていません。
このようなケースの場合、連携するのはこんな感じです。
・教育(学校)→不登校支援
・福祉(児童相談所)→家庭支援
・医療(病院)→本人へのケア
こういう感じで、さまざまな団体や組織が本人と家族等を支援します。
この橋渡し的な存在になるのが、それぞれの心理師であったり各支援者となります。
意外と高度なそして専門的なことが求められているのです。
私がこれからやりたいこと
私はこれまで教員として、特別支援コーディネーターという役割をしてきました。
これは学校内の支援が必要な生徒と保護者を、学校内外で橋渡しをする仕事です。
これからはスクールカウンセラーをめざして、新たな一歩を踏み出そうと思います。
もちろん心理職は経験なし。
教員経験しかありません。
今から勉強していき、カウンセラーとコーチ。
クライアントが望む未来を描く、オリジナルのセッションをご提供できたらと思います。
背中をそっと押してほしいときは、
カウンセリング。
もっと前に進みたいときは、コーチング。
気軽に利用していただけるよう、これからも勉強していきたいと思います。
ぜひあなたの「人生が前に進むお手伝い」をさせてくださいね。
———🌈———
体験セッションのお申し込みはこちら⬇️
各種SNSはこちら⬇️
よろしければサポートをお願いいたします😊
