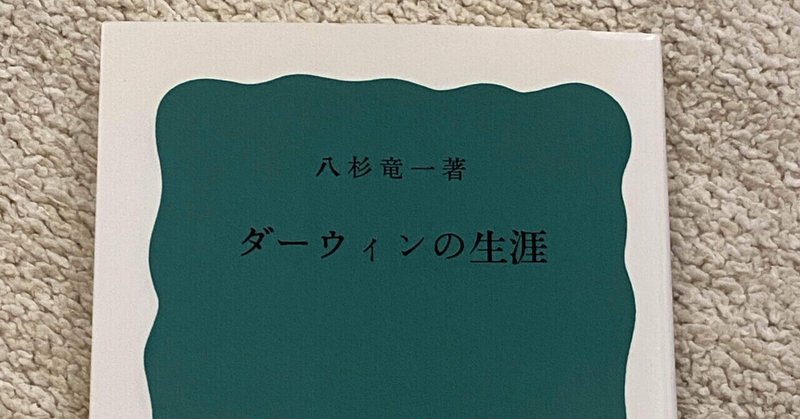
本に愛される人になりたい(78) 八杉竜一「ダーウィンの生涯」
学生時代に本書に初めて出会い数十年が経ちましたが、今でも気が向いたときには書棚から取り出し、子供の頃からのチャールズ・ダーウィンの姿を追っています。
八杉さんは本書のまえがきで、「私は、青年ダーウィンを描きたい。」と書かれています。「壮年および老年のダーウィンの姿を、この青年時代からの人間的発展として、しっかりととらえるということだ。」と宣言のような言葉が続きます。
老年になって過去を振り返り本人の姿を自ら描くとき、そこにはその年月でいられた体験や知識が加味されてしまい、青年時代の姿が歪に描かれる可能性があります。
例えば、10歳の<私>のことを描くとき、その10歳の私はそれ以降に得られた体験や知識などもっているわけがありません。ところが、70歳になった<私>は、ともすればその60年間に育んできた経験や情報をその10歳の<私>にもあったがごとく描く可能性があります。
哲学者の鶴見俊輔さんの言葉を借りれば、10歳の<私>をそのまま描くのは<期待の次元>で、60年分の経験や情報を加味して描くのは<回想の次元>ということになるかと思います。
そして、本書の著者である八杉竜一さんは、<期待の次元>に自分の視点を置きながら、人間的に発展してゆくダーウィンの生涯を描こうと試みられています。
ダーウィンと言えば進化論なのは誰もが思うところだと思いますが、子供の頃からの彼の思考癖や興味を持っていた遊び、宗教観や恋愛観。青年期での政治的な考え方、そして彼が出逢った人々から何をどのように得たのかを知っていると、「種の起源」執筆・発行に至る背景がよく見えてきます。
そもそも、ダーウィンは自ら<進化>という言葉を唱えたというより、生物は多様な変異をし、その都度の環境にたまたま適合した変異体が生き残ってきたと言いたかったかと思います。
現在でも、人間は最高に進化した生物だという神話のような考え方が漠然とありますが、これもたまたま環境に適合した変異体が生き残り人間に至るのだと私は思っています。人間が発生して約500万年。恐竜など絶滅するまで約2億年。ミミズが地球上に現れたのは約4.6億年前。こうして考えても人間という種は、40億年の地球の歴史のなかで一瞬だけ立ちあらわれ消えてゆく生物なのかもしれません。これまでも、地球上の大陸はすべて結合して超大陸を形成し、また分裂し、再び結合し…を繰り返してきました。数億年後の超大陸形成期に果たして人間はその環境に適合しているのかどうか、おそらく様々な変異種を作り出し新たに適合するのか、それとも系統樹が途絶えるのか。
本書の初版は1950年なので、およそ75年前になりますが、ダーウィンという名前や進化論という考え方は、ざっくり知っていたとしても、その考え方に至る道筋を理解している人は、現在でもあまりいないと思います。
時には、そうした道筋を知ることも良いかもしれません。そうすれば、「種の起源」をより深く理解できると思います。
因みに、ダーウィンは、フジツボやミミズの研究者としても名高くて、彼のフジツボやミミズの研究から学ぶことが多々あります。中嶋雷太
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
