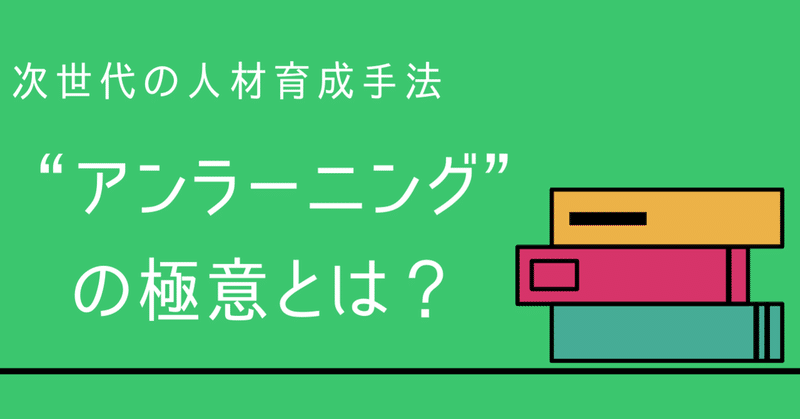
見えない未来を切り開け!次世代の人材育成手法「アンラーニング」の極意とは?
皆さん、こんにちは!株式会社リディラバの石井です。
新型コロナウィルスの流行から1年が経ち、社会情勢も人々の生活も一変しました。
社会の変容に合わせて、大企業もビジネスの根本的な刷新を求められています。「これまで通りのことをやっていればOK」とはとても言えない状況です。
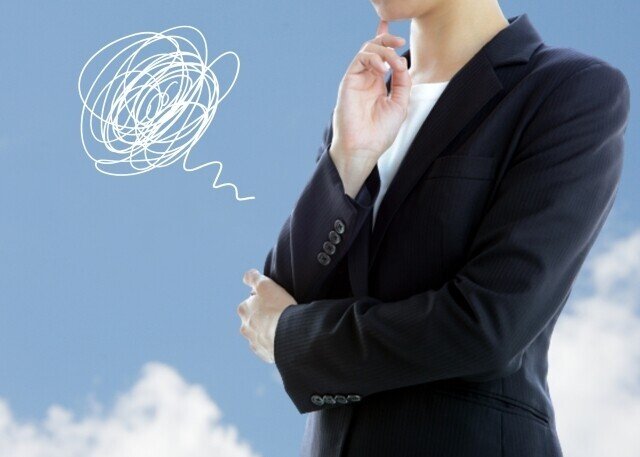
人材育成部門のミッションも、大きく変容しています。
ただでさえ、コロナの逆風を強く受けている部門でしょう。年次研修のオンラインへの切り替え、e-ラーニングの導入、新人教育の刷新・・・
それに輪をかけて、ビジネスの根本的な刷新に伴う「新しい人材育成」を打ち出すことを迫られているのではないでしょうか?
人生100年時代の到来を迎え、「新卒一括採用」「年功序列」「終身雇用」といった、これまでの価値観では通用しない社会が目の前に迫っています。
変化の激しい時代に対応できる組織を作りたい・・・!
今までの価値観や、これまで当たり前だった会社と社員の関係にとらわれず、新しい取組み・新しいビジネスを自発的に考え、行動する社員を育てたい・・・!
でも、どうすれば良いのかわからない・・・
今回は、「今までの価値観にとらわれない」人材を育てるために、いま注目されている手法「アンラーニング」についてご紹介します。
新しい人材育成の一手を打ちたい!社員の意識を根本から塗り替えたい!
そんな想いを持った人材育成部門の方々の一助となれば嬉しいです。
アンラーニングとは何か?
アンラーニング(un-learning)とは、読んでそのまま、学んできた物事を捨てる「学習棄却」とも呼ばれる概念です。
人間は、組織に適応しようとする生き物です。
大企業の一員として入社し、成長してきた多くの社員は、組織の目的に自分をフィットさせるために「組織の理屈」をどんどん学習します。
「この仕事は、毎年やっている事務手続きだから、スピード重視で処理すれば問題ない」
「このプロジェクトは今までの傾向を見ると6か月かかりそうだから、それに応じてスケジューリングにしよう」
「来年は部下がまた1人配属されるだろうから、部下教育に10%くらいの時間を投下することになるだろう」
このように、これまで組織が積み上げてきたこと、あるいは自分の経験から「学習」することで、新しい物事にもゼロベースではなく効率的に対処することができます。
学習は、組織が効率的に仕事を回す上で欠かせない機能なのです。
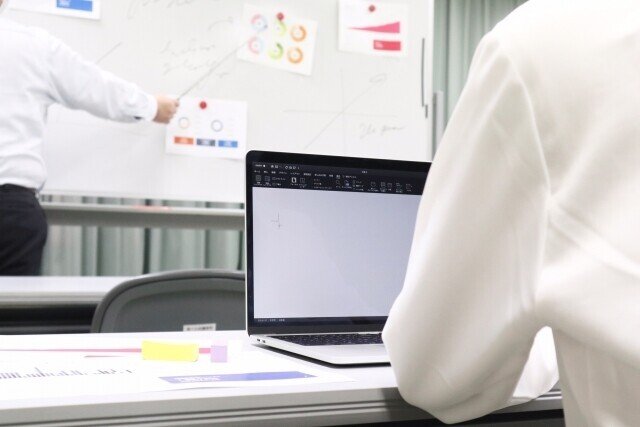
しかし、これらは「毎年同じような仕事が生まれる」「形は違っても本質的に同じプロジェクトが連続している」からこそ活用できる作法です。
一番最初に書いたように、今の時代は「過去と同じように」事業が回っていくことの方が少なくなってきました。
そもそも国内のマーケットは人口減時代で右肩下がり。
今までと同じような売り方では、業績は下がり続ける一方です。
社会の変容に応じて、「今までと同じやり方ではダメなんだ!」という強い自覚のもと、日々の業務を見直し、刷新する力が1人ひとりに求められています。
この時に必要となるものが「アンラーニング」です。
アンラーニングとは、単に学んできたことを捨て去るだけではなく、来るべき未知の時代に備えて、今までの組織・自分の価値観を鵜吞みにせず、新しい発想・価値観・知識をどんどん取り入れようとする「柔軟性」を身につけることなのです。
アンラーニングは自力では不可能!?
とはいったものの、どうすればアンラーニングを実現できるのでしょうか?

アンラーニングは、ビジネススキルや組織規定といった「表面」だけでなく、むしろ暗黙の論理や組織に浸透している価値観などの「深層」に切り込まなければほとんど意味がありません。
普段全く意識していない価値観に気づき、しかもそれを「一旦捨てる」ためには、非常に繊細な設計が必要になります。
例えば、自社の役員が登壇して、社員に「今までの価値観を捨て去る努力を!」と訴えても、その構図自体が「役員が社員に"指示"する」という今までの作法を反芻しているだけなので、社員の深層では「役員の言うことはきちんと聞く」という学習がむしろ強化されてしまいます。
あるいは、人材育成担当がファシリテーターになって「価値観を見直すワークショップ」を開催し、社員に自発的に考えさせてみても、結果はほとんど同じでしょう。
そもそもビジネスマンにとっては「研修 = 会社から社員への指示」という植え付けがあまりにも強く、多少ワークショップの仕立てを工夫したところで、深層の価値観に食い込むような体験はなかなか生まれません。
アンラーニングを成し遂げるためには、「外」に出すこと
社員の「価値観」レベルに食い込むほど強い体験は、会社の中だけではなかなか生まれません。
真に価値のあるアンラーニングを実現するためには、自社の論理・価値観だけでは通用しない「会社の外」を経験させることが最も効果的でしょう。

とはいっても、「会社の外であればどこでも良い」かといえば、勿論そうではありません。
そもそも社会人は、1日8時間働いていれば、残り16時間は毎日「会社の外」を経験しています。しかしそれは、アンラーニングにほとんど活かされていないでしょう。多くの社員にとって、「会社の中」と「会社の外」はほとんど関係がないことです。
ある企業の失敗エピソードをご紹介します。
新規事業コンテストを開催した時、「自社の今までの事業にとらわれないこと」というメッセージを打ち出した結果、なぜか献立アプリの提案が非常に多く出されたそうです。
これは、
・自社の今までの事業にとらわれてはいけない
→自社の「外」で事業を考えよう
→毎日、会社と家庭の往復だったから、家庭の困りごとしかわからない
→家庭では、毎日の献立を考えるのがみんな大変そうだった
→献立アプリを提案しよう!
という、まさにアンラーニングが出来ていない事象によって生まれたものだそうです。
「会社の外」を経験させるにしても、日々の暮らしの延長線上だけでは、社員としての価値観を刷新するアンラーニングには決して至りません。
そこで、会社という枠にとらわれることなく、自分がやるべきことを捉え直し、今までの価値観から脱却するために、今注目されている手法が「越境学習」と呼ばれる育成手法です。
大企業に居ながら「外」に出る手段――越境学習
越境学習とは、研修などの機会を使って、社員が会社の「外」に飛び出し、自社では経験してこなかった未知の事象・課題に挑むことを通じて、組織の論理だけにとらわれない「価値観の刷新」を図る手法です。

経済産業省も「VUCA時代の企業人材育成」手法として注目しており、既に多くの大企業が人材育成の手段として導入し始めています。
経済産業省が定義している「越境学習の重要な要素」は、次の3つです。
・社会課題の現場
・摩擦
・多様なステークホルダー
つまり、自社のビジネスや事業領域がほとんど通用しない世界に飛び込んで、全く異なる業界の社員や、社会課題に取り組んでいる現場などの「自社の価値観と必ずしも合わない人たちとの交わり(=摩擦)」を経験することが、越境学習のキーポイントということです。
越境学習は、組織を変え、リーダーを生む
リディラバが実際に取組んでいる人材育成プログラムにおける「アンラーニング」の一例をご紹介します。
社内では、物事のやるやらないは合理的な根拠に基づいて判断されることが常で、その確からしさをどう説明するかを毎日考えていました。
しかし、「弱者側に立つ」「誰もやりたがらないことをやる」という人たちの話を聞いたり実際に取り組んでいる姿を見たりして、ガツンと頭を殴られたような感覚がありました。前例、お金、人、何もない中で、課題に対して真っ直ぐに向き合い、世の中が変わるかもしれない活動へ、地道に泥臭く取組んでいることに、物凄く価値を感じました。
自分自身は世の中に対して真摯に向き合っているのか?今の仕事は誰にどのような価値をつくっているのか?本当にその価値は生まれているのか?日々の仕事で問うようになりました。
(パーソルキャリア株式会社)
社内だけで経験を積むと、どうしても「組織のカルチャーに応じて合理的に物事を進める力」のみが優先されてしまいます。
この方の場合は、普段の仕事を離れて、新潟県の限界集落をフィールドとした課題解決プログラムに参加したことで、上記のようなアンラーニングが生まれました。

注目すべきは、単に「変化に対応しようとする力」だけでなく、「日々の仕事の意義・価値を自分から問い直そうとする力」が生まれている点です。
私たちはこれから、ますます先行きが見通せない時代へ突入します。
会社の次世代を築き上げるためには、社員の多くが今までの価値観にとらわれない「柔軟さ」を持つこと、そして会社を牽引する一握りのリーダー層が「自ら変革を起こそうとする」こと、この2つがどちらも欠けてはならないと私は思います。
アンラーニングは、組織風土を変え、そしてリーダーを生むことで事業を変えます。
先行きの見えない未来だからこそ、会社組織が一丸となって、自分たちで未来を切り開くチャンスではないでしょうか?
リディラバの「越境学習」ご紹介
私たちリディラバは、社会課題の現場と、企業・学校・国・自治体など多様なプレイヤーをつなぐ事業を10年以上行っています。
リディラバが提供する越境学習プログラムについては、以下をご参照ください。
↓ ↓ ↓
フィールドアカデミー|社会課題は、仕事の意味を変える
↑ ↑ ↑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
