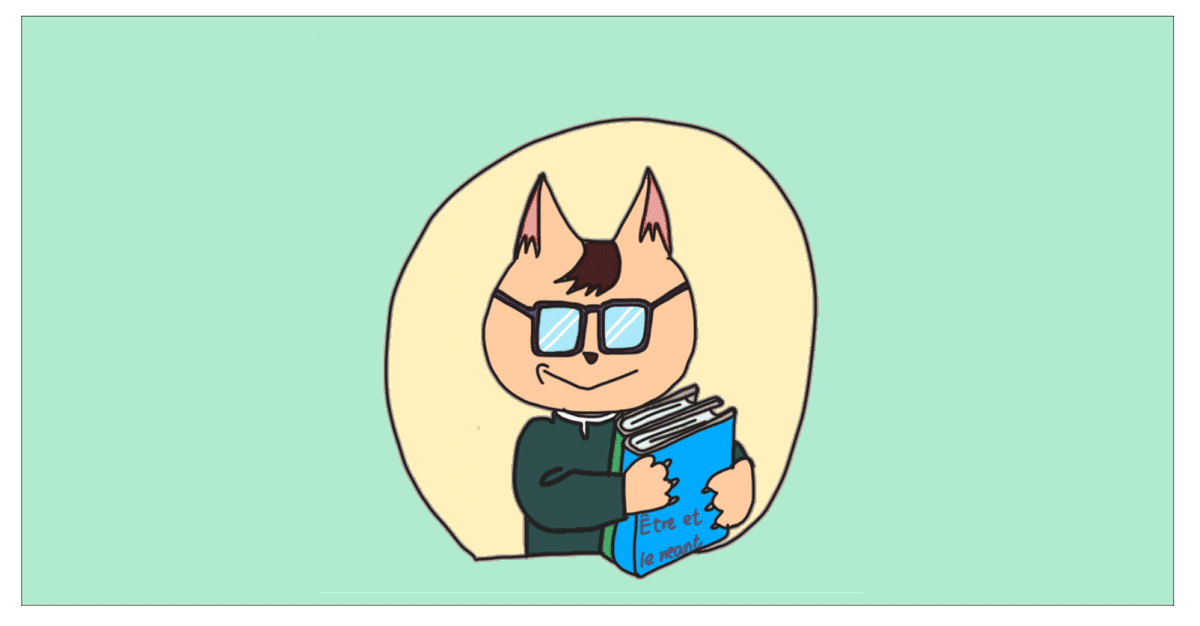
「芸術神学」批判序説 ~ 新しい公共劇場の在り方を模索するための省察 ~(9)
〈アート〉とは何か?
この問いに答えるには様々なアプローチがあるが、ここでは2つ、心理学的アプローチと歴史学的アプローチを取り上げたい。
まず、心理学的アプローチであるが、これにも種々あると思うが、ここではジャック・ラカン(1901-1981)の精神分析理論を援用(濫用?)してみたい。
ラカンは人間の精神世界を理解するため、「想像界」「象徴界」「現実界」という3つの分析概念を用いた。
〈アート〉は他ならぬ人間の営みであるから、これを転用し、〈アート〉もまた「想像界のアート」「象徴界のアート」「現実界のアート」に分類することができよう。
「想像界のアート」をイメージしやすいとても簡単な事例として、『ファイナルファンタジー』などテレビゲームのRPGとか、かつてフジテレビで一世風靡したトレンディドラマなどを挙げることができるだろう。テレビゲームでは、自分自身が主人公になりきり、冒険の旅に出る。トレンディドラマでは東京ライフスタイル(それが虚構であるにせよ)に憧れを抱き、それを疑似体験していく。つまり「想像界のアート」では、スパイダーマンになったり敏腕刑事になったり名探偵になったりと、要するに登場人物に感情移入しながら、なりきる、自分自身を重ね合わせて楽しむことになる。
一方、「象徴界のアート」は構造的にできている。イメージしやすい簡単な事例としては、いわゆる「萌え萌えアニメ(?)」が挙げられる。たとえば大塚英志(1958-)が分析しているとおり、アニメの登場人物は記号化しており、要素の組み合わせによって構築されている。「よく喋る/無口」「眼鏡をかけている/裸眼」「料理が上手/下手」・・・・・・とかいう二項対立的要素の組み合わせでキャラ設定がなされていく。また、中心となるキャラクター群のうち、片方が「よく喋る」なら片方を「無口」にするなど、差異化が試みられる。
しかしこれは何もアニメだけの話ではない。物語にはたいてい構造がつきまとうし、それは登場人物だけではなしに、ストーリーについてもだ。たとえば、日常から非日常の世界へ旅し、再び日常へ帰ってくる、とかいう筋書きは物語の王道だろう。このような側面、構造的に構築された側面が色濃い〈アート〉を、「象徴界のアート」と呼んでおく。そういえば三谷幸喜のドラマなども構築的(構造的)要素が強い。
最後に「現実界のアート」であるが、たとえば草間彌生を知っている人なら、まさにアレがそうだ、と言えるが、言葉を足そう。
「現実界」の前に「象徴界」について少々説明を加えよう。
「象徴界」とは、もっとも平たく言い換えるなら、社会、でもある。社会にはルールがある。そのルールはたいてい無意識的なものだ。たとえば万引きをしていはいけない、と親から教わる。なんでかというと、警察に捕まるからだと言う。だったら、見つからなきゃ万引きをしてもよいのか? それもダメだと言う。万引きはダメだからダメなのだ、よくわからないけれど、それが社会のルールだ、ということになる。もちろん、万引きを自由に認めたら、自分のモノも盗られてしまうから、とか、いろいろと後知恵で理由を見つけることはできる。しかし社会のルールというのは、それがルールだからルールなのだ、とかいう日常的実践の積み重ね(継続)がルールをルールたらしめ、制度化しているという側面がある。よくわからないけれど、それがルールだからルールなのだ! そのように守られていくルールというのは、まさに無意識的なものだと言えよう。ただしもちろん、ルールがあるからこそ社会が成立する。その無意識的なルールがどのように社会を成り立たせているのか、学術的に構造分析していくことは、できる。
さて、このような「象徴界」ないし社会というのは、つねにすでに「べつに他でもあり得た」という点において恣意的である。そのようにルールが編成されて、このように社会が成立しているが、それは一面では必然的な流れであるにせよ、一面では偶然的である。ルールについては文化とか慣習とか、幅広に受け取ってもらいたいものだが、それはさておき、あるとき、こういった〈偶然的必然性〉が重苦しくなったりもする。もっと簡単な言い方をするなら、「社会への違和感」が、芽生えるときがある。社会が「正しく」、自分が「間違っている」のではなく、自分が「正しく」、社会のほうが「間違っている」のではないか、と思うことが人間誰しもあるだろう。そのような違和感、社会へすっぽり溶け込めない違和感が、あるいは苦しみが、ぼくらを「現実界」へ誘う。
「象徴界」の偶然的側面、あるいは虚構性と言ってもよいが、それが暴かれたときに垣間見えてくるものが「現実界」である。
「現実界」は表面的には「象徴界」に占拠されて、植民地化されているが、じつのところ「象徴界」は「現実界」のすべてを覆うことはできず、ところどころ「穴」が開いている。しかし「象徴界」という日常に埋没していると、その「穴」に気づかない。いや、気づかないからこそ「穴」に落ちずに「健康(健全)」で生きていられる、と言ってもよい。ところが「象徴界」への違和感から「穴」に気づいてしまう人たちがいる。この人たちの末路は2つしかない。①「穴」に落ち切り、帰らぬ人となるか(秩序を喪失した狂気)、②「象徴界」とは異なる方法で「穴」を埋めようとするか、だ。ただしこの「穴」は絶対に埋まらない。潜在的に「象徴界」の作り方は無数にあるだろうが、どんな「象徴界」であろうと、必ず「他でもあり得る可能性」が、残余として、「穴」として、残る。「社会への違和感」は、どんな社会に生きようと、ついて回る。
「現実界のアート」とは、「穴」に気づいてしまった人が(永遠に埋まらぬ)「穴」を埋めようとする終わりなき実践、決して辿り着くことのない平安(ユートピア)への憧憬である。その有様は、個々のアーティストにとって、まさに「生きるか/死ぬか」の切迫感に満ちたものとなる。「穴」を知ってしまった以上、「穴」を埋めることが、アートすることが生きる(生き続ける)ことであり、アートすることを止めることはすなわち「死」(「穴」に落ちること)を意味することになる。過去の歴史を振り返れば、「現実界」の彼方へ逝ってしまったアーティストたちは数え切れないほどいる。これが、「現実界」のアートだ。
以上、「想像界のアート」「象徴界のアート」「現実界のアート」の3分類について概観してみたが、もちろん、個々の〈アート〉には濃淡あれども3つの要素が含まれているものだ。純然たる「想像界のアート」、あるいは「象徴界のアート」、「現実界のアート」を見つけることのほうが逆に難しい。
さて、通俗的には「芸術にふれると心が豊かになる」と言われている。それを疑ってみるのが本エッセイの柱の一つであるが、「想像界のアート」「象徴界のアート」「現実界のアート」の3分類を念頭におけば、「芸術にふれると心が豊かになる」というのが妄言の類でしかない、ということがハッキリしてくる。
「想像界のアート」にふれれば、人は空想の世界に遊ぶことができる。それが、心の豊かさだろうか?
「象徴界のアート」にふれれば、たとえばクラシック音楽の(ソナタ形式がどうのこうのといった)文法を学び、知的な楽しみが増えるかもしれない。しかしそれが、心の豊かさだろうか?
「現実界のアート」にふれれば、場合によっては絶望して「死ぬ」かもしれない。「死に至る病」を抱えることになるかもしれない。それが、心の豊かさだろうか?
というより、そもそも〈心〉とは何か? について考究する前に〈心〉という概念を軽はずみに持ち出してくること自体が浅はかであり、まさにこの通俗的見解が通俗的なものでしかない理由なのであるが、この点については後述することにしよう。
ところで、〈アート〉にふれることは自由を着ることだ、と前述した。芸術にふれるとみんなハッピーになれる、というのが通俗的見解であるとするなら、「自由を着る」ということは必ずしもハッピーになることを意味しない。
たとえばセックス・アピールの欠如したコム・デ・ギャルソンの服を着てマチへ出ることは、社会(的な眼差し)への挑発になり得る。そこにあるのは牧歌的なハッピーではなく、ある種の「張り詰めた緊張」だ。
もう少し踏み込んでみよう。
〈アート〉の切実性は「現実界」から到来する。それは当たり前だと思っていたもの、秩序、「象徴界」にダイナマイトをしかける。〈アート〉にふれたぼくらは「象徴界」に(爆破された)「穴」を見つけてしまう。だからショックを受けるのであり、衝撃的な出会いとなり、忘れられぬものとして脳裏に刺さるのである。
もっと言うと、〈アート〉に出会わなければ、何不自由なく「幸福に?」生きていられたものを、出会ってしまったがゆえに「不幸に?」なってしまうこともある。
〈アート〉に出会ってしまった、それ以後においては、ぼくらは当たり前を当たり前として生きられなくなってしまったのだから。
なるほど、そこにあるのは「自由」だと言える。当たり前から解放されたがゆえの「自由」がそこにある。ただし、この「自由」が、ぼくらをハッピーにしてくれる保証はどこにもない。
〈アート〉がもたらす「自由」(ないし虚構を暴く〈真実〉)は、「薬」であるかもしれないし、「毒」であるかもしれないのだ。この両義性は、どんなに強調してもし過ぎることはない。
この〈真実〉の両義性は、西洋思想には希薄でも、もともと東洋思想には古くからあったものだろう。
たとえば釈尊が悟りをひらいたとき、己が境地(真実)を人々に伝えるべきかどうか悩んでしまった。この悩みは西洋人には理解できない。なぜなら、西洋思想における「真理」とは例外なくすべての人をハッピーにするものであるから、普及啓発するのが当たり前のことだからだ。ゆえに、たとえばキリスト教宣教師などは「真理」を伝えるべく、べつに誰も頼んでいないのに大海を渡ってくるのだった。
しかし釈尊は、〈真実〉には「薬/毒」という両義性があり、ある人にとっては「薬」になるが、ある人にとっては「毒」にもなることを熟知していた。だからその後の仏教でも、その道へ至る門は開いているものの、門から飛び出て普及啓発などというお節介はしない。なぜなら〈真実〉が「毒」となり、人を「殺す」ことがあり得るからだ。いや、大乗仏教運動は普及啓発しているじゃないか、という反論があるかもしれないが、そこで展開されているのは「方便」であり〈真実〉ではない。たとえば大乗仏教の一つに密教がある。密教の「密」は秘密の「密」であり、むしろ軽はずみな〈真実〉の伝道は「毒」になってしまう確率の方が高い、ということに自覚的である。
なぜなら〈真実〉にふれることは、「想像界(イメージ)」の幻影(夢)から覚め、「象徴界」の虚構性を見破り、「現実界」という「穴」に一度はハマることだからである。
「穴」に気づくことは、なるほど(他でもあり得た)「自由」を知ることである。「自由」に目をひらくことである。だが同時に、それはとてもキケンなことである。
釈尊にはそれがよくわかっていた。
「真理」にふれてハッピーになりましょう運動も、「芸術」にふれてハッピーになりましょう運動も、釈尊の目には、じつに浅はかものと映るだろう。
つまり〈アート〉とは、けっして無害なものではない。
公共劇場1.0は、〈アート〉の「有害性」について致命的なまでに無自覚でいる。いや、こう言ってもよい。〈アート〉の「有害性」を脱色し、無害化し、飼いならされた〈アート〉だけを取り扱いしている、と。
これは欺瞞である。
ところで、美術という制度、「象徴界」に便器(泉)を叩きつけることで爆破(内破)せんとしたマルセル・デュシャンが、むしろ先端的なアーティストとして美術という制度、「象徴界」へ再編入されていったように、「現実界」という無限の泉(穴)は、悉く「象徴界(象徴秩序)」の再活性化のために使われていく。
アンチ・モード(反象徴界)ですら、(新しい)モードに変換されていく。
「現実界」という底なし「穴」から無限の欲望(他でもあり得る可能性)を汲み、それでもって「象徴界」の硬直性を打破し、目まぐるしくメタモルフォーゼしていくのが、じつは資本主義の運動である。
「現実界」にふれることが、「新しいもの」をもたらしてくれる。
「新しいもの」が無害化・飼いならされて手に負えるものとなり、「象徴界」の仕組みをバージョンアップさせていく。
ゆえに「現実界」と真摯に向き合い闘うアーティストというのは、芸術の資本主義運動にとって格好の餌である。実際、資本主義的芸術はつねに「新しさ」を求めており、その「新しさ」は、命がけで「現実界」の「穴」にハマっていったアーティストたちによってもたらされるものである。
あるいはこう言ってもよい。一見資本主義とは無縁なところにいると思われる生真面目なアーティストほど、芸術の資本主義を支えてしまうことになる。むしろ「想像界」や「象徴界」を得意なエリアとする「エンタメ」の住人ばかりでは、資本主義は前進せずに硬直する。
アーティストの、命がけの前衛的人生が、餌になる。
アンチ・モードが次のモードとなる。
おそらくこの問題に大変自覚的であるアーティストにバンクシーらがいるが、これについては深入りしないでおく。いま考えていることはアーティストの在り方ではなく、公共劇場の在り方であるから。
さて、公共劇場1.0が無害な〈アート〉しか扱わない、あるいは「現実界のアート」の「毒性」に無自覚であるとするなら、公共劇場2.0はすべてに自覚的である。
そもそも人間の実存は「想像界」「象徴界」「現実界」を横断しており、逃れられはしない。一生背負って生きていくことになる。〈アート〉とは、それらを可視化、あるいは体感的に具体化していくものである。公共劇場2.0は「穴」を前にして目を塞がない。「穴」の毒性を知っていながら「穴」を無害化することもしない。なぜなら実存には最初から最後まで「穴」が空いているからであり、「穴」をどう生きるかが、そもそも人生というものの課題だからだ。
ゆえに公共劇場2.0では、アウトリーチ(普及啓発)をしない。どこぞの狂信的宗教団体と同じにしてほしくはない。公共劇場2.0の取扱品は「薬」であり、かつ同時に「毒」である。だから一方的な押し売りはしない。
公共劇場2.0は、ただ門をひらく。
一生のうち躓かない実存などありはしない。
躓いたとき、そこで、門がひらかれていることが重要なのだ。
門をくぐるかどうか、決断するのはあなただ。
なぜなら、門を抜けた先にハッピーパラダイスが広がる可能性は(公共劇場1.0が抱く誇大妄想とは異なり)100%ではないからだ。
あなたは門をくぐることもできるし、避けることもできる。
ただし開かれた門は、いつでもあなたの到来を待っている。
公共劇場2.0のスタッフに言えることは、ただこれだけだ。
きっと〈アート〉は、あなたの実存(的迷い)を照らす鏡になってくれる。
あなたの〈生きづらさ〉を、「象徴秩序(象徴界)」の重石を、〈アート〉は粉砕し、突破口を示してくれるかもしれない。
しかしそれで、あなたが「幸せ」になれるかどうかはわからない。なぜならあなたの「幸せ」は〈アート〉によってではなく、あなた自身の手でつかみとるべきものだからだ。
門は開かれた。
進むのは、あなただ。
〈アート〉を着て、一歩を踏み出す。
この「門」は、どことなく、たとえば曹洞宗永平寺の「門」に似ている。
公共劇場1.0のモデルは「教会」である。辛く苦しい労働(日常)から離れて、安息日(週末)に「教会(劇場)」へ赴く。そこで「真理」ないし「神の〈ことば〉」を宿した尊き芸術作品にふれて、拝み、労働動物とは異なる本来の(神に祝福された)人間性を取り戻す。芸術にふれることで、動物が人間になるのだ、というロジック。
公共劇場2.0のモデルは永平寺の「門」である。
その門には、〈仏〉を求める者のみここをくぐれ、とある。
「教会」とは「答え」を教えてもらう場所である。
「門」とは、答えを求める旅に出る、そのスタート地点でしかない。
公共劇場2.0とはすなわち、万人にひらかれた「門」である。
「禅」が「答え」を教えてくれるものではないのと同様、〈アート〉もまた「答え」を教えてくれるものではない。〈アート〉は「神の〈ことば〉」ではない。
ちなみに「禅」は無神論である。「神」はすでに死んでいる。
「神なき時代」において、「答え」を見つけるのは、あなたを除いて他にはいない。
どんなに坐禅をしてみたところで「答え」がやってくるものではないのと同様、どんなに〈アート〉にふれたところで、自動的に「答え」があなたにやってくることはない。
坐禅した時間の長さがあなたを〈仏〉にするのはないのと同様、〈アート〉にふれた時間の長さがあなたの〈心〉(そんなものがあるとして)を豊かにすることはないのだ。
いささか話が抽象的になりすぎたが、また後ほど振り返ってみることにし、次に、歴史学的アプローチから〈アート〉について語ってみよう。
《つづく》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
