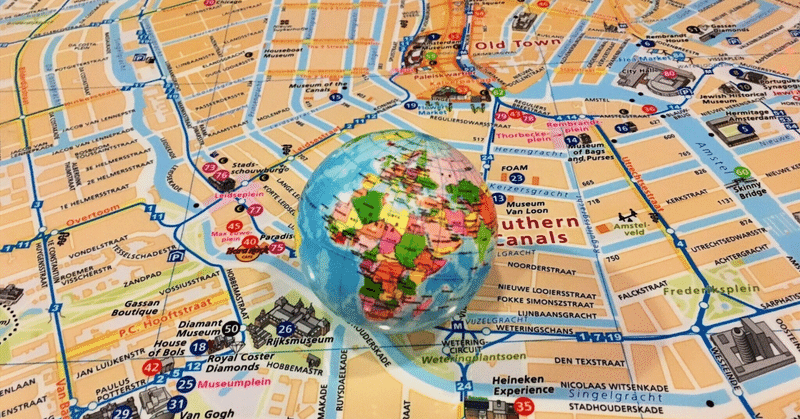
「あなた」と「環境」は分けることができない
「地図」を譬え話にちょっと。
「地図」における「地」と「図」はカップリングされていて、分離不可能である。それは「地の一部」を書き直そうとしても、「図の一部」を書き直そうとしても、両方を書き直さなければ整合性が取れないことから明らかだ。
このような『構造的カップリング』をされたものは「地図」にかぎらず、この世の事物凡てに適応される。
たとえば「あなた」と「環境」。
あるいは「あなた」と「わたし」。
プログラミングのときにこの問題は顕著になる。
「データ」と「アルゴリズム」は『完全には』分離できない。何故なら、それは元々が一体のものを分節しているに過ぎないから。
だから、logical thinking とか critical thinking とか云われるときに MECE とか云って、筆者が鼻白んでしまうのは、「そんなに都合よく要素還元論よろしく要素に分解するだけで構造を再現することはできないのでは?」という一点。
ただ、話はここで終わらない。
要素還元論は「要素」と「構造」が分離しがたいからこそ、それを敢えて分離して考えることによって、「要素」と「構造」のあいだの《諸関係》を考え直すためには、強力な武器となる。
問題は、微分的発想だけでは抜け落ちるものがあって、微分結果をたんに積分するだけではイケない、ということ。
つまり、ここでの話にあわせるなら、「微分」という事前プロセスによって、すでに恣意的に捨象された「隠れ要素」や「隠れ構造」が無自覚に存在していて、それらを積極的・意図的に探して盛り込んでいかないかぎり、「積分(/統合)」しても、(想定していたような)《システム》は構築できないよ。
だから、プログラミングしているときに、自らの《無自覚な恣意性》に気付く、《認知/認識の罠》に気付くことは大事なんだけれど、だからといって、それは要素還元論的発想の否定ではなくて、むしろそれらを補間・補完するような副次的作業が必要なのでは、ということ。
そんなことをつらつらと、昨日とある会合に参加したので、感想として思った次第。
結論としては、《よく考えろ》、《手を動かせ》、《話を聞け》、《話しあえ》以外の何物でもなかったりするんだけどね、この話。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
