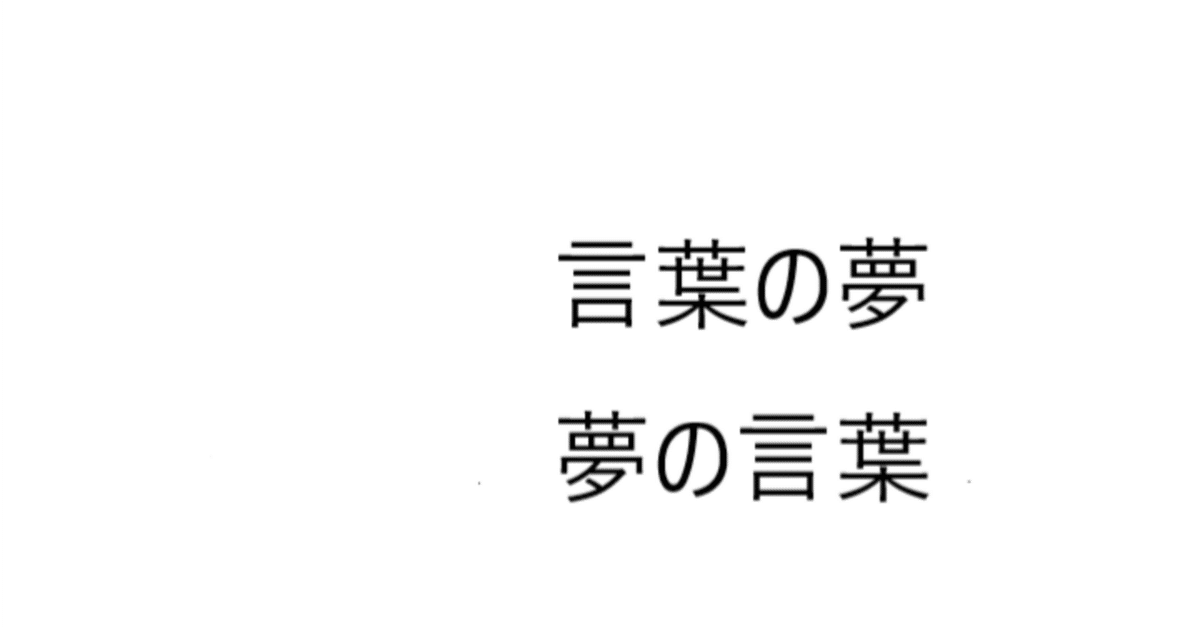
まばらにまだらに『杳子』を読む(10)
見る「彼」
『杳子』の冒頭から、視点的人物である「彼」の「見る」身振りを書かれている順に――小説ですから出来事の起こった順に書かれているわけではありません――見ていきたいのですが、とても多いので、気になる部分だけを選んで引用してみます。
彼は午後の一時頃、K岳の頂上から西の空に黒雲のひろがりを認めて、追い立てられるような気持ちで尾根を下り、尾根の途中から谷に入ってきた。
(『杳子』p.8『杳子・妻隠』新潮文庫所収、以下同じ)
上の「認めて」(見留めて)は、登山に不可欠な「見る」でしょう。このように自然のしるし(兆)を知覚して正しく認識しなければ、遭難するにちがいありません。
疲れた軀を運んでひとりで深い谷を歩いていると、まわりの岩がさまざまな人の姿を封じこめているように見えることがある。そして疲れがひどくなるにつれて、その姿が岩の呪縛を解いて内側からなまなましく顕われかかる。地にひれ伏す男、子を抱いて悶える女、正坐する老婆、そんな姿がおぼろげに浮かんでくるのを、あの時もたしか彼は感じながら歩いていた。
(p.9)
ここで「彼」は岩に人の姿を見ているわけですが、あくまでも像として映っていると考えられます。自然の兆候を見るのとは対照的な「見る」であり、幻覚や幻想と呼ばれるものに近いのしょうが、視覚的にとらえていることが特徴です。
感じ取る杳子
以下に引用するのは、この谷底での二人の出会いののちに、杳子の語った話を伝聞として記述している部分です。
誰かが上のほうに立って、彼女の横顔をじっと見おろしている、その感じが目の隅にある。たしかにあるのだけれど、それが灰色のひろがりの、いったいどの辺に立っているのか、見当がつかない、見当がつかないから顔の動かしようもわからない。
(p.15)
鉤括弧(『』)でくくられてはいませんが、話し口調に近い文体です。英語やフランス語で自由間接話法とか描出話法と呼ばれている書き方に似ています。
この杳子の発言ですが、見ているとか見えていると言えるのでしょうか。私は二回くり返されている「見当がつかない」に注目します。見当識という言葉を連想するからです。
見当識を簡単に言うと、「ここはどこ?」、「いまはいつ?」、「どちらさまですか?」という感じの、障害と言っていい状態を指す語です。認知症について語るときに、よく出てくる言葉です。
重症のうわの空状態とも言えるかもしれません。
「見当」は古井由吉がよくつかう言葉で、もうろうとした状態を描写したり説明するときにもちいられます。
*
河原に立ったとき、彼女は谷底にのしかかる圧力を軀にじかに感じ取ったという。
(p.16)
「という」からわかるように、ここも彼女の言葉を伝聞として記述している部分です。
「感じ取った」のが「圧力」つまり「力」、しかも方向性をもった「力」であることに注目したいです。p.14とp.24にある、一行空けに挟まれた伝聞の部分には、「感じる」と「力」のバリエーションの語句が頻出します。
方向というと、さきほど述べた見当と似た言葉ですが(「見当」を辞書で引くとわかりやすいでしょう)、ここでいう方向性とは、何か(どこか)から別の何か(どこか)へと働きかけるという意味です。方向性がなければ、力は釣り合いを取ることも保つこともできません。
杳子は方向性をもった力を感じ取る人物として描かれているのです。見ることは見る、見えることは見えているのですが、対象の像を見ると言うよりも、対象の姿から対象に内在する力を感じ取ると言えます。
「感じ分ける」ではなく「感じ取る」です。感じ分けるのは、むしろ「彼」のほうでしょう。
意味を見る、力を感じ取る
「彼」の場合には、見ることによって差異(異なり)や差違(食い違い)を見る、つまり言語化が比較的容易な「意味」を見ているのです。
杳子の場合には、見ることによって方向性をもった「力」を感じ取っています。その物が動きそうな、あるいは働きかけてくる気配という感じでしょう。その物に内在する方向性や志向性(指向性)という言い方もできそうです。
視覚的な像は言葉にしやすいですが、気配や方向性・指向性を言語化するのは至難のわざなのかもしれません。
「何と言ったらいいのだろう」(p.15)、「してしまうみたい、そんな風……」(p.15)、「そんな気がした」(p.15)、「どう言ったらいいのかしら」(p.18)、「遠い遠い感じで」(p.19)。
このように杳子の口調はきわめて歯切れが悪いのです。
「そんな感じ……。それともすこし違うみたい」と杳子は言い、今度はほとんど正反対なことを喋り出して、彼に首をひねらせた。
(p.19)
しどろもどろだとも言えます。本人も相手も苦しいでしょう。
*
見える意味は言葉にしやすい――。意味は意見であり意見(いみ)なのです。英語の meaning (言いたいこと)という意味での意味に近いとも言えそうです。
感じ取られる力は言葉にしにくい――。力は籠(こも)っている、隠(こも)っている。籠の中に隠れているものは見えません。気配として感じるだけの物(事かもしれません)を目に見えるように説明するのは至難のわざでしょう。意味という意味もある、英語の sense にある 「向き・方向」に近い感じです。
意味にくらべ、力や気配を言葉にするとなると、このように語数が多くなりますが、これは言い訳ですね。
*
・視点的人物の「彼」:視覚、見る、頭、考える、言葉、言語活動、文字
・「彼」から見られる存在の杳子:心、力、方向、感じる、感じ取る、声
こうした図式化が可能かもしれません。
見損じる、感じ取り損なう
上の図式で注意すべきことがあります。
大切なのは、「彼」も杳子も正しくとか適切に見たり感じ取っているわけではない点です。見ると感じ取るには正しいも適切もないからです。
見損じる、感じ取り損なう――空振りだらけなのが人でしょう。
この作品では、「彼」も杳子も常時見損じ感じ取り損なうのです。見損じると感じ取り損なう身振りが、この作品のテーマではないかと言いたくなります。
*
いずれにせよ、いわば見る人である「彼」が視点的人物なのは偶然ではなく必然だと私は思います。言語活動、とりわけ書き言葉である文字をもちいての小説の執筆は「見る」を基本としているからです。
「彼」を視点にしないで、この小説は書けないと言えます。ところが、「彼」を視点にしても、というか「彼」を視点にすると、以下に引用する文章のような書き方しかできないのです。
「右」「左」「上」「下」
言語活動(とくに文字を書くこと)と視覚(見る)は親和性が高いとも言えると思います。
いっぽう、心(感じ取る)は言語化が困難であり、言語活動のなかでは声で語るよりも、むしろ、流れるように声でうたう(歌う、唱う、謡う、詠う、詩う)という形で、ほのめかしたり、心や身体に働きかけてうったえる方法を得意としている気がします。つまり、詩の方法です。
杳子は言葉を記したり言葉を奏でたりする(うたう、詩う)のに長けた人物としては描かれていません。そして、それは散文であるこの作品では必然だと私は思います。
言語化が困難な対象をあえて言葉で描写するのが、この小説の主眼となっているからです。流れるような書き方が選ばれていないという意味です。
見損じる人でありながら、ある程度言語化できる「彼」の視点で、感じ取り損なう人であるうえに感じ取ったものをうまく言語化できない杳子との交流を記述する。杳子の名から取った『杳子』は、そんな小説なのだと私は思います。
その「彼」と杳子が接近する場面がどう書かれているかを見てみましょう。
*
右に左に、上に下に――この小説では「左」「右」「上」「下」という言葉が、くどいくらいにくり返しもちいられています。
文字どおり、右往左往、凸凹、アップダウンしながら、遠回りをしつづけているのです。ようするに、迂回であり宙吊りです。
迂回しつづけているのは、作品に書かれている内容も、そして作品を構成している言葉の身振りもなのです。
この迂回と宙吊りは作品の最後まで一貫して続き、最後の最後になっても終わりそうもありません。さらに言うなら、書かれていない最後の後になっても終わらないだろうという予感がします。
学生時代および大学教員時代の古井由吉がフランツ・カフカを読みこんでいたらしいこと(古井の大学の卒業論文はカフカの「日記」を題材にしたものだったと自筆年譜に記されています、なお大学院の修士論文はヘルマン・ブロッホだったとあります)を思いうかべますが、これは安易な連想でしょう。
*
右、左、~、上、下、/\、――こうした方向と動き(力の方向と動きでもあります)を丹念に描写していれば、作品は流れるようには進行しません。この作品では、意味という意味での sense ではなく、方向という意味での sense がテーマのひとつになっていると言いたいほどです。
これは見落としてはならない細部であり、一貫した言葉(=作品)の風景だと思います。
*
【※ここで見落としてはならない細部の見落としに気づいたので書きます。「一」では「岩」という言葉が頻出するのにかかわらず「石」という言葉が「石ころ」という言い回しでp.11とp.18の二箇所だけにもちいられているとこれまで書いてきましたが、あとで引用する箇所と同じ段落の冒頭に「山靴に触れて小石がひとつ転り出し、女のほうに向って五、六米落ちて、勢い尽くして止まった。」(p12)というふうに出てきます。ごめんなさい。石ころがころころ転がっていくのを見損じていました。】
Sを描くS
たとえば、この作品の「一」には、「彼」のじつに不可解な行動が描かれています。不可解な上に、その書かれ方がもどかしいのです。同時に進行する杳子の身振りもまた妙と言えば妙です。
気がつくと、彼の足はいつのまにか女をよけて右のほうへ右のほうへと動いていた。彼の動きにつれて、女は胸の前に腕を組みかわしたまま、上半身を段々によじり起こして、彼女の背後のほうへ背後のほうへと消えようとする彼の姿を目で追っていた。
(p.13)
上とそっくりな「彼」の動きと杳子の身振りが、改行と一行を隔てて、直後に反復されます。
彼の歩みは女を右へ右へとよけながら、それでいて一途に女から遠ざかろうとせず、女を中心にゆるい弧を描いていた。そうして彼は女との距離をほとんど縮めずに、女とほぼ同じ高さのところまで降りてきて、苦しそうに軀をこちらにねじ向けている女を見やりながら、そのまま歩みを進めた。
(p.13)
?ですね。迂回に見えなくもない「?」という約物の形のことです。
「右のほうへ右のほうへ」に続いて「右へ右へと」ですから、むしろ、Sでしょうか。Sという文字が「彼」の動きと、それにともぶれ(共振)するかのように、身を「よじり」「ねじ向けている」杳子の姿にも見えなくもありません。
……そのとたんに、杳子の目は男の姿をはじめて視野の中心に捉えた。男は二、三歩彼女に向ってまっすぐに近づきかけて、彼女の視線を受けてたじろぎ、段々に左のほうへ逸れていった。男は杳子から遠ざかるでもなく、杳子に近づくでもなく、大小さまざまな岩のひしめく河原におかしな弧を描いて、ときどき目の端でちらりちらりと彼女を見やりながら歩いていく。
(p.22)
同じ場面が伝聞という形で杳子の視点から語られて反復されると上のようになります。
*
まるで作品の最後近くになって明らかになる「彼」のイニシャルであるSのようだとは言いませんが、上の彼の動きからそのように連想する読者がいるかもしれません。SがSを描くなんて、いかにも安易な連想でしょう。
それともSというよりも8でしょうか。迂回と宙吊りが作品をとおして反復されていくのだから ∞ でしょうか。はたまたメビウスの輪とか帯でしょうか。
連想は印象であり感想ですから、個人的なものであり、他の人といっしょに確認もできず共有もされません。印象は検証できないのです。
*
8を横にすれば無限の符牒としての ∞ が得られると指摘してみせたところで、しかし「作品」としての『覗く人』は8への還元を素直にうけ入れたりはしないし、まただいいち、8の主題の反復は、はじめからこれみよがしに配置されていて、隠された構造というより、むしろ表層に露呈した可視的な細部であって、視線を表皮へとつなぎとめる機能しか果たしていないのだ。
(「アラン・ロブ=グリエ――テマティスムの廃墟」(蓮實重彦著『批評 あるいは仮死の祭典』せりか書房所収)p.90)
*
アラン・ロブ=グリエ作の『覗く人』はともかく、『杳子』においてのSや8や ∞ の連想が論外なのは言うまでもありませんが、上で見た場面ばかりではなく、この作品のあちらこちらに右左だけでなく上下といった方向の動きの細かい描写が見られます。
これは現にそういう言葉(文字)があちこちに書かれていて見えるのですから、確認と共有と検証ができそうです。
反復される、くり返される――この身振り自体も古井の作品の特徴と言えます。
そのために、この小説は読みにくくなり、上で述べたような描写が読みとばされることにもなります。
そうした描写が小説の進行にとって無用の細部であるとか、描写というよりもノイズであるとする意見や感想もあるにちがいありません。私も目や耳にしたことがあります。
*
私はこうした書き方をいいと言っているのではありません。こう書かれていると言っているのです。さらに言うなら、この作品のテーマはこう書かれるしかなかったと言いたいです。
言葉で書かれている作品の内的必然によって、しかるべきさまに言葉が並べられているという意味です。
引用箇所で描かれているのは心理ではありません(心理の投影と見ることは可能でしょうが)。比較的言語化しやすい心理ではなく、言語化が困難な動きが描かれているのだと思います。あえて描かれていると言うべきかもしれません。
この場合の動きとは、定型や決まり文句で容易に記述可能であり、じっさいにそうした言葉や言い回しをもちいて記述されている動き(たとえば野球のラジオ中継での言葉による動きの見事な記述です、そこには名詞と名詞と化した動詞・形容詞・副詞が組み合わされています、型の決まった「名詞」からなるパッチワークなのです)ではありません。
引用した「彼」と杳子の動きは、定型におさまらない、そしておそらくこの作品で一回きりしか見られない動きなのです(一回きりどころか、他の複数のあるいは多数の作者による複数のあるいは多数の作品で読んだような動きの描写に満ちた小説が読み物と呼ばれるのでしょう)。
いずれにせよ、どのような動きであれ、その描写は言葉にとって、もっとも不得意としているものかもしれません。
言葉で動きを記述することについて考える必要があるようです。
(つづく)
#杳子 #蓮實重彦 #意味 #力 #言語化 #動き #描写 #記述
