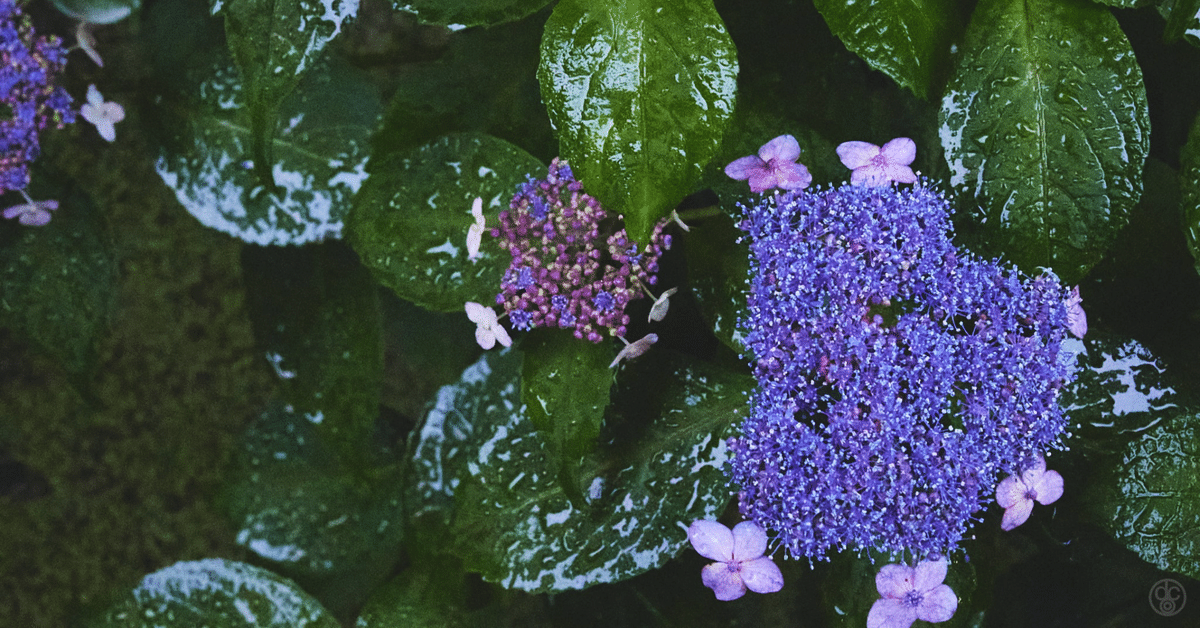
雨の日に
澤なほ子
2009年発行 ランチュウ作品集より
きょうは土曜日の午後。朝からずっと細かい雨が降っている。窓ガラスの向こうに、紫のあじさいの花が重たそうに首をたれていた。
中学二年生のテツヤは険しい顔つきで小麦粉やらサラダ油を戸棚から出している。頭の中はきのうの担任とのやりとりでいっぱいだ。
七つ年下の弟のダイゴはキャベツを危なっかしい手つきで刻み始めた。テツヤが重ねてくれた葉はダイゴの小さい手ではつかみきれない。
「ざく、ざく、ざく」
ダイゴは丸い頭を振りながら、小さい声で調子を取っている。
「あっ」
ダイゴの高い声にテツヤは、はっと我に返った。弟の手元をのぞきこむと包丁がすべったらしい。けがはしていなかった。二センチ幅くらいに切ったキャベツの葉がまな板いっぱいに、調理台にも床にも散らかっていた。
ダイゴは息を吸い込み、散らかったキャベツをながめていたが、やがて包丁を持ち直した。そのダイゴにテツヤは怒鳴った。
「バカ、気をつけろ。それに、もっと細かく切れよ」
「もっとぉー?」
ダイゴは語尾をのばして、嫌そうに、甘ったれた声を出した。ほほをふくらませ、厚い唇を突き出している。その顔はまるで、父さんが飼っている熱帯魚だ。フグの仲間のその熱帯魚はクルクルよく動く大きな目も持っていてかわいい顔をしている。でも、鋭い歯があって、どう猛だ。
どう猛といえば、とテツヤは担任の顔をまた思い浮かべた。真っ赤に塗った薄い唇をゆがめて笑っても、いつも目の底が冷たい細く長い顔。その担任に、きのう数学のテストでカンニングを疑われ、今回は大目に見てやる、といわれた。
「あいつは、サメだ」
テツヤは思わず、吐き出すように口に出した。
ダイゴがふしぎそうにテツヤを見た。テツヤはあわてた。弟が切ったキャベツを一掴みにすると包丁を入れてみせた。
「これくらいに切れ」
キャベツは親指の先くらいの大きさになったが、兄の乱暴な切り方に驚いて、ダイゴはその顔を見上げた。
「あれっ」
ダイゴは丸い眼をみひらいて、すっとんきょうな声をあげた。
「兄ちゃんの鼻の下、ひげが生えている」
ダイゴは興味いっぱいという目つきで、背伸びをしてテツヤの顔に手を伸ばしてきた。
テツヤはダイゴの手を強く払いのけた。鼻の下がうっすら黒く見えるようになっているのは自分でも気がついていた。頬っぺたにプツンとできているニキビよりも気になって、毎朝顔を洗うたびに鼻の下を念入りに見る。でも、父さんに電気かみそりを貸して、といいだせずにそのままにしている。
「キャベツが終わったら、このネギも。目が痛いなんていって、ピイピイ泣くなよ。泣いたらダイゴの分はないからな」
テツヤの突き放した言い方に、ダイゴは肩をすくめてまな板に向かった。
テツヤは半年ほど前から無性に腹がすく。母さんにどんなに呆れられたって、学校から帰って食パン一斤くらいをぺろりと平らげないではいられない。それでもまだ何か食べたくて、うろうろと台所に出たり入ったりしてしまう。何にもおやつがなかったとき、焼きめしを作ってみた。それが意外にうまくできて、以来、料理にはまった。今ではカラー写真いっぱいの料理雑誌を片手にだが、いろいろ挑戦している。
きょうは雨だし、出かけるのもおっくうで、きのうからのむしゃくしゃした気分を振り払おうとテツヤは台所に立った。すると、ダイゴが遊んでいたブロックを放り出してまつわりついてきた。じゃまだ、と追い払ったが、腰にぶら下がって離れない。ボクシングごっこをしようというのだ。テツヤはしつこい弟を追い払うつもりで、手伝ったら、といった。それが逆効果だった。ダイゴは持ったこともない包丁を握った。
テツヤは冷凍庫にイカの袋をみつけた。料理雑誌にあった「絶品!シーフード入りお好み焼き」が目に浮かんだ。
「ダイゴ、母さんに、これ使っていいかって聞いてこい」
そういいながら、テツヤは、まるで自分の胸のうちのもやもやした塊を押しつぶそうとするかのように、ダイゴの細い首すじにイカの袋をぎゅっと押し付けた。
「ひゃー、なんだよー」
ダイゴは派手な声を出して、すばやく冷凍袋から逃れた。そして、うれしそうなたれ目になってテツヤの腹にげんこつでドンと一発食わせる。放り出した包丁が流しの中に大きな音を出して落ちた。
「バカ、危ないだろ。足に落ちたらどうする」
「兄ちゃんがしかけてきたんだろ」
叱られて、ダイゴはまた口を尖らせた。そして、もう一発テツヤの腹を叩こうとした。そのこぶしがテツヤの腹に届くよりも早く、テツヤはダイゴのあごに軽くパンチをくらわせた。
「ボクシングごっこ、今は無し」
「兄ちゃんから始めたのに、ずるいや」
テツヤがダイゴに何かちょっかいをかけると、いつもそれはボクシングごっこ始まりの合図だ。テツヤはしばらくサンドバック代わりになってやる。終わりはダイゴが泣かない程度のパンチを一発。手加減を知らないダイゴが相手なので、けっこう運動にも、気分転換にもなるのだった。
「もう、ぼく、手伝わない」
ダイゴはまた鼻にかかった声を出した。目をこすって泣きまねをしながら、テツヤのようすをうかがっている。
「いいよ、けっこう。それじゃ、ダイゴの分は無し!」
テツヤはさもさばさばしたようにいった。
ダイゴはあわてて手を目から離した。唇を尖らせてテツヤをにらみつけていたが、あきらめてイカの袋を手に取った。
ダイゴがリビングに行ってみると、テレビには流氷が浮かんでいる海が映っていた。その前のソファーの上で母さんはラッコになっていた。さっきまで鈎針を動かしていたのに、胸の上にテレビのリモコンをのせて、両手でかかえている。
ダイゴがそばに近寄ってみると、スースー寝息が聞こえた。ダイゴはそっとリモコンを取り上げ、テレビを消した。そのとたん、母さんはパッと眼を開けた。予想したとおりだった。
「何よ。見ているのに」
ダイゴは白く曇ったビニール袋を、母さんの前につきだした。
「うそだあ。寝ていたよ。これ、兄ちゃんが使っていいかって」
ちらっと袋を見ただけで、母さんはつごうが悪いのをごまかすかのように、大きな声をだした。
「何を使ってもいいけど。それよりもブロックを片付けなさい」
ダイゴは急いで台所に逃げ込んだ。
「使っていいって。何でも」
それを聞くと、テツヤはニヤリと笑った。
「作戦成功」
「作戦って?」
「オレが聞きにいったらこうはならない。何を作るのかって聞かれて、しまいには、あれもだめ、これもだめさ。さあ、早くキャベツを刻めよ」
テツヤはイカの袋を蛇口の下に放り、思いっきり強く栓をひねった。袋にあたって飛び散る水を見ていると、胸にしこっている黒い塊が少しは溶けていくような気がする。
「さあて、絶品のお好み焼きを作るぞ」
テツヤが自分を奮い立たせるように言うと、ダイゴがキャベツを切る手を止めて、顔を兄のほうに向けた。
「絶品って?」
テツヤは干した桜色のエビのほかに豚肉、もやし、焼きそばも出してきて、小麦粉のそばに並べ、まじめな顔をしていった。
「ダイゴが今まで食べたことがないような、まずーいやつってことさ」
ダイゴは声を立てて笑った。
「うそだあ。すごーく、おいしいーんだ」
テツヤはうなずきながら、母さんの分も必要だな、と思った。いい臭いがしてくると母さんは必ず台所に顔を出す。そして、味見といって、かなりの量をつまむ。出かけている父さんの分はどうするか。冷めたお好み焼きは味が落ちる。でも、チンすればいいか。父さんが食べないならオレが食べればいい。
テツヤは冷蔵庫からキャベツの残りを取り出し、手早く洗うと流し台に置いた。
「キャベツ、追加だ。これも刻んでくれ」
テツヤはソースつくりにかかった。ボールにソースとだしの素を入れる。それを泡だて器でかしゃかしゃ混ぜ合わせ、みりんやケチャップを追加した。人差し指につけて味見をする。
「うーん」
何かが足りない。でも、その何かがわからない。
考えているうちに、今回は大目に見てやる、という言葉がまた頭をよぎり、テツヤの胸を押しつぶした。テスト中にテツヤは背伸びをした。その肩を背後から押さえられ、振り向くと担任だった。組んだ両手を頭の後ろにあてがって伸びをするのはテツヤの癖だ。何かを考えていて行き詰まるとつい出てしまう。
テスト終了後、テツヤは担任に呼び出された。そして、説教。
「兄ちゃん、ぼくにもそれ、混ぜるの、やらせてよ」
ダイゴがボールをのぞき込んでいった。
「だめだ」
ダイゴはまた唇を突き出し、丸い目でテツヤをにらんでいたが、黙ってキャベツに向かった。
テツヤは思い切ってマヨネーズを少し加えた。それから激しく泡だて器をボールに打ち付けた。
ダイゴはキャベツを全部切り終わった。ザルに入れるとこんもりと盛り上がる量だった。ダイゴはその多さに満足して、テツヤに見せた。
テツヤはそんな弟を無視して、気合を入れなおすようにいった。
「次は、生地、だな」
テツヤは大きなボールに卵と水を入れ、小麦粉を加えると菜ばしで軽くかきまぜた。そして、ダイゴの頭の上から手を伸ばし、ザルを取ってボールにキャベツをあけた。
キャベツは小麦粉にまぶされていく。小麦粉のどろどろの中にあっという間に沈んでしまった。
「あんなにいっぱいあったのになぁ」
大きなボールを覗き込みながら、ダイゴはもったいないというようにつぶやいた。
テツヤは空いたザルでもやしを洗い、ネギの青い部分のほとんどをちぎって捨てて、ダイゴに命じた。
「ダイゴ、早くこのネギを刻め」
捨てられたネギは流しの隅のごみ受けで青々している。
「何でそっち捨てたの?」
ダイゴはテツヤを見上げて返事を待った。また兄のひげが気にかかった。さっきよりも黒くなっているような気がする。
テツヤはうるさいというように眉を寄せ、もやしもキャベツが入ったボールにあけた。
「いつか、母さんが味噌汁作るの見ていたら、全部、先っぽまで使っていたよ」
「それは柔らかかったか、もったいなかったからじゃないの。たぶん、もったいないほうだ。母さんの料理はそれでイマイチの味になっちゃう。材料のバランスを考えない」
その自信たっぷりのいいように、ダイゴはすっかり感心して兄を眺めた。
テツヤは袋からイカを二匹取り出した。イカは背中が黒く光っている。ダイゴの視線を感じて、テツヤはもったいぶって、重々しい声でいった。
「うまそう。いいイカだ」
テツヤはイカの胴に指を入れ、内臓を引っ張り出した。茶色い内臓は灰白色の光る膜に包まれていた。
テツヤはわざとダイゴの目の前に内臓をぶら下げて、揺らした。内臓が鼻にくっつきそうになった。ダイゴは身をそらせて、それをよけた。
「兄ちゃん、やめてよ」
ダイゴが悲鳴に近い声をあげた。
テツヤはしつこく内臓を弟の鼻先にぶらさげながら思った。もっとねばり強く、担任にカンニングはしていない、伸びをしただけだといえばよかったのか。が、どんなに言っても担任は首を横に振って、口元だけ笑って、大目にみてやる、といっただろう。
「兄ちゃんのバカ!」
ダイゴは叫びながら、鼻先の内臓を手で叩き落とした。
テツヤはもう一本の包丁を包丁さしから抜くと、大目にみてやるとはなんだ、とくりかえしつぶやきながらイカを切った。気がつくと胴も三角のところも足も必要以上に細かく切ってしまっていた。
テツヤはホットプレートの上に手をかざして温度を確かめ、薄切りの肉を並べて乗せた。その上にイカや桜エビをいれた生地を流し込み、フライ返しを使って型を丸く整えた。
やがて、生地の下の肉が焼ける、香ばしいうまそうな臭いがしてきた。ダイゴはその臭いを鼻いっぱいに吸い込みながら、テツヤのシャツのすそを引っ張った。
「兄ちゃん、終わったよ。見て」
ダイゴはネギを刻み終わった。
テツヤはフライ返しを手に、生地の端が白くなって、反り返ってくるのをじっと待っていた。
「目なんか痛くなかった。ちっとも痛くなかった」
ダイゴは兄の気を引こうとして、声高にいった。
それでもテツヤは生地から眼を離さなかった。やがてフライ返しを生地の下に差し込み、ひっくり返しながら思わず声を出した。
「サメめ、許せねえ!」
ダイゴは驚いて兄を見つめた。
「なに?どうしたの」
テツヤはあわててフライ返しを持った手を上げ、ポーズをつくってみせた。
「うまくひっくり返せただろう?」
「うん。ぼくも泣かなかったよ」
「そうだな」
ホットプレートの空いている場所で、テツヤは焼きそばを炒め始めた。さっきのソースを焼きそばに絡めると少し甘酸っぱい臭いが台所いっぱいに漂った。
テツヤは焼きそばの上に生地をひっくり返して乗せた。上になった豚肉はちぢれてこげ目がこんがり付いていた。それに、ソースを塗る。
ソースを塗りながら、テツヤは、このままではだめだ、とつぶやいた。もう一度担任に話しに行くか。それとも次のテストでも背伸びをしてやろうか。
ダイゴは小鼻をふくらませて臭いをかぎながら、出来上がっていくお好み焼きをじっと見まもっていた。
最後にテツヤはダイゴが刻んだネギとかつおぶしをたっぷりふりかけた。こってりと光る茶色のソースの上で、湯気でかつお節がちりちり踊っている。厚さが五センチはありそうなお好み焼きが出来上がった。
母さんがテツヤの予想通り台所に入ってきた。いい臭い、と言いかけて、呆れたという顔でテツヤをなじった。
「まあ、この散らかしようったら!ちゃんと片付けしておいてね」
「母さんの定番のせりふ、だ」
テツヤはダイゴの耳元でいった。
「それに、何もかも使ってしまって、夕飯どうするのよ」
「使っていいって、いったんでしょう。ねえ、ダイゴ?」
テツヤは思わず険しい声で応じた。
「それにしても、こんなにたくさんの生地、みんなテツヤが食べるつもり?」
ボールをのぞき込んでたたみかけるかあさんの質問には答えずに、テツヤは出来上がったお好み焼きを大皿に取った。
「できたぞ、ダイゴ。さあ一緒に食べよう」
ダイゴは満足そうな笑みを浮かべて、兄を見上げた。その顔がおとなのように見えた。
「母さん、兄ちゃんの鼻の下おひげが生えているんだよ」
母さんはテツヤの顔をちらりと見て、うなずきながらダイゴの頭をなでた。
「雨が上がったよ。ダイゴ、食べたらお買い物に行こうか?」
母さんはそういうと、当然のように取り皿を三枚とアオノリを食卓に運んだ。
テツヤは思わず鼻の下に手をやった。そうか、母さんも気がついていたのか。ならば、今夜、父さんに電気かみそりを借りよう。ひとつは解決だ。もうひとつは・・・。テツヤはまた最初から昨日のことを思い返し、唇をかんだ。
