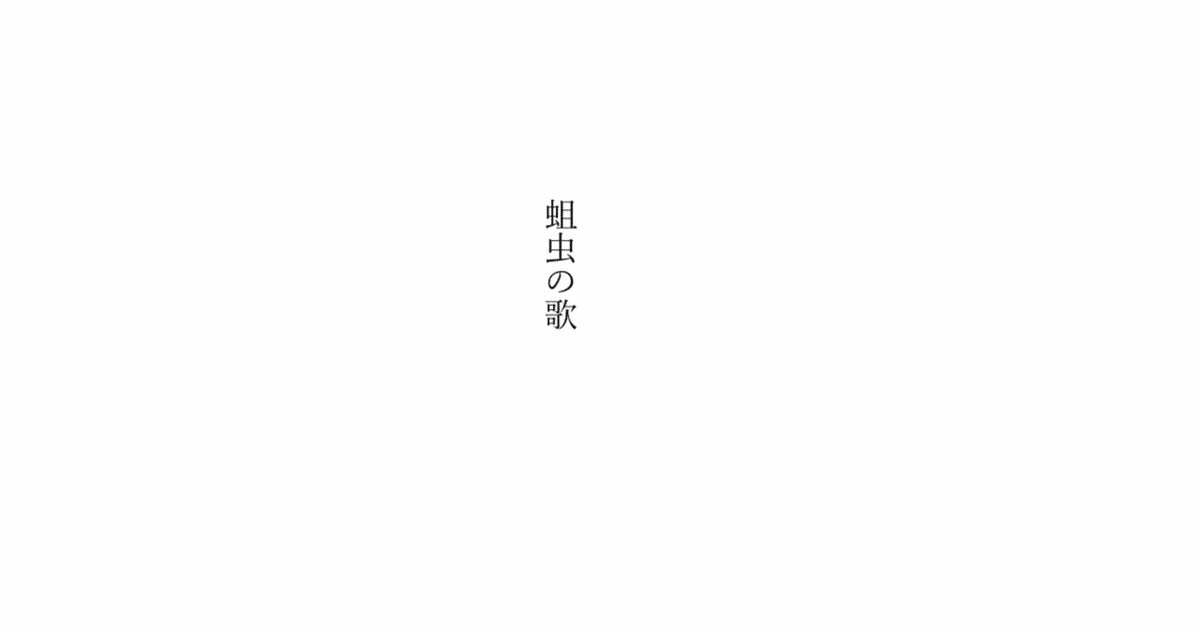
蛆虫の歌 5
5
目を覚ますと、天井が見えた。なんだ、天国にも天井があるのか。てっきり、天国には天井が無いものと勘違いをしていた。じゃあ、神はどこだ?いや、生前あんなに無気力にいきていた僕なんか神に謁見することなんて許されないか。じゃあ天使はどうだ?僕を迎えに来る天使くらいはいるはずだ。すると、耳元で声が聞こえた。
「大野さん目を覚まされました!」
なんだ、目を覚ましただけで誰かに報告するなんて中々いい待遇を受けているじゃないか。生前、あんだけ散々だったんだ。天国でくらい良い思いをしたっていいじゃないか。
「雪成…!雪成!」
聞き覚えがある声がする。まさかと思って横を見るとそこには母親の姿があった。どうしてだ、母親はまだ死んじゃいないぞ。何故だ、そう思って視線を少し下にやると右の内肘に点滴が繋がれていた。
僕はここでやっと何が起きているか理解した。どうやら、僕は死ぬことに失敗したらしい。僕が天使だと錯覚したあの声はただの白衣の天使であった。そして、僕が目を開けて最初に見たものは、天国ではなくただの見知らぬ天井であった。
ここでようやく、僕は自殺に失敗したことを理解した。体がベッドに深く沈み込む重力の感覚を身体のあらゆる部位から感じ取りながら、自分の体が何も欠損することなくそこに存在していることを確認する。強いて言えば今までに感じたことがないくらいの身体の怠さがあるくらいだろうか。身体を起こそうという気にもならないくらい、体が重力に支配されているような感覚があり、逆に血が通って生きているということを再実感する。
「ごめんなさい。」
僕が最初に発した言葉は母に向けた謝罪であった。現状、僕に出来ることと言えばそれくらいであった。
「全く、心配かけさせて…。とりあえずゆっくり休んでなさい。バイト先には病気をして出ることが出来ませんと伝えておいたから。話は退院して家で聞くから、何も変なことしちゃダメよ。」
「もうしないよ。ごめんなさい。」
母の心配の言葉が右耳から左耳へ吹き抜けていった。何よりも自分に落胆してしまって、人の言葉など頭に入るはずもなかった。
今、僕は地球上で最も弱い存在であるのかもしれない。朝目を覚ました時に感じる身体の重さの数万倍の重さが身体にのしかかっている。今僕が出来るのは視線を動かすことと、手足の先を閉じたり開いたりするくらいのことしか出来ないが、それだけあれば自分が生きていて死んでいないことを実感するのには十分な材料となっていた。
視線を動かして部屋を見渡す。僕が今いる場所は入院患者が4〜5人ほど入る病室の窓際から最も離れた角のベッドのようで、それは僕がまた自殺未遂で飛び降りるのを阻止するために、または僕が発狂しようものならすぐさま対処して押さえつけられるようにという意図を汲み取ることが出来る場所であった。
生きていること、即ち僕にとって死ぬことに失敗したことであるが、不思議と今は希死念慮のようなものを自分の中から感じないでいた。しかし、生きている心地がしないのもまた事実である。生物として生きている実感はあるものの、人間として生きている実感が湧かないという表現の方がしっくりくる。
僕が目を覚ましてから三十分ほど経過しただろうか。ここまで視線を動かして辺りを見渡してみたり、色々考えたりした結果、自殺未遂による後遺症などは見受けられないように思えた。未だに身体は重いが、先程よりかはマシになってきた。自分自身がどのような現状にあるか確認出来たタイミングで、それが伝わったかのように白衣のおじさんがカーテンを開いて僕に話しかけてきた。
「こんにちは。恐らく僕のことは分からないと思いますが、今回あなたの手術を担当した小俣です。大野さんの体調の確認と、今回に関しての説明をしに来ました。」
「ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ありがとうございます。」
そう言うと、小俣先生は僕に小さく会釈をして言葉を続けた。
「手術と言っても、胃の中の薬物を洗い流すという作業をしただけなんですけどもね。あとは今あなたの右腕に繋がれている点滴による投薬治療で今回は事なきを得ました。これに関しては、僕ではなくお母様のご対応が迅速であったからに他なりません。私からも感謝申し上げます。」
「家で私が寝ていたら、息子の部屋からドタドタドタとなにやら尋常ではない何かが倒れる音が聞こえたもので、部屋を空けたら息子が意識を失って倒れていたので、すぐさま救急車を呼んで私が出来る限りの応急処置をして。こちらこそ、迅速な対応をして頂き本当に感謝しか言葉がございません。ありがとうございます。」
母はうだつの上がらない僕の分まで先生に感謝の意を述べた。すると今度は、先生は僕の顔だけを見て今回に関しての説明を始めた。
「胃の中からは多量のアルコールと同じく多量の向精神薬が排出されました。言葉を選ばずに率直に申し上げるなら、自殺未遂をしたものかと思われますが。はっきり、ここで申し上げますとそれらで自殺するのはかなり無理があるのです。今回、排出されたものから見ても同じことが言えますが、仮にこの数倍の向精神薬と数倍のアルコールを摂取したところで人間そう簡単に死にはしないのです。ただ、目を覚ましたあとに人間として生活不可能な後遺症を残すだけとなるでしょう。」
どうやらそもそも、僕は死ぬことなんて出来るほど材料を持ち合わせていなかったようだ。存外、人間というのは頑丈に出来ていることを小俣先生から教えられたが、よく考えてみれば、人が死ぬことの出来る量の薬をそもそも精神科も処方する訳がないのだ。そのことを考えると途端に自分がとても恥ずかしく思えた。そして、立て続けに先生はこうも続けた。
「私は普段内科の担当をしているのですが、精神科についても過去に別の病院で診ていたことがありましたが、あなたのような「自殺未遂とも言えない自殺未遂」と言えるような状態で運ばれてくる患者を何人も見てきました。これは私が言うのに相応しいことでは無いのかも知れませんが、自殺をするのも現代は中々難しいというのを覚えておいて頂きたいのです。私たちの仕事は無論『患者の命を救うこと、または健康にすること』であり、安楽死や延命治療を放棄すると言った行為は到底許されることではありません。医療が今ではかなり発達して、限りなく死んでいる状態に近くとも延命をさせることも出来てしまうのです。」
先生は医者でありながら、個人的な死生観をその影に隠しながら僕にそう伝えた。甘さや怒りなんかを一切排除した真の優しさを先生から受け取った僕は、年甲斐もなく泣き崩れた。
「本当にごめんなさい。もう二度としません。命を救ってくれてありがとうございます。」
初めて言葉を覚えた赤子のように、この言葉をひたすら反芻した。かつて無いほどの自責の念と感謝の意を先生に伝えようとしたが、僕の拙い人生ではこれくらいしか言葉が出てこなかった。
その後、先生は二、三日もすれば退院出来るであろうと僕と母に説明し、以後一週間に一回通院することを僕に命じた。その説明を受けた後、母はこれ以上ここにいる意味も無いからと言い残し帰宅した。そして、先生の言葉通り2、3日も経つと点滴治療のお陰がすっかり体力も回復して以前と同じように活動出来るようになった。
帰宅し、病院から指示された内容の食事を母が作ってくれたものを食べた。ここで初めて、人間として生きていると実感してまた涙が溢れた。しかし、これは自殺未遂をする直前に流した涙とは全く別物であり、活力を感じさせるものであった。
そして、今回何故自殺未遂に至ったのかの事情を事細かに母に話した。すると、母は僕を殴ることもなく静かに「もうこんなことは二度としないで」と背を向けて呟いた。その背中は普段僕が見ていたはずのものであるのに、いつもよりも偉大に見えた。
家に帰って、またベッドに入った。あの病院のことを悪く言うつもりは毛頭ないが、やはり病院というのはどこか無機質で冷ややかである。それに比べて、家、とりわけ自室というものはなんと人間味のある温かさに溢れていることであろうか。一度、人間の最底辺に沈んだ経験から元いた場所に戻ってくると、その場所が如何に恵まれた環境であるか再確認出来るのは怪我の功名と言ったところであろうか。
そう言えば、自殺未遂をして意識を失う直前にケータイに何件か通知が来ていたことを思い出した。立て続けに通知が来ていたことは覚えているため、広告などではなく誰かから連絡が来ているものだろうと思われた。もしや夕夏と純介ではないのか?と始めに考えたが、ケータイの充電をした後に恐る恐る電源をつけると連絡していたのはあの2人ではなく、康太郎であった。
「お、いいねやろうよ。」「じゃあ俺曲作るから、家行っていい日連絡してよ」「酒か一本巻くかしながらやりたいね」
と三件連絡が来ていた。一瞬なんのことか理解するのに時間がかかったが、僕が康太郎に「バンドをやりたい」という趣旨とその日殴り書きした歌詞を送った履歴が残っており、そのことに対する前向きな返事であった。
僕は入院していた日も含め、四〜五日ほど何も返せずにいた。そのため、このような嬉しい連絡にもどう返していいか戸惑ってしまい小一時間悩んでしまったため、流石にこれだけの期間返信しなかったことを康太郎は変に思うだろうか。僕が四〜五日音信不通であった理由を全てここで話した方がいいのか。いや、それは会ってから話そうか。それとも一生黙っておこうか。これらのことを堂々巡り何回も繰り返し考えた挙句、
「酒はいいや、とりあえずいつでも空いてるよ」
とだけ返した。すると、すぐに既読がついて返事が返ってきた。
「いいね〜。楽しみだわ」「なんかデモみたいなの作っていくよ」「もう一曲作りたいから先に歌詞考えといて!」「明後日行ってもいい?その日休みだわ」と
康太郎も文面で分かりやすく心躍らせた様子で返してきた。
僕にとって康太郎は「光」そのものであった。これから康太郎と様々な曲を作るのだろうが、それが僕にとって生きる活力となった。この先の未来に完成された曲が待ち受けているのかと思うと、死んでしまわなくて良かったと心の底から感謝の気持ちが溢れてくるようだ。
ついこの間死の淵を垣間見たというのに、不思議と今はまた前向きな気持ちでいられているのが不思議に思えた。後悔がない訳では無い、自責の念を忘れてしまった訳でも無い、かと言って白痴になってしまうほど壊れてしまった訳でも無い。この感覚は夕夏と純介と会う直前までの気持ちに似てはいるが非なるものであった。遠からずも全く別の、もっと精神的に深いところから何か泉が湧き立つように、これからの生きる活力が出てくるのを感じ取ることが出来る。あの時は訳も分からずただ生きる活力とも思えた空元気の源泉を、あたかも自らの力で湧き立たせていると錯覚しているに過ぎなかったのかもしれない。今では明確に誰のお陰で生きていることが出来ているのか、それに感謝しつつも決して後ろを振り向くこともなければ、僕の過去を蔑ろにする訳もなしに、全てに対して正対した状態で生きる活力を実感することが出来ているのが、今とあの時の差となっているのでは無いだろうか。
これからの僕が生きる理由は康太郎と始める音楽だ。僕にはこれからを託す子どももいなければ、愛する女性さえいない。誰かのために生きるということも素晴らしいことこの上ないことだと思うが、僕にはその気持ちは到底理解も出来ないだろうし、理解するのも烏滸がましいとさえ思う。
康太郎からもう一曲分の歌詞を書いてほしいと言われていたため、また基盤となる歌詞をもう一個用意することとなったわけだが、すぐさま思い浮かんだのは「生きる活力とあの時みた青い光」というテーマであった。僕にはエモいともてはやされるような恋愛の歌詞も、ましてや世界の平和を願うような歌詞を書くことは出来ない。しかし今の僕には何だか暖かい気持ちになれるような歌詞が書けるような気がしていた。
しかし、以前暴走機関車のように走っていたペンを動かす手が思ったように動いてくれない。前回は一瞬たりとも止まりはせず、逆に言葉がダムを壊してしまうほどに溢れていたが、今回はその言葉のダムが枯れてしまっているようだ。これは何も言葉に詰まってしまっているというよりかは、躁にも似た初期衝動が足りないからのような気がした。あの時は書きたいテーマもなければ、歌詞を書くのも初めての経験であったのにも関わらず、走り出すペンが止まらずに逆に上手くまとめるのに困ってしまうほどであった。
あの時の初期衝動は一体どこへ行ってしまったというのだろうか。言葉に詰まるストレスの気を紛らわすため、少し散歩にでも出てみることにした。
時刻は午後八時を回っていた。前回とは打って変わって空の青さは夜の昏さを見せている。天気も前回は一点の曇りもない快晴であったが、今はどんよりとした厚い雲が空を覆っていて、快晴であれば見ることの出来る月と小さな星々も雲に隠されてしまっている。しかしそんなことには構いもせず世の中はまわっているように、金曜日のこの街には飲み屋を練り歩く人々で溢れる。この前までこの世界に受け入れられずにいることを、自分の思い通りに世界が回ってはくれないことを心のどこかで嘆いていたが、もう今ではそのことにも諦めがついた。僕はどれだけ社会に迎合するためにこの世の中のことを考えたところで、僕と僕以外の人間では見ているものであったり、感じたりすることの全てが違うのだ。これは僕が社会を侮蔑しているからではなく、むしろリスペクトを持っているからこそ感じる違いであり、お互い交じり合えあえないのであればそっと関わりあうことを辞めた方が、僕も社会も都合がいいと感じたからに過ぎなかった。
僕以外の社会で真っ当に生きている人間からしたら、何かを楽しむことに星空は必要無いし、雨が降っていなければ自分が楽しみたいことを態々取り止める必要もない。それほどに社会に生きる人間というのは鈍感であり、ある程度環境が変わろうと生活は変えずに強くあることが出来る。僕は社会に鈍感に生きることが出来るほど頑丈に作られた人間ではないし、何か少しでも環境が変わってしまおうものなら気を病んでしまうくらいには繊細で軟弱な人間であるため、そもそもこの社会で生きようとするこがお門違いである話なのだ。
逆に少し外に出て、今日の空の様子を見るだけでここまで一喜一憂することの出来る僕はとても幸せだ。きっと世の中で真っ当に働いている人間の中にも、本質的には僕に近い人間もいるのではなかろうか。この飲み屋街の人混みの中にも世の中に対して、いやこの世界に対して僕と同じような視線や感覚を持って生きている人間もいるはずだ。生まれやそれまで生きてきた経歴、性格なんかの都合で社会からはぐれてしまうことを恐れて、自分なりに生きたくともそれをすることが出来ないでもどかしい思いをしている人間がこの中にもいるのだと思うと、同情もしたくなるし応援したくもなる。恐らく、康太郎もそのような思いを抱えているからこそ、僕と音楽を始めることを喜んでくれたのだろう。
三十分ほどの夜の地元徘徊を終えて考えをまとめることが出来た。テーマとなる「生きる活力と青い光」というのを基に、何か頑張っている人々を元気づけられるような、勇気づけられるような歌詞を書くことに決めた。そのように考えを纏めると、初めて歌詞を書いた時のようにペンを走らせることが出来た。
「君をここから連れ出したいんだ
ここじゃ狭くて息苦しいから
君が心を失わぬように
君が命を絶やさぬように
君の生きる理由となる火を
決して消えることのない光を
いずれ来る終わりの青が
憂鬱を帯びて僕を迎えに来た
まるで死の色を帯びた鮮やかな青だった
ならば生きた朱い炎を僕らは燃やそう
いずれ僕らにも終わりは来る
青い光が僕らを迎えに来る
太陽も月も雲も星もすべてが愛おしい
それを隠す石の柱が
僕らの肺を壊すんだ
ならばここよりもどこか遠くへ
誰もいない広いどこかへ
滾る命が消えることのない
空の見えるどこか遠くへ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
