
WanTu ルールが変わってる。ヘンテコなゲームをご紹介します
プロフィールですでに書きました通り、私はゲームシステムのコレクター&ゲームシステムのクリエイターです(自称)。
そんなことを主張する人物なだけあって、私は「ヘンテコなゲーム」、すなわちボードの形がヘンテコなものとか、あるいはゲームルールが「変・奇妙」なのとか、どっちかに当てはまるゲームが、実はものすごく刺さります。そういうの大好きなんです。
そんなわけで、本日はWanTuをただ単にゲーム紹介します。それだけに終始する記事です。
WanTuは、Hiku Spiele社というドイツの工房が開発したゲームです。この会社のゲームはヘンテコ物品がかなり多いのです。後日の記事で、あと2~3つほど、この会社の作品をご紹介したいなと計画中です。
ところで、BGGに書き込まれた「まことしやかなウワサ話」によりますと、どうやらHiku Spieleの創業者2人がすっごい不仲になってしまい、その影響からおそらく新作が出るのは絶望的だろう・・・なーーんて書き込みがあります。
うわさですからね。実際のところは、どうなんでしょう?
とにかくドイツの出来事なんで、それが事実でもデマカセでも、どっちにしても私には手の打ちようもない話です。
ただ、もし、この会社から新作が出ないとすれば、とっても悲しいです。だって、ヘンテコゲームが多いんだもの。ここ。
ここのゲームって、ゲームシステムコレクターの血が騒ぐような、マジでヘンテコ作品が多いんです。私にとっては、ゲームそのものが楽しいかどうかよりも、システムが新規でヘンテコかどうか、のほうがずっと刺さります。
ということでゲーム盤はこんな感じです。
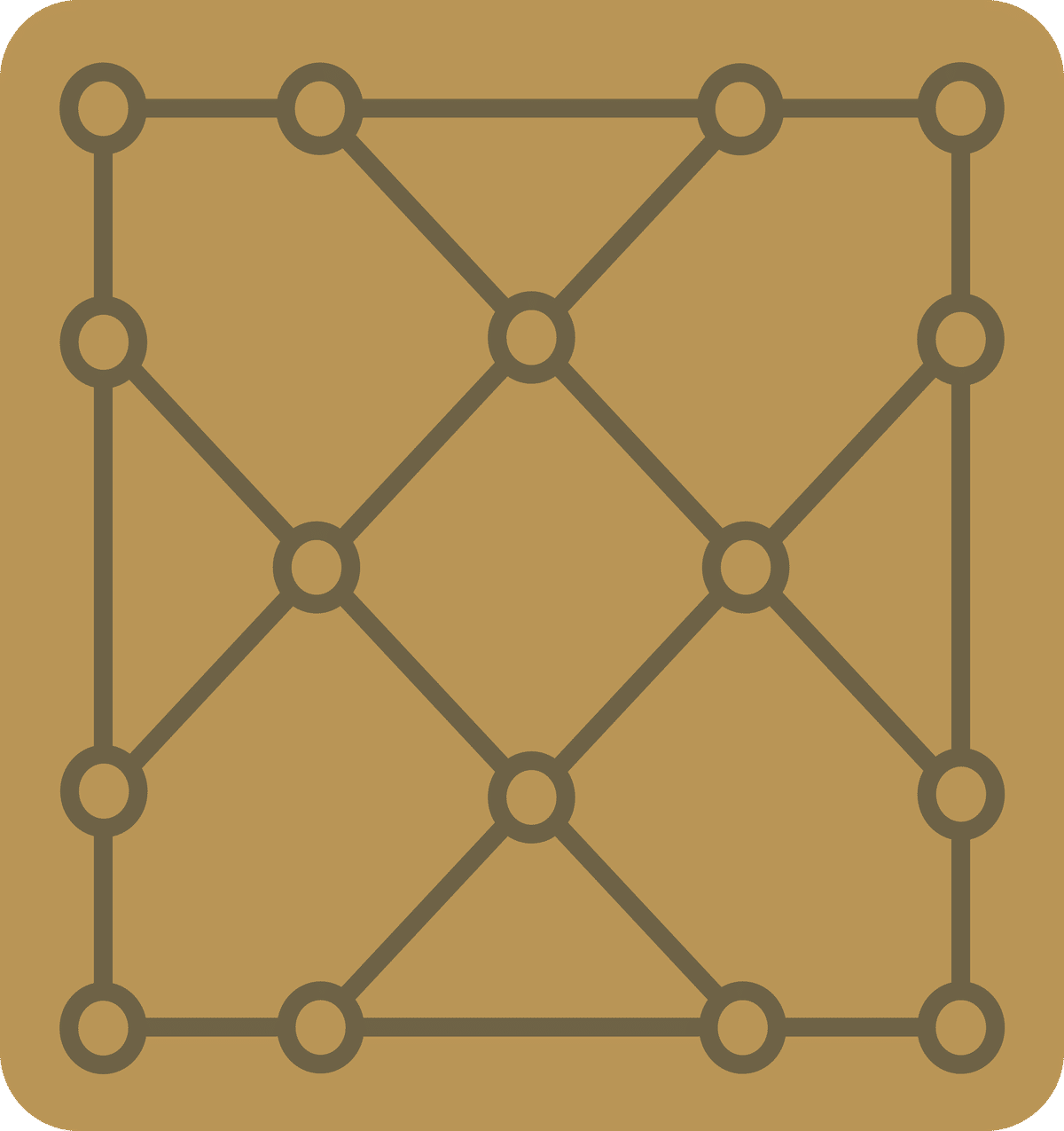

私の手作りイラストですんで、これらの画像には著作権を主張します!
第1期と、第2期とでゲーム盤デザインが全然変わっています。なんか、見た目が全然違うんですけど!
でも、同じルールで遊んでみたところ、確かに、全く支障がないことを確認いたしました。
和訳をご紹介しますね。なお、この和訳はゲーム本体からではなくて、ドイツのEssen Messe(ゲーム見本市 at Essen)のビデオ映像(BGGが所蔵)から日本語化したものです。私が。
(ドイツ語、かなり分かんないので、ちょっと大変でした。)
ゆえに、たぶん誤訳はないだろうとは思うのですが、万が一くらいの確率で誤訳があるかもしれません。
WanTu 2 players
勝利条件:
ルールに従って交互にターンを行う。いちばん最後に、自分のターンを完了できた人が負け。
=ルールを守ろうとすると、自分のターンが完了できない人が勝ち。
用具:
ゲーム盤 全部で16個のスポットがあるもの
コマ 赤緑白 の3色。各々が6個ずつあり、合計18個。
準備:
ゲーム盤の16個のスポットすべてに1つずつ、コマをランダムに置く。全18個のコマがあるので16個のスポットに置くと2個のコマが余る。
余ったコマは各自1個ずつ「手持ちのコマ」として持つ。(すぐ後で使用する)
遊びかた:(自分のターンで行うこと)
ゲーム盤上から、隣り合っていて、しかも同じ色同士の2つのコマを取り除く。ただし全く自由に選べるわけではない。以下の★の条件を可能な限り守らなければいけない。
★2つのコマを除去した直後に「手持ちのコマ」をゲーム盤に出すことになる。そのコマの色は除去した2つのコマとは異なる色にできるように、除去する2つのコマの色は、できるだけ配慮しなければいけない。
コマを除去した2つのスポットのうちどちらか一方に「手持ちのコマ」を置く。このコマの色は、除去したコマとは、必ず別の色でなければならない。
除去した2つのコマのうち1つは新しい「手持ちのコマ」になる。もうひとつは、ゲーム盤の横の「捨て場所」にまとめて置いていく。
*自分のターンが完了できた場合は、ゲーム盤上からコマが2個減って、違う色のコマが1個増える。
*自分のターンが完了できないならば、あなたの勝利。
バリエーションルール:ルールを部分的に変更してもよい。
・除去する2つのコマは、すぐ隣り合っている必要はなく、同じ線の上にあれば良い。
・同じ線から2つのコマを選ぶ、というルールを正反対にして「2つのコマを選ぶ際には、同じ線に属しているコマを選んではいけない」とする。
・2つ除去した後に別の色のコマを1つ置くルールに関しても、コマを除去したスポットから選ぶのではなく、除去したコマと同じ線の上なら別のスポットに置いてよい。
追伸:
バリエーションのところは原作にはありません。私が勝手に加筆したものです。
ゲームシステムのデザイナーって、何なの?どういう意味? そんな疑問は、私の記事群によってご理解いただけるものと期待してます。 ラジくまるのアタマの中にある知識を活用していただけるお方、サポート通知などお待ちしています。
