
楽しさとストイックさのバランスをとりながら選手寿命をのばす食の知見が蓄積
男子400メートルハードルの日本記録保持者で、五輪にも3度の出場経験がある為末大さんは、2012年に競技生活を引退して以来、さまざまな活動を通してスポーツや健康、ライフスタイルなどに関する発信をしています。体づくりがダイレクトに成績に響くアスリートたちは、ストイックに食と向き合うイメージがありますが、それは競技や人によりけりで、意外にも、アスリートと食の研究はまだ歴史が浅く、伸びしろは十分にあるようです。
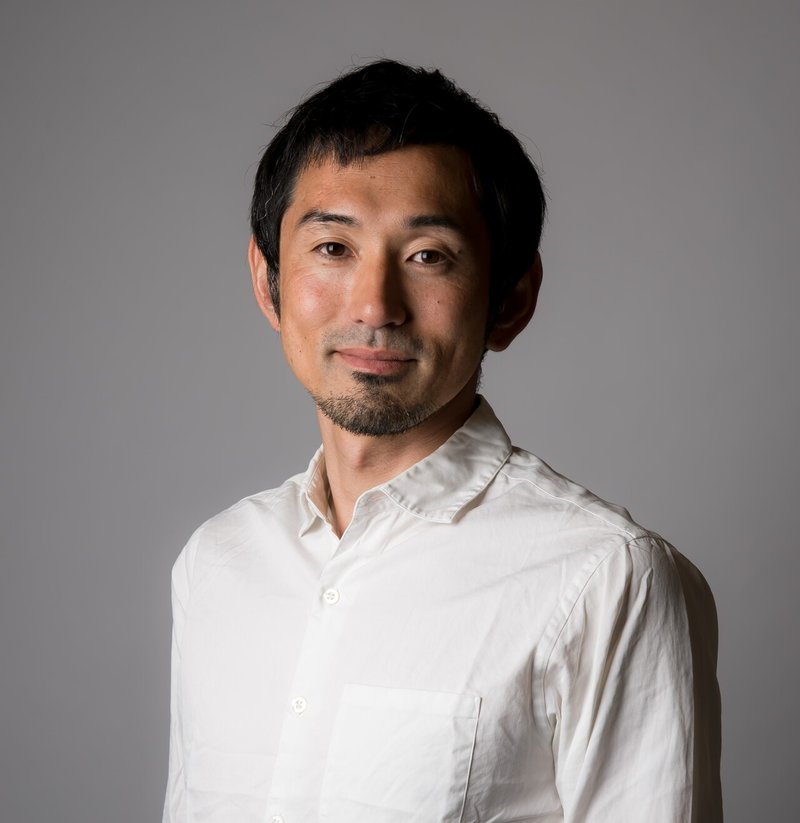
為末大(ためすえだい)
1978年広島県生まれ。スプリント種目の世界大会で日本人として初のメダル獲得者。男子400メートルハードルの日本記録保持者(2021年10月現在)。現在は執筆活動、会社経営を行う。Deportare Partners代表。新豊洲Brilliaランニングスタジアム館長。Youtube為末大学(Tamesue Academy)を運営。国連ユニタール親善大使。主な著作に『Winning Alone』『走る哲学』『諦める力』など。
高齢ランナーに対する知見は日本がリードできる
――為末さんの最近のご活動からお話を伺えますか?
為末 10年くらい前に引退してからはさまざまな活動にチャレンジしています。その活動の柱は3つあって、ひとつは「身体やスポーツに関わることの言葉化」です。今回のようなインタビューの仕事や講演会、そしてコメンテーターとして、アスリートの立場からスポーツのこと、身体にかかわることを、言語化して広めていく活動です。ふたつめは、会社事業としての「ランニングを中心としたビジネス」です。ランニングを行う施設を作り、クラスを開き、それに関わるテクノロジーといったものの開発をしています。
――為末さんのお名前はIT業界からもよく聞こえてきますし、投資家としても活動されていますよね。
為末 スポーツのスタートアップへの投資ということで5~6年前から一生懸命やってみて、今もなんとか会社としてこぢんまりとやっているんですが、しっかりやるならばVC(ベンチャーキャピタル)やファンドを作って取り組まないと駄目なんだなっていうことがわかりましてね。自分がそこまでの覚悟があるかというと、能力的にはむずかしいかも知れないと思えてきたので、今は若者に頼まれて、それが未来ある投資だったら、個人で粛々とできるレベルでサポートするつもりでやっています。
――為末さんのお力でしたら、そこからすばらしい成果が生まれていきそうです。
為末 ありがとうございます(笑)。 3つめの活動は、「アジアの選手たちを育成すること」です。日本を含むアジアの力ある選手たちを育てていきたいですね。そしてゆくゆくは日本とアジアのさまざまな国の選手間同士が支え合えるランニングビレッジみたいなものを作りたいと思っています。それができたら各国から日本に長期のランニング合宿に来られたり、日本に住む幅広い年齢層の方がこの村で思う存分、ランニングを楽しんだりすることができる。そして我々は、そのノウハウと知見を蓄積していくことが重要だと考えているんです。
――スポーツにおける知見の蓄積ということでいえばアメリカがトップを走っていますよね。日本とはスポーツビジネスとしての成熟度の違いもあるのでしょうが。
為末 おっしゃるとおりで、アメリカと日本では大きく差が開いています。でも、高齢者のランナーに対する知見という意味では、日本の方が、実はこれから先行していくんじゃないかと思っているんです。要するに、生涯にわたって長く走り続けられるにはどうするか、ということです。私自身、現役のときに膝を痛めてしまったんですが、この膝がなんとかならないかなぁ、もう一度走れないかなぁと思っていて。再生医療といったことも必要なのかもしれないですが、我々はトレーニングによるリハビリによって、なるべく多くの人が「走れなくなる」ということが「ない」ようなサポートを考えているんです。
――高齢化は日本ならではのいい仕掛けですね。
為末 高齢化って、もともと日本の中に文化として存在し得るものなのかな、って思うんですよね。私もまだ入り口に立ったばかりではっきりと申し上げにくいのですが。たとえば、選手の怪我というのは局所的なもので、膝なら膝、肩なら肩と、その部分に特化して治せばいい。いっぽうで高齢化というのは、人体の統合的な問題だと思います。内臓に問題が出たとしても、実は歩く量が減っていたことが原因ということがある。つまり高齢化の医療というのは、西洋医学的なアプローチがとてもやりにくい世界といいますか。どこか悪いところがあったら、原因はいろいろなところにある。だから、年齢を重ねても変わらず歩くことや走ることができることが示せれば、人類全体にとって、非常によいインパクトが与えられるんじゃないかと思っています。
――具体的にはどうすればいいんでしょう?
為末 たとえば、よく行われているウエイトトレーニングというのは、足に負担が大きいんですよ。歩行・走行寿命を短くしてしまいます。トレーニングをやり過ぎたために選手生命を短くしていた、という話はよくあります。歩行や走行にとって関節は非常に重要なファクターなんですが、ウエイトは重たいから関節に負担がかかる。関節は消耗品なので、負担が強くかかり過ぎるとダメになってしまいます。関節を少しでも長く生かすためには、もしかしたら将来的には、ある年齢以降の関節にとって適切な負荷値のような数字が出ていて、歩いたり走ったりするためには、どこどこの筋肉は、これ以上はつけないようにしましょう、といったようなコントロール法も出てくるんじゃないかと思っています。だから私は実験的に、太らないようにしています。いまは65キロぐらいなんですが、それをキープして自分の身体を観察しているんです。
――そういえば、テニスの選手は選手寿命が長くないですか? アスリートとしてトレーニングはするんですが、ただパワーのためにがむしゃらに筋肉をつけるのではなく、怪我をしないように体をやわらかくしながら、食事を含めてトータルで、体の仕組みを考えつつトレーニングをしている。その結果、年齢が高くてもプレイをし続ける人が多いように思います。
為末 テニスの場合はシーズンが長いですからね。1年で1~2か月しか休めないと聞いています。長い期間戦い続けるためには体調の維持が必要不可欠ですから、知見がたまってきているんでしょうね。だから、選手生命が長い選手がたくさんいるのではないでしょうか。でもそれも最近の話ではないですか? 僕の世代は、まだもうちょっと粗かった感じがします。僕の選手としてのピークは30歳ぐらいとされ、世の中的にもなんとなくそうだろうな、ということになっていて。でも、今思えば、34歳ぐらいまでは引っ張れたんじゃないかと思っています。選手時代の最後のほうは膝とアキレス腱を痛めていたんですが、これも今思えば20代の頃に結構 硬い地面をバンバン走っていて、それが終盤にマイナスに効いたような気がしています。
――世代によっては、水を飲んではいけなかったとか、トレーニングにうさぎ跳びがあったとか、今思えばおそろしいことをやらされていましたね。
為末 我々の世代の選手というのは、そういった若いときの後悔があるので、フィードバックしてみて、身体がなるべく壊れないようにして競技を長く続け、引退後も健やかに生きていくような方法は何だろう? という考え方が、陸上でもようやく回り始めてきていますね。
モチベーションの維持には食べる楽しさも必要
――トレーニング方法だけではなく、体をトータルで考えるという点では食生活が非常に重要だと思うのですが、
為末 そうですね。食生活は非常に大事ではあるんですが、なかなかむずかしいところはあって。というのは、僕が選手時代、栄養士の方がついて、「完璧にやるぞ!」みたいになったことがあったんですね。あれはダメ、これはダメ、体づくりのためにはこれを食べなさい、といった厳しい指導がありました。そこで何が起きたかというと、今度はメンタルの方のカウンセラーが、ちょっとやめてくれないか、と栄養士にストップをかけてきたんです。好きなものを食べる、食べたいものを食べるということができないと、選手のモチベーション切れちゃうんだって言っていました。だって、アスリートは食べることぐらいしか楽しみがないでしょう? みたいなことで、栄養士とカウンセラーがぶつかったんですよね。でもそれを見てきて僕が今思っているのは、そんな両極端で議論するのではなく、全体で考えて、健康で長生きしたいけど、そのために我慢したくないという心理も大事にしたいと思うんですよ。健康や長寿といったキーワードを機械的に突き詰めると、楽しさの方がなくなってしまうことがありますよね。そのバランスのとり方が、おそらく未来はもっとうまくなっているように思うし、うまくならなきゃダメだと思います。
――食事はエサではないですものね。楽しみたいです。
為末 先ほどテニスの話が出ましたが、杉山愛さんは、食べ物にはほとんど制限をかけなかったっておっしゃっていました。それはやっぱり、テニスみたいに長いシーズンを過酷に戦っていくなかで自分をキープするためには、もう食べることしか楽しみがなかったそうです。もちろん、アスリートのなかには思いっきりストイックにいける選手もいますけれど、食生活に関しては選手によって選択肢がもっと出てくるんじゃないかなって気がしていますね。
――スポーツ選手には、ストイックにこれしか食べない、という人たちも多い印象です。イチロー選手のカレーの話は有名ですが。
為末 そうですね。まだはっきりとした研究は少ないんですけど、アスリートは一般の方たちよりも、ストイック性が強い傾向にある人は多いようです。野球や陸上というスポーツは単調な動きを何万回も繰り返して、その微細な違いを察知しながら、いかに修正できるかがとても重要な競技です。そういう競技に強い人は、ルーティンを大事にしています。同じ服、同じごはんがあることで自分を落ち着かせる傾向にある。毎回同じ食材、料理を持ち込んで食べていた人たちもいます。栄養バランス的にはどうかと思う場合もあるんですが、その人にとってはそれでいい。でも、これから未来になるとわからないですよね。ルーティンを大切にしている人たちにとってパーフェクトフードのようなものが出てきて。それをルーティン化することで記録が伸びるということがあるかもしれないですからね。
――為末さんの選手時代の食生活はどうだったんですか?
為末 僕はあんまり気にしてなかったですね、でも栄養学的な知識は入ってきました。90年代では、ちょうど僕が中学生の頃ですが、炭水化物、タンパク質、ビタミンといったことを大まかに分類して、そこに、乳製品的なものを加えるのがよいというようなことを陸上合宿の度に叩き込まれていました。ですから、ざっくりと、ですが意識をしながら食べるクセはついていました。でも本当に厳密にやっていたかというと、そんなことはなかったです。

(c)月刊陸上競技
――これからは食べ物をもっと意識する時代になり、それに特化したインフルエンサーが出てくるということはありますか? アスリートたちは記録を出したいから、何を食べれば記録が出るか? 最大限のパフォーマンスができるか? ということを知りたいと思うんです。
為末 それはあると思いますね。僕が理解しているスポーツの中で、もっともシビアなのは女子マラソンなんですよ。というのが、女性は脂肪がつきやすいのに体重制限がかなり厳しい。脂肪が10g増えるだけで着地の度に足の負担はかなりになりますからね。できるだけ軽い状態を維持したい。といって、脂肪は大切で、マラソンを走るときのエネルギーになります。女子マラソンには栄養学の知識が不可欠だと思っていて、たとえばポテトチップスが好きでバクバク食べてしまうと、結局、脂肪はつくけれど、脂肪を燃焼できる栄養素が不足してしまうし、タンパク質などの大事な栄養素も足りないからハードなトレーニングについていけなくなる。どのような食生活をしていくかが、記録に大きく影響していると思いますね。
――なるほど。マラソンでは脂肪のコントロールが必要なんですね。
為末 マラソンはF1に似ているな、と思います。ガソリンカーのレースではガソリン自体の重さも影響します。最後の何週目かではガソリンを入れないで、最後にちょうど無くなるようにぴったりとガソリン量を合わせたりするそうなんですが、マラソンもそうです。だから体内の脂肪の量を、42.195キロを走行したらちょうど使い終わるように調整しておかないとダメなんです。体を絞り過ぎてしまうと35キロ付近でガソリンが切れてしまって動かなくなってラストスパートができない。逆に多すぎるとそれ自体が重さとなるので足に負担がかかる。そういう意味で、僕が知っているスポーツのなかで、体の管理が一番シビアなのは女子マラソンだと思っているんです。だから、女子マラソンは食について相当な知見がありますよ。彼女たちはアスリートと食に関するインフルエンサーになり得ると思います。
――単純に体重を軽くすればタイムが出るということではないんですね。
為末 はい。でも、女子マラソンはちょっと特別で、それ以外のスポーツに関しては、食生活に関してそこまでシビアではないと思いますね。もちろん、取り組んでいるところもあるんでしょうけれど。食に関する考え方は西洋と東洋とでは差があるように思っていて。たとえば、特にアメリカはケミカルな(人工的な)ものへの抵抗感はなくて、科学的に追及する印象があります。でも東洋は、もっと医食同源みたいな思想を選手たちは肌感覚で持っていますから、ケミカルというよりはリアルな食べ物でリカバーする傾向があるように思います。練習方法の精度がかなり上がってきて、だいたいこういう風にやればいいということがわかってくると、最終的にはリカバリーの話だね、ってことになっていきますね。リカバリーとは結局、寝るか食べるか、しかないので、未来はその点の精度が高くなっていくのではないでしょうかね。
――アスリートにとって30年後の食べ物が変わる可能性はおおいにあるということですかね。
為末 可能性は高いでしょうね。パフォーマンスの向上ということでいえばスポーツ界で起こったことが世間に与えるインパクトは大きいです。陸上はスポーツのなかで比較的早く科学が入りやすいんですよ。タイムという形で出ますからね。そうそう、試合前にバナナを食べるといいというのは80年代に陸上競技で始まったことなんですよ。1984年のロス五輪の時にアメリカの選手たちがみんな試合の1時間前にバナナを食べていたんです。その時は世の中的にはまだバナナがいいなんて知見はなかったんですが、アメリカのチームはすでに研究していて、試合の1時間前に消化のいいバナナを入れるのがいいってことになって、実際にそうしたら、メダルラッシュになって。それからスポーツ界はバナナを食べるっていう文化が一気に広がったんですよ。それがまず、スポーツ界の食が変わったできごとでしたね。
――それから30年後もバナナは食べられていますね。そしてこれから30年後の食というとどう思われますか?
為末 30年後は、そうですね……アスリートに限らず食の世界にはふたつの面があると思っていて、ひとつは、分解して最適化した栄養的要素の追求といいますか、徹底した分析によってある成分を完全に揃えたものを体内に摂取するという世界です。いきつくのはプロテインやパーフェクトフードでしょう。もうひとつの世界は、普段食べているものを食べていけばいいじゃないかというものです。これには、地球環境のバランスが保たれている中に自分がいるという意識があって、自然のなかで育まれた産物を摂取して、それがまた排泄され、廃棄されるという一連の生態系の中に、自分を位置づけていたいという考えですね。両方とも未来の姿だと思います。
――環境ということでいえば、SDG’Sの波が全世界的にきていて、アスリートのなかには環境のことを考えるとスポンサーと契約しないほうがいいといった考えをする人も出て来ていますよね。これまではスポンサーが絶対的存在だったものに変化が見えるように思うのですが。
為末 アスリートのなかでもSDG’Sの流れは大きくて、ESG投資(長期的なリターンをめざす投資)もそうで、ヨーロッパ中心の流れではありますが、日本企業もそれに対応していくんだろうなと思うんですね。ちょっと食そのものから離れるかもしれませんが、もしかしたらここ10年で、スポーツ界に対して大きな問いかけになりそうだと思っているのは、スポーツ選手のドリンク問題です。禁止薬物の混入を避けるなどの目的で、アスリートたちは大会の度に大量のペットボトルをひと口つけては捨て、ひと口つけては捨て、と、やるんです。1試合でひとりの選手が30から50本ぐらい捨ててしまうのではないでしょうか。これに対しての批判が来るのは十分ありえるだろうなと思っているんですよ。そのボトルにはスポンサーの名前が入っているわけですから、批判があると、スポンサーの意識も変わっていくでしょう。ただ、このペットボトル問題はなかなかむずかしくて、全部紙コップにして、スポンサードではなくパブリックなものに変更すると、今度は目を離したすきにコップにテストステロンなどを入れられる可能性がある。そうなると、ドーピング検査に引っかかってしまうリスクが出てきます。ペットボトルの口は小さくて締められるから、そうしたものの防止になってきたわけです。ペットボトルはヨーロッパの人たちが最初にクレームを言っていた印象があるので、日本も変わってくるのではないですかね。
――日本は自動販売機がいっぱいあるペットボトル大国ですからね……。
為末 スポンサーという問題がからむとなかなかむずかしいとは思うのですが、企業とともに、何か変えていかなければならない時代が来るとは思います。あと、SNSで本音をダイレクトに選手が発信する時代になりましたからね。表明してしまえば、あとはスポンサーだのなんだの、という面は関係なくなって突き進んでしまうことはあるかもしれません。
――先ほど話されていた、「突き詰めた栄養の摂取としての食」か「自然と寄り添ったごく自然な生活の食」という二面性についても、アスリートたちはSNSで自分のスタイルを発信されていきますかね。
為末 きっと発信されていくと思いますし、ひとつの問題提起になることもあるでしょうね。僕はどちらかを選ぶというより、両方とも見ていく立場でいたいです。実は選手というと、記録のために完璧な食事に行き着きそうなものなんですが、案外そうしたものではなく、ごく普通の食べもので摂取しようとしている選手は結構います。ふたつの面をそれぞれの選手が選択しているように思いますね。
個人によって栄養摂取能力は異なる
――それは、選手個人の判断で選択しているんですか?
為末 基本的には個人の判断ですね。そうそう、栄養摂取能力というものは人によって違うと言われていて、たとえばですね、ケニアの長距離選手は、日本の栄養基準でいくとやや栄養不足で、炭水化物の過剰摂取なんですよ。それでも世界記録を出しているわけです。「いや、それは環境が整っていないからであって、彼らはもっと速く走れる。だから先進国に来なさい」と言って移住させて、データに基づいたパーフェクトな食生活をさせようとしても、さほどパフォーマンスか変わらないときがあるんですね。なぜなのかっていうことを説明するにはまだ症例が少ないんですけど、一説には人間はどうも、体が摂取に慣れてしまうみたいなんですよ。つまり、凝縮したものから栄養素をとったほうが理論上は効率よく摂取できるはずなんですが、効率よく摂取し続けていると、吸収する能力が下がってくるんじゃないかというんです。だから適度に負担をかけながら摂取したほうが実は効率がいいのではないか、と。これらは科学的な根拠がわからないし、あくまでもまだ説ですが、思想的にそう考えている人はいますね。
――見えないものへのリスペクトってありますか?
為末 そうですね。実証的に選手がやってみる。そして、なぜだかよくわからないけれどもよさそうだ、ということになったらそれを科学的に証明していく。この両サイドで進んでいくんじゃないですかね。たとえば今はヴィーガンが注目されていますが、肉を食べないでやってみたところ、けっこうパフォーマンスがいいよね、ということになると、本当に肉を食べなきゃいけないんだっけ? と思うようになるでしょう。となると、もうちょっときちんとデータをとってみようかな、ということになるはずです。そうやって知見は蓄積されていきます。選手の身体は実証実験のセンサーみたいなものだな、と僕は思っています。
――アスリートの方々は我々よりもはるかに自分の身体と対峙していますよね。
為末 僕の場合、選手時代に一番よくなかったのは、何を食べるかというより、試合の時間帯によって食べるタイミングが狂うことでした。だから、朝と昼と夜をなるべく同じ時間に食べようとしてましたね。それぐらいですかね。
――海外の遠征など大変でしょう?
為末 試合時間に合わせて1週間前くらいから食べる時間を変えていましたよ。日本時間で夜10時というレースもあって、そうするともう1週間前ぐらいから夕方5時ぐらいからごはんを食べるようにしていきますね。夜型に変えていって、朝起きるのも10時とか11時にしていってっていう、そんな調整をしていました。
――食べ物と睡眠の関係はありますか?
為末 エビデンスはよくわからないんですが、僕は寝る3時間以上前に食べるということは意識していました。食べる時間と寝る時間の間隔が短くなると、朝起きたときに消化の方にエネルギーがもっていかれる気がするんですよね。寝ることによって体を回復させる方向にエネルギーが使われないというか。食べてすぐに寝ないということと、睡眠時間を削らないことには気をつけました。あと、感覚的にお酒は夜9時以降には飲まなかったです。
――お酒はアスリートにとってどうなんですか?
為末 体育会系といって昔は運動選手がやたらお酒を飲む印象がありましたけどね(笑)。アスリートの視点でいうと、お酒はやっぱり体の回復を遅らせるので、厳密に言えば飲まないほうがいいんでしょう。でも、飲む選手はいますよ。僕も飲んでいましたし。ただ、夜9時以降は飲まない、飲むのは週に1回だけ、というルールを決めて楽しんでいました。あと、トレーニングを激しくした日には飲まなかったです。アスリートにとって大事なことはリカバリー力ですから。ビジネスマンが翌日の朝からフルにパフォーマンスを発揮したいのであれば、お酒はよくないとは思います。とはいえ、お酒が好きな人にとっては飲むことがいい方向に向かう可能性もあるわけで、人それぞれということでいいんじゃないですか。先も言いましたが、30年後は両極端で議論するのではなく、全体で考えて、健康で長生きしたいけど、そのために我慢したくないという心理も大事にしていきたいです。健康や長寿といったキーワードと、生きる楽しさとのバランスのとり方が、未来への課題だし、そのために、アスリートのデータが貢献できたらいいと思っています。そしてアスリートは、目の前の記録を伸ばすためだけではなく、少しでも長く競技生活が送れるような食のあり方を考える時代になればいいと思いますね。
インタビュー:吉川欣也、土田美登世(構成)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
