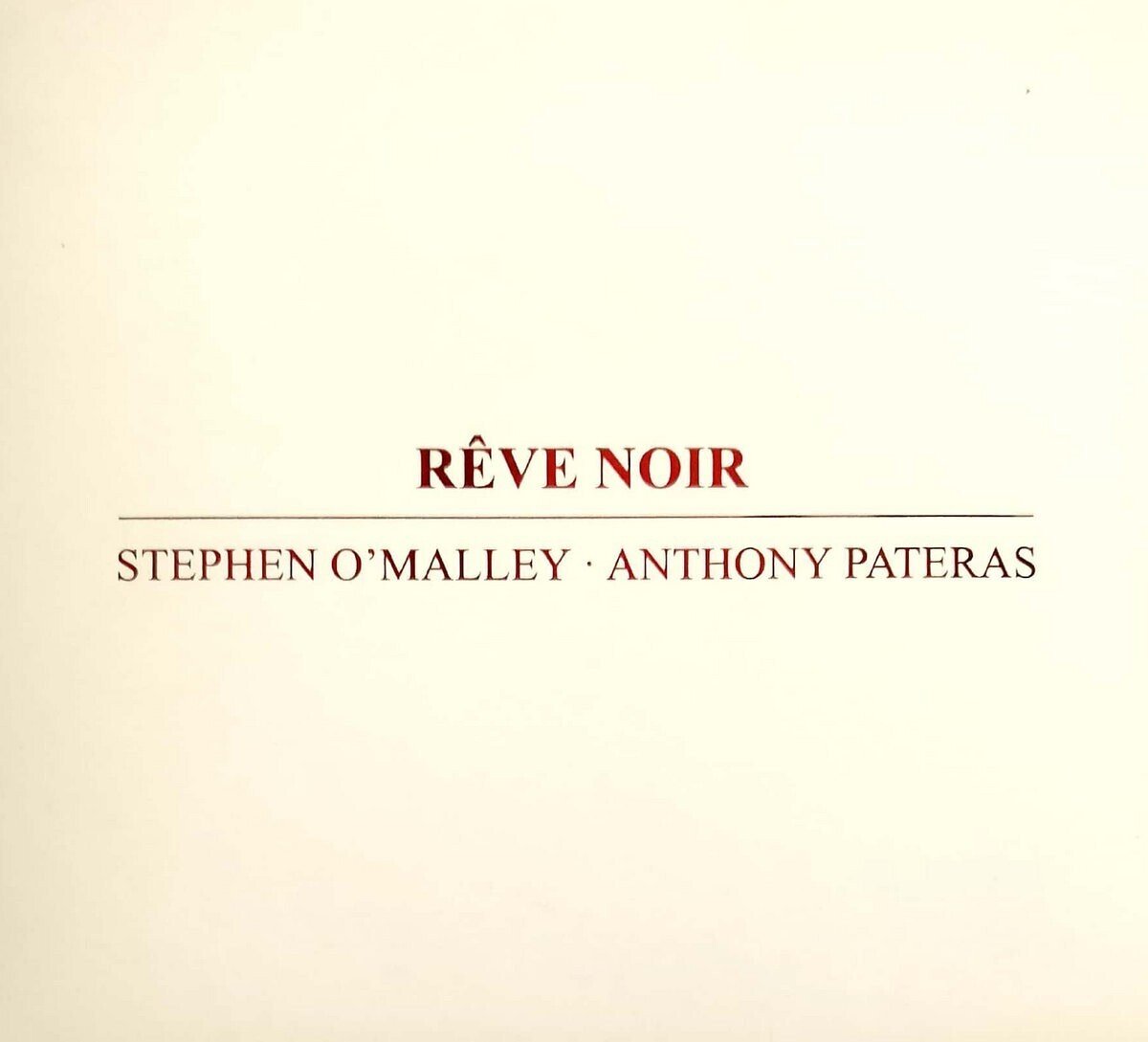「インプロ・りぶる 」というツイッター(というか現在では「X」と呼ぶべきか)のアカウントが、8月15日に「フリー・インプロヴィゼーションに初めて触れる人のためのディスクガイド──デレク・ベイリーから連なる音たち」という記事を公開した。カンパニー社 より以前出版されたJohn Corbett の書籍『 フリー・インプロヴィゼーション聴取の手引き 』 をベースとし、代表格的なDerek Bailey の作品を中心にセレクトしたものだ。
当ページではDerek Bailey [AIDA] (1980)、齋藤徹 [パナリ] (1996)、齋藤徹 & 長沢哲 [Hier, c’était l’anniversaire de Tetsu.] (2017)、阿部薫 [彗星パルティータ] (1973)、川島誠 [Homo Sacer] (2015)の計5作品が紹介されている。別にこの記事に対してケンカを売るとかそういった感情は皆無なのだが、1970年頃から現代にいたるまで50年以上の年月があり、なおかつ現在でも生き残っているジャンル/音楽手法/音楽へのアプローチの仕方であるということを鑑みると、どうも記事としてはあっさりしすぎている気がした。もちろんレジェンド的なレーベルや演奏家は多くいる。しかしここで紹介されている5作品のうち、Derek Bailey、齋藤徹、阿部薫はすでに逝去されている。それを念頭に置いて読んでみると、あまりに教科書的で、現在のシーンを蔑ろにしているように思ってしまったのだ。
そこで今回、僕個人は現行シーンから作品を選んでみようと思った。作品というものはその性質上、演奏そのものではなくそれをパッケージングしたものであり、どこまで完全な即興演奏か(下準備されていたかなど)、またエディットやマスタリングをとおしてその瞬間の音がその場の空気まで含めて収録されているかまではわからない。ただ、その場に身を置き、かつ作品を多く聴き買っている者のひとりとして、2010年以降の作品を国内外問わず20作品紹介するディスク・ガイドを作成した。もちろん、ここで紹介しているのはあくまでも氷山の一角にすぎず、ここに載っていない範囲で興味深い演奏家は多く存在する。その方々については、ぜひ当記事の読者が直接会場に足を運び、見つけていただきたい。
【国内から】 遠藤ふみ (Fumi Endo) [Cold Light in Warm Blue]
遠藤ふみによる初のソロCD作品。はじめて演奏を観たのは水道橋Ftarriだったはずだ。極端に無音の部分の音の多いそのピアノ演奏には衝撃を受けた。もちろん無音の時間が「長すぎる」というわけではない。むしろ聴き手が彼女の時間に対する感覚を共有するような演奏だった。現在はかなりハイペースに演奏をしているので、是非どこかのタイミングでそれを体感していただきたい。ちなみに僕自身によるレーベル"zappak"からはすずえりとの共演作品[トイピアノ即売会] なる作品を発表しているので、あわせてチェックしていただければ幸いである。 鈴木彩文 (Ayami Suzuki) [Vista]
自身の声を楽器のように扱い、ソロやセッションなどで精力的に活動するサウンド・アーティスト、鈴木彩文。歌のようでいてその演奏の録音はここCosima Pitzにとどまらず、さまざまなレーベルより作品化されリリースされている。あるときはエフェクトをかけて、またあるときはアコースティックに使用され、彼女の声はアンビエント的に空間のなかに溶け込んでゆく。ちなみに彼女のはじめての即興演奏デュオの相手となれたことは僕個人の自慢の種としたい(その演奏の録音はFaltより[Undercurrent/Wanderlust] として作品化されている)。 本藤美咲 (Misaki Motofuji) [Yagateyamu]
ジャズを中心にさまざまなヴェニューで活躍し、楽曲提供や複合パフォーマンス・グループなどにも参加している本藤美咲は、ご多分にもれず(非ジャズ的な意味としての)即興演奏にも参加している。本作はFtarriにてソロ演奏したときの録音作品である。普段はバリトン・サックスを中心に演奏しているが、ここではそのほかにクラリネット、ホイッスル、エレクトロニクス、フィールド・レコーディングなどが並行して用いられている。45分という1セットとしてはやや長尺な演奏のなかで本藤はそれらをその時々で使い分け、抑揚や展開を意識して見事にまとめ上げている。本作はそんな彼女が非イディオム的におこなった、ソロ演奏としては初となる記録である。 竹下勇馬 (Yuma Takeshita) [semi-automatic 3]
かつては様々な機器をフレットレスのエレキ・ベースに装着させた楽器(electro-bass)での演奏をおこなっていた竹下勇馬だが、近年は自作の装置(mechanized instruments)を制作、演奏している。本作は後者の自作楽器による演奏。半自動的に動く機器を竹下が微調整することによって鳴らされる音は変化する。シンセサイザーやミュージック・ガジェットによる電子音楽的な演奏とは異なり、かなり「機械(メカ)そのものの音」というようなサウンドを生み出している。時にはスピーカーも自作、持参して全方位に回転させながら音を出すこともある。彼の演奏の様子は言葉で説明しづらいため、下記の動画を参考にしてもらえたらと思う。 山㟁直人 (Naoto Yamagishi) [響む (Toyomu)]
演奏する際のクレジットは「パーカッション」と表記されることが多いが、「叩く」という行為よりも「擦る」などの要素をもちいて、低域から高域までありとあらゆる音が広がっていく。画像のリンク先より聴けるサンプルからもわかるように、彼の演奏にはいろいろな表情があることがわかるだろう。彼はその後[電話太鼓 ]なる作品を発表している。こちらはふたつの太鼓をバネでつなげあわせて演奏したもので、FM Einheitらの演奏 を想起させるようなビヨンビヨンと金属が鳴らす音とシンバルによる金属的な音の見事な邂逅を楽しむことができる(おそらく下記の動画もそのひとつであろう)。あわせておすすめしておきたい。 松本一哉 (Kazuya Matsumoto) [鐵冴ゆる / Sinking into the Cold]
さまざまな音具、銅鑼、パーカッション、また音の鳴るものを場に広げては、ときには演奏し、ときには場に佇み、残響や空間の余白をコントロールする演奏家、松本一哉。本作は(おそらく)もともと会場限定で販売されていたCD-R作品で、アルバム[無常]に収録されているもののアンカット・ヴァージョンにして、現在はBandcampにてデータを購入できる。[無常]はフィールドレコーディング的な側面がかなり強かったが、本作は氷上にて演奏をおこない、それを氷上と水中から録音しミックスしたというもの。それ単体として非常に面白い試みであるとともに、現在の彼の演奏スタイルを知るための恰好の作品に位置づけられるのではないかと思われる。 山本達久 (Tatsuhisa Yamamoto) [Ashiato]
2020年、自由にライブ活動ができない時期のなかで制作された作品。本作は同年にBlack Truffleより発表された[Ashioto ]と対をなす作品であり、両作品とも、とあるひとつの脚本を2種類の解釈から演奏し分けたものである(本作では石橋英子と須藤俊明がゲスト参加、[Ashioto]では藤原大輔と石橋英子がゲスト参加している)。本作のほうが静謐さのなかにある緊張感がより一層強く感じられて個人的に好みであったので、本作をピックアップした。現在はソロでの演奏を観る機会も多くあり、そこでのパフォーマンスも非常に興味深い。同じく関心がある方は是非生で観てみては。 毛利桂 (Katsura Mouri) [M21]
京都のレコード・ショップ「Parallax Records 」のオーナー(?)であり、ターンテーブルを使用し極めてノイジーな演奏もおこなう毛利桂のソロ作品が、「0奏 」によるレーベルから発表したソロ作。ときにハーシュに、ときに静謐に、彼女の演奏には「ノイズ」とひとくくりにできない魅力がある。本作はストイックな内容を1時間弱に凝縮した内容となっており、ノイズ・ミュージックに嫌悪感を抱いていたり、食傷気味だったりするリスナー陣にも届くのではないだろうか。 秋山徹次 (Tetuzi Akiyama) [S/T]
国内の即興演奏のフィールドにおいての「キャプテン」こと秋山徹次。本作は東北沢にあるヴェニュー、OTOOTOにておこなわれたアコースティック・ギターとエレキ・ギターそれぞれで演奏された2曲を収録している。これまでの彼の長いキャリアの集大成という表現は適当ではないと思われるが、他の演奏家と共演する機会がかなり多いように思えるため、ソロとしての録音、それもアコースティックとエレキでの2種類の演奏を1作品のなかで楽しめるというのは非常に貴重に思える。 【海外から】 Valentina Magaletti & Laila Sakini [CUPO]
Valentina Magalettiは元Tomagaのメンバーであり、Holy TongueやMoinのメンバーとして活躍するいっぽう、ソロや共作のリリースでも活発だ。そんな彼女がセルフ・リリースした本作は、DJ兼マルチ奏者であるLaila Sakiniとのコラボレーション。SakiniはこれまでにBoomkat EditionsやModern Loveなどの大きなレーベルからもソロ作品を発表している。Magalettiのドラムは淡々と反復するようなものが多く、伝統的なトランス音楽のような雰囲気があった。本作ではそのあたりをSakiniが打ち破っていったのだろうか。ここではアンビエンスに満ちた、特異な空間が常に広がっている。 Charmaine Lee [KNVF]
今日のアメリカでのエクスペリメンタルなシーンにおいて、「ヴォイス」のアーティストとしては真っ先に彼女の名前が出てくるだろう。複数のマイクやポータブル・レコーダーを使い分け、自身の声だけでも即興的にさまざまな質感の音を作り上げている。自然体な彼女の声はノイズの波のなかに消えていき、また唐突に現れる。彼女の口からは何の音か想像もつかないような音を生み出されており、本作は彼女のこれまでのレパートリーをひとまとめにした集大成的な作品のように感じられる。ちなみに、ヴォイスといえばAmirtha Kidambiも興味深いパフォーマー(後述するLea Bertucciとも頻繁に共演している)であるので、ここであわせて紹介させていただきたい。 Marina Rosenfeld & Ben Vida [Vertice]
ターンテーブル(およびそこでプレイするレコード)を主たる楽器として演奏するMarina Rosenfeldと、モジュラーを中心にシンセサイザーでの演奏を多くおこなうBen Vidaによるデュオ作品。この二人によるデュオ作品はほかにも901 Editions やiDEAL から発表されているものの、その作品群ではBen Vidaの電子音が主体となっているように感じられ、本作では両者の演奏のバランスや組み合わさり方が面白くまとまっているように感じられる。Marina Rosenfeldはソロで作品をいくつか発表しているため、彼女の魅力はそちらからのほうが感じ取りやすいかもしれない。なお、Rosenfeldの存在をはじめて認識したのが下の動画。本作と同じくBen Vidaとの共演で、掛け合いが面白い。 Lea Bertucci & Leila Bordreuil [L'onde Souterraine]
今ではすっかり有名人の仲間入りをはたしたLea Bertucciが、フランス出身で現在はブルックリンを拠点とするチェロ奏者のLeila Bordreuilと連名でリリースした作品。Lea Bertucciはクラリネットのほか、シンセサイザーやオープンリールを使用した演奏をソロ/セッション問わず極めて頻繁におこなっている。いっぽうのLeila BordreuilはRelative PitchやAstral Spiritsなどジャズ系のレーベルを中心に作品を発表している。ただしそのイディオムにとどまらない演奏をするのが彼女で、その様子は下の動画からも感じ取れるかと思う。なお、本作はこの記事で紹介した作品の中で唯一Bandcampに掲載されていない作品のため(各種ストリーミングでの配信されている)、上の画像をクリックすると4曲目'Stag with Lightning in Its Glare'のYouTube動画に飛ぶようになっている。 Various Artists [silence is shit]
当初の予定では個人やセッション、ユニットなどの作品を紹介しようという考えがあったが、中国の最先端のシーンを紹介するにあたって誰かひとりに絞るのは非常に難しいと思えて、本作を選んだ。Sub Jamは中国のエクスペリメンタルなシーンの先駆け的存在のYan Junによるレーベルで、これまでさまざまな作品をリリースしてきた。そんな彼が若手(?)を中心に9人を選出し、それぞれが作成した作品を9個ひとセットにして発表した。個人的には知らない名前が多いが、中国の地下シーンはなかなかオープンに活動することが難しいため、これを聴くだけでも(各作品の面白さはもちろんだが、)資料的価値があると思う。なお、ここには参加していないが、「Zoomin' Night (レーベル兼イベント)」およびその運営をおこなっているZhu Wenbo も現在の中国シーンのキーマンのひとりであるので、チェックすると面白いかと思う。 Valerio Tricoli [Clonic Earth]
リール・デッキを中心的に使用して、複雑なコラージュを即興的に作り上げる印象の強いValerio Tricoli。彼の作品は演奏とは異なり割とスタジオ編集的なものを感じるものが多いため、キャリアのなかでは少し古い作品ではあるが、本作をピックアップした。微細な音から激しいノイズまで縦横無尽に行き来する様子は、即興的な演奏であることを疑ってしまうほど。いくらかの演奏の映像ではDJ用のCDプレイヤーなども使っているため、プリペアドされた音も多く使用されているのだろうが、この混沌とした音響を巧みに作り出すスキルは素晴らしい。来月にはMordecoli名義(Ecka Mordecaiとのデュオ)での新作[Château Mordécoly ]がALTERより発表される。そちらも楽しみに待ちたい。 Jérôme Noetinger & SEC_ [La Cave Des Étendards]
もともとはMetamkineのオーナーとして、レーベル運営やディストリビューションなどにも携わっていたJérôme Noetingerと、イタリアの中堅SEC_による共演の様子。ともにRevox社製のオープンリールのデッキを使用して、両者とも即興的にそれを演奏する。リール・テープのなかにはすでに何かが収録されているかもしれないし、そうでないかもしれない。スクラッチDJのようにキュルキュルとこすってみたり、わざと遅く引き伸ばして不思議な音を生成する。本作はその緩急が絶妙に取れた作品となっており、各曲の後半に現れるヘヴィーな反復する音も刺激的。なお、下の動画は本作に収録されている演奏の様子の一部である。 Stephen O‛Malley & Anthony Pateras [Rêve Noir]
Stephen O'Malleyを説明するにあたって、「Sunn O)))のメンバー」という言葉はもう不要だろう。ソロとして、灰野敬二らとの共演者として、ときには作曲作品にも取り組み、Southern LordやIdeologic Organのレーベル運営もおこなっている。本作は彼の得意とするギター・ドローンの演奏で、対するAnthony Paterasは電子オルガンやピアノ、エレクトロニクスで対峙する(普段の彼はピアノの演奏をメインでおこなっているという印象があり、本作を発表したレーベルImmediataも彼の運営している)。フィードバックを中心としたエレキ・ギターとPaterasによる電子オルガンによる持続音は非常に有機的に絡まっており、そのときどきにアクセントとしてエレクトロニクスやピアノが使用されている。収録されている3曲はおそらく一続きではないが、聴き手に強い緊張感を与えてくれる。長いキャリアのなかでつちかわれたお互いのセンスには脱帽する。 Mika Vainio, Kevin Drumm, Axel Dörner, Lucio Capece [Venexia]
Mika Vainio、Kevin Drumm、Axel Dörner、Lucio Capece、という名だたるメンバーでの演奏の記録。4人組でMika Vainioや器楽演奏家が参加しているというところからVladislav Delay Quartetの作品 を想起してしまうかもしれないが、そこで聴けたような音楽的な様子はここではほぼ皆無で、複雑でアブストラクトなものが生み落とされた。弱音を中心にそれぞれ異なる持続音のレイヤーを出しては重なり合って複雑な音響に包まれるが、ところどころにおいてそれぞれの個性が炸裂する。Mika Vainioが存命でないことから本作を選ぶべきか悩んだが、残りの3名も活動的で素晴らしい存在なので、是非ともここで紹介させていただきたかった。 Mats Gustafsson & Joachim Nordwall [A Map of Guilt]
リード奏者(主にバリトン・サックス)兼ノイズ・エレクトロニクス類の演奏家Mats Gustafssonと、レーベルiDEALを運営する電子音楽家Joachim Nordwallによる共演。不穏な空気を漂わせながら演奏は進んでいき、終盤でお互い強力な持続音を放出する。それぞれがかなり激しい演奏をおこなう機会に恵まれているので、このように緊張感をたもったまま抑え気味の演奏をおこなっているというのは珍しいように感じられる。ちなみに、Mats Gustafssonは2020年にdoubtmusicから大友良英との共作[Timing]を発表しており、そちらも面白かったので、ここに紹介しておく。 Bill Orcutt [Odds Against Tomorrow]
吟遊詩人よろしく、ギターと静かな対話をおこなうように演奏するBill Orcutt。これまでにZoh AmbaやChris Corsano、またOkkyung Leeなどと共演しており、普段演奏するフィールドはやや(フリー寄りの)ジャズ寄りなのかもしれない。しかし、本作のようなソロ作品では禅的で(これを日本人がもちいるのは非常に危険なように思えるが)、アコースティック・ギターをメインとして演奏する増渕顕史のような存在とも共通項があるように思われる。ちなみに、彼とOkkyung Lee(チェロ)とのデュオでの演奏が[Live at Cafe Oto ]としてCafe OtoのレーベルOtorokuより発表されている。そこで聞こえる音はお互い極めてノイジーなものだが、読者にとって興味深いものとなることを期待している。 いかがだっただろうか。「あの人がいない」という感想はもちろんあるだろう。しかしすべてを紹介するには限界があるのでこの辺りで許していただきたい。また、これが読者にとってなにかの一歩になることを期待している。