
【トークイベント】アメリカ保守主義とは何か? ―分断されるアメリカとポスト・リベラリズム―(11/15)
ぽすけん企画 第15弾 井上弘貴著『アメリカ保守主義の思想史』(青土社、2020年)刊行記念トークイベント
アメリカ保守主義とは何か?
―分断されるアメリカとポスト・リベラリズム―
出演者:井上弘貴×石川敬史×田中東子(司会)
日時:2020年11月15日(日)18:30開場/19:00開演
場所:Readin' Writin' BOOKSTORE(参加費:1000円/10枚限定)
zoom(参加費:1000円(一般)、500円(大学生以下))
※当日のトークイベントは書店「Readin' Writin' BOOKSTORE」より配信しました。
【トークテーマ】
トランプ大統領は、2020年のアメリカ大統領選の直前にカトリック信徒である保守的なエイミー・バレットを新たな最高裁判事として指名し、議会もそれを承認しました。大統領選挙の結果にかかわらず、アメリカ社会のリベラルと保守の価値対立、とくに女性の自己決定権と中絶にかんする意見の対立、同性婚の賛否、移民の受け入れをめぐる論争についての合意の道筋がみえないまま、アメリカ社会は次の時代に突入することになります。
アメリカは一体、どこに向かっているのでしょうか? 当日は、2016年にトランプが勝利して以降のアメリカ保守主義グループのなかで生じた、保守内部の主流と傍流との交代劇に注目して現代のアメリカを鋭く描いた『アメリカ保守主義の思想史』(青土社)を刊行したばかりの井上弘貴さん、そして建国期のアメリカ政治思想史がご専門の石川敬史さんをお迎えし、分極化したアメリカと世界の今に迫ります!
司会は、大妻女子大学の田中東子が務め、リベラルとはまったく異なる世界観を構築してきた保守の側の論理をお二人に語ってもらうことを通じて、アメリカの過去・現在・未来について詳しくうかがっていく予定です。
【出演者プロフィール】
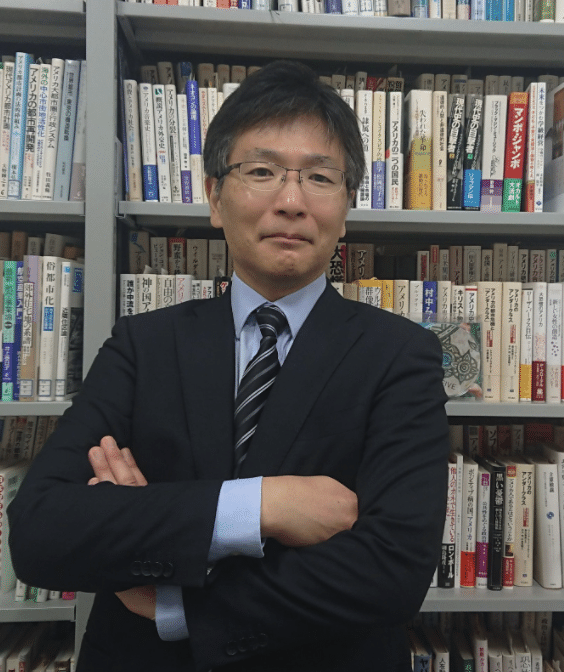
井上弘貴(いのうえ・ひろたか)
1973年東京都生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。博士(政治学)。自治体非正規職員、早稲田大学政治経済学術院助教、テネシー大学歴史学部訪問研究員などを経て、神戸大学国際文化学研究科准教授。専門は、政治理論、公共政策論、アメリカ政治思想史。著書に新刊『アメリカ保守主義の思想史』(青土社)、『ジョン・デューイとアメリカの責任』(木鐸社)、主な翻訳に『ユニオンジャックに黒はない――人種と国民をめぐる文化政治』(月曜社、田中東子、山本敦久との共訳)
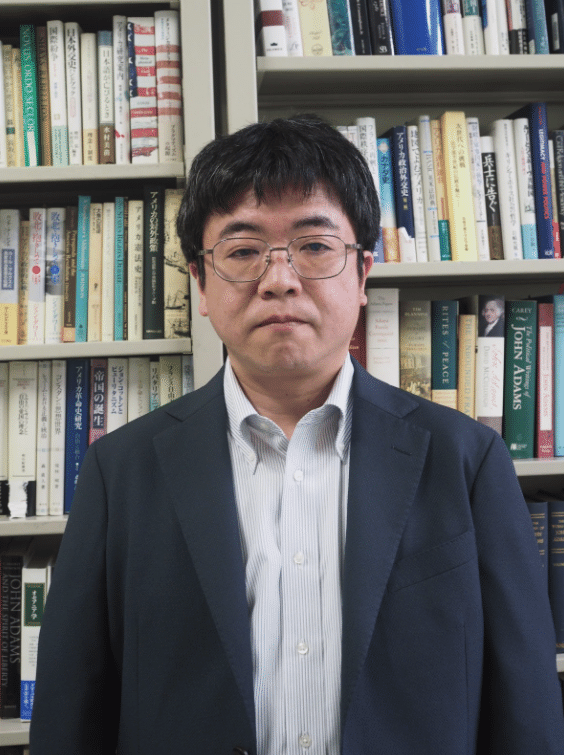
石川敬史(いしかわ・たかふみ)
帝京大学文学部史学科教授。1971年、北海道稚内市生まれ。北海道大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。博士(法学)。北海道大学法学部助手、東京理科大学基礎工学部准教授を経て現職。専門は、アメリカ革命史、植民地時代からアメリカ建国初期の政治思想史。著書に『アメリカ連邦政府の思想的基礎ーージョン・アダムズの中央政府論』(渓水社)、共著に『岩波講座 政治哲学2 啓蒙・改革・革命』(岩波書店)、『教養としての世界史の学び方』(東洋経済新報社)など。将来の夢は、井上弘貴さんとアメリカ政治思想史という学問分野をメジャーにすること。

田中東子(たなか・とうこ)
1972年横浜市生まれ。大妻女子大学文学部教授。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。博士(政治学)。専門は、メディア文化論、ジェンダー研究、カルチュラル・スタディーズ。第三波フェミニズムやポピュラー・フェミニズムの観点から、メディア文化における女性たちの実践について調査と研究を進めている。著書に『メディア文化とジェンダーの政治学-第三波フェミニズムの視点から』(世界思想社、2012年)、『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(共編著、ナカニシヤ出版、2017年)『私たちの「戦う姫、働く少女」』(共著、堀之内出版、2019年)、その他『現代思想』や『早稲田文学』などに第三波フェミニズムやポピュラー・フェミニズムに関する論稿を掲載している。
【以下、トークの内容】
山本:みなさんこんばんは。ポスト研究会15弾です。今回は「アメリカ保守主義とは何か」というテーマでお送りします。神戸大学の井上弘貴さんが書かれた、今話題の新刊『アメリカ保守主義の思想史』(青土社)をもとに、今夜はトークを進めていきます。著者である井上さんをお招きしてのトークをお楽しみください。
この1ヶ月間、世界のメディア、日本のメディアを席巻したアメリカ大統領選挙ですが、すっかりそこに我々の関心がもっていかれました。まだ選挙の決着がついたのかどうか分かりませんが。でも案外、私達はアメリカの保守勢力の人たちのことを知らないのではないか。ここがトークのスタート地点です。アメリカの保守勢力としてテレビに映る人たちは、ちょっと変わった人たちで、むしろ社会病理的なものとして表象されてきたかもしれません。実はトランプを押し上げる背後に、長い伝統をもった保守主義というものがある。そのあたりを、井上さんを交えて今日たっぷりやっていきたい。いったい誰が、そして何が、あのBBQおじさん(※「BBQ BEER FREEDOM」というメッセージの入ったTシャツを着てトランプ支持を訴えたことで一躍注目を浴びた白人男性)を生み出したのか。そういうことを交えながらお話していただければと思います。それでは今夜の司会、田中東子さんにバトンタッチです。
田中:本日は神戸大学国際人間科学部准教授の井上弘貴さん、そして帝京大学文学部の教授である石川敬史さんをお招きして、大統領選当日、11月3日に刊行された『アメリカ保守主義の思想史』を中心に、アメリカ保守主義についてお話をうかがっていきます。
井上くんと私は――あ、もう「井上くん」って呼んじゃいましたね(笑)――、かなり古い友人で、もう四半世紀のお付き合いになるのかな? かつて同じ大学院で一緒に勉強していたんですけど、その後は専門が違っちゃったので、公的な場で一緒にお仕事することがなかったんです。でも、今日は初めてこうやってお話を聞かせていただくことになって嬉しく思います。
それから石川さん。最近は『現代ビジネス』でアメリカ政治史について重要な論稿を書かれてます。Twitterでも「オッカムさん」として人気ですね。井上さんイチオシの政治史の先生ということで、今日は多くのことを学ばせていただきたいです。
オープニングトークでも話題に挙がりましたが、11月3日にアメリカ大統領選挙があって、2016年にも民主党のヒラリー・クリントンが勝つのだろうと私は考えていました。おそらく世界中の多くの人たちがそう思っていたにもかかわらず、しかし、トランプが大統領になりました。今回もバイデンが圧倒的に勝つんだろうな…と思っていたら、意外と競っていますよね。そこで、まずはお二人に、自己紹介をかねて今回の大統領選挙についてお話しいただきたいと思います。
井上:井上と申します。このたび『アメリカ保守主義の思想史』という本を出させていただきました。装丁がシンプルで、無印良品に置いてあっても違和感ないかなと。タイトルも右寄りになってて、右寄りという内容がわかりやすくなっています。

(一同笑い)
井上:今回の選挙。そうですね、事前の世論調査に沿えばバイデン優勢というところだったので、多少は番狂わせがあったかもしれないけど、おおむね予想どおりでしたでしょうか。
石川:選挙分析を専門としている方々の研究会を何度か聴講させていただきましたが、だいたい彼らの予測から大きく外れていませんでしたね。データ的にはバイデンが圧勝という数字が多かったのですが、専門家は競るだろうと見ていたようです。実際トランプも7000万票以上とりましたからね。
田中:そのあたりは予想通りということなんですかね?
井上:この本も、たぶんバイデンが勝ってくれるかなと、誤魔化しつつ、そういう方向では書いています。
田中:お二人はアメリカ政治史の専門ということでよろしいでしょうか? それとも政治思想の専門家?
井上:我々、政治思想です。
石川:私は実のところ蝙蝠(こうもり)のようにやってきまして、ヒストリアンの集まりに行くと自分は政治思想が専門と称し、思想家の集まりに行くと自分はヒストリアンであると称してきたものですから、ここで正体をはっきり言ってしまうと両陣営から「おいおい」と。困りましたね。
(一同笑い)
石川:今後の業務に支障をきたします。
田中:ぽすけんのメンバーは境界線上にいる人たちが大好物なので、お話をうかがうのがますます楽しみになりました。それで、この色んな意味で「右寄り」のアメリカ思想史の新刊なのですが、さて。私は先ほども申し上げたとおり、井上くんとは四半世紀に渡る研究仲間……というか、意識のなかでは「お友達」なのですが、かつての井上くんはマルクス主義関係の文献ばかり読んでいた人、つまりは左派であったという認識がありました。その井上くんが本を出すと3ヶ月ほど前に聞きまして、「あぁそうなんだ~。左寄りのアメリカ史?」なんてことを考えながら、青土社のホームページを検索してみたんです。そうしたら、『アメリカ保守主義の思想史』というタイトルが出てきたので、「ふわ!? 何があったの井上くん!? 保守転向!?」みたいな感じで、すごくびっくりして急ぎ読ませていただきました。そうするとですね、やっぱりかなり保守の人たちに寄り添うかたちで議論が展開されているものですから「うーんこれはいったい、どういうことなんだろうか???」と思ってさらに読み進めていくと、最終的にはアメリカのワーキングクラスの人たちが、トランプ政権を押し上げたのだ、というところに終着する本だったんですね。つまり、本書はアメリカの労働者階級の人たちに寄り添う形で書き進められているという意味で、井上くんの関心は実はまったく変っていないんだという。研究者としての入口に立った時に抱いていた関心というのがそのまま20数年持続していってこの本に結実したことが分かって、私自身は腑に落ちたのですが、とはいえなぜ「保守主義の思想史」というテーマにたどり着いたのかしら?
井上:自分がこういう本を書くとは思ってもいなかったです。気づいたらできていたというところがあります。僕自身は保守主義者では(たぶん)ないですが、ただ相当共感して書いたのは事実です。若い頃、僕はマルクス主義の本を多く読んでいましたけど、この本に出てくる人たちの多くは、人種差別主義者であったり性差別主義者であったりする点を除けば、マルクス主義そのもので、なんというか、もう紙一重というか、僕自身すごく共感しつつ、危うい橋を渡りつつ、自分は一体、立ち位置としてどこにいるんだろうという感じで、いつの間にかこの本を書き終えました。
田中:石川さんもすでにガッツリ読んでらっしゃるそうですが、この本はいったいどういう位置づけになるのでしょうか?
石川:画期的といえば画期的なんですよ。近年の社会科学系のいろんな業界で保守主義というのが重要なキーワードだということは認識されていて、まずは常識通りエドマンド・バークを検討したりするけど、うまくいかない。保守主義自体、定義が困難でとらえどころがない上に、アメリカの保守というのは重層的なのです。これは、通常のアメリカ史の講義では、世界恐慌から60年代まで続いたニューディール・リベラリズムに嫌気がさした人々による潮流と整理されます。
私が講義を受けていた頃の大学というのは、リベラルな先生が多かったので、ちょっと頭のおかしな人々が登場してきたという印象を持ちました。マッカーシズムに代表されるような病理現象として描かれるのがアメリカの保守主義を大学でやる場合のオーソドキシーでしたね。「赤狩り」の風潮に示されるような社会的病理現象を保守主義と認識する傾向が強かった。つまりマッカーシズムというのは、政治思想の後退現象として語られることが多かったと思うのです。
ところが井上さんのご著書は、いきなりマッカーシズムを応援していた人たちの話から始まるんですよね。つまり井上さんの本を読むと、出てくる名前で知ってる人がほとんどいないのです。大学で行われるアメリカ史の講義では論じるに値しないとして十把一絡げにされてきた人々が、丁寧に拾われているのです。私が大学院生の頃に、こんな人たちの研究をしていたら、それこそ大学ではパージされていたでしょう。
(一同笑い)
先ほど私は、アメリカの保守主義は、60年代のニューディール・リベラリズムに嫌気がさした人々の思想潮流と言いましたが、井上さんのこの本によれば、ニューディールの時代にはもうすでに準備が始まっていて、70~80年代に我々がアメリカの保守主義の姿を認識する頃には、すでにかれらなりの保守が確立していたことを内在的に明らかにしたのが、今回の井上さんの本なのです。通常の政治思想史を研究している人たちが知らない分野に井上さんはつっこんだなと、ここからいろんなことが始まるんんだなと、そう思いました。
井上:日本ではいないことになっている人たちです。こういう人たちのことを論じると、東大とかの先生だったら経歴に傷がつくと思うんですよね。
田中:なるほど(笑)。井上くんがこの本を書かねばと思った衝動は、いないことにされている人たちが非常に重要だと感じたということですよね。そのあたりについてもう少し補足してください。
井上:あとがきでも触れましたが、僕は東テネシーというところで生活したときがあって、メンフィスや州都のナッシュヴィルと違って、東のアパラチア山脈のところは、住民はほとんど白人なんです。アジア系でそこに住むと、いろいろあたりが強いなと感じるときもあって。地元のチームと、フロリダのペンサコーラのチームとの野球の試合を地元で観たときも、選手にはアジア系の人もいればヒスパニックもいるんですけど、グラウンドの外はアジア系は僕一人で。白人の子どもが僕のことをじろじろと、しかも憎しみのこもった目でみるんですね。その視線が本当に痛くて。僕なんか、日本で街を歩いていても誰も気がつかないような地味な人間なのに(一同爆笑)、なんでこんなに憎しみのこもった目でみるんだろうという驚きがあって、しかもその後、トランプが勝ったということで、これはやはりこういう人たちがなぜトランプを支持するのか、それを思想史の観点からどう書けるのかをやんなきゃと思ったんです。
田中:最初はアジア系への憎しみに驚いたところから着想して、ゆくゆくはシンパシーを覚えるようになっていったという風におっしゃっていますが、シンパシーを感じるに至った経緯もあとで聞きたいですね。そのお話に行く前に、アメリカの保守の人たち、「BBQ BEER FREEDOM」TシャツでおなじみのBBQおじさん――白人のトランプ支持の方というと、いまや全世界的にあのおじさんの姿が脳裏に浮かぶ訳ですが――彼らがどういう人たちなのかというと、実は誰もよく分かってないし、日本のメディアもなんとなく「これは映してはいけないヤバい人たち」って感じで画面から排除してしまう。井上くんが勉強しにいった土地でたくさん生活しているトランプを押し上げた方たちというのは、どういう勢力として、どういう力をもつ人たちなのかというところから、お二人にお聞きしたいです。
井上:そのあたりパワーポイント使っても良ければ、説明させてください。
(画面共有)
井上:ちょっとパワーポイントを使わせていただきます。トランプといえばMake America Great Again。オバマはYes We Canですね。トランプは「アメリカをふたたびグレイトにする」と言うものですから、BBQおじさんも大興奮だったわけです。このフレーズの頭文字をとってMAGA(マガ)とよばれます。このMAGAの帽子をかぶった人たちが、集会にわんさか押し寄せるわけですけど、ほとんど白人です。もっと具体的にどういう人かと言えば、大卒ではない白人有権者、あるいは白人の労働者階級です。平均収入が6万ドル弱のひとたちで、この定義だと、中小の事業者や低収入のホワイトカラーも含みます。そういう年収で大学にいっていない、アメリカのアパラチア山脈とロッキー山脈のあいだの中西部、南部、西部に住んでいる白人の人たちが、トランプを支持してきたというところがあります。
トランプが誰に声を届けようとしたか、あるいは誰の声を聞こうとしたかについて、思想史の話にひきつけると、19世紀末にウィリアム・サムナーという人がいて、このひとが「忘れられた人びと」ということを言いました。

サムナーはこんなたとえ話をします。Aさんという人が、Xさんという困っているひとを見て助けなきゃと思う。で、AさんはBさんに、Xさんを助けるために法律をつくろうと持ちかける。法律は、社会全体に影響を与えるので、Cさんにも影響は及ぶわけですけど、サムナーはXさんのことを気にかけるんじゃなくて、黙々と働いているのに巻き込まれてしまうCさんの声を聞かないといけないと言ったのです。
この「忘れられた人びと」というキーワードはその後、フランクリン・ローズヴェルトが使っていくのですが、そのときに意味が大きく変わるんです。Cさんじゃなくて、この窮乏のなか、生活が立ちいかなくなっているXさんのために、分配や公共事業をやらないといけないと。ニューディールのときにローズヴェルトの側近たちが意識してしてコトバを転換していくわけです。
田中:つまり社会的に助ける必要のある2つのグループがアメリカにはあるということですかね、具体的には、Xさんは例えば黒人というか非白人の人たち、それから、今の言葉で言うとアンダークラスの人たちということになるのかな……。
石川:サムナーが言ってる「忘れられた人々」(=Cさん)というのは、「普通に真面目に働いて自立自存している人々」、「自分の努力で生計を立てている善良なアメリカ人」です。つまり中産階級の人々のことです。これに対してローズヴェルトは「忘れられた人々」を「非常に貧しい苦境に陥っている人々」というふうに意味内容を転換した。そういう意味では非常に今日的リベラル。ですから、中産階級の人たちこそが忘れられた人々、というのがアメリカ保守の共通認識ではないでしょうか。
田中:そうすると、このCさんたちというのは、ローズヴェルト以降は文字通り忘れられてしまった人々ということになりますね。つまり、忘れられたままだったCさんの声を聞いたのが、トランプってことですか?
石川:Cさんが忘れられた人なのか、Xさんが忘れられた人なのかの結論がまだ出ていない、あるいは争点そのものが忘れられた状況にあって、再びトランプが「忘れられた人々」というコトバを使う。トランプのtwitterで、象徴的なのは「忘れられた男女」という表現なのですけれど、ここで彼が言う「忘れられた人々」というのは、CさんであってXさんではない。
田中:最近の日本で流通している言葉でいうなら、Cさんは「自助できている人たち」ということですよね。だとすると、私なんかは、CさんでなくXさんたちこそ社会が救わなければならない人たちである、と思ってしまうのですが。
井上:ポイントは、Xさんこそが忘れられた人であると考える人がいる傍らに、トランプを支持した7000万ものもう半分の人たちがいるということです。分極化してると言われますけど、その根底にある「忘れられた人びと」のイメージとして、CなのかXなのかということで、見えてる世界が違う。
石川:ヨーロッパで意味するような社会福祉という制度も概念もアメリカにはまるでないわけですよ。だいたいCさんもカツカツなんですよね。私からすると、何であんな陽気なんだろうというくらい先行き不安な人たちがCさんなのです。そういう人たちはたぶん自分たちの税金を使ってもっと怠惰な連中を助けるということにたいして憤りがある。ひとつには多分キリスト教倫理もあるのかもしれません。つまり自己責任で貧しい状態に陥っている人間が制度によって救われるということは、非常に不道徳であると。自分たちだって自助努力してやってるのに、やれ腰が痛いだの膝が痛いだの、挙げ句の果てには、酒や薬に溺れたとかいうどうしようもない人間を「福祉」という制度によって助ける連中に対してとてもイライラしているんだろうと思います。チャリティー(慈善)は良いんですよ。でも制度で助けるというのは不道徳なのです。
田中:それはもう歴史的に、そういう考え方が根深くあるということなんでしょうか?
石川:ちょっとウェーバー・テーゼを彷彿させますけど、やっぱりアメリカ大陸入植以来ですね、勤勉というのがアメリカの道徳の根本にあるんですよね。考えてみると、ヨーロッパでは身分制度がありましたから、庶民の労働といっても、例えば靴を作る人々、農業をやる人々っていうふうに、身分の中に居場所があって、そうした運命の中で労働に従事していたわけですけど、アメリカにはこうした身分がないわけです。例えば農業に着目すると分かりやすいのですが、ヨーロッパでいう農民とは身分ですけど、アメリカでは身分じゃなくて職業なんです。だからその職業倫理からすると、チャリティはかまわないけどろくに仕事をしていない人間を税金で助けるのはとんでもないという考え方はもっともだったはずです。「予定説」というプロテスタント神学の話になると非常に話が厄介になるので割愛しますが、アメリカでは「救いを予定されている人は金持ちの可能性が高い」と考えられてきたわけですね。
田中:この「Xさん」バーサス「Cさん」という戦いが入植以来のアメリカ社会にそもそも埋め込まれて、2016年にトランプが出現して以降、「Cさんこそが忘れられた人々だ」という声を支持する人たとが急激に浮上してきたという理解でいいですか?
井上:そうですね。BBQおじさんもそのなかに入ってくるわけです。
田中:その人たちが、いわゆる保守ということですか?
井上:その保守と一口に言っても、この本の中には、いろんな保守勢力が登場します。パワーポイントをまた使いましょう。
(画面共有)
井上:この本で書いたかつての保守の主流には、エリート主義なところがあったんですけど、いまの保守の、主流を奪いつつある潮流は、ポピュリスト的傾向があるわけです。タッカー・カールソンという、フォックスニュースというケーブルニュースネットワークがありますけど、そのフォックスの夜のアンカーとして知られていて、平均視聴世帯が400万世帯――同時間帯のCNNは、アンダーソン・クーパーの『360』ですが、100~200万世帯です。ぶっちぎってフォックスのタッカー・カールソンが数字をとっていて、ものすごい数の人たちが観ているのですが、このスライドは、選挙の最終盤の10月31日、ペンシルヴァニアのバトラーというところでトランプが集会をやったときの様子をカールソンが番組で紹介しているところです。

バトラーは、ピッツバーグの北側にある人口1万3千人の、19世紀末にプルマンっていう寝台列車をつくった伝統的な工業の街だったけど、今は衰退しています。この、Cさんがいっぱいいるところでトランプが集会して、タッカー・カールソンが番組で紹介したのですが、キャプションにあるように、トランプはアメリカの支配階級の告発者だって言ってるんです。支配階級という人たちがアメリカを支配していて、自分たちはある種の抵抗者なんだという身振りというか、ポジショニングを保守は取っていく。
キーワードはこの「支配階級」です。トランプは大金持ちだし、かれも支配階級なんじゃないのと思われるかもしれないけど、トランプはたしかに金持ちかもしれないけど自分たちと同じブルーカラーの成金という意識。BBQおじさんもトランプには親近感がある、(トランプも)BBQが好きそうだし。BBQを焼くのはアメリカでは男の仕事ですね。英語でピット・マスターって言いますけど。アダム・リッチマンというひとが、アメリカ全土で食べ放題に挑戦する『マンvsフード』っていう番組がアメリカのケーブルテレビで放映されてましたが、そういうところに出てくる人たちと同じメンタリティをもっている。イエール大学の教授とかと比べれば、何倍も親近感がある。トランプは、世の中を牛耳っている連中を俺たちの代わりに倒してくれる、と。そういう声を聴いてくれるのは彼しかいないんだって。そういうメンタリティに寄り添って、タッカー・カールソンがポピュリスト的な情熱をもって視聴者に語っていくというのが、いまのアメリカの保守主義。
田中:さきほど「見ている世界が違う」という言葉がでてきました。つまり、アメリカには2つの世界観があって、拮抗していると。そこで石川さんにお聞きしたいのは、日本で私たちが大学なんかで学ぶアメリカ史には、こういうBBQおじさんって今までほとんど登場してこなかったわけですよね。だからアメリカをこれまで、歴史であるとか、アメリカ研究をしてきた人たちがどういう視点からどういう世界観として捉えてきたのか解説していただけるとありがたいです。
石川:まずアメリカンスタディーズというのはもちろん、人種やジェンダーに対してデリケートな研究蓄積があることはたしかです。我々外国人がアメリカに留学すると、もちろんエリートの世界にいくわけですから彼らから学ぶわけです。ところが井上さんがおっしゃったようなクソ田舎があるわけで、そこでの現実を我々は見落とすのです。それでこれは大事なことなのですが、トランプを支持してる人たちは貧乏人もいるわけですが、これは要するに豚が肉屋を応援する仕組みに僕らは感じるわけです。これは、日本においてかつて小泉政権を支持していた貧乏人と相似形であるように見えるのですが、アメリカはちょっと違うわけですよ。あくまで主はその貧乏人たちで、トランプは代弁者なんですよ。だからトランプは彼らとディール(取り引き)して大統領の座にのぼるわけですけど、決して支持してた人たちはトランプに騙されているわけではないのです。彼の品性が上等なものではないことは皆が判っている。しかし、この男であれば自分たちの声を代弁してくれるだろうということなんですよね。だからトランプは確かに「忘れられた人々」とディールしていたのです。
実は、私は井上さんのように怖い人たちがいる南部に行くことがあまりなくて、主にボストン、ケンブリッジといった北東部の大学で史料収集しているのですが、そのアメリカは、外国人でも聞き取りやすい英語で、ハートフルに接してくれます。ただそこから見ると井上さんがおっしゃったもう1つのアメリカの姿が可視化されない。バイブルベルトとか、井上さんの本ではハートランドと記述されている地域の、あの人たちの不満というのは、我々のような外国人はおろか、同じアメリカのエリート層にも届いていないように思われるのです。
これはアメリカ史に昔からよくあることで、開拓期のアメリカからそうなのです。開拓期は、アメリカ白人によるインディアンへの侵略の歴史だと我々は理解しています。しかし、もし自分がフロンティアに生きているアメリカ白人だと想像してみましょう。そうすると主観的には、「恐ろしいインディアン」に囲まれている状態だったはずです。当然、最寄りの州政府に助けを求めるわけです。ところが東海岸の都会にいるエスタブリッシュメントの人々はインテリですから、「そもそもインディアンの縄張りに入り込んで行ったのは君たちなんだから、現地のインディアンとうまくやりなさい」とか、近代的なことを言うわけです。そうすると「なんだあいつらは自分たちの言うことを全然聴いてくれないじゃないか」という思いになるわけです。これが移民国家アメリカ、開拓によって膨張したアメリカではそれが常態だったんだろうと考えられます。「リベラルな連中は自分たちを救ってくれない、冷たい人たち」というのが、ポピュリズムの契機なんでしょうね。おそらく「リベラル的な価値が自分たちを救ってくれたことは一度もない」という理解があるんだろうと思います。
田中:いま開拓時代まで時代が遡りましたけど、実はそのあたりの歴史もね、知ってるようで知らないんですよね。開拓期からリベラルな人たちは東海岸にいたというお話でしたが、リベラリストというのは建国のときからいたということですか?
石川:アメリカ建国の頃というのは啓蒙主義の時代ですから、いわゆる個人の権利を重視するという考え方があったわけですよね。もちろんアメリカ植民地など、現実は辺境の村社会なんですね。ただ、今の村社会と違って当時は、ジェントルマン階級っていうのが物凄く偉いのですよ。これは早くから入植した人々の中の指導者層の末裔で、資産と教養があり、遡ればアメリカ入植前のイギリス本国での社会的地位も高かった人々です。開拓時代のアメリカには、確かに貴族こそいなかったけれど、ジェントルマン階級というのが事実上の支配者で、普通の住民は彼らに軽口など使えなかったのです。こうした階層の人々がイギリスとの交渉を行うのですが、インテリ同士だから話があうんですよ。例えば、ケベック法。今のケベックあたりにフランス系のカトリック住民がいたのですが、プロテスタント住民はそれが許せなかったのです。しかしイギリス本国や東海岸のエリートは啓蒙主義教育を受けているので、「信教の自由」というものがあるのだから、彼らの居住権も認めろとか言ってくるのです。そうすると現地では梯子を外されたような気持ちになるのですね。その手の疎外感は、開拓時代からあったのです。
田中:その時代からすでに2つの世界観があったと。
石川:一人の人間の中にも、リベラルな自分と古層の二重性はありますよね。アメリカの場合、それが地域間とか教育環境という形で端的に現れます。リベラルの観点からすると世界が平等に向かっているという、俯瞰的なものの見方をいわばお気楽にするのだけど、フロンティアの現場とのズレがもう当初から起きていたわけです。
田中:なるほど。インテリ層は俯瞰するのが仕事ですからね。だから、なかなか保守の心性が理解できない。
井上:だから俯瞰しない人たちにいかに声を届けていくか。
石川:方法論では俯瞰でとどまっているので、彼らに寄り添うというか、寄り添うというのは違いますね、内在的に見るという視点を我々は欠いてきたのではないか。アメリカ研究に関しては特にそうだったのではないかと思うのです。フランスに関してはフランスの民衆のあり方、それこそ『ベルサイユの薔薇』から始まって色々あるんですけどアメリカの開拓の前線にいる人たちの思いというのは、なかなか共感できなかったんじゃないかな、インテリ層が。
井上:西へ西へというフロンティアはヨーロッパにはなくて、フロンティアにいる人と、東海岸にいて偉そうにしている人たちとの距離、というのはヨーロッパにはない独特の配置かと。
田中:そうすると歴代大統領選というのは、この2つの戦いになるわけですか?
井上:フロンティアと東部の距離が広がっていくなかで、大統領選をめぐる配置も変わってくる。
石川:だから大統領選挙の予測が困難なのです。資料と違う結果がでるんですよ。そこにスポットを当てたんですよね、井上さんの本は。これはまぁちょっと話のオチを先に言うことになるかもしれないですが、この井上さんの「アメリカの保守」を検討した本は、切実に求められている本なので多くの学者に読まれると思う。でもたぶん実際読んだら、ぎょっとすると思います。僕らがこれまで「わけのわからない連中」として扱ってきた人々の思想を内在的に描いているので、井上さんは一回、アメリカ研究業界のメインストリームの人々と戦わなければならない。
(一同笑い)
石川:でも、そのあとじわじわ評価を上げていくだろうと思います。これは私が保証します。何の資格があってのことか分かりませんが。
井上:インテリのなかに確信犯的にトランプを支持し、彼の言ってることを理論的に精緻なものにしようとする知識人がいるということ。これが日本ではあまり知られていない部分かなと思います。
石川:そこにスポットを当てたと思いますね。僕の言い方だとフロンティアにいる人たちの、いろんな情念について語りましたけど、井上さんの本はこれを理論的に精緻化した人たちを扱っています。つまりトランプを応援しているインテリがいて、彼らはアメリカの忘れられた人たち(=Cさん)の思いを体系化していく。特に冷戦の終焉までのこれらのインテリたちには明らかに共通点があって、要するに亡命知識人やユダヤ人ですね。こういう人たちが、つまりアウトサイダーが理論化を行うんですよね。考えてみると保守的感情を理論化するっていうのは、これはフランス革命の時もそうですけど、保守的感情を理論化して保守主義にしたエドマンド・バークって、アイルランド生まれのホイッグ党の人なんですよね。イングランド人ですらない野党の人です。そう考えると実はヨーロッパにおいても保守的感情を理論化した人物はメインストリームの人じゃないんです。そうするとアメリカの場合に、アウトサイダーの知識人がフロンティアにいる人たちの感情を理論化して政治思想に練り上げてきたということですね。
井上:常にアウトサイダーから出てくるねじれた社会改革が、実は保守。リベラリズムに対してアンチをつきつけ、リベラリズムこそ支配者なのだと。それに対して自分たちはマージナルな立場から声を聞き取って、それを体系的にぶつけていくと――それがアメリカの保守思想。
田中:リベラルの人たちの世界観というのは、虐げられたマイノリティの人たちを基本的人権であるとか平等な社会にとりこんでいくことで、パイを等しく分けるようにしていこうというものですよね。つまり、リベラルの人たちというのも、足りていないところにリーチをのばして平等な社会を築こうということだと思うんですけど。
井上:それはまちがっていないんです。ただ、非常に皮肉なことにリベラリズムが成功すればするほど、平等を達成すればするほど、より完璧な「ユニオン」をつくればつくるほど、まるで既得権にみえてしまう。リベラルこそがアメリカのエスタブリッシュメントであり、支配する側にまわったんじゃないか、という構図に正当性を与えてしまうような状況が増えてしまったことを、保守がうまく利用していくというか、そこを突いているというところですよね。
田中:つまり、BBQおじさんというのは、リベラルの側からみると「アメリカのど真ん中にいる人」にみえるのだけれど、あのおじさん自身は「自分たちはマージナル」だと考えているってこと?
井上:あのおじさんは、本当は何にも考えていないかもしれない。ただ重要なのは、あなたたちは忘れられているという意識を外部から前衛が注入していく。マルクス主義と一緒なんですよ。
石川:保守主義というのは例えばフランス革命においては、リベラリズムという歴史に跡づけられないものに基づいて伝統によって培われた文化・文明を破壊する野蛮な思想であると保守主義者は言う。あくまでディフェンシヴなものなのです。しかしアメリカの保守主義はアクティブなんですよね。ただあれですよね。西部邁氏もそうかもしれないけれど左翼から転向してきた人たちって、そういうところありますよね。だから戦闘方法が似ているんですよね。
田中:井上くんの本の一番ヤバいところは、実は右派と左派の戦闘方法が似ているということに気づかされてしまうというところなんですよね。
石川:いますよね、マルクス=レーニン主義者みたいな人々が。
井上:本の第5章に出てくるサミュエル・フランシスは、グラムシを使っていきます。
田中:そうそう! 読んでいるとグラムシが登場してきて呆然とするっていう。保守がグラムシ推しちゃうんだ、っていう衝撃!!
井上:アウトプットは違うのに戦術は一緒。ペイリオコンのフランシスは、(ニューライトの)バーナムという人の弟子って感じの人ですが、かれがマルクス主義の理論に沿ってゴリゴリの人種差別主義を白人に注入していくっていう。
田中:そのあたりの、敵の戦略を取り込んででも戦わなければいけないというようにかれらを駆り立てるものって何なんでしょう?
井上:マイケル・アントンのようなトランプを支持する知識人は、アメリカはグローバルなニュークラスである「ダボス階級」にのっとられていると考えている。陰謀論的なひとたちに似ているものの、かれらはもっと精緻な形で世界の絵図を描いていて、完全な陰謀論じゃない。そういう、リベラルと異なる世界観を持っている人たちがインテリのなかにいるってことですよね。
田中:保守思想内部のいろいろなグループの話しが出てきましたね。キーワードとして出てきた「2つの世界観」、つまりリベラルと保守から見たアメリカがあるということでしたが、ここで保守の側からみたアメリカについて、アメリカが保守の側からどう見えてきたのかというお話しをしてもらっても良いですか。
井上:リベラリズムこそが支配者なんだという保守の考えについてはこの本の序章でまとめていまして、3つのリベラリズムの波に抗する反革命の立場が保守なんだ、という基本的構図を描きました。ひと口にリベラリズムと言っても、3つの波があったと本では整理しています。

まずは(さきほどから話に出ている)ニューディールリベラリズムです。Xさんを助けるために公共事業をしたとリベラルはみるわけですけど、保守の側からするとそれは、経済回復の名を借りた、経営者階級による支配の拡大にすぎないというわけです。それに抵抗するのが戦後に登場するニューライトという構図です。
2つめは、1950年代後半から公民権運動の時代に入り、ケネディが暗殺され、ジョンソンが引き継いで「偉大な社会」というかたちでの改革を1960年代に進めていきます。この時期は、参加民主主義の拡大の時期と言われ、それはフランスでも5月革命ということで、左派が今でも拠り所にする時期なんですけど、右派からすると全く違う。ニュークラスという戦後に登場したコミュニケーションテクノロジーをみにつけて新しい上昇を果たしていった高度専門職の人たちが主導権を握っていった時期ということになります。
そして今がポリティカル・コレクトネス・リベラリズムの波の時期です。多様性の拡大はリベラルにとっては望ましい一方、トランプを支持する保守にすれば、多様性という名のもとに グローバルなかたちで富を獲得しアメリカ社会を牛耳ろうとしている、今日のニュークラスの支配拡大の時期とみえているわけです。
このような支配階級の拡大プロセスに自分たちは抵抗しないといけないという、3つのリベラリズムの波に抗する動きがあって、その波ごとに、保守の中では主導権争いが起きてきたという構図だと思うんです。
次のスライドをみてください。この本には本当は保守の潮流を図式化するための図表をつけたかったんですけど、出来損ないのお役所のポンチ絵みたいになってしまって恐縮しています。

詳しくは本をお読みいただければ。自分でスライドを作っておきながら、この図を説明することができそうもないです。
田中:本で読むと、保守の各グループ間の関係がすごく分かりやすく説明されてるんだけど、図にする方が分かりにくいというのはレアケースですね、これは。
(一同笑い)
石川:同意見になりまして、結局図にするとこうなるんですね。本書を読破するとなるほどーってなりますが、ただこの図から入ったら分からないでしょうね。
田中:これ多分、立体化してxyz軸で時間の変化まで入れると分かりやすいのかな。保守内部の対立のなかで比較的新しいのは、ネオコンvsペイリオコンですね。
井上:2000年代のイラク侵攻のときにネオコンという人たちが全面的に侵攻を支持し、チョムスキーのような左派がアメリカでは戦争に反対したというのが、普通に日本で見えていた構図だと思うんです。しかし、保守の側でも戦争反対の立場をとっていた人たちがいて、それがペイリオコンと呼ばれる人たちです。そこから枝分かれした人たちを含みつつ、アンチトランプの人たちに対抗してトランプ支持の保守を形成し、自分たちがこれからは主流になるんだという動きがつくられてきたのです。
石川:冷戦以降に我々外国人に可視化されたペイリオコンというのは、普通は分からないと思います。戦争をやってる最中でもそれに反対する保守がいるんですよね。これは世界恐慌のときにアメリカ人のほとんどが政府に従順になった時代であっても、それでも中央政府が財政出動を行うことに反対する保守もいた。アメリカとは本当に多様な国なんですよね。
井上:じゃあ、(戦争反対だから)リベラルがかれらと組めるかというと、他方ではゴリゴリの白人至上主義者だったりするわけですね。
田中:戦争反対では組めるけど、それ以外は相容れないということなんですね。なるほど。それで保守のまとめというか、保守のなかの、主流と傍流の争いがあるということだったのですけれども、それは反戦を軸に対立していたんですか?
井上:かつて保守を束ねていたのが融合主義というもので、そのなかでも反共主義だったのですが、それが冷戦が終わって、そのタガが外れていくわけですけど、しばらくはアメリカの民主主義に反する勢力や国家に対しては断固とした立場をとるというネオコン的な国際主義が延命措置として束ねる力をもっていたわけです。けれど2000年代のイラク侵攻のときに大量破壊兵器はなかったじゃないか、っていうことでネオコンが失墜するなか、いよいよ保守が分解してさまざまな潮流が表に出てきた感じです。
石川:イラク戦争の失敗は保守の中でもネオコンが退場したに過ぎなくて、無数にある保守の層は揺るがなかったという感じがします。
井上:もうひとつはグローバル化の進展です。冷戦以降のグローバル化の進展でずっと、今日の話に出ているアメリカ内陸部の白人の大卒でない人たちの生活が悪くなっている。それなのにネオコンは、グローバルエリートとつるんで グローバルじゃないとアメリカはだめになるって言ってるんだけど、自分たちの生活がどんどん悪くなっているっていうところで、経済的ナショナリズムを支持するタッカー・カールソンなんかは、左派と同じようなことを言うわけです。
3つめは、911以降の、外国から得体のしれない連中がはいってきているという意識。トランプを支持してる人たちは国境から随分離れてる人たちも多いんですけど、かれらが、トランプがグレイトでビューティフルな壁を築くと言うと、そうだよねってなる。不安感や恐れ。自分たちがどんどん立場が弱くなっているという不安に対して、声を届けることが保守主流はできないところを、傍流は「お気持ち」を聞きとることに成功してきた。その全てを一身に背負ったのがトランプということです。
(対外戦争反対、グローバル化反対、移民反対の)すべての要素をトランプだけが全部言ったわけです。他の(共和党の大統領候補の)人は、それこそアメリカの経済再生とか言ったかもしれないけど、17人の共和党の大統領候補のなかでトランプだけが、全ての要素を言ったわけです。だからトランプに賭けなきゃいけなかったわけです。
田中:ありがとうございます。保守のなかには戦後史がリベラルの躍進の時代という世界観があることが分かりました。さらにもうひとつ気になった点があるんですが、井上くんのこの本では保守の側が、「これ、もはや保守じゃないじゃん! 守ってないじゃん!」って思うぐらいラディカルになってますよね。
井上:そうです。
田中:だから保守っていうのは「守るぞ!」っていう人たちであるはずなのに、ものすごく攻撃的でアメリカ社会を変えねばならないと主張してますよね。これ、ただのラディカルじゃんっていう。
井上:他方でリベラルはどうですか? 攻めてますか?
田中:リベラルねぇ。
井上:守るものが多くなる?
田中:なってるかもしれない。守りに入ってるのかも。
井上:フェミニズムはどうですか。
田中:フェミニズムは攻めてますよ。まだまだやらなきゃいけないことがいっぱいあるから、まだまだどんどん攻めていきます! でも、保守と一緒には組めないですよね。それで、井上くんの図でひとつ、私がここはどうなの? って感じたのが、階級闘争という意味においてCさんとXさんは組めるはずなのに、人種やジェンダーへの考え方が邪魔をして組めなくなってしまっているんですよね。それが残念だなと。
あと移民について、エスタブリッシュメントがメイドさんや庭師の仕事を移民に押しつけたいからどんどん移民の流入を認めてしまっているというように保守の人たちが考えているという記述があったんだけれども、そのへんはなんかすごく鍵なんじゃないかな。日本もケアワークを移民の人たちに来てもらってやらせようって、日本の場合は自民党が言うわけですけれども、そういうところですごく今の、なんというかケアワークやつまらない仕事を移民の人たちにやらせようとすることから生じる階級や格差の問題と、保守の白人たちが言う、俺たちはニュークラスに支配されてるんだっていう部分は手を結べないのでしょうか? 無理なのかなあ。
石川:共闘の障害物は、だから「お気持ち」の世界になってくるんでしょうね。共闘は難しいのかな、という風に思いますね。さっきの図を拝見して思ったのが、共闘できないのが保守達なんですよ。内ゲバなんですよね、保守なのに。やってることは左翼ととっても似ていて内ゲバがあるんですよ。ただ共通点は明らかにあって、中央権力に対する抵抗といいますか、自分たちがコントロールできない中央権力、これに対する反発という意味では一致する。それはあるときは古典的なエリートかもしれないし、ニュークラスかもしれない、あるいは連邦政府かもしれないけれども、それに対してアメリカン・ウェイ・オブ・ライフを維持したいという点ではそれぞれ一致してる。しかしメンタリティが違うのかもしれません。お気持ちなんですけど、お気持ち問題にふれてもいいですか?
(一同笑い)
石川:ちゃんとこの本のテーマに戻りたいと思うんですけど、私、北海道生まれの北海道育ちで、ずっと北海道にいたんですけど、東京生まれ東京育ちの人に、懇親会か何かで、「どうして北海道の人は熊を殺すのか、熊と仲良くしてほしい」っていわれたんですね。マリー・アントワネットの伝説的天然発言(「パンがなければケーキを食べれば良いじゃない」という作り話。シュテファン・ツヴァイクによれば、確かにこの話は事実ではないが、そんなことを言いかねない天真爛漫さが彼女にはあったという)を聞いた時のフランス民衆ってこんな気持だったんじゃないか(笑)。これはうまくいかないのですよ。政治っていうのはやっぱりちゃんと「お気持ち」を組み込まなければならないのであって、リベラルにはこれが決定的に足りないのかもしれないっていう気がしました。特にデモクラシーの国であるアメリカの場合。リベラルの人たちって、「お気持ち」を鬱陶しがりますよね。
田中:合理的で理知的な人たちですから。
石川:とっても頭いいんですよね。
井上:啓蒙を求めるわけですよね。
田中:とにかく啓蒙的なんですよね。そこに「お気持ち」をどう組み込めるか……うーん。
石川:ただお気持ちを理論化して政治思想にまで練り上げた知識人がアメリカにはいて、さらに特徴的なのは、理論化と同時に戦闘方法も注入したのです。
井上:保守は、左派の理論をいろいろ学んで自分たちに応用しています。ではリベラルは、保守のどこを学ぶのかというとあれですけど、お気持ちポリティクスとどう向き合うかという。
田中:人々のお気持ちや情念を切り捨てないでどう政治に取り入れていくか、みたいなことはもう少し真剣に考えてもいいかもしれない。お気持ちって主観的なものなんで、それらをどう調整してどうシステムなり政策なりに取り入れていくのかというところは、もうちょっと考えてみたいかもしれないですね。ただ、保守主義のマッチョなところが私はどうしても耐えられなくて。だってこの本もね、読んでて時々イライラしながら読んでいくんですけど、もちろん人種的な意識も相容れないんですけど、保守主義って、やっぱり男の話だねって感じじゃないですか。そのあたり、トランプ支持の女性って結構たくさんいるんだけど、そのへんの保守女性というのはどうなっているんでしょうか? 理論的にはたぶんそれこそ見えなくされ、不可視化されちゃってる。保守思想の世界では、女性の問題は見えないものになってしまっていると感じます。
井上:それは、この本では十分に扱えていないところです。アメリカにおいては特に、中絶をめぐる問題は重要で、トランプが(自分が指名する)3人目の最高裁判事としてエイミー・バレットを指名し、上院が承認したわけですけど、彼女は女性としてプロライフの立場をとるんです。
女性の身体をめぐる権利をめぐって、アメリカの内部で激しいぶつかりがある。そこの中核にあるトランプの岩盤支持層である福音主義のことは、残念ながらこの本では扱うことができませんでした。
田中:ありがとうございます。いま福音主義という言葉が出てきました。これについては石川さんにお聞きしたいんですけど、本書には最初の方でモラルと言う言葉が出てきましたが、アメリカってすんごい合理主義的な国かなと思いきや、保守の側について書かれたものを読むと、現代においても、宗教、キリスト教や聖書に基づいて色々な決定がなされているということに、ちょっと驚きを禁じえないんですけれども、そのあたりについて。
石川:そうですね。もう1つ忘れてはならないのはアメリカはキリスト教国家であるということです。異論もあると思います。そうじゃないという話が、まさにそれがリベラルな立場なんですけど、アメリカのキリスト教はヨーロッパのような制度化されたキリスト教とはとても言えない。フロンティアに爆進する住民をあとから牧師が追っかけて行くんです。荒野ですから、『神学大全』なんか持っていけない。『聖書』だけもっていくんですね。当然、説かれる教えは我流になるし、日常生活に対する悩みに応えるキリスト教になっていくんです。たぶんそれがモラルというものをつくって、それがやっぱり民主主義のなかでは政治的見解を形成していくんだろうと思います。ですからあれをポピュリズムと切って捨てると、アメリカ政治の重要な部分を見落とすのです。それがモラルです。モラルの分析を見落とすとアメリカ政治そのものを見落とすのです。
あともう1つキリスト教に関して言うと、それが階級の問題を克服するツールであるということです。ジェンダーの問題、例えば女性の保守をどう考えたら良いのかということですが、上流階級の白人女性の見方と、そうではない白人男女の見方が違うんだろうと思います。アメリカのキリスト教は、普通の人々(コモン・マン)の平等を保証してくれるんですね。歴史的にはキリスト教には二つの顔があって、キリスト教は神の下での万人の平等を説いているとされる一方で、キリスト教が階層秩序を正当化したという見方もあります。フランス革命前のキリスト教は明らかに後者で、それゆえ革命家たちは、貴族と同様に教会を破壊の対象としました。しかし前者の立場は「十字架の神学」といいますが、こちらは平等の原理となる。アメリカの荒野におけるキリスト教は、前者の立場にあります。制度化されていない我流キリスト教というのはまさに平等の原理としてのキリスト教のひとつの現れだと考えられます。そしてキリスト教は宗教であるが故に、社会主義とは敵対関係になります。
井上:だから、ジェンダー、階級、エスニシティ。ますます複雑になっていますね。チャットのコメントに「黒人やラテン系」について書いてくださった方がいますけれども、バイデンはソーシャリストの大統領候補っていう言い方をトランプはしたのですが、そのソーシャリストという言葉は、キューバ系にはカストロをイメージさせるのです。反共主義は終わったといいながら、あるいはサンダースを支持する人たちにとって社会主義は未来のビジョンかもしれないけど、キューバ移民の2世や3世にとってみれば、カストロにつながるものなわけで、ならじゃあトランプに入れようかって話になる。非常にいろんなものが結びついて、どう結果に出てくるかが、一層みえにくくなってきているかもしれないです。
田中:今回の選挙ってどっちの陣営も最高得票を獲得しましたよね。かなり盛り上がったということは間違いないわけで、それはやっぱりアメリカがいま極めて危機的状況だということなんでしょうね。
井上:みんな、右も左も危機的だって思ってる。
田中:それがみんなを投票所に向かわせる。でも代表する声は、2つしかない。
石川:複数性っていう発想がないですね。多党制(小選挙区制度を止める)にすると本当に国が分かれちゃうんでしょうね。それくらい多様なんでしょうね。
井上:本当は(アメリカは)ひとつなんですっていう話なので、n+1で2になってるところはあります。
田中:そうすると、アメリカのなかは非常にモザイク状になっていて、それがパフォーマティブにあたかもひとつになったかのような気分になれるのが、大統領選なのかな?
井上:だから(選挙で)負けた人たちは、私たちは民主党員でも共和党員でもなく、みなアメリカ人なんだから、また一緒になりましょうと言うわけで、そう言わないとオチがつかないところを、トランプは言わないっていう……。
田中:言わないと、どうなるんですか?
井上:言わないままっていうのもおもしろいかも。
田中:常に負けた人たちが、「負けたけど勝った陣営と一緒にひとつになります! アメリカはひとつ! USA!」って言うことで亀裂を隠してきたと思うんだけど、今回はたぶんそうは言わないですよね。
石川:1800年の大統領選挙でのトマス・ジェファソンの勝利がアメリカにおける初の政権交代だったのですが、彼は「私達は異なった名で呼び合ってきましたが、同じ原理を信奉する同胞であります。私たちは皆リパブリカンズでありフェデラリスツであります」としてワンアメリカを強調しました。この形式が今日まで踏襲されてきてるんですよね。しかし今回それを言わないやつがでてきた。ということはいよいよ冷戦という共通のタガが外れたのは大きいと思いますね。だからもう構造的には南北戦争的ですよね。南北戦争のときはワンアメリカじゃないんです。1860年にリンカンが勝利したのをきっかけに、南部諸州は離脱するわけですよ。南部諸州の指導層は、リンカンは自分たちを放置しないだろうということを見抜いてアメリカ合衆国から逃げたんですね。南北戦争は形の上では南軍が先制攻撃をした形で始まりましたが、南部諸州の主観では明らかに追い詰められていたのは自分たちだと思ったでしょう。案の定、リンカンの連邦政府は追いかけて来て62万人死ぬ殲滅戦争をやりました。死傷者じゃなくて死者ですからね。
それからさっきちょっとでたかな、アメリカの1つの文化として、啓蒙主義的リベラルな精神と土着的な宗教的な精神が昔から割と共存していた感じはあるんですね。大覚醒という新興復興運動が1730年代から40年代にかけてあったのですが、同じ時期にベンジャミン・フランクリンが「アメリカ哲学協会」というのをつくっていてアメリカ啓蒙主義も同時に進行していたのです。啓蒙主義と宗教精神がアメリカという一つの身体で不思議なほど共存している。今でも、牧師がテレビに出て、鼻にピアスしてる若者相手に説教して彼らが涙を流して聴くっていう情景があります。啓蒙がもたらした近代的テクノロジーと信仰というのはもともと一緒になっているところがアメリカにはありますよね。
田中:南北戦争のときは勝った側の大統領がこわいから逃げろ逃げろってなった。今回は負けた側が負けたって言わないっていうことでちょっと違うわけですよね。今回はどうなるんだろう? 南北戦争、再び?
石川:大統領選挙自体は、どんなに泥仕合いになろうといずれ決まるわけです。そもそも2000年の大統領選挙の時のブッシュだって本当は当選が怪しかったのですよね。これをアメリカン・デモクラシーの危機と見た論者もたくさんいたわけですが、私は、アメリカンデモクラシーの底力というのはまさにこうした波乱を乗り切る力なのだと考えているのです。これから色々あるでしょうが、結局トランプは破れますよね。連邦最高裁は、相手にもしないと思います。なぜかというと、トランプは法廷闘争のために慌てて保守派の判事を入れたわけだけど、連邦最高裁の判事の任期は終身制ですから。要するに一度就任してしまえば、トランプの言うことを聴かなくていいんですよ。法曹の頂点に到達したスーパーエリートが自分のキャリアの傷になるような判決を書いて汚名を残す義理はないのです。良くも悪くも今の制度なら 南北戦争じゃなくてポスト・リベラリズムというか、リベラリズムが今後どうなるかの問題ですよね。
井上:アメリカで続いている「文化戦争」という対立は、全然収束する道筋が見えないままです。
田中:大統領が決まり、ワンアメリカ的にはなるけれども…
井上:南北戦争のロジックを使えば、この本のなかにでてくるようなトランプ支持の知識人たちは「冷たい南北戦争」として現状を規定しています。直接に人は死なないけど、アメリカは南北戦争のときのように、完全にふたつに分かれてしまっている、「われわれ」と「かれら」にです。62万人は死なないけど、かつての冷戦の国内バージョンです。この分極化したアメリカが、世界に輸出されているのではないかと恐れます。BLMのような運動が大西洋をわたってグローバルな連帯をつくると同時に、性差別や憎悪といったものもまた、グローバルに湧き出していて、もうアメリカだけの話じゃないわけです。
田中:これはでも、どう調停しても、どちらかがどちらかを撲滅しない限り終わらないのか。それとも、何か手立てはあるんですかね。たしかにアメリカから世界に輸出されている分極構造というものはあると思うんですけど。
石川:私は、世界規模での分極を終わらせることは不可能だと思います。片方を撲滅することも、両方を押さえつける強大な権力を構築することも、できるわけがありません。トマス・ホッブズの「リヴァイアサン」のように国内レベルなら可能でしょう。要するに社会契約を結んで1つの強大な権力をつくって「万人の万人に対する闘争」を終えさせることは理論上可能かもしれないけれど、これが世界レベルになるとそれは不可能ですね。
じゃあそれが果たして私達にとって地獄なのかどうかというと、ひょっとしたらそういう対立が文化とか思想とかを深めていく原動力になっているのかもしれない。いろんな対立があって、例えばジェンダーに対する感覚だってね、私達が子供の頃なんてひどかったですよね。あの男社会っぷり。それから20~30年経ってみると世の中、様変わりしましたよね。そういうことでたぶんその対立というのはマイナスだけではないのだろうと思います。ただ、対立はマイナスだけではないという言い方はもうリベラルと言えるのかなあとは思います。
田中:なるほどねぇ。井上くんはどうです? 本の最後で、対話可能な保守の可能性について書いてたと思うのですが。
井上:僕がこの本で書いたのは、ひとつは保守の主流と傍流の確執のなかで、かつての傍流が反転攻勢をかけているということですが、書いた後で、ただ保守といってもいろんな保守がいるということは強調したいです。リフォーミコンみたいな、少し冷静な人たちがトランプのときにかなり脇に追いやられていましたけど、そういうひとたちはリベラルとは相容れないところはかなりあるわけですけど、トランプを支持する知識人たちよりは、対話が可能かもしれない。そういうところとどう対話するか、対話できなくとも問題のすりあわせをどうしていくかというところで、お気持ちポリティクスに還元されないやりとりをどうできるか、でしょうか。
田中:その可能性をもった思想家や知識人も一部いると。トランプがこのまま静々と退場していけば、またそういった脇に追いやられていた人たちの言葉が浮上するかもしれない?
井上:トランプは、またでるかもしれないですよ。2024年にでるかもしれない。ただ、タッカー・カールソンみたいな後継者をという声もある。
田中:なるほど。今ちょっと質問も来ておりまして。「保守思想は忘れられたひとびとの不満に対して、実際具体的にどういう政策をするのですか」という質問です。思想面での関係性は分かったけれど、実際この4年間で保守主義者たちは何か具体的な政策で応答してくれているのだろうかということですね。いかがです?
井上:結局、実際に効果があるかということよりも、自分たちの声を聞き取ってアクションをとってくれているかが大事です。たとえば移民のことでいうと、DREAMers(ドリーマー)という人たちがいます。
田中:どんな人たちですか?
井上:アメリカの外でうまれて、アメリカに違法に入国して育ったヒスパニックの若者たちのことを言います。物心つくまえにアメリカの外で生まれて、親と一緒にアメリカに来たら、違法は違法なわけですよね。そういう若者たちに市民権を与えるべきだっていう議論は、ずっとあります。オバマ大統領はそうしたかれらに対して、強制送還を猶予するDACA(ダカ)というプログラムを実施したんですけど、トランプはそれを廃止しようとしました。結局、裁判をやってひとまず負けてます。廃止したって、オハイオとかの白人にとっては何の影響もないわけですけど、そういう(廃止のような)ことをやってくれた、違法な連中を追い出そうとしてくれたという、お気持ち的に納得なわけです。
再生エネルギーに補助金を出すということもトランプはカットしている。炭鉱労働に携わっている人たちは、自分たちの産業がもう終わりだって分かっているけれど、自分たちの声を聞いてくれているっていうシグナルをトランプが出してくれていることは、お気持ち的には大事なのです。
石川:我々も例えば裁判で負けても頑張った弁護士なら恨まないですよね。頑張ってくれた弁護士には、感謝しますよね。
井上:マスク着用をバイデンは言ってるけど、トランプは言いません。
田中:そこ、つっこんでいいですか。なんであんなにマスクつけたがらないんですか? それはやっぱり、マスクをつけない自由ってこと?
井上:国家に強制されるのが……。だってそれ(マスク着用)を強制したミシガン州知事のグレチェン・ウィトマーを、あいつをこらしめてやろうっていうことで誘拐未遂した民兵(ミリシア)が捕まったりしている。
田中:そうなってくると、常軌を逸していると思ってしまうんですけど……。
井上:自由を守るためです!
田中:やっぱり、バーベキュー、ビアー、フリーダム?
井上:そう、アメリカはフリーダムですから!!
石川:いまの井上さんの語調からも分かるように、本書もそうですが、井上さん、最近は本当にフリ切っているのですよ。
(一同笑い)
石川:自由っていうのはそういうことなんだろうっということですよね。私、北海道から東京にきて急にリベラル化してきたんですけど、井上さんの最近のフリ切り方は眼を見張るものがありますね。
田中:行く末をね……。長年の友人として見守っていきたいところではありますけど(笑)。
井上:それくらい(保守思想には)危うさがあるということです(笑)。
田中:それくらい危機意識があるっていうことですね。もうちょっと質問に答えてもらってもいいですかね。「合衆国から分離独立ということは生じているのでしょうか?」 これはいまもそうだし歴史的にも、離脱についてなにかあれば。
井上:セセッション(連邦離脱)てやつですね。今も言ってる人はいます。
石川:言ってる人はいるんですけど、ただ、それね、やっぱり建国初期の頃ですね。また古い話で申し訳ないですけど、第2代大統領の頃くらいまでは、北部諸州が離脱して、カナダの方で新しく奴隷制のない国家をつくろうという動きがありましたし、第16代大統領(リンカン)の時には南部諸州が離脱しようとしましたが、今はもう連邦離脱よりもむしろ大統領職のゲットに向かう戦いという形が続くでしょう。結局は「冷たい南北戦争」は大統領選挙に収斂していると見て良いでしょう。
井上:もし、大統領になっても無駄じゃないかという議論が主流を占めるようになったら……。
田中:どういうことですか?
井上:大統領になって自分たちの理想の実現ができれば、わざわざアメリカの外にでなくてもいいやってなると思うんですけど、仮にアメリカ大統領になっても自分たちの理想が実現できないとなったらアメリカにとどまる必要がなくなるかもしれない。せっかくトランプが大統領になったのに、この4年で自分たちの思うような国にならなかったじゃないかって声が強まったら……。
石川:そうなると白人がもうマイノリティになっている世界なんですよね。だから、離脱っていう選択は、理論上今言った理屈でありえるけれども。つまりこの保守、というのは文字通り一種の悲鳴の現れで、忘れられている、弱くなっているという自己認識ですね。でも白人が弱くなっているというエビデンスはないんですよ。平均寿命は白人が圧倒的に長いんですよね。だから全然弱くない。だから主観の問題ではあるのです。
田中:やっぱりお気持ち……。
石川:ですよね。
田中:後は、日本にいる熱烈なトランプ支持の人たちについて質問が来ています。これは私もね、この人たちに話を聞きたいんですよね。しかも日本語でツイートしててトランプへの熱烈な愛を。これはねえ、日本語で書いてもトランプには届かんだろ、って思っちゃうんですけど。結構いるんですよ。バイデンの悪口を書き、トランプを称えている日本人のツイッタラーというのが。これはまぁちょっと……。
井上:メディア研究者としてどうですか?
田中:メディア研究者としてはめちゃめちゃ関心があるんですが、この話し、しないほうがいいのかなぁ。
石川:僕もあれですね、ネット記事に「バイデンの勝利になるだろうが」という、なんてことない普通の一行を書いたらそれに対するリプライで「まだ決まってないだろう」、「バイデンが勝ったって思わせたい一派の人ですか」ってのが来て、何言ってるんだろうと思ったけどこれはコプト語より分からない。
田中:それもまた病理として見たくなるんだけども、なぜこの人はこんなに熱烈にトランプを支持してることを日本語で世界に向けて訴えなきゃいけないのかっていう。トランプの…なんていうんですかねえ…モンスターぶりというか……。
石川:先ほど井上さんが分極化の輸出ということを言われましたけど、たぶん普遍性があるんですよ。
田中:トランプ的なるもののアメリカ外への転移とか、2つの世界観の対立が世界中に輸出されているというなかで、トランプの……声なのか、肉体なのか、パフォーマンスなのか分からないんですけど、忘れられた人たちに呼びかけちゃうんですか? トランプというのは……。
石川:もう1つ思うのは、トランプを日本語で応援している人たちもたぶん低所得者、低学歴とも限らないんですよね。そこそこの大学を出ていながら疎外感をもっている人たちというのもいて。
田中:だって『現代ビジネス』の記事を読んだ人たちってことですよね。まぁまぁな学歴の人たちですよね、たぶん。
石川:しかもあのクソ長い論考読んだ人たちですから。そう考えると、つけ足す言葉が思いつきません。ただ、分からないでもない自分もいる。僕も僻地で生まれ育って地方大学で学位とった人間なので、「いや、僕は基本的に君らの側の人間なんだけど……」という思いもありまして。
井上:トランプを「おやびん」って呼んでる人いますよね。やっぱりグローバルにあそこまでおやびんな人はいないということかもしれないです。
田中:TOP OF おやびん、みたいな? もうひとつ質問読みましょう。「両先生としては、今のお話の理解は研究対象なのか、共感なのか、純然たる興味です。熊の例えはたいへん分かりやすかったです」。
井上:両方です。危ういかもしれないけど。限りなく共感はしているけれども、一線を僕が越えてしまっているかどうかはみなさんに判断いただきたいです。「みんな逃げてー」という感じです。
田中:「逃げてー、僕、熊になっちゃうかもー」みたいな(笑)。
石川:全く共感できないものは、研究対象にはなりえないんでしょうね、たぶん。
井上:特に思想史の場合は、内在的に理解するということを学問的にトレーニングをしますので。
田中:内在的って、でも危ないですよね。そのビジョンで世界を見てしまうので。だから、井上くんのこの本はやっぱりものすごく危ういんですよ。ものすごく内在的に書いていくので、ところどころ共感してしまう怖さっていうのがありますよね。
石川:だからこの本、やっぱりジェンダーとかエスニック研究してる人からするとおそらくカチンとくるところもあると思いますよ。私は井上さんと一緒に研究させてもらっていて、井上さんの知性を信じているから最後まで読み切れたというところはありますよ。でも、アメリカ政治思想史はここを分析しなきゃ始まらないのです。
田中:なるほどね。そうですね。まぁうん。私もあとがきの最後に「2020年9月18日、ルース・ベイダー・ギンズバーグ逝去の日に」とあって、この一言がこの本の、両義性というか、意図するところをこの一言で言い表しているので、私は非常に良い本だと思うし、ぜひ読んでほしいと思うんだけれども。なかなかね、だからマチズモ問題とかそのあたりは今後、また議論できればと思います。あと会場内から1つ質問が。保守主義は今後、中国との関係についてどう考えているのか?
井上:反中主義が反共主義にかわる接着剤になるのかっていうのは、この本の最後で少し触れましたが、どうですかね。ソ連はやっぱり、アメリカとは異なる世界を築こうという、そういう陣営としての思想的な圧があったわけですけど、中国は官僚主導であれば民主主義はいらないんじゃないかという論点は示すものの、思想としての圧がどれくらいあるかというところが保守の知識人にとってはポイントだと思います。圧があるかないかで、思想的な危機感は違ってきます。
田中:トランプがいま反中を言うのは、経済的な問題として?
井上:関税戦争とか、経済のところで戦ってますけど、本当は、権威主義的な体制がトランプは好きじゃないですか。
石川:あるいはアメリカの保守は、思想的な圧がない限り、外交には無関心ですよね。だからネオコンを別とすれば、やっぱり基本的には孤立主義・反中央権力が基調でしょう。共産主義が元気だったころは戦いに行くんですけど基本的に外国のことに興味がない。そういう意味では、思想の話とはズレるのですが、東アジア情勢には空白ができると普通は見るべきでしょうね。じゃあ中国がじわりじわりと覇権を握るかというと、そこはヤンキーコンサバティブですよね。本能で多分アイツラ違うと気づくだろうと思います。アメリカ人の「自由」さを侮ることはできないと私は思います。
田中:会場に、今日もたくさんの方が……ソーシャル・ディスタンスのとれる限りにおいてのたくさんなのですが、ありがとうございます。もしご質問ありましたらいかがでしょうか。なんでも。
フロア:トランプさんの支持層が年収700万円ということは、いわゆる低所得労働者が支持層っていう理解で良いのでしょうか? 日本だと平均年収が400-500万なんですけど、ある程度、所得がある人が支持したということですか?
井上:ある程度はそうだと言って良いと思います。所得水準が本当に貧困線を下回るようななひとたちは、民主党を支持しているというのは、2016年にもデータでは出ていた。やっぱりポイントは、人種だと思うんです。日本でもそうかもしれないけど、そこそこお金がある人のほうが過激なことをネットで書いている。本当に困っているひとは民主党に流れ、生活が上向いているのか、それとも下に向いているのかというところで、先行きについての、目指す目線の上がり下がりで、トランプを支持するのかしないのかというところがかなり左右されていそうです。ダイレクトに経済というよりも、その他の要素があって、その延長線上に経済のことを解釈していくという位置づけが大事かと思います。
田中:他にもしございましたら、最後にもうひとつだけ受け付けます。
フロア:今日のリベラルとコンサーヴァイヴは、白人の話だと思いました。その一方で白人はもはやマイノリティという発言も出ましたけれど、そうすると今後は、黒人であったり、ヒスパニックをコンサーヴァティヴへと取り込んでいくのでしょうか? そういう動きがあるのかどうか。今後のコンサーヴァティヴとリベラルの動きというところで、展望というか、あるいはすでに起きている潮流とかはあるのでしょうか?
井上:フォックスが保守のケーブルネットワーク・ニュースでこれまで主流だったわけですけど、今日、フォックスからさらに保守の、ニュースマックスというチャンネルが保守のなかで名前を知られるようになっています。このニュースマックスに、クリス・サルセードというアンカーがいるのですが、彼はヒスパニックです。ヒスパニックの保守のテレビアンカーというのは、今後を占うひとつの事例かもしれません。
石川:たしかに仰るとおり今回のポイントはデータを見ても明らかなように、ヒスパニック系だから黒人だから民主党支持で、トランプを支持しないかと言うとそんなことはない。むしろ移民なんかはアメリカ社会の改善というよりアメリカ社会への同化を目指します。そうすると、リベラルなエリートが鼻持ちならない連中であるという構造は変わらないわけです。つまり、白人保守と同じような意味で保守になる可能性は高く、アウトサイダーである人々ほどより強固な保守になる可能性は十分にあります。
田中:ジェンダーやエスニシティのダイバーシティを獲得しつつ、それぞれの勢力が内部でごちゃごちゃ小競り合いを繰り広げて、いつかはワンアメリカになれると信じながら生きていくというダイナミズムのなかで、アメリカの政治、思想、言論、あと文化、そういったものが生み出されているということなのかな。
井上:(そのダイナミズムは)まだまだ続いていくんじゃないんでしょうか。
田中:ちょうどいま21時ジャストなので、本日のぽすけん第15弾「アメリカ保守主義とはなにか」を終わりにしましょう。保守主義について、ご理解いただけたでしょうか? 井上さん、石川さん、本日はどうもありがとうございました。
記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。
