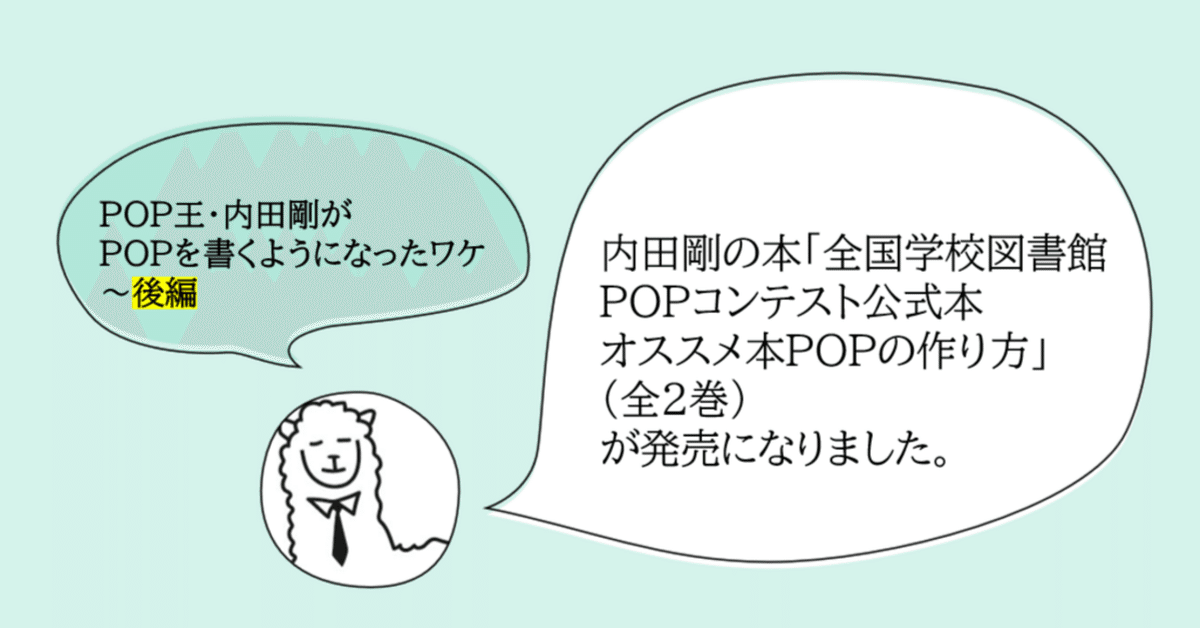
「全国学校図書館POPコンテスト公式本 オススメ本POPの作り方」の著者、内田剛さんがPOPを書くようになったワケ~後編
2024年4月に発売となった「全国学校図書館POPコンテスト公式本 オススメ本POPの作り方」(全2巻)。本を探してPOPの形にするまでの流れがよくわかる『気持ちが伝わるPOPを作ろう』と、アイディアのヒントとしてPOPコンテスト受賞作を多数紹介した『こまったときのPOP実例集』。この2冊があれば誰でもかんたんにPOPが作れるようになります。
2024年度から使用される光村国語4年上の教科書にある「本のポップや帯を作ろう」の単元にも役立つ内容です。ぜひ、チェックしてみてください。

著者の内田剛さんが、これまでに書いたPOPは6000枚以上。POP王の異名をもつ内田さんですが、意外にも、本を本格的に読み始めたのは書店員になってからだそうです。そして、上野創『がんと向きあって』(晶文社)との出会いをきかっけに、猛烈にPOPを書くようになります。
これは本気で伝えなければならない一冊だ。
書店員である自分にできることはなんだろうか?
このときを境に、手書きPOPに「売りたい」思いを込めるようになります。仕事に対する考え方も劇的に変化したという、内田さんのPOP人生、ぜひ以下でおたのしみください。
(前編はこちら)
三十にして、文芸の沼へ
当時、デパートの店舗では「汚いから」という理由で、売り場に手書きPOPを使用するのはNGでした。しかし、津田沼の書店で、新潮文庫『白い犬とワルツを』が一枚の手書きPOPから大ベストセラーとなったことから、一夜にして「手書き推奨」となったことも追い風となりました。
こうした奇跡的な巡りあわせもまた、運命なのでしょう。
『がんと向きあって』(晶文社)以降は、自分の担当ジャンルである文芸書を中心に、片っ端からPOPを書き続けました。これまで歴史書を中心にノンフィクションばかりに目を向けていて、小説にはまったくといっていいほど縁がなかったのですが、だからこそ読む作品すべてが清々しく心にしみわたりました。
この世にこれほど素晴らしいエンターテインメントがあったとは。
三十歳にして初めて物語の、そして作家たちの凄みを素直に肌で感じたのでした。
「ハリー・ポッター」シリーズ(静山社)の登場やケータイ小説のブーム、山田悠介『リアル鬼ごっこ』(幻冬舎)の仕掛けも忘れられませんが、特に思い入れが深いのは大崎善生『パイロットフィッシュ』(KADOKAWA)、吉田修一『パーク・ライフ』(文藝春秋)、蓮見圭一『水曜の朝、午前三時』(河出書房新社)あたり。個人的に作家の「両横綱」だと思っている角田光代や重松清作品との出会いも、この頃です。
読んでよかった、だけではない。それをどうやったら的確に人に伝えられるのか。頭の中はいつもそのことで一杯でした。


「POP王」、誕生!
入社十年にしてようやく書店の仕事に目覚めたのですが、次の異動先は、店舗開発室というまたしても現場を離れてマーケティングの部署でした。POPを約2年間、毎日店頭に立て続けていましたが、ついにその場所がなくなるわけです。
それを惜しんでくれた版元営業の方が、「それはもったいない。ウチで使わせてください!」と言って始まったのが「WEB本の雑誌」での連載コーナー「店頭POP製作所」でした。いただいたペンネームは「POP王」。この絶妙なネーミングもその後のPOP活動に大きく影響を与えることになります。
ちなみに、新宿の居酒屋でおこなったWEB連載の打ち合わせの流れで、「日本でも本屋が作る賞があってもいい」という話になりました。つまり「POP王」と「本屋大賞」は同じ日に生まれたのです。

「POP王」というキャッチーな名称での連載が、編集者の目に留まって初めての書籍『POP王の本!』(新風舎)にもつながります。
そしてこの書籍が名刺代わりとなって、「タモリ俱楽部」への出演や各地でのPOPをテーマにした講演やワークショップ開催にも広がっていきました。とりわけ学校図書館は横の連携も強く、中には十年以上のお付き合いのある場所もあります。次第に、自分の夢も「目指せ、POP甲子園!」と明確になっていきました。その経験と実績が「学校図書館POPコンテスト」に結びついているのです。
やれることを全てやりきる
売場のなかった本社勤務から再度、前の百貨店の店に一年半、副店長として戻ったあと、世田谷区の住宅地にある駅ビルの店舗に異動となりました。
初めての店舗責任者、店長という立場での勤務で自分のやりたいこと、やれること全てをやりきった忘れがたい場所です。
縁があって本屋大賞の設立メンバーの一人となって、文芸作家との交流も密接になりました。『天地明察』(角川書店)で本屋大賞を受賞した冲方丁を迎えたり、五年越しのラブコールが実って角田光代のサイン会を開催したり、大崎梢、大崎善生、小川糸、伊吹有喜、髙田郁、柴崎友香、吉田篤弘など、この店で絆を深めた作家たちは数知れません。
店長はジャンル担当を持たないのですが、店舗入口の一角に「店長棚」を持って、その時々の注目作品にPOPをつけて展開をしていました。その棚から新しい作家を知った、面白い本に出会った、というお客様からの声もいただきました。

書店は、書籍の売上だけでは予算を達成できません。いまでこそ文具・雑貨の取り組みは当たり前となりましたが、その先駆け的な試みもしていました。西洋絵画、浮世絵、リトグラフ、古地図、古本などの販売。定期的な絵本の読み聞かせ会。イベントスペースでの子供向けイベントの開催。地元大学生や職人、ショップとの連携など。まさに、書店は誰もが楽しめるテーマパークであることを、分かりやすいカタチで表現していたのです。
それから本部に移り、商品仕入の担当として出版社との窓口業務を務めることになります。様々な事情のある店舗の特性を見極めつつ、より良い情報と商品を共有すること。それは各店舗のためであり、会社のためでもありますが、何よりも書店に期待を抱いて足を運んでくれるお客様のためでした。一時、店頭販売業務との兼務があったり、一年以上の長期にわたって酷い腰痛に悩まされたりと辛い時期もありましたが、気持ちを奮い立たせてくれたのは、「お客様の役に立ちたい」という強い気持ちだけでした。
書店という枠をこえて
これまで半世紀以上生きてきて、数えきれないほどのピンチがありました。会社生活は「心」「技」「体」「縁」の四輪で成り立っています。その車輪が、いったい何度パンクしたことでしょう。ひとりでは乗りこえられない高い壁、そして目には見えない深い溝だっていくつもあります。しかしそれらの厳しい境遇を救ってくれたのはいつも本であり、本を介して出会った人たちでした。
出会いはすべて「学び」です。そのすべてが血肉となっているのです。
本と人に助けられ続けてきた人生の後半は、恩返しの毎日。約三十年間勤務した会社を辞めた大きな理由は、書店という枠をこえてメッセージを発信したいと思ったからです。
本屋大賞はもちろんのこと、図書館、学校、地域を巻きこみながら、POPを通じてたくさんの本との出会い、その喜び、楽しみを読者に伝え続けたい。
2024年の春、ご縁があって世に出すこととなった新たな本は、シンプルな想いを収斂した原点回帰の一冊であり、これまでの自分の集大成でもあります。誰かの心に小さくとも確かな変化をもたらすことができたとしたら、これ以上の喜びはありません。
内田剛(うちだ・たけし)
POP王。ポプラ社全国学校図書館POPコンテストアドバイザー。ブックジャーナリスト。
1969年生まれ。約30年の書店員勤務を経て、2020年よりフリーに。無類のアルパカ好きで、8月1日アルパカの日に「オフィスアルパカ」設立。文芸書ジャンルを中心に各種媒体でのレビューや学校図書館などで講演やPOPワークショップを実施。NPO本屋大賞実行委員会理事で設立メンバーのひとり。これまでに作成したPOPは6000枚以上。著書に『POP王の本!』(新風舎)、「全国学校図書館POPコンテスト公式本 オススメ本POPの作り方」(全2巻、ポプラ社)がある。
「全国学校図書館POPコンテスト公式本 オススメ本POPの作り方」の著者、内田剛さんがPOPを書くようになったワケ~前編
もあわせてどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
