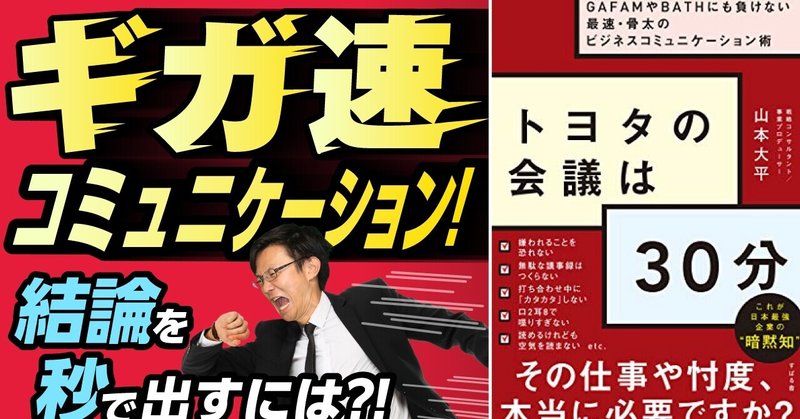
【名著紹介】「トヨタの会議は30分」の要約・感想 | 名著に学ぶテレワーク実践スキル
「リモート起業家」の私がテレワークに関する名著について、その要点&考察をお届けする「名著に学ぶ!テレワーク実践スキル」シリーズ。今回紹介する名著は、「トヨタの会議は30分~GAFAMやBATHにも負けない最速・骨太のビジネスコミュニケーション術~」(山本大平(著)/すばる舎)です。
「トヨタの会議は30分」という凄く気になるタイトルですが、実は私は以前よりかねがね「オンライン会議は30分にしましょうね」といったことを様々な機会で言ってきました。まさにピンとくるタイトルでしたので、本屋さんで見つけて読んでみたのですが、もの凄く面白い本でした。
最初は会議本かと思いまして、会議の進行の仕方みたいなことを教えてくれるのかと思いました。勿論そういう内容もありますが、本質は副題に書いてあるように、GAFAM(=IT企業の雄である5社(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)の頭文字を取った呼び名)やBATH(=中国を代表する有名なIT企業である4社(Baidu(バイドゥ)・Alibaba(アリババ)・Tencent(テンセント)・Huawei(ファーウェイ))の頭文字を取った呼び名)に負けないような最速骨太のビジネスコミュニケーション術というところで、トヨタに学べるビジネスコミュニケーションの真髄、無駄無理のないコミュニケーションとは何なのかといったことが書かれています。
著者の山本 大平さんは、京都大学大学院を卒業されて、新卒でトヨタ自動車に入社し、その後TBSテレビに行って、その後アクセンチュアに行って独立されたという凄い経歴の方なのですが、この山本さんがトヨタで学んだビジネスコミュニケーションスキルを余すところなく披露するという内容になっていて凄く参考になる点が多い本でした。 今回はこちらの名著の要約と感想をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひご一読ください!
▼今回の内容は以下の動画でもご覧頂けますので、ぜひご覧ください!
今回の学び:5つの実践スキル

本書の内容は多岐に渡って色々なテーマが書かれていて非常に面白いので、皆さんにもぜひ読んで頂きたいのですが、今回はこの本の中でも特に参考になる5つの実践スキルに関して要約&紹介して行きたいと思います。
「ギガ速で成果を出すためのコミュニケーション力」とは

この本は、今求められているコミュニケーション力がどんなものなのかということが書かれています。 色々な企業が「コミュニケーション力が重要です」と採用要件や募集要項に書いているのですが、そのコミュニケーション能力とは何なのかという部分でこの本に書かれているのは、「ギガ速で成果を出すためのコミュニケーション力」が重要であるということです。
時代の変化も非常に早くて、コロナでビジネスコミュニケーションの世界もバーンと時代が進んでしまい、しかもこの先どうなるか分からない。リモートワークが続くのか続かないのか、各業界がどうなっていくのか全然わからないという中で悠長な時間もない。
いかにスピーディーにコミュニケーションをとって意思決定をして成果を出していくのか、この力がビジネスにおいて一番重要ということがこの本で説かれています。
無駄を徹底的に嫌うトヨタのコミュニケーション力

著者が主張するのは「日本企業はめちゃくちゃ遅い」ということです。会議一つにとってもどうでもいい雑談から始まって、さらに参加者が遅れてきたりして、とにかく全然生産性が高くないと。
一方でこの著者はコンサルとしてGAFAMやBATHとも仕事をしているそうですが、彼らは凄く早いと。即断即決で、会議の生産性も非常に高く、成長するのも当然だと。日本企業が差をつけられるのも無理もないというのが、著者が実際に感じた肌感らしいのです。
実は、そういった日本企業にあってもトヨタは時価総額もダントツ日本一ですし、世界の時価総額ランキングでもかろうじて上位に入っている唯一の企業です。このトヨタのコミュニケーション術は凄いと。トヨタの無駄を徹底的に嫌うマインドは、生産だけではなくてコミュニケーションにおいても徹底されていて、それによって非常に速い速度でビジネスを回すことができるし生産性が高いと紹介されています。
前述のようにこの著者は、トヨタの後に、TBSテレビに行って、その後にアクセンチュアに行って、その後独立したという輝かしい経歴を踏んでいる訳ですが、新卒で入ったトヨタのコミュニケーション術がもの凄く活きていて、これによって成長させてもらったと書かれています。
それでは、いよいよ次から本題の「5つの実践スキル」について紹介していきたいと思います。
実践スキル1:会議は30分

実践スキル1 つ目は表題の「会議は30分」です。Microsoftも基本的に会議は30分にしていることで有名です。トヨタもこの会議時間30分というのを徹底しているそうです。
30分で終わらない場合はとにかく1回終了して、別の機会をとって再び30分の会議をすると。なぜ30分にこだわるかというと、それ以上時間を長く取ってしまうと、それだけ余裕が出て無駄な時間が増えてしまうと言います。
著者が指摘するのは、日本の大手企業やある程度の規模の企業になると1日に会議が2〜3回あるそうです。1年間に平日が240日ぐらいあるとして平均1日2.5回会議があるとすると、会議の回数というのは年間約600回になると。この年間600回の会議が毎回1時間の場合は600時間になります。これが30分の場合は当然半分になるので300時間になると。これは言い換えれば300時間もの時間をカットできるということであると言うのです。
ひと月の平均労働時間が160時間と言われているので、300時間は約2ヶ月分の労働時間と同じです。会議を1時間から30分にするだけで2ヶ月間分の労働時間捻出に等しく、非常に重要であると。こういったことに基づいて徹底的に会議は30分にこだわって運営されているというのがトヨタ方式であると紹介されています。
・「今日の会議、議題はどうなっているんだ」

それではどうやって会議を30分で収めるのかという部分で、当然30分で行うからには、まず「何を話すか」ということ、つまり議題が事前に明確になっていて、周知しておく必要があると言います。
この会議の「議題」よくアジェンダとも言いますが、トヨタではこれが決まってない場合は、参加者から会議の前にバンバン連絡が来て「今日の会議、議題はどうなっているんだ」ともの凄く言われるそうです。「それが無かったら会議始まらないぞ」ともの凄く怒られると。トヨタでは「会議をする」=「議題が決まっていて事前に周知されているのは当然」で、無い場合は「お前どうなってんだ」という風にガンガンと詰められると。これによって会議の前に議題を共有しているので、無駄なく最初から本題に入れるということだそうです。
またトヨタでは「前の会議との繋ぎを大切にする」ということも紹介されています。大半の会議というのは、その会議単体で行われるのではなくて、前に行われた会議や前提があってその続きが話し合われますよね。だから前からの繋ぎがすごい重要なのだと。前の会議で次回何を話すかを必ずきちんと決めておくことで、その次の会議ではスムーズに議題を続けられるようになる。つまり、会議は毎回事前に話す内容が明確になっており、最後に次回何を話し合うかを明確にする。それによって、繋がりが出来て無駄な会議が無くなるということに徹底的にこだわっているということが紹介されています。
ちなみに少し別トピックですが、トヨタには「定例会議」は無いそうです。会議が必要であれば、必ず都度都度30分会議を設定すると。無駄な定例会議では話す内容がなくても時間がとられてしまうし意味がないということです。
この様に、トヨタでは「会議の時間は1分たりとも無駄にするな」と新人時代から徹底的に叩き込まれるそうです。 そういう英才教育によって、きちんと事前に議題を決めて周知徹底し、会議は30分で終わり、次の会議の内容も明確になっているという生産性が非常に高いスタイルが徹底されていることが紹介されています。
本の中では、会議当日どういう風に内容をまとめるのかや、ホワイトボードの書き方なども紹介されていますので、興味があったらぜひお読みください!
実践スキル2:1分でOKをもらう資料

続いて2個目の実践スキルは「1分でOKをもらう資料」です。日常の業務で上司や同僚に確認をしてもらって許可を取らなきゃいけないという場面があります。その時に皆忙しいのであまり時間が貰えないことがよくあります。日本のトップ企業トヨタではなおさらそうです。トヨタではこういった場面で「1分でOKをもらう資料作り」を徹底しているそうです。
・「ペライチの資料にまとめて持ってきて」

当然1分でOKをもらえるということは、要旨が凄くまとまっていないと不可能ですよね。トヨタで必ず言われるのは「ペライチの資料にまとめて持ってきて」ということだそうです。この本ではなんとこのトヨタ流の「1分でOKがもらえるペライチ資料」の作り方(=フォーマット)を紹介してくれています。これは凄く貴重です。皆さんの会議や日々のチャットやメールでのコミュニケーションでも使えるので、ぜひしっかり覚えてください!
【トヨタ流】資料の構成

トヨタで徹底される「資料の構成」は以下の通りです。
①論点:何の話か
まず「論点」=「何の話か」を最初に入れるということです。要するに相手は忙しいので、いきなり話の本題から入ってこられても何の話なのか分からないというのです。そこで例えば「エンジンの改善について」とか、他の会社の例であれば「採用に関する新卒採用のセミナー・ネタについて」といった、「論点」=「何の話か」を最初に必ず書くということです。
部下からすると自分が任されている仕事ということで、そのことで頭が一杯なので何の話かは明らかです。しかし上司はそれ以外の色々なことを考えているので、急に言われても何の話か分かりません。そこでまずは「何の話か」をスパンと明確に伝えることが非常に重要です。
②要望:何をして欲しいか
次に要望=「何をして欲しいのか」を書きます。相談する相手にどんな判断や意思決定をして欲しいのかを書くのです。例えば「新卒セミナーで登壇者を探してます。AさんBさんがいるので、この2人のどちらにするか決めて欲しい」という何をして欲しいのかという要望を書くということです。
③結論:どうしたいと思っているのか
次に②の要望に対して結論=どうしたいと思っているのかを書きます。先程の例えで言うと、「私としてはAさんの方が良いと思っています」と自分の結論を必ず書くということです。
④論拠:なぜそう思っているのか
次に論拠=なぜそう思っているかを書きます。なぜAさんが良いと思うのか、「Aさんはこういうキャリアで若手に受けます。Bさんも結構良いが、話しの内容が難しくて新人には向いていないと思います」といった感じで③結論の論拠を書くということです。
⑤補足
最後に必要に応じて補足情報を書きます。 例えば「Aさんは登壇費用10万円かかりますが、予算の範囲から大丈夫です」といった補足事項があれば最後に書き添えます。
以上の5点でまとめたペライチの資料ができると、1分でぱっと判断してもらえるそうです。この資料の構成を、トヨタでは徹底的に叩き込まれて身につけるそうです。筆者もその後のキャリアで様々なクライアントワークをする際にとても役立っているそうです。
私もこれまで全く同じではないですが、ほぼ同様のアプローチをしていました。こういったアプローチができると、やはり色々なクライアントの所に行っても、とても喜ばれて非常に良い結果に繋がることが多いです。これはぜひ皆さんに身に付けて頂きたいスキルと言えます。
実践スキル3:聞き手を迷子にしないプレゼン

続きまして、実践スキル3「利き手を迷子にしないプレゼン」です。聞いている側が途中で何の話か分からなくなってしまわないようにするということですね。特にオンライン会議ではリアルにまして聞いてる側が迷子になりやすいということがあります。この本はテレワークに関して書いている訳ではありませんが、この聞き手を迷子にしないプレゼンというのは、特にオンライン会議においては特に有益だと思います。
・「もういい、やめろ!」

トヨタでは、皆が激しく思ったことをストレートに言うので、プレゼンが下手だったり準備されてないと「もういい、やめろ!」と言われるそうです。「もうやめろ!そんな意味わかんない話するんじゃねえ!」とめちゃくちゃ怒られて、何度も心が折れそうになったと著者は言っています。しかしそういう苦い体験を踏まえて迷子にしない分かりやすいプレゼン術を習得したとも書かれています。
【トヨタ流】プレゼンの4つのポイント

この本で紹介されているトヨタ流の聞き手を迷子にしないプレゼン方法は4つのポイントがあります。
①専門用語・横文字を避ける
まず1点目は話をする上で「専門用語や横文字は避けましょう」ということです。 これは私も意識して相手に合わせて言葉とか変えるようにしているのですが、ちょっと油断すると専門用語や横文字を使ってしまいます。つい「アジェンダ」とか「レイヤー」とか言ってしまいます。これはダメですよね。 専門用語とか横文字は避けましょう。
②冒頭に何を話すかを言う
続いて2つ目、プレゼンの「冒頭に何を話すかを言う」です。どんな話をされるかが分かっていないと聞く準備ができないし、理解しづらくなってくるので、「今日はこの話をします」と、きちんと伝えてから始めましょう。いきなり本題から入られると、全体像が分からなかったりして不安になってしまうので、必ず冒頭に何を話すかを言うことが大切です。
③章立て通りに話す
続いて3つ目は「章立て通りに話す」です。事前に「議題」や「アジェンダ」を共有して、章立てを紹介している訳ですが、割と多くの人がアドリブで章立てと違う順にプレゼンをしてしまうケースを見かけます。これは参加者を非常に混乱させ、不安にさせます。不安になってしまうと話が頭の中に入らなくなってしまいます。章立て通りに話さないことは、参加者を迷子にさせる大きな要因と言えます。
④節目節目で不明点を確認する
続いて4つ目は「節目節目で不明点を確認する」です。これも非常に重要です。会議の節目節目で「ここまでの所で分からないことありませんでしたか?」「質問ありませんか」と聞きましょう。これはリアルの会議でも重要ですが、オンライン会議では非常に重要なポイントです。 オンライン会議に不慣れな方は、焦ってしまってガーッと一気に話してしまいます。そうすると分からないまま進んでしまい迷子になってしまいます。特にオンラインの場合は途中で止めにくいので、よりこのポイントが重要になります。
実践スキル4:口2耳8で話す

続きまして、実践スキル4「口2耳8で話す」です。これは私もこの本で初めて聞いた言葉でした。要するに喋るのは2割、あとの8割はきちんと聞くということです。このバランスはとても重要です。私はこの「口2耳8で話す」という言葉は、この本の中でも1、2を争うほど良い言葉だと思いました。
このバランスが絶妙ですよね。よく会議で見かけるのは口0耳10、つまり会議に参加しても一切喋らずに聞いてるだけというケースです。これでは会議に参加してる意味がありません。トヨタではこういった人を、空気の様ないるかいないか分からない存在の「空気くん」と呼んで会議での存在価値を否定されてしまうそうです。
一方で口10耳0とか口8耳2になってしまうと、その人が話しすぎた結果、会議のバランスが崩れてしまいます。トヨタでは皆このバランスが上手く出来ていて、話し過ぎる人もいないし、黙りすぎる人もいないそうです。
実践スキル5:さっさと電話する

最後の実践スキル5は「さっさと電話する」です。今、世間的に電話することに対して否定的に見られる風潮があります。これが著者の山本さんが異を唱えたい一番のポイントだと思います。本では「電話コミュニケーションの復権」と書いています。
堀江貴文さんや色々なビジネスマンや論者が、電話をかけてくることに対して、人の時間を盗む「時間泥棒」だと言います。私も正直その様に考えていた節があります。
しかし、今回の本では、分からないことがある時にそのままにしておくことの方が問題だと言います。メールやチャットで聞こうと思っても文章を打つのは時間がかかります。かつ打った後の返信にも時間がかかります。何度もリレーすると時間がかかって話が全然進まない。こういった状況は問題であると警鐘を鳴らします。
・「そんな面倒なことしてないでさっさと電話しろこの●●ヤロー!」

そんな時にトヨタの場合はどうなるかと言うと、「そんな面倒なことしてないでさっさと電話しろ、この●●ヤロー(自主規制)!」と言われると。要するに、電話すればパッと解決できると。何度も往復が必要な事項ということは、早く電話して確認することがビジネス的には重要であるということをトヨタの中では徹底しているそうです。
・時間泥棒>>給料泥棒

次の言葉が面白かったのですが、トヨタでは「時間泥棒」よりも「給料泥棒」の方が悪であるとされるそうです。
先述の様に、世間では電話してくることを「時間泥棒」と呼びがちです。しかし、トヨタでは電話しないで不明点をそのままにしているというのはその間の給与を泥棒している「給与泥棒」だと言われ、そして「給与泥棒」の方が「時間泥棒」よりも何倍もたちが悪いと言われるそうです。パッと電話して意思決定ができるんだったら、気を使わずに電話して決めるということです。
勿論、考えなくどんな場合でもすぐ電話するのは、今の時代に合っているとは言えません。しかし、重要性と緊急性に応じて電話することも大切だと言えます。「電話は悪」みたいなことだけが走ってしまうのは違うということは、この本を読んで確かにそうだなと学びになりました。
今回の復習

最後に今回の復習として、「本日の学び:5つの実践スキル」を振り返ります。
まず1点目は「会議は30分」です。30分にすると密度が上がるし、それによって無駄な時間がなくなっていきます。30分にするにはきちんと議題を決めてアジェンダを作って事前に伝えておく、かつ次の会議の議題も明確にすることによって、30分の生産的な会議ができるというのが、ここで紹介されたスキルでした。
2点目は「1分でOKもらう資料」です。「論点」「要望」「結論」「論拠」「補足」でまとめるという話でした。
3点目は「聞き手を迷子にしないプレゼン」です。4つのポイントがありました。1つ目「専門用語や横文字を使わない」。2つ目「最初に全体像を示す」。3つ目「章立て通りに話す」。4つ目「都度都度確認を取る」。これらによって聞き手を迷子にしないプレゼンができるということでした。
4点目は「口2耳8のバランス」です。黙りすぎず喋りすぎずが大切です。
5点目は「 さっさと電話しろ」です。メールやチャットで入力に時間がかかったり、ラリーを何回もするような場合は時間がかかってしまうと。そういう時はさっさと電話して、パッパッと話した方が圧倒的に生産性が高いと。「時間泥棒」よりも「給料泥棒」になるなというのがトヨタ流だそうです。
ということで、本書の内容は本当に盛りだくさんでお勧めですので、ぜひ興味がある方は読んで参考にして頂ければ幸いです。
***********
▼動画はこちら。参考になりそうであれば、ぜひチャンネル登録お願いします!
▼YouTubeチャンネル「テレワークで活躍したいなら~池田朋弘のリモートコミュニケーション実践塾」
▼テレワークで活躍したい方のためのnoteシリーズ
この度、リモートでの会社経営・チーム運営を続けてきた中で得られた知見や実践例をまとめた書籍『テレワーク環境でも成果を出す チームコミュニケーションの教科書』をマイナビ出版さんから出版しました。
ぜひ、テレワークを導入される皆様の、より良い職場環境作りや、より楽しくて幸せなチームコミュニケーションの一助になればと心から願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
