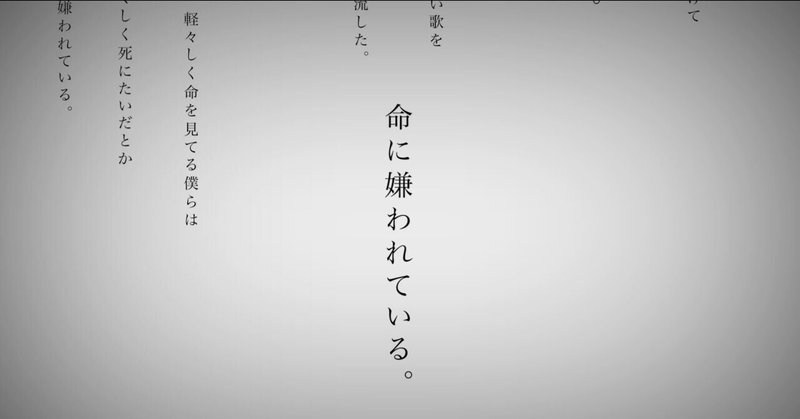
【後編】ボーカロイド自殺論——命を救うためのボーカロイド
※【前編】はこちら ↓
要約
ボーカロイドは自殺の苦しみを歌うのみならず、自殺を防ぐための、自殺に反対するためのメッセージをも歌っている。本論は、カンザキイオリ「命に嫌われている」、Omoi「君が飛びおりるのならば」の2曲に焦点を当て、これらの楽曲が自殺を防ぎ命を守るためのどのようなメッセージを発しているかを検討する。「命に嫌われている」は命を守ることを定言的に擁護する義務論的主張によって、「君が飛びおりるのならば」は自分の苦しみを相談できるような具体的他者の存在を強調することによって、自殺にきっぱりと反対する。両者の主張はそれぞれ普遍性、個別性を有しているゆえの強みと弱みを抱えているが、こうした自殺を防ぐための主張を知っておくだけでも、それは我々を自殺から守る防護壁となる。
序論:命を救うためのボーカロイド
さて、前編は自殺をテーマとするボーカロイドの三つの楽曲(Ayase「ラストリゾート」、和田たけあき(くらげP)「わたしのアール」、みきとP「少女レイ」)を取り上げ、これらにおいて自殺がいかにして表象されているかを論じた。そこで明らかになったのは、3曲に共通する要素として二つの不在——「自殺者の声の不在(語られない自殺者の苦しみ)」と「助けを求められるような他者の不在」が歌われていること、そして、これが現実社会における自殺の問題の写し鏡であるということであった。
だが、ボーカロイドは自殺の問題を浮かび上がらせるのみならず、自殺を防ぐための、自殺に反対するためのメッセージをも歌っている。そこで後編では、ボーカロイドが現代社会における自殺の問題に対し、命を救うためのいかなるメッセージを歌っているかを論じていく。前編が「ボーカロイドにおける自殺の描かれ方」を論じた編であるとすれば、今回の後編は「ボーカロイドにおける自殺防止のメッセージ」を論じた編である。絶望、不安、自殺願望、言葉にならない悩み——ボーカロイドはJポップシーンにおいて排除され続けてきた商業主義的ではない感情を掬い上げ、歌い続けてきた。誰にも打ち明けられない悩みを抱えるたくさんの人々の悩みに寄り添い続けてきた。「ラストリゾート」、「わたしのアール」、「少女レイ」が彼らの苦しみへの寄り添いであるとするならば、「命に嫌われている」、「君が飛びおりるのならば」は、彼らに未来の可能性を提示する一筋の光である。
命に嫌われている:生きることを定言的に擁護する
「命に嫌われている」は、2017年に公開されたカンザキイオリによる一曲で、現在に至るまで実に多くのアーティストやクリエイターによりカバーされており、2021年の紅白歌合戦では歌い手「まふまふ」によって歌われるなど、昨今のボカロシーンを代表する1曲である。
同曲は、冒頭、メジャーなポップシーンに対する直截的な批判から始まるが、この冒頭の一節は、これまで見てきたようなボーカロイド楽曲の想像力の延長戦上に同楽曲があることを如実に示している。
「死にたいなんて言うなよ。」
「諦めないで生きろよ。」
そんな歌が正しいなんて馬鹿げてるよな。
「ラストリゾート」、「わたしのアール」、「少女レイ」——前編で我々はボーカロイドが商業主義的でない感情を歌っていることを確認してきたわけであるが、ボーカロイドは匿名化、透明化されてしまう痛みを、苦悩を、声を、拾い上げ続けてきたのであった。その意味で、「命に嫌われている」の冒頭を飾る上の一節は、強烈なパンチラインとして楽曲のアティチュードを端的に示すリリックであると同時に、この楽曲が反商業主義的なボカロ的想像力の系譜上にあることを示していると言えよう。
ゆえに、「命に嫌われている」は、「死にたいなんて言うなよ」、「諦めないで生きろよ」といった綺麗ごとを並べて自殺を否定するわけではない。「「寂しい」なんて言葉でこの傷が表せていいものか」——「ラストリゾート」、「わたしのアール」、「少女レイ」が克明に示していたように、「わたし」の苦しみは一言で表現できるようなものではない。「命に嫌われている」は一人一人が抱えている苦悩や痛みに無頓着にただ「生きろ」と歌うのではなく、個々人の痛み、苦しみに寄り添った上で、最後に「生きろ」というメッセージにたどり着くのである。
さて、少し結論に先走ったが、今しがた述べたように、この曲は「生きろ」というストレートなメッセージで幕を下ろす。だが、同曲の大部分を占める感情は、生きる意味なんてない、というニヒリズムである。
お金がないので今日も 一日中惰眠を謳歌する。
生きる意味なんて見出せず、
無駄を自覚して息をする。
幸福も別れも愛情も友情も
滑稽な夢の戯れで全部カネで買える代物。
明日死んでしまうかもしれない。
すべて無駄になるかもしれない。
朝も 夜も 春も 秋も
変わらず誰かがどこかで死ぬ。
結局いつかは死んでいく。
君だって僕だっていつかは枯れ葉のように朽ちてく。
幸せ、愛、友情といった夢の戯れを追い続ける日々——それらは、結局のところ死んでしまうのであれば、全て無駄なのではないか。私も君も私の周りの人たちも、皆、いつかは死んでしまう。であるならば、幸福も、別れも、愛情も、友情も、全て意味がないのではないか。
だが、最後の「それでも」という逆説が全てをひっくり返す。
命に嫌われている。
結局いつかは死んでいく。
君だって僕だっていつかは枯れ葉のように朽ちてく。
それでも僕らは必死に生きて
命を必死に抱えて生きて
殺して、足掻いて、笑って、抱えて
生きて、生きて、生きて、生きて、生きろ。
これほどまでにどうしようもなく無理やりな「それでも」が他にあるだろうか。人はいつか死ぬ。人生に意味などない。——にもかかわらず、「生きろ」という。定言命法的に、生きることを絶対的に擁護する。人生に意味や目的はない。だが、それでも我々は、ただ、生きるために生きなければならない。
こうして議論はイマニュエル・カントの義務論に接続する。カントは自殺を道徳的に許されざる行為であると主張したが、この主張は上のような「生きることそれ自体を定言命法的に擁護する」姿勢から発している。
自己自身の人格における人倫性の主体を破壊するということは、まさしく、目的それ自体である人倫性そのものの存在を、その主体に関しては、この世から根絶するに等しい、したがって、任意の目的のための単なる手段として自己を処理することは、その人格における人間性(homo nounmenon)の尊厳を奪うということなのである。
自殺とは、日々の苦しみから逃れるために死ぬ、といったように、何らかの目的の為に人間の命を捨てる行為であり、その意味で、人間の生を何かの手段とみなすことの結果であると言える。カントはこのように生を何らかの目的・手段とみなすことは人間性の尊厳を奪うことだと言い、自殺を強く非難する。そして、同じ理由で、生命を維持することはそれが目的自体であるゆえに擁護される。カントは、人間は他でもない「人格としてのその性質」によってのみ、自分の生命を保存するような義務を課せられているのではないか、と考えた。我々は人間性そのものであり、生き続けることは人間の一義的な義務である——と。カントにとって、人間は道徳性を備える「道徳的存在者」であり、この道徳的主体は、道徳法則の遵守を使命とする限りにおいて目的自体として存在するというのである。
また、カントは、死に立ち向かうことを可能にする勇気こそが、その人の価値を証明するのであり、同じ人格の強さを生き続けることのみに使うべきと考えた。
「きわめて強い感性的動機をも支配するほどの大いなる権力をそなえた存在者」はみずからの命を奪ってはならない。自殺は自然に対する冒瀆であり、本来、他者に、またとくに自分自身に対する不道徳である。自殺するほどの強さを持つ者は、生きていくのに十分すぎる強さを備えているのだから、自分自身を殺すべきではないし、人々にも必要とされている。
自殺をする者は生き続けるのに十分すぎるほどの「強さ」をもっている。そして、自殺したいという感情を抱きながらも、「それでも」、自殺を思いとどまれる者は、強い感性的動機をコントロールできる強さを備えている。我々は皆、いつの日か必ず死ぬのであり、命に嫌われている。だが、今、命に嫌われていながらも生きていることそれ自体が、生き続ける強さを持っていることの証である。我々は命に嫌われているが、命を抱えて必死に生きている。いつか死んでしまうこと=「命に嫌われている」ことは、我々の弱さを示すのではなく、それは、「それでも」生きる我々の「強さ」の証明なのである。
だが、カントの主張する定言命法的な生きることの擁護は、いささか抽象的な論理に寄りかかっており、自殺を予防するための実効的な主張としては「弱い」論拠であることもまた事実である。カントが自殺をしてはならないというとき、その主張の論拠となっているのは抽象的な論理であり、訴求力をもつ主張であるとは言い難い。論理的妥当性は確かだとしても、現に苦しみ自殺を考えている人に対して自殺を防ぐための有効な手立てとはなり得ないだろう。
ここまで、「命に嫌われている」をその歌詞に着目して、それが定言的な生きることの擁護、カントの義務論的な主張をしていることを確認してきた。それは生き続けなければならない抽象的論理を追求するあまり、苦しみの中にいる人々に届きにくいメッセージとなってしまっているのであった。だが、カントの議論の弱さは必ずしも楽曲「命に嫌われている」の弱さを意味しない。上の結論はあくまで「命に嫌われている」の歌詞のみから導かれた結論であるが、カントと異なり、「命に嫌われている」にはメロディがあり、歌があり、映像がある。実際に、同楽曲が最後、「それでも」「生きろ」と歌い上げるとき、この「それでも」の力強さは言葉で説明できるようなものではなく、曲を聴いてはじめて理解できるようなものであろう。歌詞の主張それ自体は訴求力を持たないかもしれないが、それが音楽というフォーマットで見事に再構築されることで、命の定言命法的擁護は人々の心に響くメッセージとして生まれ変わるのである。
君が飛び降りるのならば:論理ではなく、ただ隣にいるということ
カントの主張は全ての人間に妥当する普遍性を追求するという点において非常に優れているが、一方で、抽象的な論理である故に人々への訴求力は限定的であり、実際に苦しみ自殺を考えている人に対して有効な主張であるとは言い難い。Omoiが2020年に発表した「君が飛び降りるのならば」は、カントの主張とは対照的に、具体的、個別的、日常的な観点から自殺を止めようとする一曲である。
いきなり歌い始めてごめんね
ちょっとだけそのまま聞いててね
本日お伝えしたいのは
とっても大事な君のこと!
たまにはケンカもしてきたけど
だからこそ何でも知ってんだ
君の長所はマジメなこと
ただ妄想癖がひどい!
同曲の冒頭で宣言されるのは、これが他でもない、「君」のための歌であるということである。「ラストリゾート」や「わたしのアール」とは対照的に、「真面目で妄想癖がひどい」「君」は、個別的、具体的な像を伴っている。
君が飛び降りるのならば僕は
笑って一緒に飛び降りる
止めてくれるとでも思ったか!
僕らの絆を見くびるか!
そして手を繋いで落ちて行こう
地面めがけてピースしよう
ここに、自殺をしてはならない「論理」は一切存在しない。君が飛び降りるのならば、「僕も一緒に飛び降りる」というのだから。だが、同時にこのことは、「僕」が「君」にどんなときも寄り添うということ、自分の苦しみを相談できるような具体的他者が存在するということを意味している。前編で確認したように、悩みを相談できるような具体的他者の存在は、自殺を防ぐ大きな防波堤となりうる。「君」は自殺をしてはいけない論理によってではなく、隣にいる「僕」によって、自殺を思いとどまる。
でもそういえば何かを
忘れているような……
ああそうだ!見たいテレビがあった!
やっぱり飛ぶの後でにしませんか!
そして、「ああそうだ!」と申し訳程度に付け加えられる自殺をしない「論理」は以上のとおりである。「見たいテレビがあるから自殺をやめよう」という提案は、常識的には不釣合いなものであると言わざるを得ない。だが、一方で、この提案が自殺をしなければやってくる未来をリアリティをもって想像させることに成功していることもまた事実である。自殺を思いとどまることで続いていく何でもない「君」と「僕」の日常がある。宇野常寛の言葉を借りれば、ここにあるのは、<ここではない、どこか>を夢想する「仮想現実」的想像力ではなく、<いま、ここ>を多重化する「拡張現実」的想像力である(注1)。見たいテレビがあること、好きな漫画の気になる続きがあること——側から見れば馬鹿げているような自殺を防ぐ「”非“論理」は、具体的な未来の日常をイメージさせることで、訴求力を持つ「強い」主張へと転化する。
ホントのホントーに飛べる日 目指して
もうちょっとだけ一緒に居ませんか!
最後、この曲は「飛ぶ」の言葉の意味を見事に読み替える。「自殺」のメタファーとして用いられていた「飛ぶ(飛び降りる)」という言葉の意味が、ここにきて一転、前向きな未来への飛翔の比喩に転化する。命を断つためではなく、未来を生きるために、彼らは飛び立つ。こうした言葉の読み替えは、自殺をいかにして防ぐかを考える上でも示唆に富んでいる。言葉と意味のつながりを意識的にずらすこと——それは見方・立場を変えることで今の自分の感情や置かれている状況をメタ的な視線で捉えなおすことであり、苦しみの中にあって視野狭窄に陥ってしまっている人たちの救いになる考え方かもしれない。命を終わらせるためではなく、未来を切り拓くために飛ぶ。それは単なる言葉遊びではなく、我々の人生にはいくつもの可能性があること、死ではない別の可能性が広がっていることを想起させるのである。
さて、ここまで「君が飛びおりるのならば」の歌詞について分析してきたが、「命に嫌われている」の歌詞、ひいてはカントの主張に長短があったように、具体的他者としての「僕」が「君」に寄り添い自殺を止めるというこの曲の図式もまた、明らかな欠点を有している。それは、どこまでいっても私を救ってくれる「僕」=具体的他者の存在に依存しているという点であり、「僕」のいない者に対して実効性をもたないことである。どんなときも隣にいる「僕」の存在は、確かに自殺を止める上で実効的な「強い」主張である。だが、具体的他者である「僕」が存在するか否かは個別的・具体的状況に強く依存するものであり、自殺を考えるほどの苦しみのただなかにいる者にはそうした他者が存在しないケースも少なくないだろう(あるいは実はいるのだが、そのことに気付けないケースもある。)。その意味で、「君が飛びおりるならば」は自殺を防ぐための分かりやすく実効的な「強い」主張を提示していながら、具体的・個別的な状況に依存するゆえに十分な普遍性をもたない。実際、「僕」が隣にいればただそれだけでいいという主張は、自殺をしてはいけない理由を論理的に考えることの放棄とコインの表裏の関係になっていたのであった。
カントがあらゆる人間に共通する自殺をしてはいけない普遍的・論理的理由を追求した一方、それが抽象的主張である故に自殺を防ぐ上での「弱い」主張となってしまっているように、「君が飛び降りるのならば」は隣にいる「僕」(=具体的他者)が「君」を苦しみから救うという自殺を防ぐ上で実効力のある「強い」主張をしている一方、具体的他者の存在を前提とする故に自分を救ってくれる具体的他者を有する者のみに妥当する「持つ者の論理」となってしまっている。「君が飛び降りるのならば」が代入不可能な他者の存在を前提にしているとすれば、この曲は「ラストリゾート」、「わたしのアール」、「少女レイ」の主人公らにとっての救いとはなり難い。
だが、「命に嫌われている」のパートでも最後に触れたように、ここまでの「君が飛びおりるのならば」における議論もまた、あくまで同楽曲の歌詞のみに着目したものにすぎない。実際に、同楽曲のミュージックビデオをみると、同曲の代入不可能性を幾分和らげるような仕掛けを見出すことができる。ミュージックビデオは、「僕=ショートカットの女の子」が「君=白い球体」に歌いかける構図となっているが、この「君」の記号性・抽象性は、代入可能な者として「君」を描いていると言えよう。また、本楽曲のリリースの3年前に発表されている姉妹曲「君が飛びおりるなら」は、「君が飛びおりるのならば」と同様のメロディ、ほぼ同様の歌詞からなっているが、歌詞にマイナーチェンジ(「君」の性格が「妄想癖がひどい」から「中二病がひどい」に表現が変化、自殺しない”非”論理が「見たいテレビがあること」から「聴きたい新曲があること」に変化)が施されている。この仕掛けは、具体的な他者の複数性、「君」と「僕」の関係の複数性を示唆するものであると言える。「君」は自殺をしてはいけないという論理によってではなく、他でもない、隣にいる具体的な存在=「僕」によって、自殺を思いとどまる——だが、それは「きわめて特別な僕」にとってだけの歌ではない。なんでもない僕たちは、白い球体に自分の姿を重ね合わせ、「僕にとっての」君の存在を見出すのである。
結論:愛と論理とボーカロイド
絶対に自ら命を断ってはならないという「論理」と君の隣にずっといたいという「愛」——「命に嫌われている」と「君が飛びおりるのならば」の2曲は、いわば「論理」と「愛」の両側から、自殺をしてはいけないというメッセージを歌い上げる。「論理」には客観的妥当性があり、普遍性を有しているという利点がある一方で、訴求力を持たないという欠点がある。苦しみの中にいる人に、カントの論理は響かない。「愛」=「僕」を助けようとする「君」の想いには自殺を防ぐ訴求力がある一方で、そのような「君」が存在しない人、或いは存在していても苦しみのあまりそのことに気付けない人にとっては空虚にしか響かない。
だが、「命に嫌われている」における定言的な生き続けることの擁護は苦しみの只中にいるときに訴求力を持たないかもしれないが、自殺をしてはいけない論理を「知っておく」ことは、自分が苦しみに苛まれたときの助けとなるかもしれない。「君が飛びおりるのならば」における「君」を隣で支える具体的他者の存在の強調は、「君」の周りに実は助けてくれる「僕」がいることに、「#いのちSOS」や「よりそいホットライン」など、「君」の周りにはたくさんの助けの手が差し伸べられていることに、気付くきっかけになるかもしれない。
確かに、自殺をしてはいけないという主張には何らかの「弱さ」があるのかもしれない。だが、我々には「命に嫌われている」が、「君が飛びおりるのならば」があることを、命を守るメッセージがあることを知っておこう。自殺の問題を意識から排除してしまえば、いざ気持ちが弱くなったときに、武器を持たずにひとりで立ち向かわなければならない。だが、これまで見てきたとおり、我々には、自殺を防ぐための、命を守るための、たくさんの防護壁があるのであり、苦しみに苛まれたとき、これらの武器とともに自殺に立ち向かうことができる。飛び降りるためではなく、飛び立つための一歩を踏み出すことができれば、「そのあとはどんなことも起こりうる」(注2)のだ。
脚注
(注1)宇野常寛『リトル・ピープルの時代』
(注2)ジェニファー・マイケル・ヘクト『自殺の思想史』p.248
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
