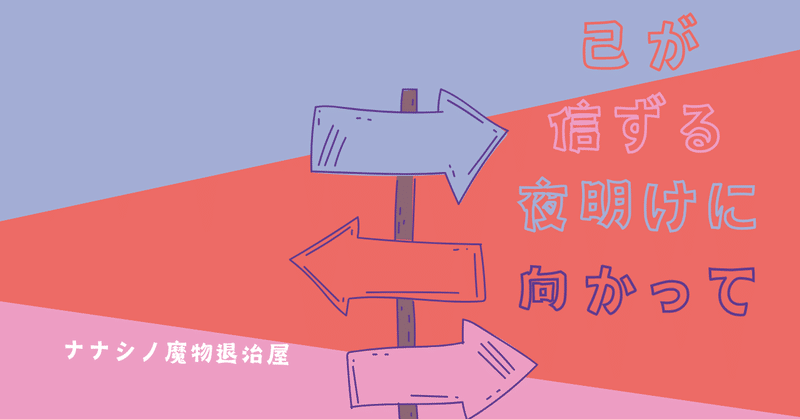
【短編小説】己が信ずる夜明けに向かって 4話(最終話)
「地区の医者はもう手が塞がっています」
「中級程度の治癒の魔術なら展開できますが……」
職員とノアがほぼ同時に口を開いた。女性職員は「そんな……」と絶望の表情を浮かべて項垂れてしまった。
「中級程度の治癒の魔術じゃダメなのか?」
「応急処置程度にはなるとは思います。ただ、患者さんが魔術嫌いなんです」
ラスターが、ああ……と落胆の声を上げた。地区の住民の大半は生まれつき魔力を持たない「アンヒューム」と呼ばれる人々だ。魔術師から強く迫害されてきた歴史を持つ彼らの中には、徹底的に魔術を嫌う魔術嫌いの人もいる。そういった人々は、例え自分の命がかかっている状況でも魔術を体に受けるのを拒む傾向にある。
「行くだけ行ってみよう」
「説得とか考えない方がいいぞ? あいつら無駄に頑固だから」
「ラスターの口なら何とかならない?」
「あらありがと。でも俺の口も万能じゃないぜ?」
ノアは小さく息をついた。たぶん何とかできる、という楽観的な希望は、すぐに絶望一色に塗りつぶされることになった。
……足をもつれさせながら逃げ出す魔術師が出てきた時点で、既に。
大怪我をしたという住人を見たラスターが開口一番「なるほど」と何かに納得する。何がなるほどなのかは分からない。いや、分からないふりをしたかった。
浅い呼吸を繰り返しながらも、その婦人は「魔術は嫌」と言う。ヒョウガとコガラシマルを警備の名目で置いてきたのは正しかったかもしれない。もしもここにコガラシマルがいたら、怪我人の喉元に刀の切っ先を添えて脅しにかかるだろう。
ラスターが手持ちの薬で応急処置をするも、焼け石に水と言える。
「魔術は嫌。嫌なの……」
救う手立てはあるにはある。ようは彼女に魔術を展開したのだとバレなければいいのだ。その手段をノアが持っていない……というわけではないが、問題がある。にわかに騒がしくなった外もその理由の一つだ。もとよりこの魔術は医療用だった。魔術が発展途上だった時代、治癒の魔術の展開は患者に強烈な痛みを与えた。激痛に耐えられなくなった患者が精神を崩壊させることがないように、その魔術は精神を安定させる目的で開発された。眠るなら賑やかな昼間より静かな夜がふさわしいのと同じ理論だ。
ノアは迷った。自分の技術でそれができるかどうか、迷った。もしも失敗すれば患者が自分たちに抱く信頼そのものが失墜する。
「何をしているの?」
そのときだ。
あの騒ぎの元凶が、声を張ってこちらに姿を現した。
「シノさん!? 謹慎じゃなかったんですか!?」
職員が声を上げたが、シノは彼を無視して患者に目をやった。
「魔術は嫌」
性懲りもなく患者はそう言ったが、その瞼がゆったりと閉じられていく。シノが何かを呟いている。ノアは目を見張った。既に幻術が展開されている。
何がなんやら、と言わんばかりの様子でついてきたらしいアカツキが、ノアを見てぴっと背筋を伸ばした。ようやっと状況が分かるといわんばかりの様子であった。
「なぁ、これどういう状況なんだ? 俺全然分からなくて……」
「アカツキ、治癒の魔術展開して!」
シノが声を張った。ノアはアカツキの背中をポンと押して、シノの方へと向かわせた。
「何で幻術展開したんだ?」
「いいから早く、時間がかかればかかるほど嘘がバレる!」
訳が分からない。
アカツキは、少し前のことを思い出す。言い争いの最中、突如響いた爆発音に姉はすぐに反応した。アカツキの手を取って地区の道を走る。当然瞬発力も体力も男のアカツキの方に軍配が上がるので、アカツキはおとなしくシノのペースに合わせて走った。音の割に爆発の被害は少なく、家は小屋以外無事らしい。同胞が数人、地面に項垂れたり茫然としたりしている様子が見えた。姉は姉で「謹慎じゃないのか」というツッコミを無視して立ち回り、即座に状況を把握している。
……こっちをものの見事に置き去りにして。
それも仕方のない話だ。こんな緊急事態に自分の扱いをどうこう文句を述べている場合ではない。
「早く!」
アカツキは頭をぽりぽりと掻いて、指先に魔力を乗せる。あたたかな光が夫人のケガに吸い込まれていき、あっという間に傷を塞いだ。
「あなたは怪我なんてしてなかった。少し腕を打っただけ」
仕上げの暗示をしっかり添えて、シノは婦人にかけていた術を解いた。
「魔術は嫌……」
「魔術? 必要ないわよ。あなたどこも怪我してないもの」
女性はぱっと顔を上げて、信じられないという顔をして見せた。が、シノは平然と「嘘だと思うなら、よく見て」と言う。婦人は恐る恐る自分の腹を見たが、実際そこにはヘソ以外のものはなかったのだ。
「きっと爆発と衝撃にびっくりして、怪我をしたって思っちゃったのね」
ギルドの職員が豆鉄砲を食らったような顔をしている。一方で婦人は自分の腹を不思議そうに見つめていたが、どれだけ見ていても怪我らしきものは出てこない。いそいそと腹をしまって、ぺこりと軽いお辞儀をしてその場を去っていった。
「すごい……」
「シノさんの幻術も的確だけど、それ以上に……」
ギルド職員の二人が茫然と呟く。その気持ちはノアにも分かる。アカツキの治癒の魔術に圧倒されているのだ。擦り傷程度の怪我でも魔力の制御を緻密にこなす必要があるというのに、アカツキは魔力をぽいと投げるだけで展開した。荒いわけではない。魔力の扱いという面においてアカツキは相当に器用なのだ。普通の術師なら数分かかるはずの展開を、彼は数秒で終わらせる。それがアカツキの実力だ。
ふわふわとどこか浮足立っているように見える職員二人を、アカツキは不思議に思う。超がつくほど初歩の治癒の魔術を飛ばしただけで、あんな露骨に高陽するものなのだろうか?
「ねぇ、彼のことスカウトしてみない?」
「た、確かに。ちょうど先月退職者が出たところだったし」
「スカウト?」
ノアは思わず尋ねてしまった。ギルド職員は、嫌な顔一つせずに答えてくれた。
「はい、実は――」
一方その頃、ラスターは死体を見ていた。
シノとアカツキがわちゃわちゃとやってきたどさくさに紛れて出てきた先にこれである。頭上から降りる影を見上げれば見慣れたカラスの姿。
あとはもう予想通りと言うべきか。
死体の胸には穴が空いている。そのすぐ傍でコバルトが「運べ」と短い命令を下してくる。
「で、これは誰?」
「精霊花火プロジェクトに協力していた地区のやつだ、精霊族を追い払うのに……花火をボカン!」
「なんか動機がアホくさくて力が抜けそう」
ラスターはため息をついた。地区の情報屋たちもそそくさとやってくる。遺体運びも道の掃除も、ここでは立派なお仕事だ。
「まぁ、でもいいや。こっちの問題も片付きそうだし、一応一件落着ってことで」
満足そうに頷くラスターの傍で、コバルトが肩を落とす。
「俺としては、あの煩い精霊族にはアルシュを離れてほしかったが……」
「そんなこと言って。また夢の魔物が来たらどーすんの?」
「二度も同じ轍は踏まない」
ラスターはため息をついた。コバルトはそういうやつだった。
後日――。
こちらが拍子抜けしてしまうくらいに、シノの謹慎はあっさりと解けた。
犯人探しなんてする必要もなく、もともと彼女との折り合いが悪かった女子職員が腹いせにチクっただけのことだった。女子職員はシノを何とか辞めさせようとあれこれ画策しており、ついにシノが精霊族であるという秘密を得たのだという。それをダシにしてシノをクビにする算段だったが、シノの勤務態度が良かったのと今回の対応のよさが評価されたのが仇となりクビにはならなかった。勿論、故意に身分を詐称したことについては説教があったが大したことではない。一方で情報をチクった女子職員はその内容を大幅に脚色していたこともあり、いたたまれなくなったのか退職していった。
「でもよかったよな。何事もなくなって」
ニコニコと嬉しそうなヒョウガに、シノは小さく息をついた。ナナシノ魔物退治屋の拠点はやたら賑わっている。シノのクビ回避お祝いパーティが開催されているからだ。
「もう少し謹慎しててもよかったかもしれないわ。仕事めちゃくちゃ溜まってそうだもん」
「仕事、いつから?」
ノアの問いに、彼女は少し残念そうに、というよりは、おどけて答えた。
「来週から。もう勘弁してほしいわね?」
シノの視線がアカツキの方に向く。アカツキは苦い顔をした。
「……俺さぁ、ギルドのこととか全然知らないけど、どこの馬の骨とも分からんような奴をねじ込んでいいもんなのか?」
外は明るい。昼から酒を飲める大義名分を得たへべれけ二人組がずーっとゲラゲラ笑いながら酒を飲んでいる。これはこれで面白いな、とノアは思った。
「いいのよ。ギルドの緊急救助隊なんて常に人手不足なんだから」
緊急救助隊。
ギルドに所属する魔物退治屋が依頼中に大けがをする等して動けなくなったときや、ギルドの近隣で魔物退治屋が集まるまで時間がかかるが急を要する事故が発生した時に暫定措置として出動する部隊のことだ。ギルドの命令を直に受けてすぐに動くことができるため初動が速い。その一方で人数が多いとは言えないので、場合によっては彼らの出動そのものが焼け石に水だったりする。
討伐任務が絡む関係で戦闘能力を求められる魔物退治屋とは違って、彼らに必要なのは治癒や解呪といった回復系の補助魔術。確かに、アカツキにはうってつけかもしれない。
「それにあたしの弟だってバレてるんだし、どこの馬の骨かぐらいはバレてるもんよ。それに、しっかり試用期間二か月ってのもおいしいわよね?」
シノが意地悪な笑みを浮かべる。
「緊急救助隊の仕事が合わなければ島に帰る選択肢だって出るんだし。そうすればあたしもギルド辞めてあんたについていけるし」
「は、はぁ!? なんでねーちゃんがついてくる話になってるんだよ! ていうかまだそのつもりでいたのか!?」
「当たり前でしょ。バカ弟。あたしを守りたいなら死ぬ気で頑張りなさい」
そうじゃないぃぃ……と呻くアカツキの肩を、コガラシマルがぽんと叩いた。
「とりあえず一件落着で、よかったよかった」
満足そうに頷くノアと、「よくないっ」と声を絞り出すアカツキを交互に見ながら、ヒョウガは瞬きを繰り返す。
「……よかった、のか?」
「よくねーよ!」
アカツキは吼えた。そこにささっと誰かの手が伸びる。ラスターのものだ。彼の手には盃が握られており、アカツキはヤケになってそれを一気に飲み干した。
「よかった」
シノの呟きに、ノアの口元が弧を描いた。
が、それも長くは続かなかった。
「ねーちゃんがさぁ、おれにさぁ、わーわーうるさくてさぁ」
「うんうん、分かるよ。ラスターちゃんならアカツキにそーゆー思いさせないのにな」
「まあまあ、まずはもう一杯」
へべれけ二人組改め三人集の話題はシノ本人に関することにシフトする。ヒョウガですら「オレ、もう知らない」と匙を投げた。
細く息を吐く音がする。
これはこれで、面白いかもしれないとノアは思った。その矢先、
「いい加減にしなさいこの酔っ払いども!!」
……シノの大声が、家屋の壁を突き抜けて高く高く響き渡っていった。
己が信ずる夜明けに向かって 完
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
