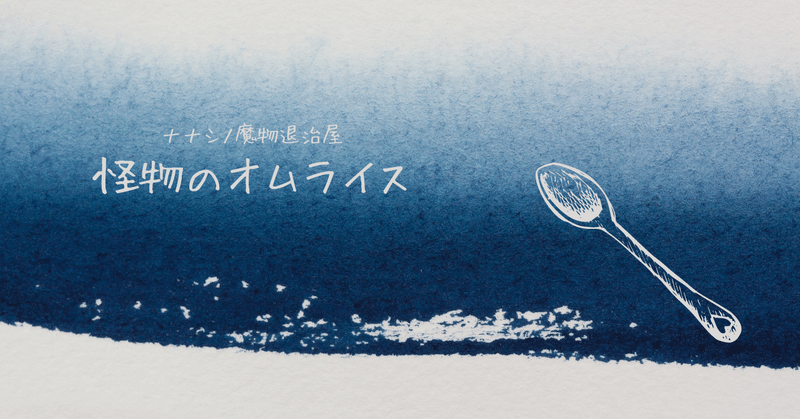
【短編小説】怪物のオムライス -AFTER-
(「石礫の痛みくらいこらえればよかったじゃないか!」と笑う男の影は、他でもなく自分のものだった)
バカが来たと思った。
「こんにちは。僕はビトスといいます。食堂を開いたので来てください」
アルシュの地区の外、つまり都市の中にアンヒュームが食堂を開くのはまだおかしな話ではない。ただ、想定する客に節操がなさすぎる。コバルトは自分にチラシを差し出す男を見ながら思った。人の悪い部分をなんら知らなさそうな、よく言えば純粋、悪く言えば愚かな男である。
「お前さん。本当に俺に来てほしいと思って言ってるのか?」
「あたりまえじゃないか。来てほしくなかったらチラシなんて渡さないよ」
やっぱりバカだ。
「お前さん、魔術に詳しくないね? 俺は呪いをかけられてるんだよ。そんな奴と同じ場所で食事したい奴なんていないだろ」
「どうして呪いをかけられている人と食事をしたくないの?」
「お前さん、化け物が人間を頭から食ってるのを見ながら食事したいか?」
男は眉をひそめた。
「僕の店では、人間をメニューとして提供することはしないかな」
コバルトは少し呆れた。
「……俺の例えが悪かった。お前さんは、化け物がオムライスを食い散らかしているところを見ながら食事をしたいか?」
男は笑った。
「君は人間じゃないか。どうしてそんな卑屈になるんだい?」
今度こそ、コバルトはものすごく呆れた。
「実際そうだからだよ。俺が地区の外に一歩踏み出してみろ、石ころや生卵がすっ飛んでくる。地区の中でだってたまに悲鳴が上がるぞ」
「そうなんだ。じゃあ、僕の店に来てくれる?」
――なんでそうなる。コバルトはぐっと言葉を飲み込んだ。代わりに喉がぐうぐう言った。
「気が向いたらね」
なんだか一気に疲れてしまって、コバルトはチラシを受け取った。ビトスは満足して「ありがとう!」と言って他の場所にチラシを配りに向かった。
「新規開店ぽかぽか亭へようこそ」「ビトス店長オススメ☆オムライス」「ふわとろしあわせ!」「エビピラフ」「ハンバーグセット」「おこさまらんち」「おなかもまんぷく!こころもまんぷく!」
チラシという名前の通り、「書きたいことを書き散らした」と言わんばかりの言葉の攻勢。コバルトはため息をついた。
裏路地の、生ごみ捨て場になっている区画の最奥には人が来ない。身を隠すのにはうってつけの場所。そこに、あのバカは来た。まともな神経の持ち主なら「あ、生ごみが置いてある。チラシを配ろう」なんて思わないだろうに。
コバルトは左下にくっついていた小さな紙切れをはぎ取った。「サービス! 銀貨一枚割引!」と書かれたそれは、微妙に綴りが間違っていた。コバルトは軋む体に鞭を打って歩きだした。
裏口から店に入って「お前さん、綴りが間違ってるよ。これだと銀貨十枚割引になる」と言うだけだった。それだというのに彼は勝手にコバルトを店内に押し込んで、「初めてのお客様!!」と言ってクラッカーを鳴らした。
コバルトは呆れすぎていよいよ頭痛を覚えた。
「そりゃそうだろうよ、チラシの開店日は明日になってんだから」
「…………」
ビトスはぽかんとしていたが、コバルトからチラシを受け取った。
「ホントだ!」
そして、大声で笑いだした。
結果として、店は軌道に乗った。
来るものを拒まないというスタンスは迫害に疲弊したアンヒュームたちの心をつかみ、一部の魔術師たちも店のうわさを聞いて冷やかしにやってきたものの、飯の美味さで黙る羽目になった。胃袋をつかまれてしまってはアンヒュームがどうこうなど些細な問題である。そして、コバルトが地区の普通の店で食事をしている、というニュースにアングイスは大喜びであった。
「アイツ、いっつも怪しい変な店でアブラと塩と砂糖濃いめの不健康メシばっかり食ってたからな!」
その一方でラスターも興味本位で来店していた。確かに味がよかった。にぎわうのも納得がいく。店が出て一年少ししてもビトスの勢いは衰える調子を見せない。
「コバルトはどうしていつも裏口から入るんだ?」
「言っただろ。石ころを投げられることがあるからって」
「じゃあ、このシールを貼ってよ。ぽかぽか亭の名前があれば、きっと誰も石を投げないよ」
店名が記載された巨大なシールを、青いコートに貼る気にはならなかった。だが、試しに持って歩いてみたら確かに何も飛んでこなかった。偶然かもしれない。しかし、こうして人は根拠のないオマジナイを信じるのだな、とコバルトは思った。
地区住民には専用の墓地がある。なんてことはない。ただの隔離政策の名残だ。地区住民にまともな身内がいる方が珍しいので、たいていの墓は随分と荒れたものになっている。その中でぽつぽつときれいな墓石があるが、それは定期的に誰かが来て掃除をしてくれているということだ。
ビトスの名が刻まれた墓石の前で蹲ったコバルトはしばらく動かなかった。押しつぶされた声が悲しみを吐いている。ユリの花束を抱いたノアは、墓前に置かれた様々な供え物に泣きそうになった。これだけで如何に彼が慕われていたかが分かる。
先ほどまで姿を消していたラスターが、ノアの手からユリの花束を預かろうとした。「どこに行っていたの?」と問われた彼は「知り合いに挨拶」と答えた。その時、ラスターの目が別の墓石に向けられたのを、ノアは見逃さなかった。ラスターは花束の包装を剥いだ。根元の茎を少し折ってから、備え付けの花瓶に差し込む。そうしている間も、コバルトは動かなかった。
ラスターはあの日のことを覚えている。王都移転の事後発表に凍り付いた店内と、心配を通り越した怒りに歪んだコバルトの顔を。
王都とえば、この国で唯一地区がない都市として有名である。アンヒュームが力を付けたとき、彼らを徹底的に排除したのはこの都市だけであった。魔術師優位のコミュニティでは才能のない魔術師だって暮らすのには骨が折れる。いくら味のよいオムライスやハンバーグを作れるといったところで、アンヒュームであるというそのたった一点がハンデどころの騒ぎではない。
「やめとけ。今からでもやめとけ。王都じゃアンヒュームは生きたまま皮を剝がされて三日三晩さらし者にされるぞ」
なんとか軌道修正をしようとラスターが叩いた軽口は何の効果もなかった。
「死ににいくようなもんだぞ」
ぞっとするくらいに低い声を繰り出すコバルトに対し、肝心のビトスはにこにこ笑いながら言った。
「大丈夫。だってこのお店だって魔術師とアンヒュームを結び付けたんだよ?」
「このバカが! 王都とここを同列に語るな!!」
「やってみないと分からないよ。最悪、僕がアンヒュームだってバレなければいい」
コバルトの唇がわなわなと震えた。ラスターは、彼がいつ拳銃を取り出してもおかしくないと思った。この中で緊張しているのは自分だけで、他の客たちは不安そうにビトスを見つめる者もいれば、彼の強い決意に折れて応援する気持ちになっている者もいた。
「……勝手にしろ!!」
銀貨十枚をテーブルに叩きつけて、コバルトは店を出てしまった。ラスターは思わず背もたれによりかかって息をついた。
「なあ、ビトス」
「うん?」
コバルトを追いかけるために席を立ったラスターは、店を出る直前にビトスに告げた。
「もしも、もしもだぞ? あんたが王都で店をやって、運悪く失敗したら……その時は、絶対、絶対にここに戻ってきてくれ」
ビトスはにっこり笑った。
「大丈夫。僕のオムライスには、みんなを仲良しにする力があるんだから!」
どうしてビトスは、約束を守ってくれなかったのだろう。静かに泣き続けるコバルトの背中が、わずかに震えるのを見ていると自分が眩暈に襲われているのかどうかの判断すら怪しくなる。ラスターは手中のメモを見た。「コバルト ごめん ぼくがバカだった」という黒いペンで書かれた遺書である。ビトスは手紙の中でも助けを求めるようなことはしなかった。もっと強く止めていれば。もっと強く「戻ってこい」と言っていれば。こんな結末にはならなかったのかもしれない、否、ならなかっただろう。
ノアが地に膝をついた。そしてコバルトの背中を撫でた。いつものコバルトなら、その手を乱暴に払いのけたことだろう。しかし今日はそうしなかった。
コートから、一通の手紙が落ちる。ラスターはそれをそっと拾い上げた。コバルトが持ってきていたビトスからの手紙である。少し浮かれている筆跡が楽しそうに便箋の上で踊っていた。
「ありがとう、二人とも」
蹲った体の奥からそんな言葉が聞こえた。ラスターはまだ途中までしか読んでいない手紙を丁寧にたたんだ。
「……帰ってくることができてよかった」
ノアは空いている方の手を強く握りしめた。掌に傾斜がつく。体を起こしたコバルトが、泣きはらした目でノアを見た。
「だから、お前さんもあまり引きずるな」
「……コバルト」
「俺が言っても説得力がないかもしれないがね」
コバルトはポケットからハンカチを取り出そうとして、動きを止めた。すかさずラスターが探し物を差し出す。
「読んだか?」
ビトスからの手紙を受け取ったコバルトの質問に、ラスターは一瞬ためらった。隙間に風が通る余裕もなかった。
「読んだ」
ラスターは素直に答えた。しかし半分は本当で半分は嘘だ。コバルトは肩をすくめた。
「大した理想だよ。俺には到底真似できない」
コバルトがその手紙をノアに手渡してきたので、ノアはそれを読んだ。その間、コバルトは鼻をかんでいた。
まるで料理人になった自分が書いたかのような手紙にノアは驚いた。そうして夢中になって読んだ。
――いつか、いつか君が、投石の恐怖に怯えることなく都市の中を歩くことができる世の中になってほしいし、そうしたい。
深い青色のインクを便箋ににじませながら、同じようなものを書いた。
そんな記憶がノアにはある。
(ビトスは一度、誰かをモデルにしたメニューを置いてみたかったのだが、誰をモデルにすればよいのかと考えたとき、候補は一人しかいなかった)
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
