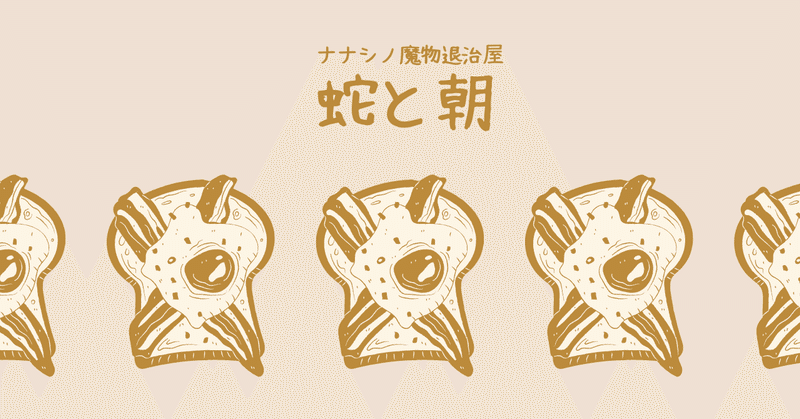
【短編小説】蛇と朝
人が寝ている。
通路のど真ん中で。
これが自分の生活圏外だったら素知らぬふりして素通りだが、幸か不幸か彼はアングイスのアパートの真ん前でグースカ気持ちよさそうに眠っていて、背中をつついても頬をつねっても起きる気配がない。
この魔力の気配は精霊族のものだ。アングイスは「むむむ」と声を上げて考える。地区に居座る精霊族は、魔術師からの扱いに辟易した者が多い。ここのルールを守って生活する者が多いとはいえ、中には人間を下に見て先住者たちを支配しようとする者もいる。そもそも、ルールを守る精霊族の割合が多くなったのだって、ルール違反者の大半が駆除されたからだ。
アングイスは試しに解呪の魔術を展開した。眠り続ける呪いであればこれで解くことができる。しかし精霊は目を覚まさない。面倒なことになった。知り合いの顔を思い出す。コバルトならゲラゲラ笑いながら自業自得と吐き捨てるだろうし、ノアであれば迷いなく自分の家のベッドを貸す。ラスターは財布からいくらかの現金を抜き取って去っていくだろう。
「ワタシはあいつらみたいにはならないぞ」
身体強化の魔術を展開し、精霊を担ぐ。足をずりずり引きずりながら、アングイスは彼をアパートに担ぎこんだ。散らかっている部屋だ。使い終わった魔法薬の瓶を蹴飛ばしつつ、アングイスは精霊をベッドに投げ入れた。
「ふん」
そして、自分はソファーに潜り込み目を閉じた。
朝が来る。アングイスはたいてい朝六時ごろには目を覚ます。だが今日は違った。拾ってきた精霊が先に派手に起きたのだ。その気配にアングイスも飛び起きる。
白亜の目と視線がかち合う。彼はどうも混乱しているらしい。
「ここはワタシのアパートだ。オマエは道路のど真ん中で爆睡していたんだ」
「夜が来たのか」
「夜は来るだろ」
「あー、それまでに戻らないといけないって分かってたんだけどな……ねーちゃん心配してるかも」
精霊はがっくしと肩を落とした。
「もしかしてオマエ、夜は強制的に眠ってしまう体質なのか?」
「何だよ、悪いか? 精霊族にはそういうのもいるんだよ」
「なるほど。通りで解呪の魔術を展開しても反応がなかったわけだ」
アングイスは納得して、ソファーから降りた。
「朝飯はどうする? 何か食べるか?」
「いいのか?」
「別にいいぞ。オマエがわるい精霊族ではないと分かったなら、助ける理由になる」
アングイスがキッチンに向かうと、精霊もついてきた。アングイスよりも身長がある。ノアより少し低いくらいだろうか。
「オマエ、名前は?」
「アカツキ」
「そうか。ワタシはアングイス。地区の美人女医だ」
「びじんじょい」
一瞬言葉の意味を理解できなかったかのような反応をしたアカツキだが、アングイスは無視した。
「ねーちゃんが心配していると言っていたが、姉がいるのか?」
「ああ。めーっちゃキッツイ性格のねーちゃんがいる」
「……そうか」
フライパンに、油を敷く。魔力のコンロで火をつける。温まったところでベーコンを敷くと、匂いが一気にはじけた。少し焼く。カリカリにするのも悪くはないが、今日は程よい焼き具合の気分。胡椒を振ってから卵を割り入れる。透明な白身が一気に白く染まったところで、フライパンに蓋をする。音がこもった。囁くようにしてベーコンと卵を焼いている。
アカツキはアングイスの傍に立って、じっと料理の様子を見ていた。
「オマエは弟なんだな」
アングイスがぽろっとそんなことを言った。アカツキは数度瞬きをして、少し首を傾げた。
「……それがどうかしたのか?」
「いや、何でもない」
トースターに食パンを二切れ。戸棚からはちみつを取り出す。フライパンの蓋を開けると半熟卵のベーコンエッグが顔を出す。そこに塩を少々。胡椒は先ほどベーコンに振りかけたので必要ない。こうすると見栄えのいいベーコンエッグができるのよ――母の声が聞こえた気がした。
「ワタシにも弟がいたんだ」
トースターがパンを吐き出した。きれいな焼き色がついている。アングイスは皿にトーストした食パンを置いて、その上にベーコンエッグを置いた。
「今も生きてたら、オマエくらいにでっかくなってたんだろうなって思った」
「……そっか」
湯気がふわりと立つ。アングイスはベーコンエッグトーストにはちみつをかけ始めた。
「美味いの?」
「塩気とはちみつの甘みがマッチして美味いぞ」
「えー」
露骨に嫌がるアカツキに、アングイスはニヤリと笑う。そして一瞬の隙をついて、彼のベーコンエッグトーストにはちみつをかけてしまった。
「あ!」と大きな声が上がる。
「ものは試しだ、食ってみろ」
アカツキは嫌そうな顔をしていたが、アングイスの勢いに押されて渋々口を開いた。一口かじるととろとろのはちみつが皿の上に滴る。もぐもぐと咀嚼を繰り返すアカツキの顔は、疑念から徐々に高揚へと変わる。
甘みが塩気を、塩気が甘みを引き立てる。味の調和という言葉はこういうときに使うのだろう。一見相性が悪そうなはちみつが、その甘みを用いてベーコンエッグのうま味を強調させている。
「……うまい」
少し悔しそうな声が出た。アカツキはそのまま、もう一度はちみつベーコンエッグトーストに食らいついた。
「そうだろう!」
今度はアングイスが大きな声を出した。
「コバルトには『残飯』と散々な評価だったがな!」
そして、自分もはちみつベーコンエッグトーストにかぶりついた。
アカツキは卵の黄身を啜る。手にはちみつが垂れるがそれもまた一興。ただ、腕に回ると服の袖が汚れるのでそれだけは阻止する。卵の相手が一段落したところで手のはちみつを舐めた。見るとアングイスも似たようなことをやっている。
「うん、うまい」
キッチンの窓から朝日が徐々に、徐々に差し込んでくる。飯を食っている間に太陽が昇ってきたのだ。
「急いでねーちゃんのところに帰らないとな。きっと心配してるぞ」
「そうかなぁ」
「そういうものだ。ワタシには分かる。姉だったからな」
ふうん、とアカツキははっきりしない返事をした。アングイスが紙袋を差し出してくる。焼き菓子の袋だ。アカツキは素直に焼き菓子を取り……いや、先に食事を済ませようとトーストにかぶりつく。
窓の外から光が漏れる。ほんのりと黄色い朝の陽ざしに、アカツキは崩れた卵の黄身を見た。
ナナシノ魔物退治屋はこうやってできた、がひとつの記事になりました!
有償ですが、その分結構思い切ってあれこれ暴露しています。創作裏話が好きな方はぜひ!
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
