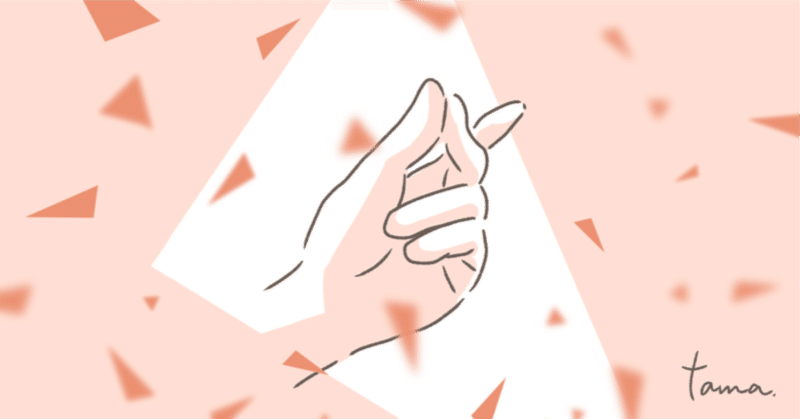
【短編小説】ウキウキ奇術にワクワクな魔術師
「ノア、明日空いてるか?」
そう言いながらラスターが手渡してきたのは、奇術イベントのチラシだった。
奇術というのは、魔力を使わない魔術である。つまり、指先や器具をうまく操ることにより、手元のコインを消すとか、トランプの絵柄を当てて見せる芸の一種。もともとは生まれつき魔力を持たない人々――アンヒュームの手遊びとして生まれた。つまり奇術師を名乗った時点で「自分は魔力を持っていませんです」という主張をするに等しい。とはいえ、今はその技術を認める動きも徐々に出ている。実際、魔力を使わずに紙を燃やしたり、厳重に施錠された箱から脱出したりするのは圧巻といえよう。
「奇術かぁ」
ノアが懐かしそうにした。
「父さんがすごく好きだったんだ。魔力を使わないとできないことを、魔力なしでできるのは才能だって」
「おっ、食いつきがいいね」
「休みを取る決心をしたよ」
ラスターはガッツポーズをした。プロからアマチュアまで、多数の奇術師が集まるイベントは注目度も高い。王都は徹底的に反アンヒュームを貫いているので、奇術イベントが行われるのはたいてい商業都市か地方都市だ。今回は運よく商業都市アルシュで開催されるらしい。
翌日、少し浮足立ちながら会場に向かったノアとラスターは、すぐに会場の異様な雰囲気に気が付いた。集まる奇術師たちから白い眼を向けられている青年がいる。
ノアはラスターの方を見た。
「何があったんだろう?」
「何もないさ」ラスターは答えた。
「何もないのに、こんな空気になる?」
ノアは明らかに困惑していた。そこに、ピエロの化粧をした奇術師が声をかけてきた。
「やあ! お客さんだね!」
ニコッと笑うピエロはコミカルを通り越して少し不気味であったが、ノアも子供ではない。
「こんにちは」
ピエロに怯えていたのは、十歳くらいまでのことだったと思う。
「せっかくのお祭りなんだ、楽しんでいってよ!」
ピエロはそう言って、ノアに手のひらを見せる。何も持っていないという証明だ。そして、手のひらを重ね合わせて力を込める。重ねた手のひらをぱっと離すと、中から銀貨が一枚出てきた。
「えっ、すごい!」
ピエロは銀貨をノアに手渡した。ノアは銀貨を確認した。間違いなく本物である。
「ねぇ、ラスター、すごい。銀貨が出てきたよ。本物だよ」
そして、ラスターに銀貨を渡す。ノアは「本物だよね?」と問いかけた。ラスターは頷いた。
「これを千回くらいやれば大金持ちってことだな」
ピエロが口を開けて笑った。ラスターはピエロに銀貨を返した。ピエロはおどけた様子でお辞儀をして、ノアとラスターは拍手をした。
「この後十一時からステージが始まるよ!」
そう言って、ピエロは別の客に手品を見せに行ってしまった。
「すごかったね」
コインの手品ですでに興奮気味のノアを見て、ラスターはちょっと気が早いんじゃないかと思った。このまま人体切断や密室脱出の奇術を見たら、悲鳴を上げながらぶっ倒れてしまうかもしれない。
奇術イベントは会場のあちこちを奇術師が歩き回り、客に奇術を披露する。また、事前に申し込みをしていた奇術師は専用ブースを設けることができ、ファンの多い奇術師たちはそこでたくさんの観客相手に手品を披露していた。
その中で、ノアは奇妙なのぼりを見つけた。
――僕はルーツ自認です。
ルーツ自認、という言葉自体になじみがない。生まれつき魔力のない人を指し示す「アンヒューム」が差別的なニュアンスを持つ一方で、「ルーツ」にはそのニュアンスがない、というのは分かるが、ルーツであることを自分から発信する人はそういない。そもそも奇術師の時点で「自分は魔力がありません」と言っているようなものだ。
病や怪我が原因で後天的に魔力を失う人もいるので、魔力がないからといってアンヒュームであるとは限らない。だから奇術師だからといって、ルーツであることを主張するのはほぼデメリットしかない。
「ルーツ自認って……」
つまり、こいつは魔力ナシを自称しているというわけだ。イベント会場入場時の空気の悪さはこれが原因だろう。それもそうだ。奇術は「魔力を使わない」という条件がついている。そこに魔術を引っ張ってこられて「自分はルーツなのでこれは魔術ではありません、奇術です」などと言い出されたらたまったものではない。
ルーツ自認の奇術師のブースを見ると、随分と人が多い。みんなカバンや服に奇妙なデザインのバッジをつけていた。
「僕は魔力もあるし、魔術も使えるけど、ルーツです。自称ルーツです。ルーツ自認を認めてほしいです。そういうバカです、っていう証拠だよ」
当事者のラスターが悪意満載の説明をしてくるが、当然であるとしか言いようがない。魔力を持っていて、魔術を扱えて、それでいて「自分には魔力がありません」と言われたらぶん殴りたくなるに決まっている。
「アンヒュームを名乗りたい魔術師は、ほんとに魔力を封印する。ああいうのはファッション魔力ナシ」
ラスターの「俺もそうなりてぇー」という小声の皮肉は、ノアにだけ聞こえた。
実際、奇術師の手のひらから出ている炎にはわずかな魔力の反応がある。これは残存魔力の類ではなく、炎を熾す魔術が現在進行形で発動している証拠である。それでも、わっと拍手が沸き起こる。
「なんか、全然すごくないね。魔術で炎を熾すのは初級も初級だから……」
炎が色を変える。形を変えて、また色を変えて、大きさを変える。すべてに魔力の反応がある。
「…………」
ノアは手のひらに魔術を展開した。炎が上がる。色を変える。形を変えて、また色を変えて、大きさを変える。ルーツ自認の奇術師が展開する奇術を、ノアはそっくりそのまま魔術で再現した。
奇術師がこちらに気付いた。むっとした顔でノアを見る。その様子に観客もノアの存在に気が付いた。ヒソヒソと悪口が囁かれる。奇術師が展開する奇術を完璧にコピーしようとするノアは集中しすぎで聞こえていなかったようだが、耳のいいラスターにはしっかり聞こえていた。
「なぁに、あれ。あてつけかしら」
「自分は魔術で奇術ができるって自慢したいんじゃない?」
ラスターは失笑した。それはそっちの奇術師のことだろう、と思ったその矢先、ノアの隣で同じ炎を展開する奴が出てきた。奇術師側の参加者であることを示す小さなプレートが首からぶら下がっているので、彼も奇術師のはずだ。
ノアもそれに気が付いたらしい。そして自分の炎の展開をすっかり忘れて見入っている。
「ラスター、ラスターすごいよ! これ、この炎は全く魔力が使われていない!」
死ぬほど当たり前すぎる、そもそもの前提。ノアは素直にそんなところを褒める。ラスターは腹に力を込めた。ぐっと込めた。必死で平静を装った。
「どうなってるんだろう、色も変わってる! 魔術の場合は魔力の出力を変えるんだけど、これは魔術じゃないんだよね! すごい! どうやってるんだろう!」
身長百八十五センチ越えの成人男性がそんなことを、「よく通る大声で」言うものだから、様々なもの見珍しさで観客が集まってくる。
「お兄さん、ちょいと下がってくれやせんかい?」
奇術師がそう指示をすると、ノアはわくわくした顔で少し下がった。奇術師は指先で魔術をかける動きをした。しかしそこに魔力はない。ただのジェスチャー。しかし、炎はその動きに答えて大きくなる。ラスターはそのとき、奇術師の指先から白い粉が生じるのをしっかり見ていた。
「ラスター! すごい! 見た!?」
「見てる見てる」
正直、奇術そのものより奇術を見ているノアの方が数倍面白い。
「魔力を使っていないのに、あんなことができるなんてすごいね! 俺なんかさっきの物真似でくたくただよ!」
それは物真似が原因なのではなく、ただただはしゃぎすぎているだけである。ノアが気づいていないだけで。
「お兄さん、その反応いいねぇ」
乱入した奇術師がにこにこしながら、炎をぎゅっと握りしめて消した。
「いえいえいえ! すごく面白かったです! あんなにキレイに色を変えるなんて!」
「そんなに喜んでもらえるなんて思ってなかったからねぇ、ワタシまで楽しくなっちゃったよ」
そして、手のひらに握りしめた何かを、そっとノアに握らせた。
「最後まで楽しんでっておくれよ」
そう言って、スキップ交じりで奇術師は去っていった。
ノアはそっと手のひらを開いた。小さな陶器の人形だ。
「これも、手品……!」
ラスターは思う。
――多分これ、ノアの親父さんもこの調子だったんだろうなぁ。
「ねぇラスター見て、陶器の人形だよ。かわいいね」
「そうだな、かわいいな」
「これ、もうひとつそろえて家に飾ろうか?」
「どうやって揃えるんだ?」
ラスターは、このとき、人間の純真さというものをここまでわかりやすい形で目の当たりにすることになるなど思ってもいなかった。
「さっきのピエロの奇術師に増やしてもらおうかなって」
「ノア、魔術も奇術も万能じゃないんだぞ」
結局、一部始終を見ていた観客が先ほどの炎の奇術師を呼び、ノアは小さな陶器の人形をもう一体もらえることになった。
「いやはやいやはや、こーんなに喜んでもらえたのは初めてだねぇ」
ラスターに陶器の人形をプレゼントするノアを見て、奇術師はからからと愉快そうに笑っていた。
(ああ! 僕が見たかったものを全て持ってくるとは、夢にも思っていなかった!)
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
