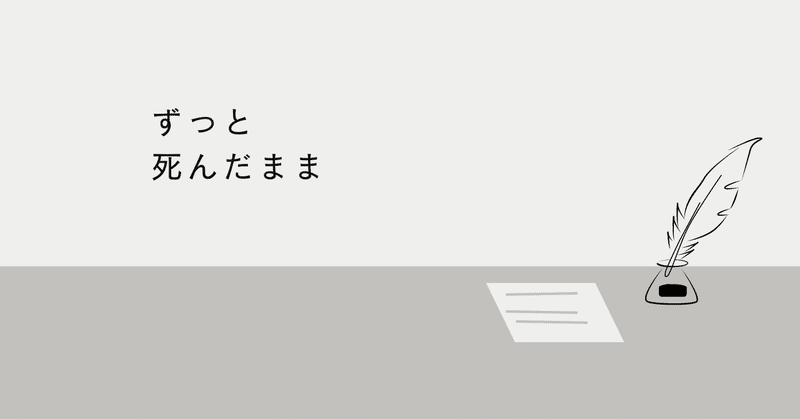
【短編小説】ずっと死んだまま
――X高校第七十三期生同窓会会場。
「遅くなりました」
あきれるぐらいに広いホテルの大宴会場、そのまた奥の扉から、もったいぶる様子もなくやってきたのがTである。N子は煙草に火をつけたくなる衝動を抑えながら、音のしない拍手をしてT先生とやらを迎えた。
一九九〇年、「墓標の足跡」で鮮烈なデビューをし、その後は主要な文学賞を総ナメ。T氏が受賞できないのは「なでしこ女流文学大賞」ぐらいだろう、というお笑い芸人のジョークは話題になった。N子はその作家と同級生のTをイコールで結んだことはなかった。高校時代のTは文学より音楽に傾倒しており、文化祭で自作の歌を歌いながらギターを演奏していたクチだ。将来は歌手になると意気込んでいて、さまざまな音楽を聴いていた。そんな奴が作家とは、人生何が起こるか分からないものである。
「よっ、大先生!」
クラスのお調子者が声を張り上げると、Tは肩をすくめてひょこりと頭を下げた。それがうだつの上がらないサラリーマンのようで、会場からは笑いが起きた。
「もっと堂々としていればいいのに」
N子の隣にいたK子がくすくすと笑う。N子は冷めたチキンステーキを口に放り込んだ。何人かの図々しい連中がTにサインを求めたが、色紙を持ってきた奴にはサインをせず、書籍を持ってきた奴にはサインをしていた。その格差もN子をイラつかせた。書籍にはしっかり「XXさんへ」という宛名まで書かれている。「転売対策かぁ」としみじみ納得する声がした。
Tの作品の大ファンらしい連中が作品の感想をあれこれ言う。読んだことのない連中が「どんな話?」と掘り下げる。
「教育実習にやってきた主人公のクラスでね、自殺者が出るの。それでね――」
つい先ほどまで、結婚がどうだの、彼氏からプロポーズされただの、そういった「らしい」話に満ちていた会場は、Tの登場によって色を変えた。Nにはそれが気に入らない。せっかく彼氏がくれた、ダイヤの指輪を自慢できるタイミングだったというのに……。
しかし、Tの著書は有限だ。話題についていけなくなった何人かがコミュニティから脱出し、ほどよく話題のグループができる。Nは左手の薬指をそれとなくアピールしながら、食いつく魚を待ち続けた。
「そういえばさぁ、Tはどうして作家になったんだ? お前、歌手になりたがってたじゃん」
何杯目かのビールですっかりできあがってるお調子者がそんなことを訪ねた。Tはさらりと疑問に答えた。
「高三の文化祭でN子に『ヘタクソ!』ってヤジを飛ばされてから、人前で歌えなくなったんだよ」
なぜ、こういった声はどんなに広い空間でも万人に届く力をもっているのだろう。今まさにワインを口にしようとしていたN子に皆の視線が突き刺さる。N子は一瞬ひるんだが、気にせずワインを飲んだ。
Tのパフォーマンスは実際にヘタクソだった。歌はまだマシだったが、ギターは聞くに堪えられないレベルの腕前だった。高校の文化祭というのはちょっと珍しい項目のパフォーマンスであれば、技量がクソでも多少のバイアスがかかる。ギターはその代表例といえるだろう。実際、文化祭で盛り上がっていたのはアドレナリンがアホみたいに分泌されて頭がおかしくなった人間と、Tの友人だけだった。他の人々はとりあえず動いていれば楽しいからという理由で曲を聞いていた。とにかくヘタクソだった。文化祭オリジナルテーマ曲もつまらない歌だった。いろいろとこじらせた年頃の人間が、耳に心地よく響く言葉をそれっぽく並べて作った自己満足の歌だ。それを毎度毎度昼の放送で流されたら気が狂うのも必然と言える。
だからN子は友人と結託して、ラスサビ手前の空白で叫んだのだ。
「ヘタクソ!」と。
スピーカーから音がしない、静寂の中でN子とその友人の声はよく響いた。Tは目を見開いて、N子の方を見た。
「え、こっち見たんだけど」
「ヤバくね?」
Tはしどろもどろになりながらもラスラビを歌い始めた。動揺は歌声と音程に現れ、ギターの運指にもミスが散見された。
N子は友人と笑い転げて、「もっとヘタクソになってんじゃん!」と盛り上がった。しばらくカラオケでTの真似をするのが流行ったが、高校を卒業する頃にはTをおもちゃにするブームは去っていた。
……アルコールで真っ赤になったお調子者の顔が、見る見るうちに真顔になる。酔いが冷めたらしく、近くにいた人(元学級委員長だ)に水を持ってくるよう頼んでいた。
「歌えなくなったって、マジで?」
「うん。『ヘタクソ』って叫ばれるのが怖くてステージに立てなくなって、歌もギターも諦めたんだ」
「…………」
会場にいる全員の視線がN子に集まっている。N子はさすがにヤバいと思った。だが、謝るのは癪に障る。自分は別に悪くない。事実を言ったまでだ。ヘタクソな演奏をヘタクソと言って何が悪い。それで傷ついてめそめそするのはTの精神が弱いのが悪い。アルコールで程よく温まった体が冷めていく。と、N子は一つの真実に行き着いた。目の前が明るくなり、気分が高揚する。これはアルコールのせいではない。もっと悪いものの影響だ。
「じゃ、じゃあ……あたしがTの演奏を『ヘタクソ』って言ったから、Tは作家の道に進めたんだね!」
胸の前で手を合わせて、オシャレで可憐な女性を演出するのを忘れたりはしない。N子はキラキラエフェクトの雰囲気を醸し出しながら、冷え切った会場で声を張った。
「Tが作家になったのは、私のおかげ……ってこと?」
カランカラン、と甲高い金属の音がした。K子がフォークを落としていた。会場に着くや否や、N子の指に輝くダイヤの指輪を目ざとく見つけ「すごーい、どうしたのこれぇ」と媚びた彼女は今、美容クリームのテスターを塗りたくってやりたくなるような顔をしていた。
「なんか、すさまじい勘違いをしているみたいだけど」
Tが口を開いた。
「君がしたことは、俺から音楽を奪ったことだけだよ」
何人かが、うんうん、と頷いた。N子は少し焦った。
「いやいや、だって私は現実を教えただけだよ? あのまま歌手デビューしてたって、どうにもならなかったじゃん。実際ヘタクソだったんだし。もっと向いている作家の方に活路を見いだせたなら結果オーライってやつでしょ。ほら、そうでしょ? 私はTがプロの道に進んで挫折を味わうことがないようにしてあげたんだ!」
N子の言葉は続かなかった。
「そうだね」
Tは呆れたように答えた。
「僕は今でも、どうして自分はピックじゃなくてペンを握っているのか分からなくて、苦しくなるけどね」
……もしも、この部屋に迷い込む者がいたら、きっと通夜会場と勘違いすることだろう。非難のまなざしを向ける連中をN子は片っ端からにらみつけた。彼らはさっと視線を逸らし、空だったり食べかけが乗っていたりする皿へ視線を逸らした。その様がより一層葬式の雰囲気を醸し出すので、同窓会会場はいよいよ手が付けられなくなった。いよいよ憎悪が明瞭な息苦しさとして露わになったとき、強烈な衝撃音が全員の意識を覚醒させた。参加者の一人が酸欠によってぶっ倒れたのだ。
彼女の倒れる音が静寂に響く様は、N子が飛ばしたヤジのそれに似ていた。だとすれば、近いうちに誰かが同じようにして倒れるだろう。確実な暴力として存在する刺激の残響は、いつだって長らく沈殿すると決まっている……。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
