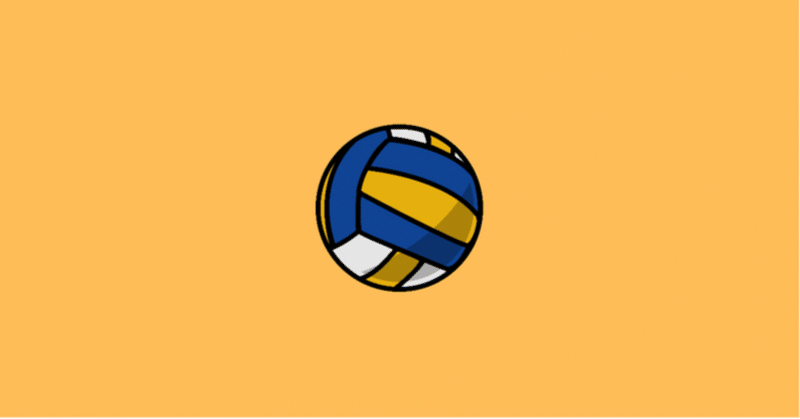
【短編小説】公開処刑
先週、僕らは負けた。体育の授業のバレーの試合だった。権田は今日の試合がどれだけ最悪だったかを大袈裟に話し、僕は腕の痛みに少し泣いた。
試合はバレー部エース、高田のサーブから始まった。強烈な勢いですっ飛んでくる球を拾って……なんてことはできず、僕はただ立ち尽くすだけだった。隣に居た権田から「拾えよ」と説教がすっ飛んでくる。僕は眼鏡をかけ直して、ボールをどむどむと床に弾ませながらサーブの出力を測っている高田を見据えた。
二度目のサーブは随分と緩かった。僕はすぐに、高田が手を抜いてくれたのだと察した。腕でボールを捕らえてから、僕は他のメンバーがわちゃわちゃとボールをやりとりするのを見た。よたよたとした軌道を描いたボールはネットに危うく引っかかりそうになりながらも、相手のコートへと落ちていく。が、それも結局拾われて、とーんとこちらへ帰ってくる。コートの線ギリギリのところで、僕は慌てて腕を出した。高田が「あっ」という顔をしたのが何故かこのときよく見えた。
権田の「拾うな!」という指示より先に僕の腕にボールが刺さった。チームメイトは「あーあ」という顔をしている。ボールはトンチンカンな方向へと飛んでいき、相手のチームへ点が入る。僕は申し訳なさにへらっと笑って「ごめん、次は――」上手く取るから、とは続かなかった。
「お前さぁ、ヤル気ある?」
権田が僕を睨みながらそう言ってきた。僕は何が悪いのかよく分からなかった。ただ、チームが負けているのが僕のせいだと彼は言いたいらしい。僕はすっかり萎縮してしまって、取れるボールも取れなくなった。無駄に差し出される腕にも容赦なくボールは食い込むので、僕の腕は無数の青あざでいっぱいになった。
それは今週になっても取れることはなくて、僕はただひたすらにこの時間を憂鬱に過ごしていた。コートに足を踏み入れるとき、僕の目の前には何か恐ろしい装置が見えて、その近くに陣取るチームメイトはみんな僕の敵になるような、そんな馬鹿げた幻覚を視た。ただ、そのおかげでチームメイトは誰一人として僕にボールを回すことはなくなったし、僕がボールを落としても何も言わなくなった。サーブはどうせ届かないし、トスしようとするとボールをキャッチしてしまう。僕はいないものとして扱われ、おかげさまで腕の具合は大分良くなった。権田はそんな僕のことを気にくわなかったらしいが、彼も高田の本気サーブを顔面に食らってからは何も言わなくなった。
二十年後の同窓会で、ふとその話題になった。権田はバイト(就活に失敗したという話はそれとなく聞いていた)で不在だったが、高田は無理矢理都合をつけてやってきていた。僕の耳元で高田は「あれ、わざとやったんだ」と笑った。僕はそこまでしなくてもと言ったが、バレー好きの高田にとってはそこまでする案件だったそうだ。
高田は今、小学校の教諭として働いていて、バレー部の顧問をしているそうだ。彼のいる学校なら体育の授業で僕みたいな生徒が出ることはないだろうし、バレーコートが断頭台に変化することもないだろう。僕は高田にありがとう、と告げて、少し大きな唐揚げを取り分けてやった。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
