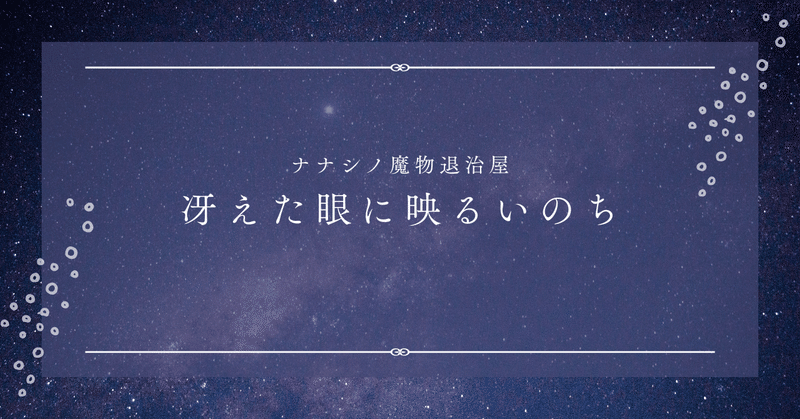
【短編小説】冴えた眼に映るいのち
地区には捨て子が多い。我が子がアンヒューム――生まれつき魔力を持たない人間だと分かった瞬間に、子を捨てる決断をする親は世間が思っている以上に多いのだ。
今日もごみ溜めの中ですやすやと眠る赤ん坊がいた。月の光に照らされた子の顔はふっくらとした丸みがあり、明日の幸せを信じて目を閉じている。こういった子供を見かけたとき、地区の住民が取る行動はいくつかある。孤児院に連絡をしてみる者。子供を引き取る決意をする者。しかし、残念ながらそういった親切な人に巡り合える可能性は、著しく低い。
コバルトは静かに銃を構える。赤ん坊の胸元に狙いを定めて静かに引き金を引く。もしも運命がもう少し狂わずに済んだのならば、彼(おくるみが青色だったので、男だと推定した)が幸せに生きる未来があったかもしれない。だがコバルトは子を育てる技術も環境も持ち合わせておらず、無理に引き取ったところで不幸が長引くだけだ。ごみ溜めで泣きわめく赤ん坊を目の前にして、地区住人が「どうする?」となすりあいのバカげた会議をするくらいなら、こういったことに躊躇しない奴が汚名を被る方がはるかに効率的だ。
いつだったかどこかの同業者に本気で怒られたことがある。彼は善性の強い人間だった。どうして無垢な子供を平然と殺せるのかと真顔の説教を食らった。あのとき、自分は呪いを食らっていただろうか。あまり記憶にない。コバルトはそのとき、どうしてこいつがここに居られるのか分からなかった。ついでに、どうして自分が怒られるのか分からなかった。だからコバルトはその赤ん坊が持っていたカードを差し出して、同業者にこう言い放ったのだ。
「この筆跡から親を調べればいい。そしてお前さんの好きな説教をしてやればいい。『あなたが捨てた子供は、銃弾を食らって死にましたよ』って」
同業者の唖然とした顔を見てもコバルトは何も思わなかった。かの有名な暗殺者「蒼鷹」が地区を平定したばかりの頃、ここは孤児が多かった。店先からパンを盗む程度の犯罪を重ね、成長した子供たちは強盗団を結成した。すばしっこい動きで店を蹂躙し、加減の知らない手は従業員を皆殺しにした。大人よりも酷い暴れっぷりを知っているからこそ、コバルトは赤子殺しを躊躇わない。引き金を引くのを諦めた瞬間、地区の秩序は崩壊する。
「彼らが子を捨てたからといって、君が子を殺していい理由にはならない」
「へぇ。だったらもう少し頑張ってごみ溜めを探せばいい。俺よりも早く子供を見つければ、助かる命もあるだろうよ」
「見つけても殺さなければいいだけの話だろう」
コバルトは嘲笑を隠すことなく吐き捨てた。その声には本能的に人を不快にさせる類の響きがこっそりと紛れていて、我ながら性根が腐っているな、と感心したものだ。ああ、その段階で思い出した。これは呪いを受けた後の話であると。
「俺に赤ん坊を殺すなというのなら、俺の前に棄てられた赤ん坊が出てこない環境づくりをしてくれ」
「無視するという選択肢はないのか」
「むしろ内臓を売りに出さないだけ良心的だと思ってくれよ!」
コバルトはゲラゲラ笑った。
「全部まとめて墓地に埋められるんだ、優しいもんだろう。それともなんだ? 使える部分は極力使った方がいいか?」
顔を真っ赤にした同業者が殴りかかってきたので、コバルトは甘んじてそれを受け入れた。
「そんなんだからバケモノに変えられちまうんだよ!」
ああ、やっぱりそうだ。呪いを受けた後の話だ。追憶に浸るコバルトは記憶の外でそんなことを思った。
「口の利き方には気をつけな、小僧」
このとき、コバルトは同業者に銃口を向けた。相手が明るい場所にいたおかげで狙いを定めるのは容易だったはずだ。
「上っ面の噂話しか知らないバカほど、全てを知ったかのようにして振る舞うのは嫌な傾向だね。そう思うだろう?」
同業者は憐れみを込めた微笑を携えて、ゆっくりと頷いた。影が大げさな動きを見せた。
「怒りに身を任せて武器をふるうのは三流だよ」
余裕のある同業者に、コバルトは嗤った。
「そうだな。確かにお前さんの言う通りだ。異論もない。まったくもってその通りだ。だが……お前さん、三日前にドゥーム派にいらんことを喋ったよな?」
同業者の顔が凍り付く。コバルトは再度嗤った。彼の足がゆっくりと地面をさすった。コバルトから離れようとしている。賢い奴だ、とコバルトは思った。言い訳を並べ立てたりしらばっくれたりとカードは様々揃っているが、すぐに自分の非を認められるというのは優秀な証拠である。
「まぁ焦るな。せっかくのおしゃべりタイムなんだ、ゆっくりしようぜ」
コバルトは喉をぐうぐう鳴らした。そして瞳孔を揺らす彼の眼をじっくりと観察した。可哀想に、と思う。捨て子を殺す時にはない現象だ。赤子はコバルトを見ても怯えない。眠気にぐずって泣くことはあれど、コバルトの相貌を理由に泣くことはない。何かの間違いで目を覚ました赤ん坊は、たいていの場合笑い声をあげる。コバルトはこの瞬間が嫌いだった。性根が腐っていても最低限人の心はある。きっと師匠も同じような理由でコバルトを育てる決意をしたのだろう、といらぬ推測までしてしまう。
「いいことを教えてやるよ、×××」
彼の名前を、コバルトは覚えていない。覚えておく必要もない。彼が漏らした情報のせいで、ドゥーム派は違法薬物を先に主要倉庫から運び出してしまったのだから。コバルトと同盟関係にある情報屋や暗殺者が倉庫に飛び込んだとき、そこはもぬけの殻だった。調査の結果、彼が余計なことを漏らしたのだと分かった。酒場の美人店員に「今度、郊外の倉庫を調べるんだ」とかっこつけたのが偶然そこにいたドゥーム派の連中の耳に入ったのだ。
「言っていいことと悪いことの区別もつかないようなやつのことを、世間じゃ子供って言うんだよ」
銃が吠える。
コバルトはこの日、一人のおおきな子供の命を摘み取った。
――赤ん坊の死骸を拾い上げたコバルトは、重い足取りで墓地へと向かった。今日は酷く目が冴えている。嫌な思い出を鮮明に再生してしまったからだろう。
別に悲劇のヒーローを気取るつもりはない。「かわいそう」という言葉は強者が自分の優越感を誇示するために使う言葉でしかない。
業を全て背負う覚悟無しで、銃なんか握るわけがない。
ああ、睡眠薬がほしい。
飲んだ瞬間に意識を飛ばして、何も考えられなくなるようなやつがいい。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
