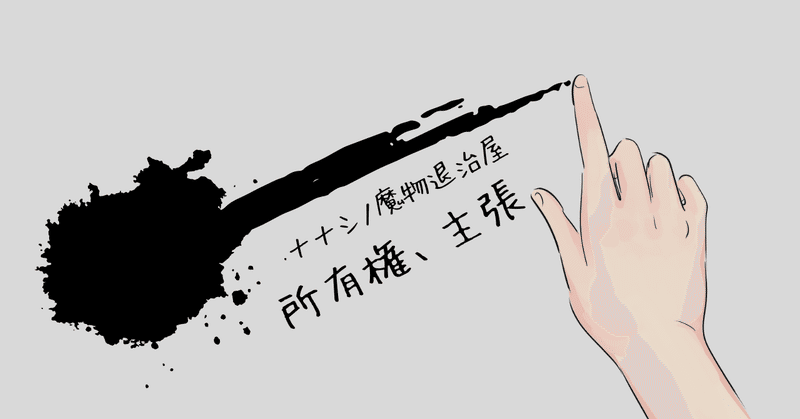
【短編小説】所有権、主張
人だかりができているだけならラスターはきっと素通りを決めていたことだろう。しかしその中心にノアが居るのを見てしまった以上、ラスターにその選択肢は無かった。
学術都市クーウィムに来てそれぞれ単独行動。五分。たったの五分。目を離した隙にコレ。コバルトへの土産話にはよいかもしれないが、当の本人にとっては状況が最悪の極みである。
目を潤ませた女たちが声を上ずらせてノアにすり寄っている。
「んゎらしー、まじゅつのさぁーのーがぁー、……」
そんな甘い声を上げて媚びる女を、蹴散らせばいいのにノアはそうしない。そうできない。そもそも選択肢にない。動けない。あくまで穏やかに終わらせようとする。
一人がノアの腕を掴んで、胸の谷間に挟んだ。大抵の男ならラスター含めて鼻の下を伸ばすに違いないが、三人の妹がいて多少の耐性があるノアにはこれっぽっちも効いていない。
頭の固い魔術師家系はより強い魔力の子孫を残すために、魔術の才を持つ者とくっつきたがる。もっとも、そこには「出来損ないの魔力なし」が産まれないようにという願掛けもある。
……まぁ、残念ながら親の魔術の才や魔力量がどれだけ素晴らしくても、魔力なしは出てくる場合があるが。
かの大賢者、カルロス・ヴィダルの息子となれば引く手数多で大変だろう。実際そうなっている。魅了の魔術を片っ端から無効化しているノアが面白いが、あのままでは魔力を使い果たして倒れてしまう。
首をくるっと回して、ラスターはするりと人混みに入り込んだ。やたらに香水の匂いがする。肘で思いっきり誰かの腹をついてしまったらしく、甲高い悲鳴が聞こえた。
「あの、ですから、……参ったな」
あー、思わせぶりな台詞。恋愛小説の鈍感イケメンによくあるパターンのやつ。虚構と違って、ノアは自分がモテる理由を知っているが。
人混みをさくっと抜けて、ラスターは即座にノアの手を取る。何かついでに貴婦人方の腕もついてきたが。
「あー、いたいた。めちゃくちゃ探したよ」
ノアと目が合った。少し目を見開いたかと思えば、すぐに可哀想な仔犬の顔になった。
蠅を追い払うようにして女性たちをノアから遠ざける。腕を絡めて身体を密着させ、女どもを威嚇する。
「勝手に俺から離れるなって言っただろ?」
こういうとき、身長差が凄まじくむなしい。ノアより背があれば映えるシーンも、現実はノアがラスターのつむじを見つめる話になる。しかし当の女性たちは目を白黒させて、妙ちくりんな勘違いに思考をシフトさせているようだ。
人混みに足を突き刺し、ノアが通れるようにする。食い気味についてくる歩調がおかしかった。
「この後二人で濃密な時間を過ごすって話だったのに色目使うなんてラスターちゃん泣いちゃうー」
「ごめん、まさか囲まれるとは思ってなくて……」
本当に申し訳なさそうにするノアが面白い。しかし「濃密な時間」にツッコミを入れてくれないのはいささか困る。腰に手を回してもノーコメントだ。とはいえ、流石にあまりにも露骨なのですぐに手の位置は戻したが。
「前にもこんなことが?」
「あったよ」
即答だった。
「へぇ。それじゃあきちんと名前を書いておかないとな」
「名前?」
「学校で習わなかったのか? 持ち物には名前を書きましょう、って」
意味深な笑みを浮かべても、ノアには全く通じていないらしい。まぁ、だからこそ通用する手だ。ここで「いや、俺は君とそういう関係じゃないよ」とか口走らないから安心して選べる切り札だ。
「で、これからどうする?」
「なんだか疲れちゃったな」
「デカい本屋に行きたがってたのに」
「次はもっと人の少ない時間帯を狙うよ」
はは、と自分の想像以上に高い声で笑ってしまったラスターが咄嗟に首を思いっきり右にかしげたその時、頭のあった位置に生卵がすっ飛んできた。思わず振り向いたノアとラスターが見たものは、嫉妬のあまり二個目の生卵を投げようとする女の姿だった。
「気分転換に運動でもどう?」
早口でラスターが問いかけた。
「……いいね」
ノアが答えると同時に、二人は学術都市のメインストリートを勢いよく駆けだした。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
