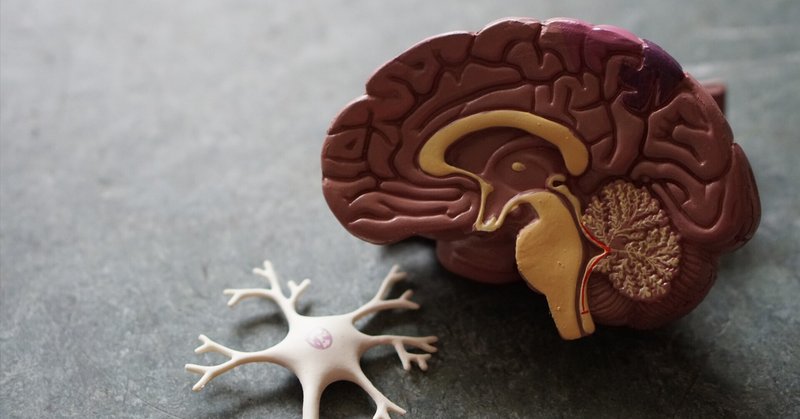
毛内 拡 「脳を司る「脳」 最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき」 読書メモ
脳のはたらきから、生きているとはどういうことかまで考察した本書、最新の脳科学の研究成果を平易な言葉で解説している。
知性とは、脳ならではの能力なのです
そうだよね、と思うこのフレーズはかなり深い意味を持つ。人工知能は知能であって知性ではない。脳こそが知性をもつ。
そして生物が生きているとは、どういうことか。
かつて動物の「死」は、呼吸や心臓が止まってしまうことと定義されてきました。現在も、死をそのように捉えている方も多いかもしれません。ところが、医学の技術が発展することによって、電気ショックや薬剤を用いて、一度停止してしまった呼吸や心臓のはたらきを蘇生することが可能となりました。これにより、動物の不可逆的な「死=心臓の停止」という常識は、徐々に変化してきています。従来の概念に代わって、人間にとっての本当の意味での死は、脳の死ではないかという議論が起こり、現在でも賛否両論があります。言い換えれば、「生きている」とは、「脳が生きている」ことと捉えられるようになってきているのです。
脳が生きているということを問うこと。
死んだ豚の脳の電気的な実験、試験管の中で培養された脳、人工的に作られたコンピューターの脳、これらの脳は生きていると言えるのか。
脳の働きはニューロンの働きとして研究されてきたが、それだけではこころの働きを説明できない。
電気信号を化学物質に変換するのは、一見すると効率が悪いように思えますが、このしくみによって、情報の「質」を変えることができるというのがポイントです。脳の中で情報を伝える化学物質にはさまざまな種類があるため、記憶や学習、喜怒哀楽などの複雑な脳のはたらきを可能にしているのです。
脳はブラックボックスだという。その動きを知るためには外観を観察しているだけでは分からない。心臓なら、鼓動によって正常かどうかを判断できる。ブラックボックスの試験(確認)というのは、とても骨が折れる。キャリア開始の頃、プログラマとして仕事をしていたが、ブラックボックステストの確認を任されていた。仕様書がまだ出来上がっていないけれど、モノは出来上がったとしてデバイスや、ライブラリだけ渡された。ソースコードも提供してくれればいいけれど、それは大抵の場合機密事項になる。パラメータを少しずつ変えて、どのような性能なのか試験した。これをブラックボックステストと呼ぶ。
脳の構造の複雑さ。脳に限らず、絶妙なバランスの事象は多い。
私たちが普段「正常」だと思っているものが、いかに脆くて、いかに絶妙なバランスの上に成り立っているのかを思い知らされる
第二章は科学者による脳の観測について、歴史とともに解説されている。ブラックボックス的に脳の機能を推定する方法、脳は電気信号を発していることから、その電気を観測する方法、そして顕微鏡の進歩によって、直接細胞を観察する方法、顕微鏡の技術によって、直接脳が機能している様子を観察することができるようになった。
よく分かっていない脳だが、研究者は今日の研究が100年後(あるいはその先)の脳の理解の助けになると信じて研究をしている。今は仮説だとしても、観測技術の進展により、実際に確かめられることもある。
観測技術が向上すると、手に入る情報も膨大になる。もはや人の手では分析が困難になる状況であり、ここでビッグデータの技術が助けになる。
研究者は、生物学だけでなくより幅広い知識をカバーする必要に迫られています。
厄介な時代と考えるか、変化のさなかの刺激的な時代と捉えるか。
次の文は科学についてのテキストだけど、キュレーションにも当てはまる。
これだけ科学が発達してもまだまだわからないことは多く、新しい発見やブレイクスルー、パラダイムシフトが求められています。研究者であれば誰しもが、前人未到の新発見や大発明を夢見るものです。「新しい発見」とは、これまで誰も見つけていなかった現象を見つけるだけではありません。もうすでに見つかっているのに、単に見逃している、あるいは重要性が認識されていないものにきちんとスポットを当て、再発見する、新たな価値を見出す、ということも科学の進歩には欠かせません。
詩人がいとも簡単に真理に到達する、とフロイトが言っていたらしい。詩人にも苦悩はあると思うが、これには同意する。
生物の体の環境を一定に保つしくみのことを恒常性といいますが、ヒトも含めて生物にとって体内環境は、「変わらないこと」が重要です。 約800年前、常に流れ続ける河の流れを見て鴨長明は「無常観」を発想しましたが、現代の生物学が、脳脊髄液が常に流れて入れ替わることが脳の「恒常性」に重要であると発見したのは、逆説的でじつにおもしろいではありませんか
本書の終わりの方にある小見出しのテキスト”変わり続けることが「生きている」ということ”、生体環境を一定に保つためには変わり続けなければならない。これを捉えてビジネスの世界では成長することと言ったりするが、変化と成長は違うと思う。とはいえ、思考停止や思考拒否は気をつけなければならない。
キメラマウスの説明があった。ヒトの脳細胞をマウスに移植すると、記憶能力が飛躍的に向上したらしい。絵空事だった物語が現実になるのかもしれない。
生きているとはどういうことか?
脳の機能の研究が進むと、脳の機能がどのように構成されているかが分かってくる。脳のこの機能が停止した時に死と捉えるのか。
今まで注目されていたニューロンとシナプスの働き、それ以外の脳の機能がある。これがこころを生み出す仕組みであるのではないかという。(まだまだ分かっていないことの方が多い)
ニューロンのネットワークレベルの知見と、行動学や心理学で得られている知見とがあまりにも乖離していて、その間にある隔たりを完全には埋められないままでいます
脳という実態というよりも、脳を構成する器官の様々な関係性により成り立っているのではないか。
脳も、ニューロンのような個々の要素だけでは存在することができず、それぞれが相互に関係していることで存在することができ、ある時ある瞬間の関係性そのものが脳のはたらきなのではないでしょうか。
筆者が解説する動画、3分以内で本書で解説していることのエッセンスを紹介してくれている。
いただきましたサポートは美術館訪問や、研究のための書籍購入にあてます。
