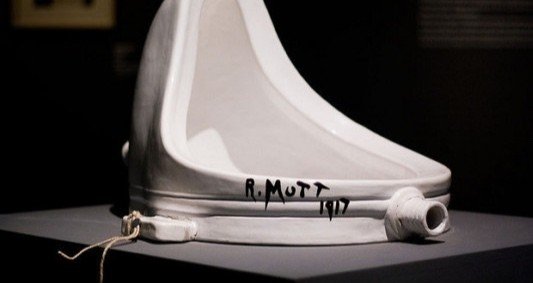#リオタール

Les Immatériaux or How to Construct the History of Exhibitions 考察メモ
非物質化または展覧会の歴史の構築の仕方。TATE PAPERSとして公開されているテキストを読んでみたメモ。JOHN RAJCHMAN の2009年に書かれたテキスト。 1985年の『Les Immatériaux(非物質的なものたち)』展は、哲学から現代アートへ接続する展覧会だった。それは、アートの境界を解放し、何にでも接続できるように捉えなおした、ある種の実験的な取り組みだったのだろうと推測する。その後の展覧会においても、考え方の拡張を提示することとなった。これほど重大