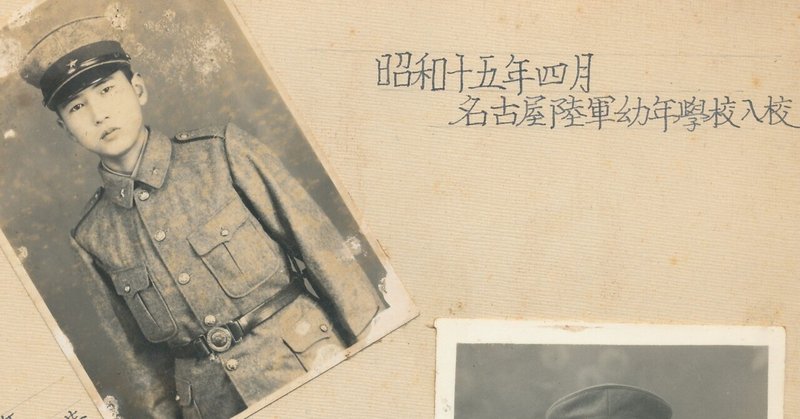- 運営しているクリエイター
#思い出

「For somebody, "YES", and for somebody, "NO"! They are stupid!」日本人中学生の素朴な?セクハラ?質問にアメリカ人女子高生はあきれ果てていたけれど (エッセイ)
昨日の続きです。 日本に来ても家の中に引き籠っているばかりのアメリカ人女子高生は、交換留学組織の提案で、日本の学校に《体験入学》することになりました。 長女の通う中学に話を通すと、「英語の勉強にもなる」と興味を示し、1週間(だったと思う)一緒に通学することになりました。 そんなある日、私が勤務先から戻ると、珍しく彼女がリビングにいます。どうやら、今日、学校で起こったことを妻に話しているようでした。 基本的には、その学校の生徒たちがいかに 《stupid》 であるかをまく

「Boys are all stupid!(男子はみーんなバカ!)」アメリカから来た女子高生は冷ややかに言った (エッセイ)
Snoopyと称するビーグル犬や、頭髪が手抜きで描かれたCharlie Brownという男の子が登場する4コマ漫画の傑作、「Peanuts」はよくご存じでしょう。 あるいは、TVアニメの方が知られているかもしれません。 このマンガにかなりの頻度で登場する単語に、 《stupid》 という形容詞があります。 バカ、間抜け、愚か ── そんな意味です。 Charlie Brownもよく使いますが、特に、わがままで口うるさい女の子Lucyが、SnoopyやCharlie Bro

「密輸はやめよう」カシュガルの大通りにはためく横断幕に書かれたスローガンを、「中国ータリバン」関連ニュースで想い出す (エッセイ)
昨日のニュース(↓)で、遠い記憶がよみがえりました。 中国は新疆ウイグル自治区を介してアフガニスタンと国境を接している。 35年前、「カキモノ」がらみで臨時収入があり、GWと勤め先の有給休暇をからめて旅に出ることにした。 それまでの旅で一番印象に残っていたのは、ソ連領中央アジア・キルギス共和国側から登った(といってもハイキング程度)天山山脈北山麓の、どこまでも続く《天然お花畑》の美しさだった。 それ以来、 (いつか、天山山脈の南側に行ってみたい) そう思っていた。 当時