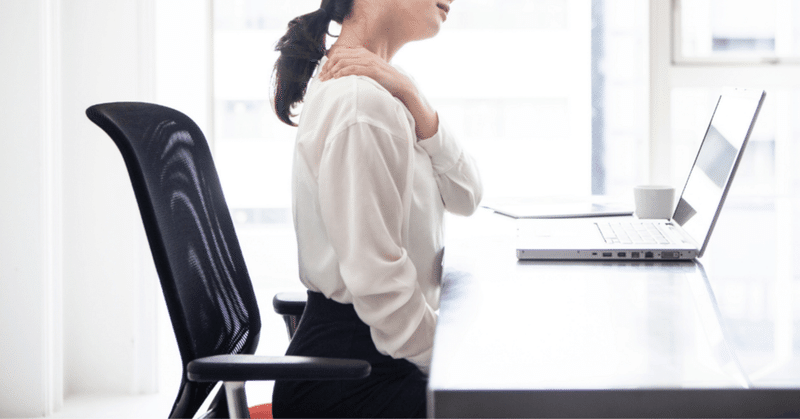
「疲労」と「肩こり」悪循環を断つ方法を解説
「疲れてくると肩こりがひどくなる」
「肩こりがつらくて、疲労感が増す」
わかる!と共感している方もきっと多いですよね?
疲労と肩こりには密接な関係があります。
疲労回復と肩こり解消のためにしっかりとしたケアが必要です。
今回の記事では、以下について紹介します。
肩こりはどんな状態か
疲労と肩こりの関係
疲労回復と肩こり解消の方法
つらい肩こりや疲労でお悩みの方はぜひ一緒に改善しましょう!
肩こりとは「筋肉のこわばり」

肩は、重たい頭を支えている首や、2本の腕につながる関節です。
肩周辺には僧帽筋という首から背中に広がっている大きな筋肉をはじめ、たくさんの筋肉が集まっています。
首や背中が緊張するような姿勢
猫背のような姿勢
長時間の同じ姿勢
上記のような姿勢では、肩周辺の筋肉が緊張し血流が悪くなり重く感じるようになります。
この肩周辺の筋肉がこわばった状態が、肩こりです。
肩こりの症状
肩こりの症状は、肩周辺の筋肉の張りや痛み、重苦しさです。
さらにひどくなると、頭痛や吐き気なども。
肩こりは、別の病気である可能性もあるので、注意が必要です。[1]
頸椎の疾患
肩関節自体の異常
心臓や肺の病気
高血圧
顎関節症 など
上記の疾患が原因である場合には、早めに専門医を受診し治療するようにしましょう。
肩こりで悩んでいる人はたくさんいる
どれぐらいの人が、肩こりで悩んでいるかご存じですか?
厚生労働省が2019年に行った「国民生活基礎調査」によると、女性が感じる自覚症状の第1位、男性の第2位が肩こりいう結果でした。
たくさんの方が、肩こりを訴えているのがわかりますね。
疲労と肩こりの深い関係

ほとんどの肩こりは、病気が原因ではありません。[2]
原因が病気ではないケースを、医学的に「本態性肩こり」と呼んでいます。
本態性肩こりは疲労と密接な関係があり、悪循環を引き起こしているのです。
疲労による肩こり
肩こりの原因として以下が挙げられます。[3]
筋肉の疲れ
目の疲れ
精神的な疲れ、ストレス
姿勢の悪化
寒さ、冷え
これらは共通して、血流が悪くなり筋肉がこわばってしまい、肩こりの原因となります。
疲労が溜まると、姿勢を維持できず、肩が下がり猫背のようになることも。
この姿勢が、さらに肩こりを悪化させてしまいます。
肩こりによる疲労
肩こりで、筋肉がこわばり固くなると、血液の流れが悪くなります。
すると、痛みの原因となる疲労物質が溜まってしまうことに。
また肩こりがひどくなると、
注意力が持続しない
思考力が低下する
イライラする
上記の状態も重なることもあり、さらに疲労がたまっていきます。
疲労と肩こりを解消せずに放っておくと、悪循環に陥ってしまう結果に。
疲労と肩こりの悪循環を断ち切る方法を紹介

疲労と肩こりの悪循環を断つには、どのような方法があるのでしょうか?
ここでは5つの方法を紹介します。
自分に合った方法を見つけてみましょう。
悪循環を断つには、1つだけでなく複数を組み合わせるのもおすすめです。
①ストレッチ・マッサージ
ストレッチやマッサージは、同じ姿勢を続けることでこわばった筋肉をほぐす働きがあります。
特に肩甲骨まわりの大きな筋肉である僧帽筋をほぐすことがポイント。
筋肉をほぐし、血流を改善することで悪循環を断つことが期待できます。
ストレッチについて、詳しく解説している記事はこちらです。
②入浴
入浴は、肩周囲を温めることで、筋肉のこわばりをほぐし血流を改善します。
入浴は、ぬるめのお湯にゆったりと首までつかって温まるのがポイントです。
お湯につかりながらのストレッチは、相乗効果もありますのでぜひ取り入れてみましょう。[4]
こちらの記事で、疲労回復と入浴の関係ついて詳しく解説しています。
今夜からはじめよう!疲労回復に効果的な3つの入浴方法のコツ
入浴時以外でも肩周囲を温めたい場合には、40℃前後が6時間持続する温熱用具などもおすすめですよ。
③貼り薬
貼り薬は、肩こりによる筋肉の痛みや炎症を改善するために使います。
貼り薬の分類や特徴をまとめました。

上記の貼り薬は、医師からの処方だけでなく、ドラッグストアや薬局で購入できます。
自分の肩こりの状態に合った貼り薬を使うのが重要です。
どれを選んでよいのかわからない場合は、薬剤師や登録販売者に相談してみましょう。
④塗り薬
貼り薬でかぶれたり、皮膚が弱い方は塗り薬をおすすめします。
冷やす効果はありませんが、痛みや炎症をとる成分を配合しているものが多いです。
最近では医療用成分のロキソプロフェンやジクロフェナク、フェルビナクなどが配合された塗り薬もドラッグストアや薬局で購入できます。
ただし塗り薬は1日3~4回塗り直す必要があるので、基本的に朝、日中、入浴後に使用します。
⑤飲み薬
飲み薬(内服薬)は肩こりだけでなく、いろいろな効果が期待できます。
今回紹介するのは、4種類の飲み薬です。
ビタミン剤
肩こり対策でしっかり摂りたいのは、ビタミンB1、B12、ビタミンEです。

市販のビタミン剤は、ビタミンB1、B12、Eを全て配合したものも販売されています。
肩こりだけでなく、全身の肉体疲労や腰痛にも効果があるのは嬉しいですよね。
疲労とビタミンの関係をもっと知りたい!と思ったら、こちらの記事がオススメです。
疲労回復に必要なビタミンの働きを薬剤師が解説
筋肉をほぐす薬
脳から筋肉へ緊張するよう伝達されるのですが、この伝達を抑えることで筋肉の緊張をやわらげます。
エペリゾンやチザニジンなどが、肩こりで主に処方される成分です。
市販でも筋肉弛緩成分を配合した「コリホグス」や「ドキシン」が発売されています。
ただし、筋肉をほぐす薬は眠くなることがあるので注意してください。
筋肉をほぐす薬は、ビタミン剤との併用も可能です。
肩こりがつらい方は服用することを検討してみましょう。
不安をやわらげる薬
不安をやわらげて精神的な疲れやストレスを楽にしたり、筋肉の緊張をやわらげたりする効果があります。
エチゾラムやクロチアゼパムなどが、肩こりで主に処方される成分です。
不安をやわらげる薬も、眠くなることがあるので注意しましょう。
このタイプの薬は、医師からの処方のみとなります。
精神的な疲れがある場合は、医師に相談してみましょう。
痛み止めの薬
肩こりの痛みがひどい場合には、痛み止めの薬を使うことがあります。

上記のように、市販のロキソニン添付文書にも、「肩こり痛」の効能・効果が記載されていますよね。

記載されているように、痛いときだけピンポイントで飲む薬です。
ビタミン剤などの薬と違い、続けて飲む薬ではありません。
服用回数や服用間隔をしっかり守って飲みましょう。
疲労と肩こり両方をケアしてスッキリ!
今回の記事では、以下のことを中心に解説しました。
肩こりは血流が悪くなり、筋肉がこわばった状態
疲労と肩こりは相互関係があり悪循環になる
悪循環を断つ方法はストレッチ、入浴、薬物治療などがある
肩こりを放っておくと、さらにひどくなり疲労にもつながってしまいます。
早い段階で悪循環を断ち切り、疲労も肩こりも改善させましょう!


【参照】
[1]公益社団法人 日本整形外科学会,一般の方へ>症状・病気をしらべる>肩こり
[2]一般社団法人 日本臨床内科医会,わかりやすい病気のはなしシリーズ47 肩こり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
