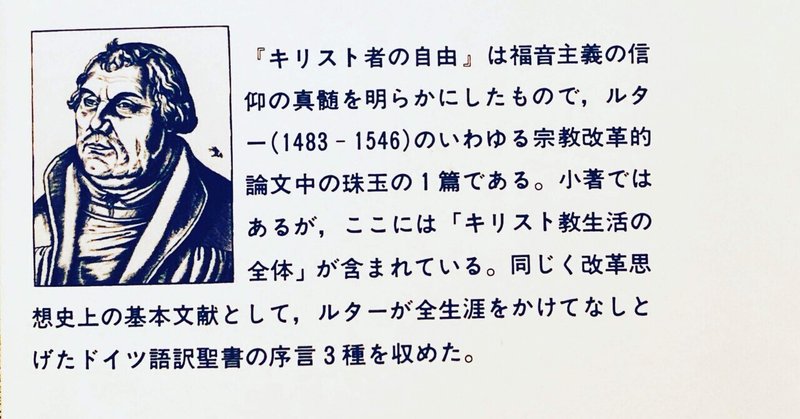
キリスト者の自由・聖書への序言
"私はまず次の二命題をかかげたいと思う。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主であって、何人にも隷属しない。キリスト者はすべてのものに奉仕する僕であって、何人にも隷属する"1520年発刊の本書は表題の原著でわずか20ページの小冊子にして、当時大きな反響を呼んだ著者の宗教改革思想上の最も重要な主著他、序言3種を納めた普遍的名著。
個人的には歴史教科書での厳しい顔こそ当然に知ってはいるも、著作は読んでいなかったので手にとりました。
さて、そんな本書は教皇を頂点とした強力な権利システムとなっていたローマ・カトリック教会。一方で歴史的必然から内部腐敗も進んでいた16世紀。罪と罰をしても免罪符さえ買えば恩恵を与えることに疑問を感じ、批判の声をあげた著者が、キリスト教の信仰の在り方について【自己の明確な意見を示さなければ】と次々に発表した三論文の一つにして、もっとも優れた内容とされる『キリスト者の自由』そして誰もが読めるように【生涯をかけて精力的に行った聖書翻訳業】のうち『新約聖書への序言』含む2種が収録されているのですが。
まず、やはり冒頭に一見すると互いに矛盾するような2つの有名な命題が掲示され、やわらかく理解をといかけてくる『キリスト者の自由』自分の個人的なアンサーでは前者の『キリスト者は隷属せず自由=身体的には違っても神の前に霊的には自由』そして後者の『キリスト者は奉仕する僕として隷属する=単独では人は生きていけず、他者(隣人)に対し無償で奉仕しなければいけない)』がどこか私には国が違えど、最近読んで感銘を受けた【親鸞『歎異抄』と似た読後感があって】面白くかつ印象に残りました。
また、このラテン語版は『教皇レオ10世に捧げる書』として【一応はローマ教皇への恭順を示すも】結局、本書の内容も教会に対する見過ごせない見解や批判があると(これは読めば、明らかに意図してるなと私でも感じます)発刊の翌年1521年には著者は破門となり、対立が決定的となるわけですが。歴史の授業ではプロテスタントとして『対立後』しか知らなかったので、その前段階を知れて【知られざる歴史の1ページに触れたような楽しみ】がありました。
プロテスタント教会で広く愛読される名著として、また宗教改革の歴史を知るサブテキストとしてもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
