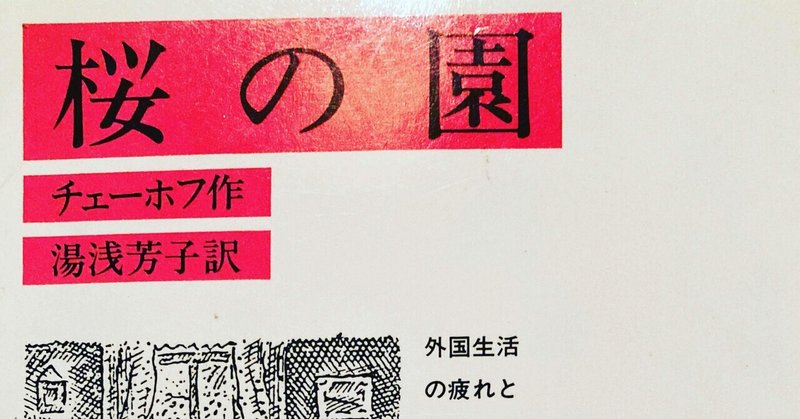
桜の園
"この園のすばらしいところはただ、これがたいへん大きいということだけです。桜実は二年に一度なりますが、それはどこへもやり場がない、だれも買いません。"1903年発表の本書は、著者最晩年の作品、代表作の一つにして、太宰治『斜陽』のモデルにもなった喪失の悲喜劇。
個人的には多くの優れた短編小説版でもある著者の四大戯曲のうち、『かもめ』に次いで、手にとりました。
さて、そんな何度も国内でも上演され、あまりにも有名な本作は19世紀末、農奴解放後の南ロシアを舞台に、時代が変わったにも関わらず過去を忘れられずに浪費を繰り返し破産の危機に陥っている『桜の園』主人、貴族のラネーフスカヤ夫人たちが、成り上がりの商人ロパーヒンの再三の助言にも関わらず、結局は数々の思い出のある『桜の園』を手放す羽目になり、没落していく姿を四幕で描いているわけですが。
まず、劇作家の井上ひさしが"一に主人公という考え方を舞台から追放、二に主題という偉そうなものと絶縁、三に筋立ての作り方を変えた"と【これまでの演劇に革命を起こした】と著者を評したらしいですが【演劇としてはとにかく】物語としては『何かが起こっても(特には)何も起こらない』ただありのままの【過ぎてゆく時間、必然的な結末】が描かれている本作。登場人物のうちでは貴族側ではなく、商人のロパーヒンに感情を重ねて読んだ自分としては『そりゃあ、そうなるでしょ!』と、正直に言えば腹がたちました(笑)
一方で、最近になって公家や大名といった、かっての上流階級、富裕層の元屋敷などを見学する機会が増える中、本来であったら私のような【庶民が見学できる】なんて、作った側は想像すらしなかっただろうな。とたまに考える私は『桜の園』を、そういった建築物と重ね合わせて捉えていて。確かにラネーフスカヤ夫人たちが少し可哀想ですし『桜の園』も新たな所有者によって【姿が変わってしまうとしても】割と『多くの人にとって』最大公約数的に希望のあるハッピーエンドではないかな?と思ったり。
演劇に興味ある方はもちろんの事、優れた短編小説に興味ある方にもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
