
茶道:お薄カフェに挑戦
はじまりのきっかけ
昨年、友人から「ご年配の方から着物をたくさん譲ってもらったけど、もう自分のたんすには入らないのでもらってほしい」という話から本当にたくさんの着物を譲ってもらった。半分ぐらいは自分がもらったり、友人に譲ったりしてきたが、それでも余りある着物。
どれもこれも状態がよくきれいなものばかり。
こんな着物を着てくれる繋がりがありそうな友人に相談した。
友人からの共感も得られ、その友人が運営する「たすきがけ事業所」のイベント「きものチャレンジvol.1」が実現する。
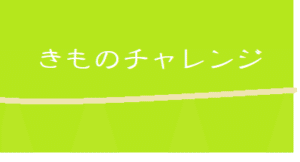
もともと「着物」の企画は、以前から温められていて、色々なタイミングから相談から2カ月ほどで当日を迎えることに。(ありがたい)
そして、「ゆる茶会」の話を以前からしていたこともあり、イベントのなかでお薄を出す「お薄カフェ」をゆるやかに行うことに。
きものチャレンジvol.1とお薄カフェ
「きものチャレンジ」では、「着物のことを体系的に学ぶ」「着物を自分で着てみる」「リメイクに挑戦してみる」「着物フリマ」そして、染織着物作家でありきものラウンジ主宰の大久保有花さんのお話ときものお譲り会という「特別企画」もあり、コロナ禍ながら小規模なイベントがちょこちょことあり、長屋の一角にある「まち農家(たすきがけ事業所のスペース)」を訪れる方へのお茶タイムにお薄カフェをさせてもらった。

お薄カフェのこだわり
「たすきがけ事業所」と直接つながりのある、顔の見える関係のものであることが大切というコンセプトをベースに。
抹茶は、ほうじ茶などで以前から扱っている健一自然農園さんの自然栽培の抹茶で決定。

普段のお茶会や茶道で飲む抹茶は、一定の味(安定の味)になるように、複数の農家さんのお茶がブレンドされている。農作物だから毎年同じ味の抹茶になるとは限らないので、茶匠さんという方が味を見てブレンドしているのだけれど、これは混じり気のない、いわばシングルオリジンの抹茶。最近こそ茶の生産地などで、単一農家さんの抹茶が手に入りやすくはなっているけれど、あまり一般的ではなく、珍しいもの。(そもそもお茶がブレンドされて売っているということ自体知られていないと思う)
そして、抹茶は味が乗りにくいそうで、無農薬や自然栽培の抹茶は味が薄くなりがち。とくに抹茶の苦味や旨味は実は肥料の味だとかなんとか、、、(茶農家の友人いわく)
という友人からおそわったうんちくもお茶の味わいのひとつに。
次にお菓子。ちゃんと和三盆のみで作る干菓子「三谷製糖」さんのものに。
https://wasanbon.com/
端午の節句が近かったので「こどもの日」の和三盆。

お話会の日は特別にWOOST engine mealsさんのレモンパウンドケーキと合わせて。
https://woostenginemeals.tumblr.com/
お道具もまち農家さんの繋がりから頂いてきたもの、持っているもの、持参したものを上手く組み合わせながら、できるだけ「本物」の道具を使うように心がける。
塗りのお盆、赤櫨焼のお茶碗も登場。(本来棗に抹茶を入れるのだけど、洗う乾かす手間を考えて飾っているだけ)

帯をテーブルセンターにして空間づくり

ゆるりと心地よくすごす時間を
お薄カフェ自体はがっつり売り上げがあったわけではないけれど、お茶を飲んでくださった方、おひとりおひとりとゆっくりとお話させてもらう時間を持つ事ができた。
お抹茶のウンチク話をきっかけに色々とお話させていただいた。抹茶とおしゃべりで免疫力アップしたらいいな。お茶を飲みなれていない方やお子さんにも飲んでいただいて、うれしいかぎり。
お話会の一呼吸にも役立てたようで、自分の心も豊かになったひと時だった。
服でなく「布」という視点
大久保有花さんのお話では、布の始まりから今の着物のことまで幅広く盛りだくさんにお話ししてくださった。
結城紬の着物が欲しい→作れるようになったらいいのでは→織子の修行
という、面白い経緯で染織着物作家となられた大久保さんのお話と絹の手紬実演。
糸のはじまり、布のはじまり。世界の布と日本の布の違い。日本は、長い長い歴史の中で庶民派「麻(ヘンプ)」を身に着けていた。藤や葛からも繊維が取れて、それを糸にし、布にしていたこともある(めちゃくちゃ大変)。短い繊維を撚って糸にする作業が大変で、布というのは本当に貴重なものだった。
貴重な布をつぎはぎしてきた生活。こういったつぎはぎしてきた暮らしに着目したのが、青森県出身の民俗学者・民俗民具研究家の田中忠三郎さん。
田中忠三郎さんが生涯をかけて収集してきた(主にボロの)衣服や民具を常設で見ることができるのが、現在浅草のアミューズミュージアムとのこと。
http://amusemuseum.com/
過去の神戸ファッション美術館や大阪民族学博物館などでも企画展があったそう。いつか見てみたい。

着物はその名の通り「着るもの」つまり「衣服」なのだが、そのもとはと言えば「布」である。今回の企画やお話を通じて、布に興味を持つようになった。これからの衣服を見る視点が変わるひとときであった。
床の場所に敷かれた布は、アフリカの伝統的な織でできた布。
着物チャレンジの裏テーマとして「和」がすべてではない、ということを言いあらわすための空間づくりでもあった、とのこと。

最後に、一呼吸おいて、参加者を対象にした「きものお譲り会」の時間。
きものラウンジ主宰の大久保さんのもとには全国各地から様々な着物が集まる。これらのきものたちを次の持ち主に譲るため、こういった企画を行っておられる。
もし、譲られたけど着なければ、またお譲り会に出してもらえたらいい、それぐらいの気持ちで持って帰ってもらったら。という気持ちよさがよいな、と思う。
これからもお薄カフェを
緊急事態宣言の発令などで茶道の稽古もお休みになり、5月はまるまるお稽古に行くことができなかった。そんなときも、このような場があることで、自分自身も心落ち着くひと時を過ごすことができた。
これからもまたこの場で「お薄カフェ」としてゆるやかにお茶を入れる時間を持たせてもらったらと思っている。
季節のお菓子とともに頂くお茶も素敵。

サポートいただけると大変うれしいです! 空堀のお店に貢献するために使いたいです。
