
2020センター国語 第2問(小説)
【2020センター国語 第2問(小説) 解説講義】
出典は原民喜「翳」(1948年発表)。
1️⃣(12行目まで) 私は1944年の秋に妻を喪ったが、少数の知己へ送った死亡通知のほかに、満洲にいる魚芳にも端書を差出しておいた。妻を喪った私は悔み状が来るたびに、丁寧に読み返し仏壇のほとりに供えておいた。紋切型の悔み状であっても、喪にいるものの心を鎮めてくれるものがあった。本土空襲も漸く切迫しかかった頃のことで、死亡通知に返事のこないものもあった。返信が来ない些細なことも、私にとっては気に掛かるのであったが、妻の死を知って、ほんとうに悲しみを頒ってくれるだろうとおもえた川瀬成吉からもどうしたものか、何の返事もなかった。
妻の遺骨を郷里の墓地に納めると、棲みなれた千葉の借家に立帰り、そこで四十九日を迎えた。輸送船の船長をしていた妻の義兄が台湾沖で沈んだということをきいたのもその頃である。サイレンはもう頻々と鳴り唸っていた。「そうした、暗い、望みのない明け暮れにも、私は凝っと蹲ったまま、妻と一緒にすごした月日を回想することが多かった」(傍線部A)。その年の暮れに、一通の封書が私のところに舞込んだ。差出人は新潟県××郡××村×川瀬丈吉となっている。一目見て、魚芳の父親らしいことが分ったが、何気なく封を切ると、息子の死を通知して来たものであった。私が満洲にいるとばかり思っていた川瀬成吉は、私の妻より五カ月前に既にこの世を去っていたのである。
2️⃣(34行目まで) 私がはじめて魚芳を見たのは12年前のことで、私達が千葉の借家へ移った時のことである。私たちがそこへ越した、その日、彼は早速顔をのぞけ、それからは殆ど毎日註文を取りに立寄った。私の妻は毎日顔を逢わせているので、時々、彼のことを私に語るのであったが、まだ私は何の興味も関心も持たなかったし、殆ど碌に顔も知っていなかった。
私がほんとうに魚芳の小僧を見たのは、それから一年後のことと云っていい。ある日、私達は隣家の細君とブラブラ千葉海岸の方へ散歩していた。すると、向うの青々とした草原の径を、ぶらぶらやってくる青年があった。私達の姿を認めると、いかにも懐しげに帽子をとって、挨拶をした。「魚芳さんはこの辺までやって来るの」。「ハァ」。彼はこの一寸した逢遭をいかにも愉しげにニコニコしているのであった。「あの人は顔だけ見たら、まるで良家のお坊ちゃんのようですね」。その頃から私はかすかに魚芳に興味を持つようになっていた。
その頃、私の家には宿なし犬が居ついて、表の露次でいつも寝そべっていた。その懶惰な雌犬は魚芳のゴム靴の音をきくと、のそのそと立上がって自転車の後についていく。魚芳はその犬に対しても愛嬌を示すような身振であった。彼がやって来るとこの路次は賑やかになり、細君や子供たちも一頻り陽気に騒ぐのであったが、その騒ぎも鎮まった頃、魚芳は魚の頭を取出して犬に与えているのであった。…こうしたのんびりとした情景はほとんど毎日繰返されていたし、ずっと続いてゆくもののようにおもわれた。だが、日華事変の頃から少しずつ変って行くのであった。
3️⃣(56行目まで) 私の家は露次の方から空地を廻ると、台所に行かれるようになっていたが、そこへ毎日、八百屋、魚芳をはじめ、いろんな御用聞がやって来る。私はぼんやりと彼等の会話に耳をかたむけることがあった。ある日も、南風が吹き荒んでものを考えるには明るすぎる、散漫な午後であったが、米屋の小僧と魚芳と妻との三人が台所で賑やかに談笑していた。そのうちに彼等の話題は教練のことに移って行った。魚芳たちは「になえつつ(担え筒)」の姿勢を実演して興じ合っているのであった。二人とも来年入営する筈であったので、兵隊の姿勢を身につけようとして陽気に騒ぎ合っているのだ。その恰好がおかしいので私の妻は笑いこけていた。だが、「何か笑いきれないものが、目に見えないところに残されているようでもあった」(傍線部B)。台所へ姿を現していた御用聞のうちでは、八百屋がまず召集され、つづいて雑貨屋の小僧が海軍志願兵になって行ってしまった。それから、豆腐屋の若衆がある日、赤襷をして、忙しげに別れを告げて行った。
目に見えない憂鬱の影はだんだん濃くなっていたようだ。が、魚芳は相変らず元気で小豆に立働いた。朝は暗いうちから市場へ行き、夜は皆が寝静まる時まで板場で働く、そんな内幕も妻に語るようになった。…
冬になると、魚芳は鵯(ひよどり)を持って来て呉れた。店の裏に畑があって、そこへ毎朝沢山小鳥が集まるので、釣針に蚯蚓(みみず)を附けたものを木の枝に吊るしておくと、小鳥は簡単に獲れる。…この手柄話を妻はひどく面白がったし、私も好きな小鳥が食べられるので喜んだ。すると、魚芳は殆ど毎日小鳥を獲ってはせっせと私たちのところへ持って来る。…この頃が彼にとっては一番楽しかった時代かもしれない。…
4️⃣(82行目まで) 翌年春、魚芳は入営し、やがて満洲の方から便りを寄越すようになった。その年の秋から妻は発病し療養生活を送るようになったが、女中に指図して慰問の小包を作らせ魚芳に送ったりした。温かそうな毛の帽子を着た軍服姿の写真が満洲から送って来た。きっと魚芳はみんなに可愛がられているに違いない。あの気性では誰からも重宝がられるだろう、と妻は時折噂をした。そのうちに、魚芳は北支から便りを寄越すようになった。もう程なく除隊になるから帰ったらよろしくお願いする、とあった。魚芳は帰って来て魚屋が出来ると思っているのかしら…と妻は心細げに嘆息した。世の中はいよいよ凶悪な貌を露出している頃であった。年の春、新潟から梨の箱が届いた。差出人は川瀬成吉とあった。それから間もなく除隊になった挨拶状が届いた。魚芳が千葉を訪れて来たのは、その翌年であった。
その頃女中を傭えなかったので、妻は寝たり起きたりの身体で台所をやっていたが、ある日、台所の裏口へ軍服姿の川瀬成吉がふらりと現れたのだった。彼はきちんと立ったまま、ニコニコしていた。久振りではあるし、私も頻りに上がってゆっくりして行けとすすめたのだが、「彼はかしこまったまま、台所のところの閾から一歩も内へ這い入ろうとしないのであった」(傍線部C)。「何になったの」と私達が訊ねると、「兵長になりました」と嬉しげに応え、これからまた魚芳へ行くのだからと、倉皇として立去ったのである。
(その後、私は成吉と歯医者で行き違いになったことがあった。)
それから二三カ月して、新京の方から便りが来た。川瀬成吉は満洲の吏員に就職したらしかった。あれほど内地を恋しがっていた魚芳も、一度帰ってみて、すっかり失望してしまったのだろう。妻は日々に募ってゆく生活難を書いてやった。満洲から返事が来た。「大根一本が五十銭、内地の暮しは何のことやらわかりません。おそろしいことですね」。これが最後の消息であった。
5️⃣(最後まで) その文面によれば、彼は死ぬる一週間前に郷里に辿りついているのである。「兼て彼の地に於て病を得、五月一日帰郷、五月八日、永眠仕候」。
あんな気性では皆から可愛がられるだろうと、よく妻は云っていたが、善良なだけに、彼は周囲から過重な仕事を押しつけられ、悪い環境の中を堪え忍んで行ったのではあるまいか。親方から庖丁の使い方は教えて貰えなくても、辛抱した魚芳、久振りに訪ねて来ても、台所の閾から奥へは遠慮して這入ろうともしない魚芳。軍服を着て千葉を訪れ、晴れがましく歯医者で手当てしてもらう青年。そして、病軀をかかえ、とぼとぼと遠国から帰って来る男。…ぎりぎりのところまで堪えて、郷里に還った男。私は何とはなしに、魯迅の作品の暗い翳を思い浮かべるのであった。
終戦後、私は郷里にただ死にに帰って行くらしい疲れはてた青年の姿を再三、汽車の中で見かけることがあった。…
〈設問解説〉
問1 (語句の意味)
(ア) 興じ合っている→①互いに面白がっている
(イ) 重宝がられる→①頼みやすく思われ使われる
(ウ) 晴れがましく→④誇らしく堂々と
問2「そうした、暗い、望みのない明け暮れにも、私は凝っと蹲ったまま、妻と一緒にすごした月日を回想することが多かった」(傍線部A)とあるが、それはどういうことか。その説明として最も適当な選べ。
心情説明問題。最初に小説の設定を確認しておくと、語り手「私」が戦後の地点(語り手の現在)から戦時中を振り返る。そのうち、1️⃣と5️⃣が妻が亡くなった年の暮れ(1944)、かつて交流のあった川瀬成吉(魚芳)の実家から彼の死を告げる手紙が届いた場面(小説の現在)となる。その間の2️⃣〜4️⃣が「日華事変」(1937)の直前から1️⃣に向かって時系列に記述される(小説の過去)。当然、徐々に戦況が悪化していく。小説世界を時系列に並べ直すと、2️⃣3️⃣4️⃣→1️⃣5️⃣。
傍線部Aは1️⃣の場面。「そうした」の具体化(a)、「…にも、凝っと蹲ったまま…回想する」の具体化(b)。aについては、妻の死、妻の義兄の死に加えて、「サイレンはもう頻々と鳴り唸っていた」(→戦況の悪化)を繰り込む。 bについては表現自体に着目し、妻の死への失意でそこから先に進めない、というニュアンスだろう。bの判断に迷うなら、aで選択肢をしぼり、bの表現に沿うかどうかを判断する。決してaだけで決めないように。前後半とも④が妥当で正解。前半で①③を許容としても、後半の「安息を感じていた」「意欲を取り戻そう」は不適切。
問3「何か笑いきれないものが、目に見えないところに残されているようでもあった」(傍線部B)とあるが、「私」がこのとき推測した妻の心情はどのようなものか。その説明として最も適当なものを選べ。
心情説明問題。「私」が推測した妻の心情、という聞き方をしているが、結局、視点人物「私」の認識が反映される。まず「笑いきれない」に至る〈場面〉を確認すると、妻は台所で御用聞きの二人と談笑している中で、二人が訓練所での軍事教練を実演し、その恰好のおかしさに妻が笑いこけているところである。では、その妻の様子を見て「私」はなぜ、妻が「笑いきれない」と感じたのか。
2️⃣の末文「日華事変の頃から少しずつ変って行くのであった」という予告と、それを承け実際、傍線Bの直後で八百屋、雑貨屋、豆腐屋の若衆たちが出征していくという記述が根拠になる。つまり、軍事教練のおかしさに妻は笑うのだが、そこに「私」はやがて戦場に駆り出される彼らの運命の悲哀を感じ、それを妻の表情にも認めたのである。以上より、前半で〈場面〉をおさえ、後半で「以前の平穏な日々が終わりつつある」としている②が正解。①は「…気のはやりがあらわで…生きて帰れないのでは」の因果が誤り。
問4「彼はかしこまったまま、台所のところの閾から一歩も内へ這い入ろうとしないのであった」(傍線部C)とあるが、魚芳は「私達」に対してどのような態度で接しようとしているか。その説明として最も適当なものを選べ。
心情説明問題。魚芳はどのように接しようとしているか、といっても魚芳は視点人物ではないし、関連する直接話法・間接話法による心情吐露もないので、その意図は直接はうかがい知れない。このような場合、視点人物の観察による当該人物の描写を参考にする。
「私」の魚芳に対する観察描写として、まず傍線部より「かしこまったまま(a)」、さらに傍線直前の「きちんと立ったまま(b)/ニコニコして(c)」を拾う。また設問条件から、魚芳の、「私達」に対する関係を踏まえると、もともと魚屋の「御用聞き」魚芳にとって、「私達」はお得意先の上客だった。その関係は、軍役を経、兵長となった現在でも変わらない、そう考えるから魚芳は「かしこまったまま(a)」閾を越えようとしないのだ。この理解から⑤が正解。「姿勢を正して/笑顔で」が上のbcと対応する。
以上が設問に対する「正解」で間違いないが、小説の本当ではないと思う。ここを「正解」のように取ると、ストーリーがずれ落ちる。昔と変わらない関係なら立派に出世した魚芳は閾を越えることができた、むしろ関係が変わったから川瀬成吉は閾を越えようとしなかった。こう見るのが、この小説の値打ちだろう。一つ裏付けとなるものを挙げておくと、この場面を含めて以下の回想部(4️⃣)で、魚芳は「あれほど内地を恋しがっていた魚芳(→かつての魚芳)」を除き、「川瀬成吉/彼」と表記される。
問5 本文中には「私」や「妻」あての手紙がいくつか登場する。それぞれの手紙を読むことをきっかけとして、「私」の感情はどのように動いていったか。その説明として最も適当なものを選べ。
心情説明問題(正答選択)。傍線が無く、選択肢ごとに該当する行数を記してあるので、先に選択肢を見て本文に戻り、選択肢に矛盾する内容があれば消去する、という方針をとる。
①「紋切型の文面から…妻の死の悲しみを共有しえないことを知った」がl2〜「紋切型の悔み状であっても…喪にいるものの心を鎮めてくれる」と矛盾する。②は1️⃣と5️⃣の時間の呼応をおさえており、「終戦後…青年の姿に…魚芳が重なって見えた」がl92の一文と対応していて正解。③「周囲に溶け込めず…心配」がl59〜「誰からも重宝がられる…と妻は時折噂した」と矛盾する。④は魚芳個人の言葉を世代に広げていて誤り。⑤は「不満を覚えた」が明らかに誤り。
問6 この文章の表現に関する説明として適当でないものを二つ選べ。
表現説明問題(誤答選択)。表現自体とその意図の説明が正しいかを確認し、明らかに矛盾するものを消去する。
①「魚芳」は川瀬成吉と同一人物で、働く店の名だと推定するのが妥当。②時の記述についての選択肢。本文を時系列に並べ直すと、2️⃣3️⃣4️⃣→1️⃣5️⃣となる。「いくつかの時点を行き来しつつ記述」は妥当。③擬態語とその意図について。擬態語の指摘は正しいが、それは事態の迫真性を高めているのであり、それ自体「ユーモラス」な効果を持つわけではないので不適当。これが一つ目の正解。④「宿なし犬」や「鵯」のエピソードは、魚芳の愛嬌や人の良さを表しており妥当。⑤「南風が…」は見た通り「午後」を修飾しており、「思索に適さない様子」を印象づけているので妥当。⑥妻の病状を断片的に示すことは、生活が次第に厳しくなっていくことと対応しないのは明らか。これがもう一つの正解。
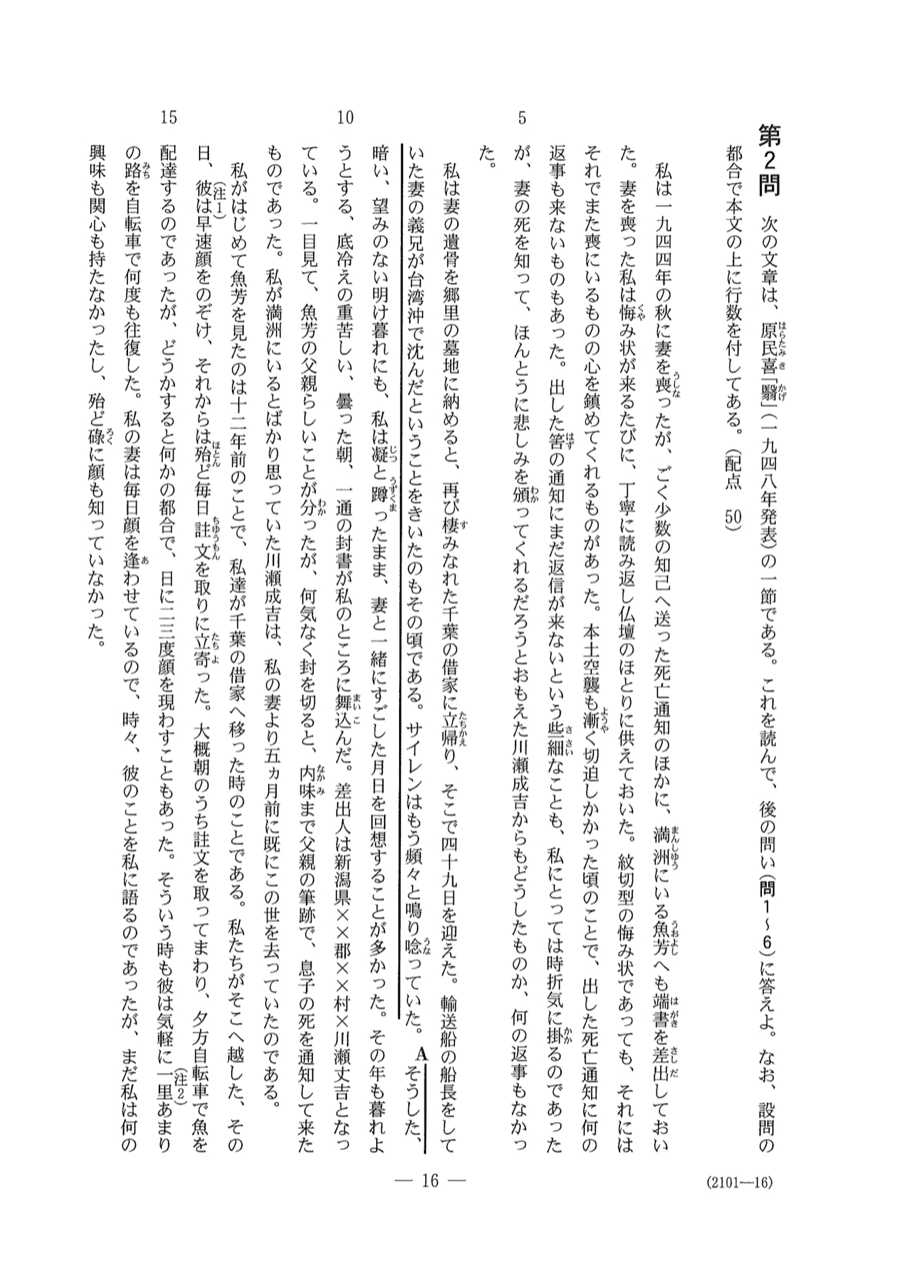


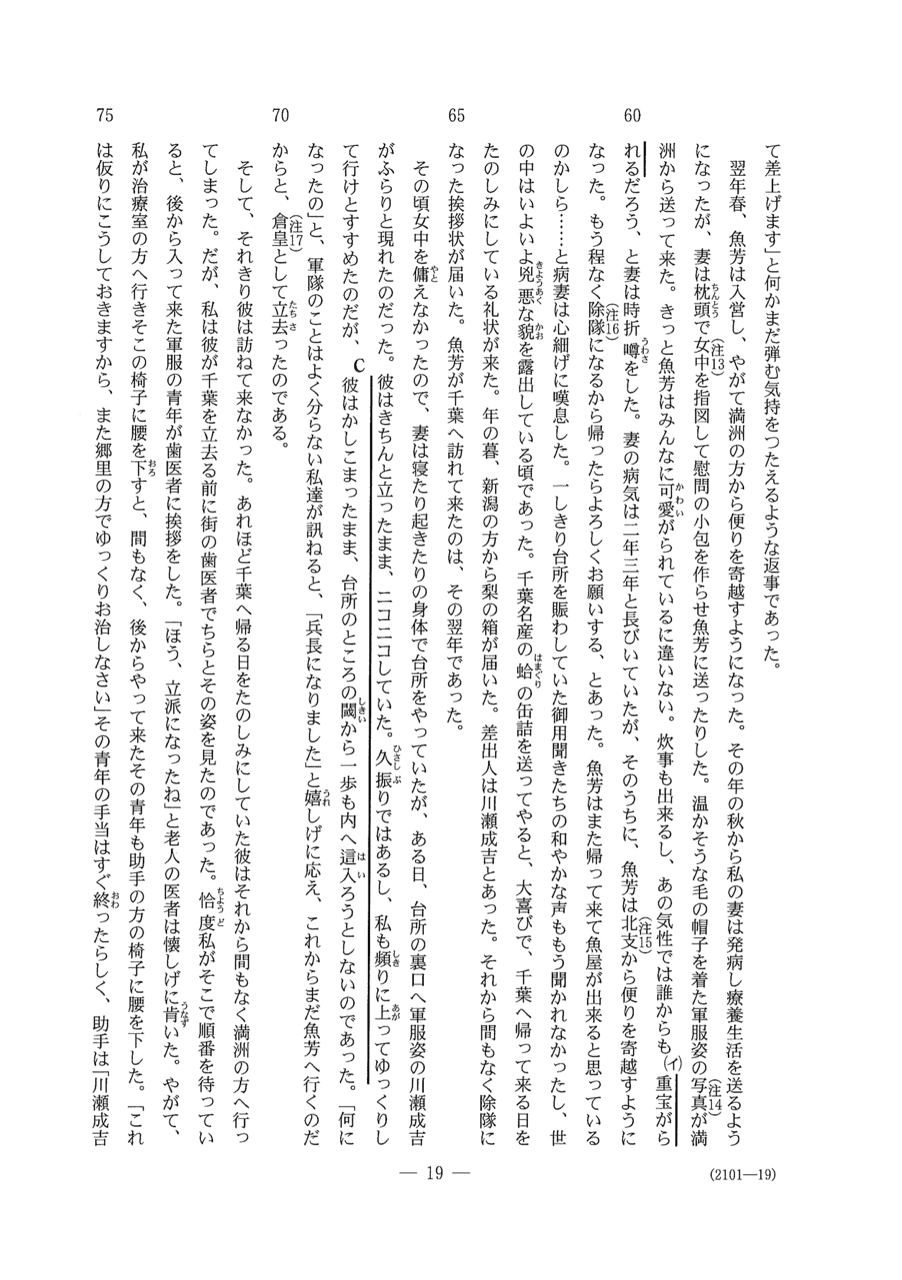







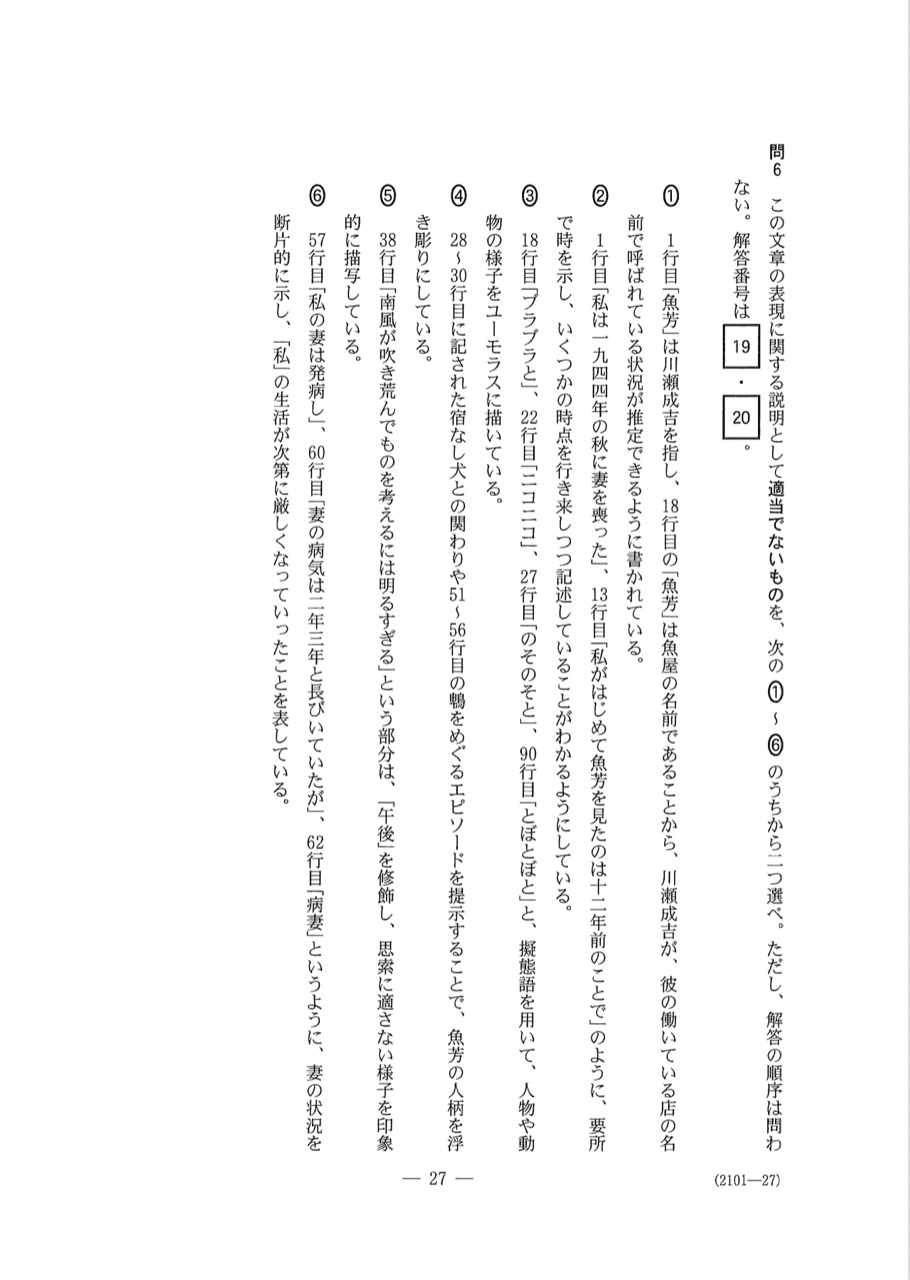
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
