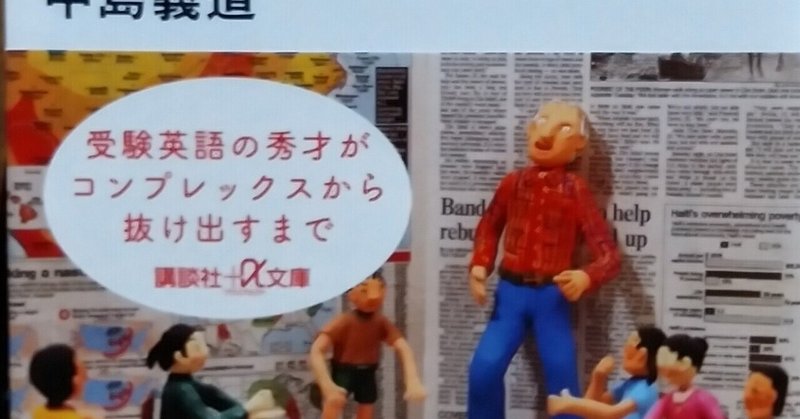
語学をはじめたくなる本(その2)
気楽な気持ちで、読めそうなものを紹介します。まずは、はじめの一歩!
① 中島義道、「英語コンプレックスの 正体」、講談社+α文庫
カント哲学者が、どのように英語をコンプレックスを克服?したか。いい意味で開き直ることが大切。
②芥川龍之介、「蜘蛛の糸・地獄変」、角川文庫
この文庫に入っている短編「毛利先生」がオススメです。英語を教えるとはどういうことかを考えてさせられます。
英語の先生に一読して頂きたい。
③鷺沢めぐむ、「ケナリも花、サクラも花」、新潮文庫
*「めぐむ」は漢字で書くと、くさかんむりに、下は月が2つ。
20過ぎまで、著者は自分に韓国の血が流れていることを知らなかった。著者がどう韓国語と向き合ったか。一読の価値あり。
④米原万里、「不実な美女か貞淑な醜女か」、新潮文庫
エリツィンの通訳や、かつて「ブロードキャスター」のコメンテーターとして、よくテレビに出演していました。
タイトルからして、興味深い。
真面目にふざけているような。ふざけているのに真面目というべきか。
今でも読み返すことがあります。
⑤シュリーマン、「古代への情熱」、新潮文庫
世界史でも登場するので、ご存知の方も多いと思います。シュリーマンがロシア語を学ぶとき、ロシア語を知らない乞食を雇って、テキストを音読した話。
人前で話すのと、1人で音読するのでは、やはり違う。先生ではないけれど、身銭を払うと、モチベになるということか?
⑥高田宏、「言葉の海へ」、新潮文庫
わが国初の近代国語辞書「言海」を独力で完成させた大槻玄沢。
辞書があるのが、当たり前だと思ったら大間違い!
いまだに辞書がない言語だってある。それと比べたら
英語は数えきれないくらいある。
辞書のありがたさ、思い出してみませんか?
⑦柳父章、「翻訳語成立事情」、岩波新書
かつて、日本には「恋愛」がなかった。「社会」も「個人」も「権利」も「自由」も「彼女」も、、、。「彼」も。
⑧関口存男、「ニイチェと語る」、三修社
ドイツ語の達人。この人、ホントにすごすぎる、としか言えない。1人の人が書く著作の量ではない。何人分の仕事を1人で成し遂げたのだろう!
⑨稲垣美晴、「フィンランド語は猫の言葉」、猫の言葉社
著者の留学記。エッセイに文法用語が多用されているのに、気にしないで楽しい気持ちで通読できます。
好きな章からお好きにどうぞ。
ここまで読んだら、そろそろ勉強を始めますか。
記事を読んで頂き、ありがとうございます。お気持ちにお応えられるように、つとめて参ります。今後ともよろしくお願いいたします
