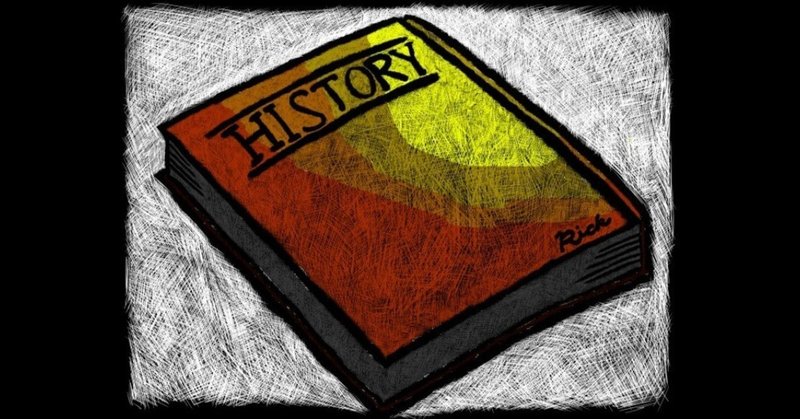
夢Ⅰ(20)
Ⅳ
大草原の中。リックは今、ヌエの一団と行動を共にしていた。
ハイビーとの別れから。多くの月日が流れていた。
季節は一巡し、大気には冬の兆しが見られ。夜の空が徐々に純度を増していく。
ヌエという呼称は、彼らがそう名乗ったわけではなく。ハイビーが別れ際に、リックに伝えたものだった。
「あの人たちのことを。私はヌエと呼ぶの。」と。
ヌエ達は、やはり、名前を持っていなかった。そもそも、協力して何かをするとき、互いに声を掛け合っている姿を見たことがない。彼らのやり取りは、終始無言。とても静かで。リックは、出会った当初、「とても不愛想な集団だな。」と思っていた。
彼らの生活に馴染み出した頃。次の日に使う薪の仕分けをしていたときに、一人のヌエが教えてくれた。「俺らには、相手の思考が聞き取れるんだ。」リックの「不愛想だな。」もちゃんと届いていた。教えてくれた彼は、申し訳なさげに笑っていた。ヌエ達は、とても温厚で優しかった。
風に乗り運ばれてくる、草木の甘い香りや獣の気配。世界の半分を空が占める大草原での、彼らの暮らしはとても質素だった。
生活拠点は、家族単位で張られた大振りのテントで。テントには、家族の寝具と来客用の寝具、それと少しの炊事道具が置かれているのみ。生活に必要な、食料や水、薪等は、ふらっと現れる行商から調達していた。
行商も当然ヌエで、大型の牛の様な生き物を引き連れて、大草原を地平の果てからのんびり歩いてくることもあれば。寒い夜明けには焚火に当たり、皆が起きるのを待っていることもあった。
行商とのやり取りは、物々交換が主体で。ヌエ達は、狩りで穫った成果をもとに行商と交渉した。
取引で特に重宝されていた商品は、「大型の鳥の羽」で。それは、きらきらと光を反射し見た目は絹のようで。手にすると、ずっしり、しっかりとした重みがあった。「街で、加工して装飾品の素材として使うのだ。」とリックが《茶色》と呼んでいるヌエが教えてくれた。
リックはヌエ達を、彼らの身に着けている「羽織りの色」で識別していた。《茶色》、《青》、《水色》、《灰色》、《黄色》に《赤》。所帯を持つヌエの男は、それぞれ異なる色の、豊かな彩の羽織りを身に着けていた。
深みのある豊かな色彩のその羽織りは、所帯を持ったその日の朝に、行商がふらっとやって来て届けていく。ヌエ達の王からの祝いの品だという。
ヌエ達の生活の主軸は、狩りであったが。狩りをしていない時間のほとんどを、彼らは、踊りや歌に費やしていた。
奏でられる音楽は、打音が主体で、打撃のリズムをずらすことで器用に旋律を作っていた。
彼らは、話すことも出来たが、言葉を会話に用いることはほとんどなかった。彼らにとっての言葉は、もっぱら踊りの振りや、伴奏のためのもので。音としての役割が主だった。
その音色はとても繊細で、リックは彼らの音楽がとても気に入った。どこか遠くで、聞いたことのあるような温かい懐かしさを感じた。
踊りや伴奏を何度も聞くうちに、いつしか、リックも一緒になり演奏に加われるようになっていった。
月の夜に、焚火を囲い。低く長くときに短く続くドラミング、繊細に高く鮮やかに織り込まれ奏でられるソプラノ。
聞き入る、大草原の気配。
彼らにとっての、大草原は狩場であり。そして、ときに大衆となった。
狩り、食い、眠り。そして、踊り歌った。
大快晴の日は、心まで晴れ渡り、高く歌い。
曇りの日は、低く奏で、大気を震わせ。
大雨がテントの屋根を打ち付ける音に。笑った。
そして、大草原を駆け抜ける深みのある風のように、緩やかに確実に時間は流れていった。
リックは、茶色の羽織りを纏ったヌエのテントで、彼の家族と一緒に生活していた。短剣も、彼のテントの片隅に立てかけられ。今は静かにしている。
ある夕暮れ、テントの中で家族と一緒に夕飯の準備をしていると、《茶色》がリックを呼びに来た。もっそ、もっそと走ってくる姿。彼らは大きい。リックの頭二つ分高く。横幅は、3倍ほどある。
「狩りだ。お前も来い。」どうやら、あの鳥がいたと斥候が伝えているらしかった。狩りを基盤としている生活には夜も昼もなかった。
夜の空気を肌に感じながら、リックは緊張と、初めての狩りに高揚を感じていた。彼らが何度か狩りに出て行くのを見送ってはいたが、《茶色》が声を掛けてきたのは、これが初めてのことだった。
おそらく、こちらの世界に来たばかりの頃のリックなら、この移り変わりの激しさに眩暈を覚えていたかもしれない。しかし、今は、この世界を楽しんでさえいることを感じ、そんなリックがいることに少し驚き、少しうれしくなった。
草原を進みながら、「その鳥は、夜は巣で休む習性がある。」と《茶色》が教えてくれた。彼の手には、弓が握られ、肩から矢筒を下げている。身に纏われた弓と矢は、いつもよりも一回り大きく見えた。撃ち込まれれば、ひとたまりもないだろう。これから、狩りに行くのだという実感が今更ながら込み上げてきた。
月は出ていなかった。星の瞬く空の方が闇が少し薄く、《茶色》の遥か前方、昼と変わらず地平がはっきりとその境界を示している。
かなりの距離を歩いていた。振り返っても、テントのある方角はわからなかった。
目標の巣は、草原の真ん中に無防備に現れた。
光を失い、深い青と黒が覆いつくす世界となった草原でも。巣に横たわる艶やかな気配が確認できた。
《茶色》が言った。「狙うのは、雄のみ。」「雌と子供は残す。」のだと。告げられた内容に、リックは一瞬怯んだ。思考の行きつく先を考えないようにした。
気が付くと、リック達とは別に黒い影が三つ、巣を囲むようにして息をひそめている。
視力に頼っているリックには、巣の中にいるものが、一体何で。何体いるのか。この位置からでは、識別することが出来なかった。
リックの横で《茶色》が静かに。弓を引き絞った。
風が止んだ。次の瞬間、音もなく矢が放たれた。
《茶色》は、歯を食いしばり。目はしっかりと獲物に向けられている。その目は、真剣で。一連の動作からは、無駄な気負いは一切見られなかった。
寸分の狂いもなく同時に四方から放たれた矢は、巣の中の影に「ドスッ」と刺さった。大型の影が一つと、小さな影が一つ空へと飛び立った。矢の刺さったと思われる大きな影は、微動だにしなかった。
ヌエたちは、急いで巣に駆け寄ると。《茶色》が腰にしていた短刀を構え、巣で横たわっている大きな影の首元を深く切り落とした。
色鮮やかな流れる水の様な羽を備えた、とても大きな鳥が巣に横たわっていた。
矢は、両羽の根元に一本づつ、残りの二本は首の根元から胸の中心に向かって刺さっていた。
四人のヌエは、大きな鳥の亡骸を囲み、静かに目を閉じた。リックも見まねで彼らに続いた。脳裏に、崖の棚の家族との日々が浮かんだ。
まるで、まだそこに留まる思いを見送るように、祈りの時間が流れた。
他の生き物の思考を聞き取ることのできる彼らには、すべてが流れ込む。思考は、綺麗に割り切れるものではなく。
喜び、悲しみ、そして痛み。
❖ ❖ ◇ ◇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
