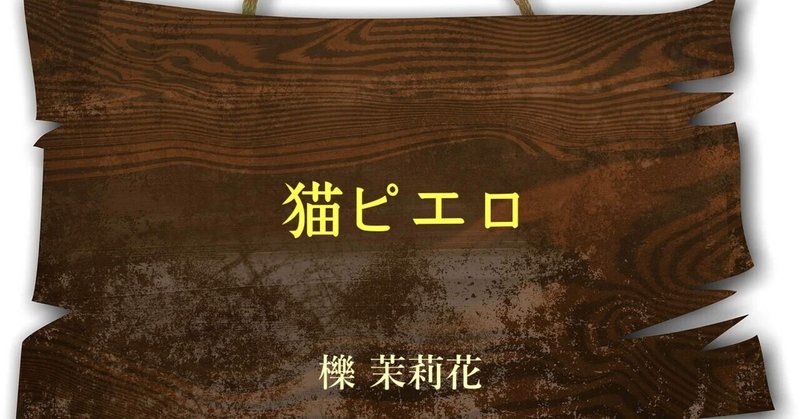
猫ピエロ
(本作は2,368文字、読了におよそ4〜6分ほどいただきます)
「吾輩は猫である。名前はまだ無い」
突然そう話し掛けられると、大抵の人は戸惑うだろう。若しくは、驚くかもしれないし、怖くなるかもしれない。しかし、その老人の場合は、戸惑うでもなく、驚くでもなく、また、全く怖さも感じなかった。おそらく、長年の人生で培った経験の履歴にも見当たらない、とてもレアでイレギュラーな事態に、状況把握の為だけに大きなタイムラグが生じたのだ。つまり、単に呆然と時間が経過しただけ。そして、そこから徐々に湧き上がった感情は、やはり戸惑いや驚き、恐怖などではなく、「これは面白い!」だった。
と言うのも、件のセリフを口にしたのは、どう贔屓目に見ても「普通の人」ではなかったからだ。
まず、見た目は道化だった。もちろん、本物の道化ではないだろう。おそらくは、道化の扮装を強いられていたのだ。しかも、それは子どもでも大人でもなく、赤ちゃんでも老人でもない。そもそも、人じゃなかったのだ。本当にまだ名前がないのなら、冒頭のセリフに嘘はないことになる。
つまり、猫だった。
「おやおや、君は何故そのセリフを知ってるんだ?」
老人は、優しく猫に話し掛けた。彼にとっては、猫がピエロの格好をしてる滑稽さや、猫が言葉を話した衝撃より、猫が漱石を知ってる意外さが先に立つようだ。確かに、レアでイレギュラーな出来事に最初こそ面食らったものの、多少のことでは動じない落ち着きも、長年の人生で培った経験の賜だろう。
「知らねぇよ、有名なセリフだったのか?」
「あぁ、とても有名な文豪が書いた名著の冒頭文だよ。まさか、君があの猫じゃないだろうな?」
漱石が『吾輩は猫である』を書いたのは、何十年も昔のことだ。言うまでもなく、漱石はとっくの昔に他界した過去の偉人なので、目の前の猫とあの猫には何の因果関係もあるはずがない。それなのに、そう分かっていてもつい聞いてしまった。そこに、一縷のロマンを求めていたのかもしれない。
「悪いけど、吾輩には興味ないね」
猫は、無愛想に吐き捨てた。憎々しげでもあり、無関心でもあるが、矛盾するようだが老人には好意的な反応にも感じた。
「ところでさ、君は何故にピエロの格好をしてるんだ?」
老人にとって二つ目の疑問は、道化の扮装のようだ。猫が言葉を話していることは、もはや疑問ですらないのだろう。
「ピエロってのが何かも知らねぇけどよ、ハッピーハロウィンとか何とか言いながら、通りすがりの知らないお姉さんに無理矢理着せられただけだ。大体、何なんだよ、ハロウィンって」
そう文句を垂れながらも、猫はコスプレ趣味でもあるのだろうか、満更イヤでもないようだ。
(そうか、今日はハロウィンなのか……)
近年に始まった若者の風習に、老人は内心辟易していた。それに、そもそもハロウィンについて、単に無秩序に騒いでるだけという印象しかなく、殆ど何も知らなかったのだ。
「そうだったのか。でもな、ワシもハロウィンのことはよく分からなくてのぉ……確か、カボチャとかおばけが出て来て……あとは、仮装したり魔女とかコウモリとか黒猫とか……あ、猫か」
「あぁ、吾輩は猫だ。でも、ピエロってのは何だ?」
確かに、ハロウィンとピエロは、結び付くようで関連性はないだろう。どこの誰だか知らないが、何故ピエロなんだ? まぁ、大した意味はないかもしれない。単なるハロウィンの馬鹿騒ぎの一環の、無意味な仮装と考えるのが自然だろう。
「すまんがのぉ、ワシにも何で君が道化にされたのか分からんよ」
すると、心なしか、猫は少しガッカリした様子を示した。
「どうでもいいよ、そんなこと……じゃあ、吾輩はそろそろ行くことにする。お別れだな」
一方的に猫に別れを告げられて、老人は急に寂しくなった。出会いから僅か数分間のやり取りなのに、老人は数年振りに楽しいと感じたし、数年振りに充実した時間を過ごすことが出来たのだ。ずっとこの猫と話していたい、ずっと一緒に暮らしていきたい……突然、そんな感情が芽生えたのだ。だから、思い切って切り出してみた。
「なぁ、にゃんこよ。君に行くところはあるのか?」
すると、猫は一点を見つめ、黙り込んでしまった。
「もしさ、何処にもアテがないなら、うちに来ないか? ずっと一緒に暮らそうじゃないか。暖かいおうちで美味しいモノいっぱい食べさせてあげるから」
「……本当か? でも……吾輩はアンタに何もしてあげられないぜ?」
「ハハハッ、何を言い出すかと思ったら……君は何もしなくてもいいんだよ。あ! そうか! 今分かったよ。あのさ、ピエロってのはな、人を笑顔に変えるのが仕事なんだ。君は何もしなくても、ずっと役割を果たしてくれるんだ」
「……本当に美味いもの食わせてくれるんだな?」
「あぁ、約束するよ。ところで、君は本当に名前がないんだな? まさか、名前は『マダナイ』とかじゃないだろうな?」
「しょうもないよ、それ……名前は本当にないけど、さっき『なぁ、にゃんこよ』って呼んだじゃないか。それを吾輩の名前にしたんじゃないのか?」
「え? あ、まぁ、そうだな、それでいいか。よし、君は今からにゃんこだ。我が家の猫、名前はにゃんこだ」
ようやく名を得た猫は、とても嬉しそうだ。得意げに胸を張り、目を細め、尻尾をツンと立てていた。
「じゃあ、早速うちへ案内しよう。その前に、一つだけ約束して欲しいんだ。私以外の人間には、絶対に人間の言葉を話さないでくれ。大変なことになるからのぉ」
某年某月、某所にて、お爺さんが猫を拾ってきたそうだ。にゃんこと名付けられたその猫は、きっとこうしてご家族と出会ったのだろうと想像している。にゃんこはお爺さんとの約束を頑なに守り、あの日以降、人間の言葉を話していないそうだ。毎日暖かいお家で美味しいご飯を沢山食べ、家族に笑顔と安らぎを与えている。
