
鍼灸臨床現場で活かせる”足と歩きの診かた”
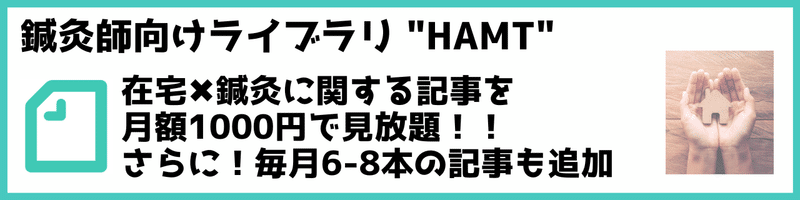
こんにちは。てっちゃんこと白石です。
これまで運動療法・フィジカルアセスメント・カルテの書き方といった基礎的なテーマについて解説してきました。読者の方からの相談では臨床についても語って欲しいというご意見をいただく機会も多いので、今回から”足と歩きの診かた”についての記事を書くこととなりました。
いきなり歩行や足の評価について語っても訳が分からなくなってしまうので、今回は”足を評価する上での最低限必要な基礎知識”について出来るかぎり臨床に即した部分に絞って解説したいと思います。
1.歩行を評価する上で”第1歩は足から”考えよう
ボク自身、”足”に関する興味は人一倍ある方で、最初の職場の面接時に
「足が大好きです。足のプロフェッショナルになりたいです。」
と言っていたのは今でも鮮明に覚えています。
鍼灸師にとっても、足に経穴は数多くあり重要な部位であることを認識している人も多いのではないでしょうか。
歩行における足は、常に身体を支えてくれる土台であり、高齢者にとって足の問題を改善することで他の症状を改善することにもつながります。
歩行が困難になってくると日常生活動作の低下にもつながり、要支援・要介護状態へと進んでしまうリスクも高まってしまいます。
在宅鍼灸師にとって、歩行状態を正しく評価することができることは非常に重要度の高いスキルであることはいうまでもありませんが、歩行の評価は非常に難解であり苦手意識を持っている人も多いスキルであると言えます。
歩行動作を全体で捉えて評価しようとしても初学者にとってはハードルが高いため、今回は足にフォーカスを当てて考えていきたいと思います。
2.足の凄さは柔軟性・固定性を瞬時に切り替えられること
足には、骨・関節・筋肉・靭帯などめちゃくちゃ沢山あり、本格的に学ぼうと思っても組織の細かさに挫折してしまう人も少なくありません。
いきなり細かい機能解剖を学ぼうと思っても余計混乱してしまうため、まずはざっくり足の全体像を押さえて理解するのがオススメです。
まず、冒頭から”足”と呼んでいる件についてですが、なぜ”足関節と呼ばないか”にも理由があります。
一般的に呼ばれている”足関節”をイメージした時、多くの方が想像するのは距腿関節ではないでしょうか?
狭義の足関節は”距腿関節”で間違いないんですが、実際の運動では距腿関節・距骨下関節・遠位脛腓関節・ショパール関節・リスフラン関節と様々な関節が複合的に動いています。よって、足関節のことを”足関節複合体”と言ったりもします。
今回は足関節複合体のことをわかりやすく”足”と呼んで進めていきたいと思います。
足の凄いところは、”柔軟性と固定性という相反する機能を瞬時に切り替えて歩行という高次な運動を遂行している”という点にあります。
これってめちゃくちゃ凄いことで、足を接地する時には衝撃を吸収するために柔軟性を高めて、蹴り出す時には足の固定性を高めて推進力へとつなげます。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜
200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…
投げ銭はいりません!そのかわり〜無料でできる〜Twitterで感想をシェアしてくださると嬉しいです(๑╹ω╹๑ )
